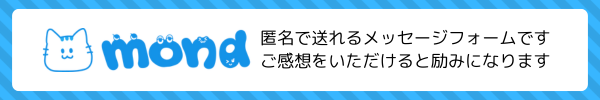秋口が会社や外の女の子と会っている様子は、佐山にもすぐわかった。
もちろん秋口本人が佐山に宣言するわけではないけれど、もともと社内でも噂話の種にされることの多い彼のことだ。休憩所や食堂での女子社員たちのひそひそ話、男性社員たちのやっかみ半分の揶揄、そんなものが嫌でも佐山の耳に入ってきた。
廊下で他の課の女子社員に呼び止められ、親しげに話す秋口の姿を見たことも、一度や二度じゃない。ここのところおとなしくしていた秋口が、どうやらまたあちこちつまみ食いを始めたらしい。それを知った女子社員たちの行動は素早かった。
『六時には仕事終わります』
携帯電話の液晶画面をしばらく眺め、佐山は細く溜息をもらすと返信モードに変えた。
『了解』
件名なしで、二文字。さっさと送信して携帯電話をポケットにしまい、佐山は目の前のパソコンモニタに視線を向けた。
女の子たちと遊ぶ合間に、秋口は佐山とも会う。会って、食事をして、別れて、それで終わりだ。まるで秋口と一緒に出かけるようになった最初の頃のよう。
他愛ない話をしながら気に入った店で食事をとって、笑って、ただそれの繰り返し。
(……疲れたな)
無性に煙草が吸いたくなったが、最近吸い過ぎなのは自覚していたので、佐山はその欲求をどうにか押し殺した。何かと休憩を取りすぎだ。同僚たちもそろそろ変に思っているだろう。溜息ばかりついて、冴えない顔色で、正確な仕事を信条としているのにケアレスミスの増えてきた佐山のことを。
(すごく、疲れた)
最初の頃に秋口と会いだした頃も、やたらと疲れていた。緊張して、楽しくて、そんな自分の感情の浮き沈みに自分で振り回されて、疲れた。
あの頃がもうずっと昔のことみたいだ。
こんな思いをしてまでどうして自分が秋口のそばにいたいと思うのか、佐山は自分の気持ちが馬鹿馬鹿しくて悲しくなってくる。
(それでも会えないよりはマシだ、なんて)
誘いを断れば、秋口は他の人と出かけるだろう。医務室で強引に組み敷かれたのを最後に、秋口は佐山の体に触らなくなったが、秋口好みの綺麗な女と出かけて、彼が相手に手を出さないなんて佐山には考えられなかった。
(こういうのも女々しいっていうのか)
傷ついて、疲れて、それでも秋口に会いたいと思い続ける自分が佐山には滑稽だった。それでもいてもたってもいられないまま、その日も秋口と会って、ただ食事をして、内容なんて覚えてもいられないような当たり障りのない会話をして、お互いの家に帰った。
「佐山、今帰り?」
秋口からのお誘いが掛からなかった平日の晩、仕事を終えてビルを出たところで、御幸に声をかけられた。
「お疲れ、御幸もちょうどか」
「いいタイミング。な、急いでないなら飯でも行かないか」
気軽な調子で自分を誘う御幸の笑顔に、佐山は無性にほっとした気分で笑い返し、頷いた。
「よし決まり決まり」
御幸が佐山の背を押すように歩き出し、駅の方へと向かう。
「ここ、久しぶりだよな」
御幸のリクエストで、ふたりお気に入りの定食屋へ入った。ふたり掛けの席に向かい合って座る。佐山はメニューを見てもあまり食欲が湧かなかったが、御幸を心配させたくなくて、焼き魚定食を頼んだ。御幸はヒレカツ定食にビール。
「俺もちょっと、飲もうかな」
ビールを注文した御幸の声を聞いて、佐山も飲み物のメニューに視線を落とした。
「えーと……生搾りオレンジサワー」
「オレンジ多めでお願いします」
さり気なく御幸が付け足して、佐山は軽く肩を竦めた。御幸は困ったように笑っている。
「ま、飲みたい気分の時もあるよな」
いろいろなことに、聡い御幸は多分気がついているだろうが、何も言わないでいてくれた。そういう相手が自分にいることを、佐山は心底から感謝する。
すぐにやってきたビールとサワーで軽く乾杯して、佐山は久しぶりに、料理を美味いと思って口に運んだ。
秋口と一緒に入る店は、あんなに気に入っていた料理なのに、最近ではその味もほとんどわからなかったのだ。
会社でのできごとや些細な日常、秋口との会話と大差ないことを話しているのに、御幸の前で佐山は自分がずいぶんリラックスしていることに気づいた。
同時に、秋口といる時の自分が、どれほど無理をしているかにも気づいてしまう。あたりまえの態度を貫くことに神経をすり減らしているのだ。
「佐山、そろそろ酒やめとけよ。顔色やばいぞ」
甘い酒が変に美味くて、少しでやめておこうと思ったのに、いつの間にか佐山のグラスの中味は半分ほどに減っている。気づいた御幸がそう釘を刺したが、佐山は大丈夫大丈夫と笑ってまたひとくち酒を飲んだ。
「前にもちょっと飲んで、平気だったんだ」
そう言ってから、その時の酒は秋口と一緒に飲んだのだということを思い出して、喉が詰まるような感触を覚える。
美味い酒で、酔っぱらって、勢い余って秋口に好きだなんて本心を告げてしまった。
あのことさえなければ、秋口と自分はもう少しマシな関係でいられただろうか――そんなことを考えたくなくて、佐山はもうひとくち酒を飲む。
本当に大丈夫かよ、と呆れたような、心配げな御幸な声が聞こえて、笑い返したつもりが、そこから先の記憶がない。
もちろん秋口本人が佐山に宣言するわけではないけれど、もともと社内でも噂話の種にされることの多い彼のことだ。休憩所や食堂での女子社員たちのひそひそ話、男性社員たちのやっかみ半分の揶揄、そんなものが嫌でも佐山の耳に入ってきた。
廊下で他の課の女子社員に呼び止められ、親しげに話す秋口の姿を見たことも、一度や二度じゃない。ここのところおとなしくしていた秋口が、どうやらまたあちこちつまみ食いを始めたらしい。それを知った女子社員たちの行動は素早かった。
『六時には仕事終わります』
携帯電話の液晶画面をしばらく眺め、佐山は細く溜息をもらすと返信モードに変えた。
『了解』
件名なしで、二文字。さっさと送信して携帯電話をポケットにしまい、佐山は目の前のパソコンモニタに視線を向けた。
女の子たちと遊ぶ合間に、秋口は佐山とも会う。会って、食事をして、別れて、それで終わりだ。まるで秋口と一緒に出かけるようになった最初の頃のよう。
他愛ない話をしながら気に入った店で食事をとって、笑って、ただそれの繰り返し。
(……疲れたな)
無性に煙草が吸いたくなったが、最近吸い過ぎなのは自覚していたので、佐山はその欲求をどうにか押し殺した。何かと休憩を取りすぎだ。同僚たちもそろそろ変に思っているだろう。溜息ばかりついて、冴えない顔色で、正確な仕事を信条としているのにケアレスミスの増えてきた佐山のことを。
(すごく、疲れた)
最初の頃に秋口と会いだした頃も、やたらと疲れていた。緊張して、楽しくて、そんな自分の感情の浮き沈みに自分で振り回されて、疲れた。
あの頃がもうずっと昔のことみたいだ。
こんな思いをしてまでどうして自分が秋口のそばにいたいと思うのか、佐山は自分の気持ちが馬鹿馬鹿しくて悲しくなってくる。
(それでも会えないよりはマシだ、なんて)
誘いを断れば、秋口は他の人と出かけるだろう。医務室で強引に組み敷かれたのを最後に、秋口は佐山の体に触らなくなったが、秋口好みの綺麗な女と出かけて、彼が相手に手を出さないなんて佐山には考えられなかった。
(こういうのも女々しいっていうのか)
傷ついて、疲れて、それでも秋口に会いたいと思い続ける自分が佐山には滑稽だった。それでもいてもたってもいられないまま、その日も秋口と会って、ただ食事をして、内容なんて覚えてもいられないような当たり障りのない会話をして、お互いの家に帰った。
「佐山、今帰り?」
秋口からのお誘いが掛からなかった平日の晩、仕事を終えてビルを出たところで、御幸に声をかけられた。
「お疲れ、御幸もちょうどか」
「いいタイミング。な、急いでないなら飯でも行かないか」
気軽な調子で自分を誘う御幸の笑顔に、佐山は無性にほっとした気分で笑い返し、頷いた。
「よし決まり決まり」
御幸が佐山の背を押すように歩き出し、駅の方へと向かう。
「ここ、久しぶりだよな」
御幸のリクエストで、ふたりお気に入りの定食屋へ入った。ふたり掛けの席に向かい合って座る。佐山はメニューを見てもあまり食欲が湧かなかったが、御幸を心配させたくなくて、焼き魚定食を頼んだ。御幸はヒレカツ定食にビール。
「俺もちょっと、飲もうかな」
ビールを注文した御幸の声を聞いて、佐山も飲み物のメニューに視線を落とした。
「えーと……生搾りオレンジサワー」
「オレンジ多めでお願いします」
さり気なく御幸が付け足して、佐山は軽く肩を竦めた。御幸は困ったように笑っている。
「ま、飲みたい気分の時もあるよな」
いろいろなことに、聡い御幸は多分気がついているだろうが、何も言わないでいてくれた。そういう相手が自分にいることを、佐山は心底から感謝する。
すぐにやってきたビールとサワーで軽く乾杯して、佐山は久しぶりに、料理を美味いと思って口に運んだ。
秋口と一緒に入る店は、あんなに気に入っていた料理なのに、最近ではその味もほとんどわからなかったのだ。
会社でのできごとや些細な日常、秋口との会話と大差ないことを話しているのに、御幸の前で佐山は自分がずいぶんリラックスしていることに気づいた。
同時に、秋口といる時の自分が、どれほど無理をしているかにも気づいてしまう。あたりまえの態度を貫くことに神経をすり減らしているのだ。
「佐山、そろそろ酒やめとけよ。顔色やばいぞ」
甘い酒が変に美味くて、少しでやめておこうと思ったのに、いつの間にか佐山のグラスの中味は半分ほどに減っている。気づいた御幸がそう釘を刺したが、佐山は大丈夫大丈夫と笑ってまたひとくち酒を飲んだ。
「前にもちょっと飲んで、平気だったんだ」
そう言ってから、その時の酒は秋口と一緒に飲んだのだということを思い出して、喉が詰まるような感触を覚える。
美味い酒で、酔っぱらって、勢い余って秋口に好きだなんて本心を告げてしまった。
あのことさえなければ、秋口と自分はもう少しマシな関係でいられただろうか――そんなことを考えたくなくて、佐山はもうひとくち酒を飲む。
本当に大丈夫かよ、と呆れたような、心配げな御幸な声が聞こえて、笑い返したつもりが、そこから先の記憶がない。
◇◇◇
「ほら着いたぞ、起きろ、下りろ」
揺さぶっても、佐山は「うーん」と億劫げな生返事をするだけで動かない。御幸は仕方なく佐山の腕を肩にかけてタクシーを降りた。
佐山の体重は驚くほど軽かったが、しかし酔っ払いのぐにゃぐにゃした体を半ば担ぐようにマンションのエントランスに入るのは、結構な苦労だった。
「うー……」
いっそ負ぶってしまおうか、と御幸が思った時、佐山の体がずるりと床に崩れた。
「気持ち悪い……」
「あたりまえだ、馬鹿。飲めないくせにあんなに飲むから」
呆れてそう言い放ち、御幸はもう一度佐山の腕を引っ張り上げた。
あんなに、と言ってもサワーをグラスに一杯も飲んでいない。それでも元々下戸な佐山には過ぎる酒量だったのだ。頃合いを見て止めたつもりだったのに、佐山は珍しく何度もグラスを口に運んでいた。
「……まあ、飲まずにやってられないのか」
佐山には聞こえないほどの声で呟き、御幸は細い体を引き摺って、どうにか佐山の部屋まで辿り着いた。
「佐山、鍵」
「鞄……あれ、ポケット?」
のろのろした動きで佐山があちこちポケットを探っている。御幸は大きく溜息をついた。
「定期入れの中だろ」
御幸は勝手に佐山のポケットから定期入れを取り出し、中のポケットに収まっていた鍵で玄関のドアを開けた。
「ほら、靴脱いで、シャワー――は無理か、このまま寝ちまえ」
御幸の言葉に操られるように、佐山は覚束ない動きで靴を脱いで部屋に上がった。転ばないように御幸がその体を支えてやると、佐山がぐったり凭れてきた。
「……気持ち悪い……吐きそう」
「待て、トイレまで待て」
「……っ」
慌てて御幸があちこち見回すが、何も間に合わず、佐山が呻きながらその場にしゃがみ込んだ。
「……おまえ……マジかー……」
思わず御幸が天井を仰ぐ。佐山のみならず、御幸のスーツといい、廊下といい、吐瀉物まみれになってしまった。
「……ごめ……」
もう意識もあやふやらしい佐山が譫言のような声を洩らし、御幸は溜息混じりに佐山の上着をひき剥いだ。
「脱げ、もう。洗濯機と風呂借りるぞ、あと着替えも」
「うー……」
汚れた自分と佐山の服を取って、御幸は脱衣所の洗濯機にシャツを放り込んだ。戻ってきたら佐山が廊下に転がっている。取ってきたタオルで佐山の顔や首を拭ってやって、その口から寝息が漏れているのに呆れと同時に安堵する。新聞紙とタオルで床を掃除して、佐山を寝室に放り込んだ。
「ったく……」
相変わらず荒れ放題の部屋の中、苦悶の表情で眠っている佐山を見下ろし、御幸は渋い顔になった。
こんなふうに酔っぱらった佐山を見たのは久しぶりだ。営業時代は接待で飲めない酒を無理に飲まされては、影で散々吐いていたが、開発に移動してからは御幸が知る限り一滴も酒を口にしていない。
『前にもちょっと飲んで、平気だったんだ』
先刻、佐山が店でそう言った。佐山がひとりで酒を飲むはずがないから、誰と一緒にいる時にそんなことをしたのか、御幸は嫌でも察してしまった。
「……どう責任取るつもりだ」
呟いた時、床で携帯電話の着信音がした。佐山と一緒に御幸が放り投げた彼の携帯電話だ。
佐山を起こすべきか迷いながら御幸は電話に手を伸ばし、サブ画面に『秋口航』の名前を見つけ、さらに表情を険しくした。佐山を見ると、起きる気配はない。少しして留守番電話モードになり、電話が切れた。メッセージは残してないようだった。
「佐山の本日の営業終了」
ひとりごち、御幸は携帯電話の電源を切って床に戻した。何の用かは知らないが、何にせよ佐山のストレスになるようなことしか言わない気がするのだ。そんなもので佐山の眠りを邪魔させる気はない。
眠っている佐山を部屋に置いて、御幸は風呂場に向かった。シャツや靴下は洗濯中で、スーツも汚れを洗い流して濡れたまま。乾燥機はないから着て帰るものもない。今日は泊まりだ、と決めてシャワーを浴びた。
ついでについ掃除も始めてしまい、ようやく風呂から上がった時、玄関の方で物音がした。御幸は眉を顰めつつ、そういえば鍵をかけるのを忘れてしまったと気づく。ひとまずタオルを腰に巻いて、脱衣所から外に出た時、人影が廊下を横切って寝室の方へ向かうのが見えた。
「――秋口?」
寝室の入口で立ち竦んでいた秋口は、御幸に名前を呼ばれると、ひどく驚いたように振り返った。
「どうした、こんな遅くに」
すでに日付も変わろうとしている時間だ。御幸はさらに眉根を寄せ秋口を見遣る。
「御幸さんこそ……」
言いかけた言葉を飲み込むように、秋口が一度言葉を切り、御幸から視線を逸らした。寝室の佐山の方へ首を巡らせている。
「電話しても出ないし、チャイム鳴らしても反応ないから、中で倒れてでもいるんじゃないかと思って。そうしたら、鍵が開いてたから」
「ああ、すっかり寝てるんだろ。俺もシャワー浴びてて、チャイムが聞こえなかったし」
そう答えながら、御幸も佐山の方を見た。佐山は俯せになって、疲れた風情で眠っている。
体にはタオルケット一枚がかかっていたが、御幸が上着もシャツもスラックスも脱がせたから、まるでタオルケット以外は何も身にまとっていないようにも見える。
秋口は佐山からまた、御幸の方へ視線を戻した。御幸も濡れ髪にタオル一枚だ。
「……なるほどね」
口許を歪めて小さく嗤った秋口のことを、笑いもせず御幸は見返した。
「仲がいいとは思ってましたけど」
皮肉っぽく嗤う秋口の顔が、明かりもつけない部屋の暗さのせいだけではなく、青ざめて見える。御幸は黙ってその顔を見返した。
「こういうことか」
一瞬、秋口の胸ぐらを掴み上げたい気分になったが、御幸は即座にそれを押し殺し、代わりに笑い返した。
困ったような、気まずいような、照れたような、我ながら絶妙の笑顔だと感心した。
「会社の奴らには内緒、な」
「……」
秋口の表情から笑みが消える。
「……みずー……」
寝室の方から声が聞こえた。まだ酔いのまったく冷めていないような佐山の声だ。
「御幸ぃ、みーずー、みず……喉渇いたー……」
「はいはい、今持ってくから!」
「はーやーくー……」
間延びした、どこか安心して甘えたような響き。多分焦れてシーツの上を叩く音。佐山は酔うと少し子供みたいに我儘になる。
苦笑して、御幸は秋口に肩を竦めて見せた。
「そういうことで、立て込んでるんだ」
普段は先輩が相手でも生意気な態度を崩さず、女子社員を侍らせて悠然とした態度でいる秋口が、すっかり顔色を失くして険しい表情をしている。
それから、何も言わずに踵を返した。
「……へえ、このまま帰るのか」
御幸の呟きは届かないまま、玄関のドアが開き、閉まる音がした。御幸も玄関に向かい、鍵とチェーンをきっちり閉めてから、冷蔵庫のミネラルウォーターを取り出し、寝室に戻る。
佐山はまた眠ってしまったようだった。
サイドボードにペットボトルを置くと、御幸はベッドの端に腰を下ろした。やっぱり苦しそうな表情で眠っている佐山を見下ろし、苦笑気味に大きく息を吐いた。
「おまえが好きになったのは、またずいぶんと頭が悪いな」
つい呟いてしまった御幸に、佐山が小さな呻き声で応えた。
揺さぶっても、佐山は「うーん」と億劫げな生返事をするだけで動かない。御幸は仕方なく佐山の腕を肩にかけてタクシーを降りた。
佐山の体重は驚くほど軽かったが、しかし酔っ払いのぐにゃぐにゃした体を半ば担ぐようにマンションのエントランスに入るのは、結構な苦労だった。
「うー……」
いっそ負ぶってしまおうか、と御幸が思った時、佐山の体がずるりと床に崩れた。
「気持ち悪い……」
「あたりまえだ、馬鹿。飲めないくせにあんなに飲むから」
呆れてそう言い放ち、御幸はもう一度佐山の腕を引っ張り上げた。
あんなに、と言ってもサワーをグラスに一杯も飲んでいない。それでも元々下戸な佐山には過ぎる酒量だったのだ。頃合いを見て止めたつもりだったのに、佐山は珍しく何度もグラスを口に運んでいた。
「……まあ、飲まずにやってられないのか」
佐山には聞こえないほどの声で呟き、御幸は細い体を引き摺って、どうにか佐山の部屋まで辿り着いた。
「佐山、鍵」
「鞄……あれ、ポケット?」
のろのろした動きで佐山があちこちポケットを探っている。御幸は大きく溜息をついた。
「定期入れの中だろ」
御幸は勝手に佐山のポケットから定期入れを取り出し、中のポケットに収まっていた鍵で玄関のドアを開けた。
「ほら、靴脱いで、シャワー――は無理か、このまま寝ちまえ」
御幸の言葉に操られるように、佐山は覚束ない動きで靴を脱いで部屋に上がった。転ばないように御幸がその体を支えてやると、佐山がぐったり凭れてきた。
「……気持ち悪い……吐きそう」
「待て、トイレまで待て」
「……っ」
慌てて御幸があちこち見回すが、何も間に合わず、佐山が呻きながらその場にしゃがみ込んだ。
「……おまえ……マジかー……」
思わず御幸が天井を仰ぐ。佐山のみならず、御幸のスーツといい、廊下といい、吐瀉物まみれになってしまった。
「……ごめ……」
もう意識もあやふやらしい佐山が譫言のような声を洩らし、御幸は溜息混じりに佐山の上着をひき剥いだ。
「脱げ、もう。洗濯機と風呂借りるぞ、あと着替えも」
「うー……」
汚れた自分と佐山の服を取って、御幸は脱衣所の洗濯機にシャツを放り込んだ。戻ってきたら佐山が廊下に転がっている。取ってきたタオルで佐山の顔や首を拭ってやって、その口から寝息が漏れているのに呆れと同時に安堵する。新聞紙とタオルで床を掃除して、佐山を寝室に放り込んだ。
「ったく……」
相変わらず荒れ放題の部屋の中、苦悶の表情で眠っている佐山を見下ろし、御幸は渋い顔になった。
こんなふうに酔っぱらった佐山を見たのは久しぶりだ。営業時代は接待で飲めない酒を無理に飲まされては、影で散々吐いていたが、開発に移動してからは御幸が知る限り一滴も酒を口にしていない。
『前にもちょっと飲んで、平気だったんだ』
先刻、佐山が店でそう言った。佐山がひとりで酒を飲むはずがないから、誰と一緒にいる時にそんなことをしたのか、御幸は嫌でも察してしまった。
「……どう責任取るつもりだ」
呟いた時、床で携帯電話の着信音がした。佐山と一緒に御幸が放り投げた彼の携帯電話だ。
佐山を起こすべきか迷いながら御幸は電話に手を伸ばし、サブ画面に『秋口航』の名前を見つけ、さらに表情を険しくした。佐山を見ると、起きる気配はない。少しして留守番電話モードになり、電話が切れた。メッセージは残してないようだった。
「佐山の本日の営業終了」
ひとりごち、御幸は携帯電話の電源を切って床に戻した。何の用かは知らないが、何にせよ佐山のストレスになるようなことしか言わない気がするのだ。そんなもので佐山の眠りを邪魔させる気はない。
眠っている佐山を部屋に置いて、御幸は風呂場に向かった。シャツや靴下は洗濯中で、スーツも汚れを洗い流して濡れたまま。乾燥機はないから着て帰るものもない。今日は泊まりだ、と決めてシャワーを浴びた。
ついでについ掃除も始めてしまい、ようやく風呂から上がった時、玄関の方で物音がした。御幸は眉を顰めつつ、そういえば鍵をかけるのを忘れてしまったと気づく。ひとまずタオルを腰に巻いて、脱衣所から外に出た時、人影が廊下を横切って寝室の方へ向かうのが見えた。
「――秋口?」
寝室の入口で立ち竦んでいた秋口は、御幸に名前を呼ばれると、ひどく驚いたように振り返った。
「どうした、こんな遅くに」
すでに日付も変わろうとしている時間だ。御幸はさらに眉根を寄せ秋口を見遣る。
「御幸さんこそ……」
言いかけた言葉を飲み込むように、秋口が一度言葉を切り、御幸から視線を逸らした。寝室の佐山の方へ首を巡らせている。
「電話しても出ないし、チャイム鳴らしても反応ないから、中で倒れてでもいるんじゃないかと思って。そうしたら、鍵が開いてたから」
「ああ、すっかり寝てるんだろ。俺もシャワー浴びてて、チャイムが聞こえなかったし」
そう答えながら、御幸も佐山の方を見た。佐山は俯せになって、疲れた風情で眠っている。
体にはタオルケット一枚がかかっていたが、御幸が上着もシャツもスラックスも脱がせたから、まるでタオルケット以外は何も身にまとっていないようにも見える。
秋口は佐山からまた、御幸の方へ視線を戻した。御幸も濡れ髪にタオル一枚だ。
「……なるほどね」
口許を歪めて小さく嗤った秋口のことを、笑いもせず御幸は見返した。
「仲がいいとは思ってましたけど」
皮肉っぽく嗤う秋口の顔が、明かりもつけない部屋の暗さのせいだけではなく、青ざめて見える。御幸は黙ってその顔を見返した。
「こういうことか」
一瞬、秋口の胸ぐらを掴み上げたい気分になったが、御幸は即座にそれを押し殺し、代わりに笑い返した。
困ったような、気まずいような、照れたような、我ながら絶妙の笑顔だと感心した。
「会社の奴らには内緒、な」
「……」
秋口の表情から笑みが消える。
「……みずー……」
寝室の方から声が聞こえた。まだ酔いのまったく冷めていないような佐山の声だ。
「御幸ぃ、みーずー、みず……喉渇いたー……」
「はいはい、今持ってくから!」
「はーやーくー……」
間延びした、どこか安心して甘えたような響き。多分焦れてシーツの上を叩く音。佐山は酔うと少し子供みたいに我儘になる。
苦笑して、御幸は秋口に肩を竦めて見せた。
「そういうことで、立て込んでるんだ」
普段は先輩が相手でも生意気な態度を崩さず、女子社員を侍らせて悠然とした態度でいる秋口が、すっかり顔色を失くして険しい表情をしている。
それから、何も言わずに踵を返した。
「……へえ、このまま帰るのか」
御幸の呟きは届かないまま、玄関のドアが開き、閉まる音がした。御幸も玄関に向かい、鍵とチェーンをきっちり閉めてから、冷蔵庫のミネラルウォーターを取り出し、寝室に戻る。
佐山はまた眠ってしまったようだった。
サイドボードにペットボトルを置くと、御幸はベッドの端に腰を下ろした。やっぱり苦しそうな表情で眠っている佐山を見下ろし、苦笑気味に大きく息を吐いた。
「おまえが好きになったのは、またずいぶんと頭が悪いな」
つい呟いてしまった御幸に、佐山が小さな呻き声で応えた。
◇◇◇
「すみませんけど、やっぱり、男なんかより女といる方がよっぽど楽しいんで」
お愛想だけの、本当はちっとも楽しくも嬉しくもないんだとわかる――出会った最初の頃みたいな笑顔でそう言った秋口の隣には、小柄で柔らかそうな女性がいた。
彼女は秋口に甘えるようにしなだれかかり、秋口の手はあたりまえのようにその腰を抱いている。
それじゃ、と言って秋口が踵を返す。あっさりと自分に背を向ける。
待ってくれ、と言いたかったのに、その後に何と言葉を続けていいのか思いつかず、秋口の名前を呼ぶことももうできない。
喉が詰まったように息ができない。
体はなまりのように重たくて、腕一本、指先ひとつ思うように動かせない。
どうせもう、秋口の背中は手を伸ばしても届かないところへ遠ざかってしまったけれど――、
「……ッ」
大きく息を吸い込んだ刹那、目が覚めた。
吸い込んだ息を吐き出すのも忘れ、佐山は全身を強張らせて、視界に入った天井を見開いた目で見上げる。
心臓が異常なくらい早鐘を打っていた。全身に嫌な汗が伝っているのがわかる。
怖くて、怖くて、今のは夢だったともうわかっているのに、まだあの場面の続きにいるみたいに、身じろぎひとつできない。
ようやく自分が呼吸を忘れていたことに思い至り、もう一度息を吸い込もうとしたら、妙な具合に喉が鳴った。
自分でその音に驚いた瞬間、ぼろぼろと、両目から大粒の涙が流れ落ちてきた。
「……っ……ん……」
声を上げて泣いてしまいそうになり、急いで歯を食いしばって両目を掌で押さえた時、隣で誰かが身じろぎする気配がした。
「……佐山?」
御幸の声だった。狭いベッドの隣に眠っているのは、誰より信頼している友人。なぜ彼がここにいるのか思い出せないまま、佐山は彼に心配をかけてはならないと、ますます力を入れて歯を食いしばった。
御幸は佐山のそんな様子に気づいて、起き上がると、そっと佐山の腕に触れる。
「どうした? 具合が悪いのか?」
「……」
佐山は答えられなくて、ただ首を横に振った。
「ちょっと待ってろ、水持ってくるから」
言葉が出ないほど体調が悪いのだと判断したらしく、ベッドを下りようとする御幸のシャツを、佐山は咄嗟に掴んだ。
「違……嫌な夢、見て」
切れ切れの、みっともない涙声で言った佐山を御幸が驚いたように見下ろし、それから、ベッドに腰を下ろし直した。ベッドサイドのテーブルからティッシュを取って、佐山に渡してくれる。
佐山はティッシュを受け取って、涙ですっかりぐしゃぐしゃになった顔を拭った。薄くて柔らかい紙は、あっという間にびしょ濡れになってしまった。
「悪い夢は、人に話すと嘘になるってさ」
また何枚かティッシュを取ってやりながら、御幸が優しく佐山にそう言った。
佐山はやっぱり途切れ途切れの、多分聞いている御幸は半分もまともに聞き取れないだろう泣きじゃくった声で、見た夢のことを話した。
終いには佐山自身も自分が何を言っているのかわからなくなって、ただ感情に任せて泣きじゃくった。
気づいたら御幸がいなくなっていて、さすがに呆れて帰ってしまったのかと思っていたら、キッチンから物音がしていた。重たい体を佐山がベッドから起こした時、両手にマグカップを持った御幸が寝室に戻ってきた。
「何で鍋が本棚に入ってたかっていう件はあとで話すとして」
湯気の立つマグカップの中身は、どうやらホットミルクのようだった。
「ほら」
差し出されたカップを受け取り、佐山はそれに口を付けた。ミルクはほどよい温度で、猫舌の佐山もすぐに飲めるくらいだった。
御幸もベッドに座り、こちらは多分コーヒーを飲んでいる。
何も言わない御幸の隣で佐山も黙ってミルクを飲み、それが半分くらいに減った時、ようやく佐山の頭の中に現実感が戻ってきた。カーテンの向こうの窓は明るいが、まだずいぶんと早い時間のように思えた。時計を見ると午前五時。やっぱり出社のために起きるには早い。
「……ごめんな、驚いただろ」
大きくゆっくり息を吐き出してから、佐山は隣の御幸に言った。ミルクを飲んだおかげか、多少掠れはしていたものの、佐山の声はそんなにひどいものではなくなっていた。
「この歳になって、こんなふうにわあわあ声出して泣くなんて……」
「歳はまあ、関係ないだろ」
恥じ入る佐山を、御幸が苦笑気味に見遣る。
「よっぽど気持ちが追い詰められてたんだな、おまえ」
「……自分でそうしようと思ってやってることだし、人に泣きごと言うつもりなんかなかったんだけど……」
「俺がいる時でよかったよ。ひとりであんなふうに泣いてるところ、考えるだけでおっかない」
御幸は軽口のようにそう言ったが、佐山には口調に反して御幸が本当に自分のことを心配しているのだとわかってしまって、申し訳ない気分になった。
「溜め込んでひとりで泣くくらいなら、俺に話せよ。その方が俺には親切だから」
「……うん。ありがとう」
笑った佐山に、御幸もほっとしたように息を吐いた。
「もう大丈夫、泣いたらすっきりした」
強がりではなく本音の部分で、佐山はそう思った。
ここのところ、秋口の前で平静でいよう、みっともないところを見せないでおこうと気を張っていて、気分が休む間もなかった。考え込んでしまえば深みにはまりそうだから、いろいろと見ないふりでやってきたけれど、知らないうちに体中を澱のようなものが包んでいたようだ。
泣き喚いたら、少し頭がクリアになった。
「……本当に、ひどいことばっかり起きてると思うんだけどさ」
温くなったミルクのカップで掌を温めながら、佐山はぽつりと呟いた。
「ものすごく傷つくたび割と投げ出したくもなるんだけど、でもじゃあどうして自分がこんなにまで傷ついてるのかっていうのを考えると……」
「やっぱり、好きだなって?」
佐山の台詞の続きを受け取り、御幸が言った。佐山は小さく頷く。
「限界までは頑張ろうって思う。まだ多分大丈夫」
佐山の傍らで、御幸がかすかに溜息をつく。
「焚きつけたのは俺だけどさ。佐山は我慢強いから心配になるんだよ。普通の奴ならもうとっくに投げ出してる」
「我慢強いっていうか……鈍感なのかもなあ」
カップを手にしたままベッドの上で膝を抱え、佐山は少し笑った。
御幸が困ったような顔になる。
「もっとひどいことがある、もっと辛いことがある、それでもいつか変わることがある。そう考えると、大丈夫だって気がしてくるんだ」
「でもな、佐山、理不尽なことは大きい小さいにかかわらず理不尽であるってことに変わりはないんだぞ?」
「少なくとも今の状況を選んでるのは俺だよ」
「……」
「昔はさ、誰かが助けてくれるまで自分ではどうすることもできなかったし……何もしないってことを選んでたのかもしれないけど、もしかしたら」
ずっと以前に、一番好きだった人と、時間が止まったような場所でふたりきりだったことがある。
それはお世辞にも恵まれた状況とは言えず、事情を聞けば誰もが顔をしかめ、泣き出してしまうようなひどい時間だったのかもしれない。佐山自身はもうおぼろげにしか覚えていなかった。覚えていられなかったのか、思い出すことができないのか、その両方なのか。
ただいつも、誰かに助けて欲しいと、ここから抜け出したいと願っていた。けれどもそうすることで、自分が誰よりも愛している人を壊してしまうとわかっていたから、何もできずにいた。
結局その長い時間は、外からの救いの手で終わることになった。
佐山は何ひとつ自分で動くこともできないまま。
「あの時とは違うだろ、今は。俺が逃げたとしても誰を傷つけることもないし、不幸にすることもないし、だから限界が来たら尻尾巻いて逃げ出すよ。俺だって進んで痛い目見たいわけじゃないんだから」
明るく言った佐山に、御幸も何とも言えない表情で笑い返した。
「もし俺か佐山が女だったり、もし俺が佐山のこと男として好きだったら、秋口なんかに渡さないんだけどなあ」
「何だそれ」
「せめて逃げ込む場にくらいならせてくれよ。おまえはもうひとりじゃないし、おまえに何かあれば俺も、それに佐山の家の人たちも心配するんだからな」
「――うん」
自分ひとりで抱え込んでいた気分だったものが、御幸の言葉のおかげで少し楽になった。
それで、何となく笑ってしまう。笑った佐山の顔を、御幸が怪訝そうに覗き込んでいる。
「どうした?」
「いや。何だか出口のないどうしようもない場所に入り込んだ気分だったけど、案外、周りが見えてなかっただけなのかなってさ。考えたらおかしくなっただけ、のめり込むタチでもないつもりだったのに、案外思い込みが激しい自分にびっくりしたっていうか」
「周りが見えてないのは、おまえだけじゃないかもしれないけどな」
「え?」
首を傾げた佐山に、御幸が「何でもない」と笑い返した。
結局ふたりとも寝直す気にはなれず、出社までの間のんびり佐山の部屋で過ごした。
お愛想だけの、本当はちっとも楽しくも嬉しくもないんだとわかる――出会った最初の頃みたいな笑顔でそう言った秋口の隣には、小柄で柔らかそうな女性がいた。
彼女は秋口に甘えるようにしなだれかかり、秋口の手はあたりまえのようにその腰を抱いている。
それじゃ、と言って秋口が踵を返す。あっさりと自分に背を向ける。
待ってくれ、と言いたかったのに、その後に何と言葉を続けていいのか思いつかず、秋口の名前を呼ぶことももうできない。
喉が詰まったように息ができない。
体はなまりのように重たくて、腕一本、指先ひとつ思うように動かせない。
どうせもう、秋口の背中は手を伸ばしても届かないところへ遠ざかってしまったけれど――、
「……ッ」
大きく息を吸い込んだ刹那、目が覚めた。
吸い込んだ息を吐き出すのも忘れ、佐山は全身を強張らせて、視界に入った天井を見開いた目で見上げる。
心臓が異常なくらい早鐘を打っていた。全身に嫌な汗が伝っているのがわかる。
怖くて、怖くて、今のは夢だったともうわかっているのに、まだあの場面の続きにいるみたいに、身じろぎひとつできない。
ようやく自分が呼吸を忘れていたことに思い至り、もう一度息を吸い込もうとしたら、妙な具合に喉が鳴った。
自分でその音に驚いた瞬間、ぼろぼろと、両目から大粒の涙が流れ落ちてきた。
「……っ……ん……」
声を上げて泣いてしまいそうになり、急いで歯を食いしばって両目を掌で押さえた時、隣で誰かが身じろぎする気配がした。
「……佐山?」
御幸の声だった。狭いベッドの隣に眠っているのは、誰より信頼している友人。なぜ彼がここにいるのか思い出せないまま、佐山は彼に心配をかけてはならないと、ますます力を入れて歯を食いしばった。
御幸は佐山のそんな様子に気づいて、起き上がると、そっと佐山の腕に触れる。
「どうした? 具合が悪いのか?」
「……」
佐山は答えられなくて、ただ首を横に振った。
「ちょっと待ってろ、水持ってくるから」
言葉が出ないほど体調が悪いのだと判断したらしく、ベッドを下りようとする御幸のシャツを、佐山は咄嗟に掴んだ。
「違……嫌な夢、見て」
切れ切れの、みっともない涙声で言った佐山を御幸が驚いたように見下ろし、それから、ベッドに腰を下ろし直した。ベッドサイドのテーブルからティッシュを取って、佐山に渡してくれる。
佐山はティッシュを受け取って、涙ですっかりぐしゃぐしゃになった顔を拭った。薄くて柔らかい紙は、あっという間にびしょ濡れになってしまった。
「悪い夢は、人に話すと嘘になるってさ」
また何枚かティッシュを取ってやりながら、御幸が優しく佐山にそう言った。
佐山はやっぱり途切れ途切れの、多分聞いている御幸は半分もまともに聞き取れないだろう泣きじゃくった声で、見た夢のことを話した。
終いには佐山自身も自分が何を言っているのかわからなくなって、ただ感情に任せて泣きじゃくった。
気づいたら御幸がいなくなっていて、さすがに呆れて帰ってしまったのかと思っていたら、キッチンから物音がしていた。重たい体を佐山がベッドから起こした時、両手にマグカップを持った御幸が寝室に戻ってきた。
「何で鍋が本棚に入ってたかっていう件はあとで話すとして」
湯気の立つマグカップの中身は、どうやらホットミルクのようだった。
「ほら」
差し出されたカップを受け取り、佐山はそれに口を付けた。ミルクはほどよい温度で、猫舌の佐山もすぐに飲めるくらいだった。
御幸もベッドに座り、こちらは多分コーヒーを飲んでいる。
何も言わない御幸の隣で佐山も黙ってミルクを飲み、それが半分くらいに減った時、ようやく佐山の頭の中に現実感が戻ってきた。カーテンの向こうの窓は明るいが、まだずいぶんと早い時間のように思えた。時計を見ると午前五時。やっぱり出社のために起きるには早い。
「……ごめんな、驚いただろ」
大きくゆっくり息を吐き出してから、佐山は隣の御幸に言った。ミルクを飲んだおかげか、多少掠れはしていたものの、佐山の声はそんなにひどいものではなくなっていた。
「この歳になって、こんなふうにわあわあ声出して泣くなんて……」
「歳はまあ、関係ないだろ」
恥じ入る佐山を、御幸が苦笑気味に見遣る。
「よっぽど気持ちが追い詰められてたんだな、おまえ」
「……自分でそうしようと思ってやってることだし、人に泣きごと言うつもりなんかなかったんだけど……」
「俺がいる時でよかったよ。ひとりであんなふうに泣いてるところ、考えるだけでおっかない」
御幸は軽口のようにそう言ったが、佐山には口調に反して御幸が本当に自分のことを心配しているのだとわかってしまって、申し訳ない気分になった。
「溜め込んでひとりで泣くくらいなら、俺に話せよ。その方が俺には親切だから」
「……うん。ありがとう」
笑った佐山に、御幸もほっとしたように息を吐いた。
「もう大丈夫、泣いたらすっきりした」
強がりではなく本音の部分で、佐山はそう思った。
ここのところ、秋口の前で平静でいよう、みっともないところを見せないでおこうと気を張っていて、気分が休む間もなかった。考え込んでしまえば深みにはまりそうだから、いろいろと見ないふりでやってきたけれど、知らないうちに体中を澱のようなものが包んでいたようだ。
泣き喚いたら、少し頭がクリアになった。
「……本当に、ひどいことばっかり起きてると思うんだけどさ」
温くなったミルクのカップで掌を温めながら、佐山はぽつりと呟いた。
「ものすごく傷つくたび割と投げ出したくもなるんだけど、でもじゃあどうして自分がこんなにまで傷ついてるのかっていうのを考えると……」
「やっぱり、好きだなって?」
佐山の台詞の続きを受け取り、御幸が言った。佐山は小さく頷く。
「限界までは頑張ろうって思う。まだ多分大丈夫」
佐山の傍らで、御幸がかすかに溜息をつく。
「焚きつけたのは俺だけどさ。佐山は我慢強いから心配になるんだよ。普通の奴ならもうとっくに投げ出してる」
「我慢強いっていうか……鈍感なのかもなあ」
カップを手にしたままベッドの上で膝を抱え、佐山は少し笑った。
御幸が困ったような顔になる。
「もっとひどいことがある、もっと辛いことがある、それでもいつか変わることがある。そう考えると、大丈夫だって気がしてくるんだ」
「でもな、佐山、理不尽なことは大きい小さいにかかわらず理不尽であるってことに変わりはないんだぞ?」
「少なくとも今の状況を選んでるのは俺だよ」
「……」
「昔はさ、誰かが助けてくれるまで自分ではどうすることもできなかったし……何もしないってことを選んでたのかもしれないけど、もしかしたら」
ずっと以前に、一番好きだった人と、時間が止まったような場所でふたりきりだったことがある。
それはお世辞にも恵まれた状況とは言えず、事情を聞けば誰もが顔をしかめ、泣き出してしまうようなひどい時間だったのかもしれない。佐山自身はもうおぼろげにしか覚えていなかった。覚えていられなかったのか、思い出すことができないのか、その両方なのか。
ただいつも、誰かに助けて欲しいと、ここから抜け出したいと願っていた。けれどもそうすることで、自分が誰よりも愛している人を壊してしまうとわかっていたから、何もできずにいた。
結局その長い時間は、外からの救いの手で終わることになった。
佐山は何ひとつ自分で動くこともできないまま。
「あの時とは違うだろ、今は。俺が逃げたとしても誰を傷つけることもないし、不幸にすることもないし、だから限界が来たら尻尾巻いて逃げ出すよ。俺だって進んで痛い目見たいわけじゃないんだから」
明るく言った佐山に、御幸も何とも言えない表情で笑い返した。
「もし俺か佐山が女だったり、もし俺が佐山のこと男として好きだったら、秋口なんかに渡さないんだけどなあ」
「何だそれ」
「せめて逃げ込む場にくらいならせてくれよ。おまえはもうひとりじゃないし、おまえに何かあれば俺も、それに佐山の家の人たちも心配するんだからな」
「――うん」
自分ひとりで抱え込んでいた気分だったものが、御幸の言葉のおかげで少し楽になった。
それで、何となく笑ってしまう。笑った佐山の顔を、御幸が怪訝そうに覗き込んでいる。
「どうした?」
「いや。何だか出口のないどうしようもない場所に入り込んだ気分だったけど、案外、周りが見えてなかっただけなのかなってさ。考えたらおかしくなっただけ、のめり込むタチでもないつもりだったのに、案外思い込みが激しい自分にびっくりしたっていうか」
「周りが見えてないのは、おまえだけじゃないかもしれないけどな」
「え?」
首を傾げた佐山に、御幸が「何でもない」と笑い返した。
結局ふたりとも寝直す気にはなれず、出社までの間のんびり佐山の部屋で過ごした。
◇◇◇
泣きすぎた目は何となく腫れぼったくて痛かったし、宿酔いのせいで頭は痛いし、胃はムカムカするしで体調は最悪だったが、御幸と話してすっきりしたおかげか、佐山はそう億劫な気分でもなく会社に向かった。一緒に出社した御幸と、途中でコンビニに寄って、一緒にドリンク剤を飲んだのも効いたらしい。
「それじゃ、へばらない程度に頑張れよ」
それぞれの部署に向かう別れ際、御幸がそう言って佐山の背中を叩いた。それが仕事に対する言葉なのか、それともそれ以外のことに対する言葉なのか、判断はつかなかったが、佐山は何となくありがたい気分で頷きを返した。
午前中、胃薬で何とか吐き気を堪えながら仕事をしていると、携帯電話がメールの着信音を鳴らした。
(――あれ)
差出人は秋口だった。いつもなら午後、仕事の終わる目処がついた頃に連絡が来るのに、こんな早い時間にメールが来るなんて珍しい。
何となく緊張しながら本文を読んで、佐山はまた「あれ?」と思った。
『昼休み、資材倉庫で』
「……」
資材倉庫、という文字を見て、ますます佐山は緊張する。ここのところまったく足を踏み入れていない場所だ。
『了解』
短く返事を打ち、佐山は落ち着かない気分で午前中の仕事をすませ、昼休みになると言われたとおり資材倉庫へ向かった。
人目を忍んで中に入り、まだ秋口が現れていないことをたしかめるとほっと息を吐いて、目についた椅子に腰を下ろす。ドリンク剤の効果も午前中までだったのか、胃もたれがひどくなった感じで、気分が悪い。よっぽど酒量が過ぎていたのか、ゆうべの話になると御幸もさすがに呆れた顔で『無茶な飲み方はするなよ』と釘を刺してきた。
鈍く痛む頭を抱えながら、水でも飲んでくればよかったと後悔した時、外からドアが開く気配がした。佐山が顔を上げると、薄暗い部屋の中に、秋口が現れるところだった。
佐山はどう挨拶をするべきか考えあぐね、そんなことすらいちいち考えなくては反応できない状況に何となく気鬱になりながら、それでも秋口に笑いかける。秋口はそれを無視して、黙ったままドアを閉めた。
「ええと……何か、話とか」
会社で、就業時間中にわざわざ自分を呼び出したのだから、何も世間話をするなどという用事ではないだろう。
――もしかしたら、もう二度と会わないとか、そんなことを告げられるのかとメールを受け取った時から佐山は怯えていた。だが秋口の性格上、そのつもりだったらいちいち断ることもなく、ただ自然に誘われることがなくなるだけだろうと察して、気持ちを宥めた。
あまり慰めにはならない気もしたが。
「……ゆうべ」
「え?」
切り出した秋口の言葉は、変に歯切れが悪かったのでよく聞き取れず、佐山は彼を見上げて首を傾げた。秋口はドアのところに突っ立ったまま、少し離れた場所で椅子に座る佐山のことを見下ろしている。
「……誰かと夜、でかけたんですか」
「ああ……うん、御幸とメシ喰いに。行ったけど」
これは世間話なのか、意味のある質問なのか、わからないまま佐山は正直に答えた。そもそも嘘をつく場面でもない。
「それで、御幸さんは佐山さんの家に泊まって?」
「うん、あれ、よく知ってるな」
少し驚いて佐山がそう答えると、秋口は奇妙な顔で佐山のことを見返した。何か苦いものを口の中で味わっているような表情だった。
「今朝は一緒に来たよ、営業が続けて同じネクタイだと都合が悪いっていうんで、俺の勝手に持っていって――」
部屋の中の空気が思い。それをどうにかしたくて、佐山は馬鹿みたいに明るく話した。
秋口はにこりともせず、ますます苦い表情になるだけだった。
「……って、オチとか別に、ないんだけど……」
「あんたは、俺が他の女とでかけてんの知ってるんだろ」
「は?」
気まずく語尾を濁す佐山に、まったく無視する調子で秋口が質問を被せ、佐山はそれもやっぱりうまく聞き取れずに眉根を寄せた。
「俺があんたと会ってない日に、他の女と寝てるのを知ってるんだろって聞いてるんだよ」
「……」
やっぱり、別れ話か。
そう思ってから、そもそもつき合ってもいないことに思い至って、佐山は頭痛と胃痛がひどくなった。
(何でいまさら、こんな話するんだか……)
以前にしたひどい会話を思い出す。自分は秋口が他の女と会っていることを責めるような口調になって、秋口はそんなことを口にするなと切り捨てた。
どうして同じ会話を今秋口が繰り返そうとするのか、佐山は混乱してしまう。
御幸のおかげで晴れた靄が、ふたたび頭の中を覆いだすような感触。
(……試されてるのか)
自分がそのことを責めたり、何か言えば、今すぐにでも『捨てる』とか。
そういう脅しなのかもしれない。
「知ってるけど」
努めて平静を装って、佐山は秋口にそう答えた。
「それが?」
「それで、あんたは何とも思わないのか?」
「何ともって……」
誘導尋問にあっている気がする。引っかからないように、佐山は細心の注意を払った。
「思わないよ、そんなの。別に、男が好き……ってわけじゃなければ、秋口だっていい歳した大人なわけだし、女の子とそういうことがあって当然だろ」
「……」
「秋口くらい色男なら、誘いだってひっきりなしだろうし、俺なんかと一緒にいて時間潰したりしたら、秋口のこと好きな女の子たちに恨まれるとか」
軽口のように、明るく笑って言った佐山は、自分を見下ろす秋口の目がひどく冷たいことに気づいた。
「……御幸にも、言われたし」
尻窄みでそうつけ足した後は、何だか秋口の顔を見ていられず、佐山はつい俯いてしまった。
どうしてか、理由をつけてこの場から逃げ出したい気分で一杯になる。
好きな相手と一応密室で一緒にいるというのに、まったく心が弾まない。
「あの、話がそれだけなら、昼まだだし」
俯いたまま、早口でそう言って佐山は椅子から立ち上がった。外に出たかったのに秋口はドアの前から退いてくれず、さらに佐山の動きを阻むように、腕を掴んで来る。
「……あきぐ」
近づいてくる秋口の体にどうしてか身が竦み、佐山は呼びかけた名前を飲み込み、咄嗟にその腕を振り払った。
秋口が振り払われた自分の腕を見て、それから視線を佐山の姿へ移す。
何の感情も読み取れない秋口の無表情に、佐山はやっぱり体が竦んだ。
怯えたように後退さる佐山を見て、秋口がふと微笑む。
「どうして嫌がるんですか」
「どうして……って……」
今の秋口を見て、怯えない人間がいるとは佐山には思えなかった。表情は笑っているのに、眼差しが剣呑だ。
「こんなの、何度もやったでしょう?」
もう一度、秋口が先刻よりも乱暴に佐山の腕を掴んだ。
強引な力で秋口の方へ引き寄せられて、佐山はよろめくように、その体に体重を預ける格好になる。体勢を立て直す間もなく顎を掴まれ、上向かされて、目を閉じる間もなくキスされた。
自分が凭れていては重たいのでは、とただそれだけの理由で、佐山は両手で秋口の胸を押した。
「だから、どうして」
佐山に押し退けられた秋口が、苛立ったように声を上げる。
「嫌がるんだよ、今さら初めてってわけでもあるまいし」
「痛ッ、何、秋口」
掴まれたままの腕を引かれ、佐山はやはり乱暴な動きで資材倉庫のドアに背中を押しつけられた。
「押さえてろ、人が来たら困るだろ」
「え……」
相変わらず倉庫の鍵は壊れっぱなしだ。
戸惑う佐山にはお構いなしに、秋口が再び唇を重ねてくる。佐山は押さえつけられて痛む肩に眉を顰めながら、それでもおとなしく目を閉じて秋口に従った。条件反射のようなもの。触れられるのは久々だったのに、秋口にそうされれば、佐山は自然と応えようとしてしまう。
秋口は性急な仕種で佐山の上着のボタンを外し、ネクタイを緩めた。
佐山は秋口が何のつもりでこんなことをしているのかが読めなくて、困惑しながら、されるままになっている。
「ん……」
口腔を深く舌で探られながら、指先できつく胸の先を摘まれ、佐山は痛みのせいか快感のせいかわからない呻き声を喉から漏らした。
秋口の動きは本当に性急だった。キスをしながら佐山の胸や脇腹を探った後、もうズボンのベルトに触れている。すぐにベルトもボタンも外して、片手を佐山の下着の中に差し入れてきた。
自分だけ翻弄されるのが嫌で、佐山も秋口の方へ手を伸ばしたが、それを片手で遮られてしまった。
「……?」
「今日は、いいですよ。しなくても」
不思議そうに手を見下ろす佐山から唇を離し、微かに乱れた呼吸で秋口が言った。その声の艶っぽさに佐山は思わず背筋を震わせる。秋口は佐山がまだ触れてもいないのに、欲情して目を潤ませていた。それに気づいて佐山の気分と体も煽られた。再び沸き上がった震えを堪えようとしたタイミングで、秋口の掌が佐山の性器をきつく握り、擦り上げる。濡れた声が零れそうになって、佐山は咄嗟に唇を噛んだ。
「これじゃ、すぐいっちゃいますね」
少し力を緩め、秋口がやんわりした動きに変えて佐山の中心を掌で弄び出す。
佐山は目許を赤くして、羞恥を堪えながら、秋口が与えてくれるだろう絶頂を待った。
「でも今日は、これで終わられたら困るから」
ひとりごとのように秋口がそう言って、その意味を佐山が問い返す間もなく、指先で佐山自身の先端を擦った。滲み出している先走りの体液を指先に絡めながら、反対の手で佐山の下衣を下着ごと押し下げている。
「足、抜いて」
絡まってうまく脱げない服に焦れたように、秋口が佐山の耳許で命令した。耳許で鳴っているかのような大きな心音を持て余しながら、佐山は秋口のことを見返した。
「……秋口……」
相手の意図を察してしまって、佐山は心許ない声を漏らした。
「待ってくれ……ここで、最後まで?」
「嫌なんですか」
思い遣って訊ねる調子とは真逆の声音で、秋口が笑ってそう言う。
「場所が問題? ちゃんと綺麗なベッドがいいとか」
「いや……そういうわけでも……」
問題はそこじゃない気がしたが、佐山にはうまく答えられなかった。
優しくもない顔で笑いながら、弄ぶみたいに秋口に触れられるのが嫌だとか、そんなことを口にはできない。
(まるで優しくしてくれって縋ってるみたいだ)
「じゃあ気分の問題?」
訊ねながら、秋口ははなから佐山の答えの内容に頓着するつもりはないようで、強引に佐山のスラックスも下着も脚の半ばまで押し下げてしまった。そのまま佐山の片脚を服から引き抜き、佐山の先走りで濡れた指先を下肢の間に押し入れて来る。
「……ッ」
迷う様子もなく秋口の指先が佐山の一番奥を探り出し、周辺をなぞった。指が中へ入ってくる感触に、佐山は体を強張らせた。
「もっと足、開けませんか」
やはり優しさや甘さからほど遠い声で秋口が言う。佐山が身動きできずにいると、秋口が小さく舌打ちして一度指を抜き出し、佐山の肩を押して体の向きを変えさせた。ドアに縋るような格好を取らされ、佐山はますます身を固くする。
佐山が逃げ出したい気分になるのは、行為に抵抗があるわけでもなく、秋口が身にまとう冷たさが悲しかったせいだ。
「やっぱり濡れないのか」
佐山の最奥の辺りを再び指先で触れながら、秋口がひとりごとのように呟いた。佐山の胸が締めつけられたように痛くなる。自分の体は女とは違う。反応が違っていて当然だ。
「持ってきてよかった」
これも誰に聞かせるでもない言葉だったが、佐山はつられるように秋口の方を振り返り、その手に小振りで細長いプラスチックの容器をみつける。
「……何……」
「薬局で売ってたローション。女用だけど、別に男に使っちゃいけないわけじゃないだろうし」
「……」
佐山は言葉を失って、今からでもこの場を逃げ出した方がいいのだろうかとぼんやり考えた。
逡巡しているうち、濡れた手が内腿に触れる。咄嗟に逃げだそうとする佐山の体を秋口の片手が押さえつけ、佐山は冷たく濡れた感触が体の中に滑り込むのを感じた。
「ぁ……ッ」
秋口の指先は容赦なく佐山の中へと潜り込んできた。ゆっくり体の中を掻き回される未知の感触に、佐山はドアに縋ることしかできなくなる。痛みよりも違和感が強い。こんな行為が快楽に繋がるなんて理解できなかった。濡れた感触と音が佐山を落ち着かなくさせる。
「力、入れないで下さいよ。動かし辛い」
囁く秋口の声音はどこか佐山をからかうようなものにも聞こえた。佐山は泣きたい気分でどうにか体に籠もってしまう力を抜こうと試みるが、徒労に終わった。緊張でどうしても体が強張ってしまう。
「あ……きぐち、ごめん、まだ無理……」
ただお互いの手や口で体を愛撫しあうだけの行為と、これは確実に一線を画すやり方だ。秋口と触れ合うようになってから、こういう事態を佐山が想像しなかったわけではないが、実際こんな状態になってみて感じるのは手ひどい拒否感だった。指だけだって受け入れることがこんなに不自然な感触なのに、これ以上のことなんて想像もつかない。
「どうして?」
止めることもなく指を動かし続けながら優しく問いかける秋口の声が、上っ面だけのものだなんてわかっていたのに、佐山はそれでもその優しさに縋りたくなった。
「きゅ……急に、全部は」
「御幸さんとは平気なのに?」
「……え……、……ッ」
ぐっと、さらに奥までねじ込まれた秋口の指が、中で動いて内壁を擦る。佐山は顔を歪めて声を押し殺した。
「御幸さんとは、したんでしょう? 昨日」
「んっ、……みゆ……、何……?」
濡れた音を立てて、秋口が佐山の中で指を出し入れしている。速さを増す動きに思考まで掻き乱されたように、佐山はうまく秋口の言葉について考えることができない。
――考えたくなかったのかもしれない。
「そりゃ、俺が他の女と寝てることとやかく言うわけがないよな。あんただって、他の男とこういうことしてるんだから」
「……っ……あ……ッ」
荒っぽく指が引き抜かれ、震えて頽れそうになる佐山の体は秋口の腕に抱え込まれて無理矢理に立たされた。薄い尻の肉を掴んで押し広げられる。さっきまで指でさんざんに掻き回された場所に、今度は別の、もっと大きな熱の塊が押し当てられた。
「秋……ッ」
嫌だ、と言おうとしたのかもしれない。自分でも何を言うつもりかわからなかった佐山の声は一瞬呼吸と共に飲み込まれ、喉で押し殺した悲鳴になった。
「……ッ……く……、……ん」
ねじ込まれる熱に、悲鳴すらうまく音にならない。
咳き込むように喘ぐ佐山の苦痛にはお構いなしに、秋口は強引に身を進めた。逃げようとする佐山の腰を抱え込み、その中に自分自身を押し込む。
あとはもう、佐山にはわけがわからなくなった。体の中を押し広げられ、熱いものが内壁を擦っている。痛いのか熱いのか苦しいのか、誰がこんな感触を自分に与えているのか、
(秋口)
佐山はただその存在だけに心で縋った。秋口がそう望んでしていることだと、辛くはないと、ぐちゃぐちゃになった頭の中で必死に思う。
到底気持ちが繋がっているだなんて思えないのに、体だけ無理矢理に繋げられる苦痛と惨めさをやり過ごそうとする。
秋口に強い力で体の中を貫かれ、途中から佐山は何も考えられなくなった。秋口の手に痛みで萎えかけた性器を掴まれ、擦られて、力ずくで快楽を揺り動かされる。
「……っ……ッ!」
まるで暴力のようだった。抱き締められるのではなく、押さえつけられたまま、無理矢理に体の中を犯される。呻き声を殺すために佐山はきつく歯を噛み締めた。がくがくと揺れる体は自分のものじゃないような気がした。
何度も佐山の中を突き上げた秋口が、不意に自身を外へ抜き出した。生温い感触が佐山の腰や腿に掛かる。
イッたんだ、とわかった刹那、佐山はその場に座り込みたくなったが、秋口はまだ佐山の体を抱えていて、両腕を使い張りつめたペニスをきつく扱いた。
「あっ……ぁ……」
声を洩らし、佐山も秋口の手の中で達した。
気がつくと、後ろから秋口に抱きすくめられる格好になっている。耳許で秋口が荒い息を繰り返していた。
佐山は秋口の体の温かさを感じながら、どの理由でかわからない涙を飲み込み、小さく啜り上げた。
その小さな音に驚いたような、怯えたような動きで秋口の体が震え、佐山の体を抱く力が弱まる。
佐山は座り込みたい気分を堪え、ドアに凭れて呼吸を整えるため大きく深呼吸した。
(――ハンカチ)
床に落ちたズボンのポケットに入っているハンカチをのろのろと拾い上げ、佐山はなるべく何も考えないよう頭を真っ白にして、あちこち濡れた自分の体をそれで拭った。
秋口も多分、億劫げな動きで乱れた自分の衣服を整えている。
佐山は鈍く痛む体を叱咤して動かし、ドアの前から身をずらした。
「先……」
振り返らないまま、秋口に告げる。
「戻っていいよ、ちょっと休んでく」
本当は今すぐにでも床に横たわってしまいたい状態だったが、そんな姿を秋口に見せるのが嫌で、佐山は努めて普通の声音でそう言った。
後ろで秋口が大きく溜息をついたのがわかり、佐山は悪寒を感じた。
決していい雰囲気なんかじゃない。そんなもの欠片もない。
「……やっぱり、女の方がよっぽど楽だ」
「……」
佐山はいっそ、笑い出したい気分になった。
「……面倒臭ぇ」
それだけ言い残して、秋口は佐山の横を擦り抜け、資材倉庫を出て行った。
「……」
ふ、と短く佐山の口から笑いが零れる。
一度笑い出すと止まらなくなって、それはいつの間にか嗚咽に変わり、佐山は床にへたり込んだ。
「それじゃ、へばらない程度に頑張れよ」
それぞれの部署に向かう別れ際、御幸がそう言って佐山の背中を叩いた。それが仕事に対する言葉なのか、それともそれ以外のことに対する言葉なのか、判断はつかなかったが、佐山は何となくありがたい気分で頷きを返した。
午前中、胃薬で何とか吐き気を堪えながら仕事をしていると、携帯電話がメールの着信音を鳴らした。
(――あれ)
差出人は秋口だった。いつもなら午後、仕事の終わる目処がついた頃に連絡が来るのに、こんな早い時間にメールが来るなんて珍しい。
何となく緊張しながら本文を読んで、佐山はまた「あれ?」と思った。
『昼休み、資材倉庫で』
「……」
資材倉庫、という文字を見て、ますます佐山は緊張する。ここのところまったく足を踏み入れていない場所だ。
『了解』
短く返事を打ち、佐山は落ち着かない気分で午前中の仕事をすませ、昼休みになると言われたとおり資材倉庫へ向かった。
人目を忍んで中に入り、まだ秋口が現れていないことをたしかめるとほっと息を吐いて、目についた椅子に腰を下ろす。ドリンク剤の効果も午前中までだったのか、胃もたれがひどくなった感じで、気分が悪い。よっぽど酒量が過ぎていたのか、ゆうべの話になると御幸もさすがに呆れた顔で『無茶な飲み方はするなよ』と釘を刺してきた。
鈍く痛む頭を抱えながら、水でも飲んでくればよかったと後悔した時、外からドアが開く気配がした。佐山が顔を上げると、薄暗い部屋の中に、秋口が現れるところだった。
佐山はどう挨拶をするべきか考えあぐね、そんなことすらいちいち考えなくては反応できない状況に何となく気鬱になりながら、それでも秋口に笑いかける。秋口はそれを無視して、黙ったままドアを閉めた。
「ええと……何か、話とか」
会社で、就業時間中にわざわざ自分を呼び出したのだから、何も世間話をするなどという用事ではないだろう。
――もしかしたら、もう二度と会わないとか、そんなことを告げられるのかとメールを受け取った時から佐山は怯えていた。だが秋口の性格上、そのつもりだったらいちいち断ることもなく、ただ自然に誘われることがなくなるだけだろうと察して、気持ちを宥めた。
あまり慰めにはならない気もしたが。
「……ゆうべ」
「え?」
切り出した秋口の言葉は、変に歯切れが悪かったのでよく聞き取れず、佐山は彼を見上げて首を傾げた。秋口はドアのところに突っ立ったまま、少し離れた場所で椅子に座る佐山のことを見下ろしている。
「……誰かと夜、でかけたんですか」
「ああ……うん、御幸とメシ喰いに。行ったけど」
これは世間話なのか、意味のある質問なのか、わからないまま佐山は正直に答えた。そもそも嘘をつく場面でもない。
「それで、御幸さんは佐山さんの家に泊まって?」
「うん、あれ、よく知ってるな」
少し驚いて佐山がそう答えると、秋口は奇妙な顔で佐山のことを見返した。何か苦いものを口の中で味わっているような表情だった。
「今朝は一緒に来たよ、営業が続けて同じネクタイだと都合が悪いっていうんで、俺の勝手に持っていって――」
部屋の中の空気が思い。それをどうにかしたくて、佐山は馬鹿みたいに明るく話した。
秋口はにこりともせず、ますます苦い表情になるだけだった。
「……って、オチとか別に、ないんだけど……」
「あんたは、俺が他の女とでかけてんの知ってるんだろ」
「は?」
気まずく語尾を濁す佐山に、まったく無視する調子で秋口が質問を被せ、佐山はそれもやっぱりうまく聞き取れずに眉根を寄せた。
「俺があんたと会ってない日に、他の女と寝てるのを知ってるんだろって聞いてるんだよ」
「……」
やっぱり、別れ話か。
そう思ってから、そもそもつき合ってもいないことに思い至って、佐山は頭痛と胃痛がひどくなった。
(何でいまさら、こんな話するんだか……)
以前にしたひどい会話を思い出す。自分は秋口が他の女と会っていることを責めるような口調になって、秋口はそんなことを口にするなと切り捨てた。
どうして同じ会話を今秋口が繰り返そうとするのか、佐山は混乱してしまう。
御幸のおかげで晴れた靄が、ふたたび頭の中を覆いだすような感触。
(……試されてるのか)
自分がそのことを責めたり、何か言えば、今すぐにでも『捨てる』とか。
そういう脅しなのかもしれない。
「知ってるけど」
努めて平静を装って、佐山は秋口にそう答えた。
「それが?」
「それで、あんたは何とも思わないのか?」
「何ともって……」
誘導尋問にあっている気がする。引っかからないように、佐山は細心の注意を払った。
「思わないよ、そんなの。別に、男が好き……ってわけじゃなければ、秋口だっていい歳した大人なわけだし、女の子とそういうことがあって当然だろ」
「……」
「秋口くらい色男なら、誘いだってひっきりなしだろうし、俺なんかと一緒にいて時間潰したりしたら、秋口のこと好きな女の子たちに恨まれるとか」
軽口のように、明るく笑って言った佐山は、自分を見下ろす秋口の目がひどく冷たいことに気づいた。
「……御幸にも、言われたし」
尻窄みでそうつけ足した後は、何だか秋口の顔を見ていられず、佐山はつい俯いてしまった。
どうしてか、理由をつけてこの場から逃げ出したい気分で一杯になる。
好きな相手と一応密室で一緒にいるというのに、まったく心が弾まない。
「あの、話がそれだけなら、昼まだだし」
俯いたまま、早口でそう言って佐山は椅子から立ち上がった。外に出たかったのに秋口はドアの前から退いてくれず、さらに佐山の動きを阻むように、腕を掴んで来る。
「……あきぐ」
近づいてくる秋口の体にどうしてか身が竦み、佐山は呼びかけた名前を飲み込み、咄嗟にその腕を振り払った。
秋口が振り払われた自分の腕を見て、それから視線を佐山の姿へ移す。
何の感情も読み取れない秋口の無表情に、佐山はやっぱり体が竦んだ。
怯えたように後退さる佐山を見て、秋口がふと微笑む。
「どうして嫌がるんですか」
「どうして……って……」
今の秋口を見て、怯えない人間がいるとは佐山には思えなかった。表情は笑っているのに、眼差しが剣呑だ。
「こんなの、何度もやったでしょう?」
もう一度、秋口が先刻よりも乱暴に佐山の腕を掴んだ。
強引な力で秋口の方へ引き寄せられて、佐山はよろめくように、その体に体重を預ける格好になる。体勢を立て直す間もなく顎を掴まれ、上向かされて、目を閉じる間もなくキスされた。
自分が凭れていては重たいのでは、とただそれだけの理由で、佐山は両手で秋口の胸を押した。
「だから、どうして」
佐山に押し退けられた秋口が、苛立ったように声を上げる。
「嫌がるんだよ、今さら初めてってわけでもあるまいし」
「痛ッ、何、秋口」
掴まれたままの腕を引かれ、佐山はやはり乱暴な動きで資材倉庫のドアに背中を押しつけられた。
「押さえてろ、人が来たら困るだろ」
「え……」
相変わらず倉庫の鍵は壊れっぱなしだ。
戸惑う佐山にはお構いなしに、秋口が再び唇を重ねてくる。佐山は押さえつけられて痛む肩に眉を顰めながら、それでもおとなしく目を閉じて秋口に従った。条件反射のようなもの。触れられるのは久々だったのに、秋口にそうされれば、佐山は自然と応えようとしてしまう。
秋口は性急な仕種で佐山の上着のボタンを外し、ネクタイを緩めた。
佐山は秋口が何のつもりでこんなことをしているのかが読めなくて、困惑しながら、されるままになっている。
「ん……」
口腔を深く舌で探られながら、指先できつく胸の先を摘まれ、佐山は痛みのせいか快感のせいかわからない呻き声を喉から漏らした。
秋口の動きは本当に性急だった。キスをしながら佐山の胸や脇腹を探った後、もうズボンのベルトに触れている。すぐにベルトもボタンも外して、片手を佐山の下着の中に差し入れてきた。
自分だけ翻弄されるのが嫌で、佐山も秋口の方へ手を伸ばしたが、それを片手で遮られてしまった。
「……?」
「今日は、いいですよ。しなくても」
不思議そうに手を見下ろす佐山から唇を離し、微かに乱れた呼吸で秋口が言った。その声の艶っぽさに佐山は思わず背筋を震わせる。秋口は佐山がまだ触れてもいないのに、欲情して目を潤ませていた。それに気づいて佐山の気分と体も煽られた。再び沸き上がった震えを堪えようとしたタイミングで、秋口の掌が佐山の性器をきつく握り、擦り上げる。濡れた声が零れそうになって、佐山は咄嗟に唇を噛んだ。
「これじゃ、すぐいっちゃいますね」
少し力を緩め、秋口がやんわりした動きに変えて佐山の中心を掌で弄び出す。
佐山は目許を赤くして、羞恥を堪えながら、秋口が与えてくれるだろう絶頂を待った。
「でも今日は、これで終わられたら困るから」
ひとりごとのように秋口がそう言って、その意味を佐山が問い返す間もなく、指先で佐山自身の先端を擦った。滲み出している先走りの体液を指先に絡めながら、反対の手で佐山の下衣を下着ごと押し下げている。
「足、抜いて」
絡まってうまく脱げない服に焦れたように、秋口が佐山の耳許で命令した。耳許で鳴っているかのような大きな心音を持て余しながら、佐山は秋口のことを見返した。
「……秋口……」
相手の意図を察してしまって、佐山は心許ない声を漏らした。
「待ってくれ……ここで、最後まで?」
「嫌なんですか」
思い遣って訊ねる調子とは真逆の声音で、秋口が笑ってそう言う。
「場所が問題? ちゃんと綺麗なベッドがいいとか」
「いや……そういうわけでも……」
問題はそこじゃない気がしたが、佐山にはうまく答えられなかった。
優しくもない顔で笑いながら、弄ぶみたいに秋口に触れられるのが嫌だとか、そんなことを口にはできない。
(まるで優しくしてくれって縋ってるみたいだ)
「じゃあ気分の問題?」
訊ねながら、秋口ははなから佐山の答えの内容に頓着するつもりはないようで、強引に佐山のスラックスも下着も脚の半ばまで押し下げてしまった。そのまま佐山の片脚を服から引き抜き、佐山の先走りで濡れた指先を下肢の間に押し入れて来る。
「……ッ」
迷う様子もなく秋口の指先が佐山の一番奥を探り出し、周辺をなぞった。指が中へ入ってくる感触に、佐山は体を強張らせた。
「もっと足、開けませんか」
やはり優しさや甘さからほど遠い声で秋口が言う。佐山が身動きできずにいると、秋口が小さく舌打ちして一度指を抜き出し、佐山の肩を押して体の向きを変えさせた。ドアに縋るような格好を取らされ、佐山はますます身を固くする。
佐山が逃げ出したい気分になるのは、行為に抵抗があるわけでもなく、秋口が身にまとう冷たさが悲しかったせいだ。
「やっぱり濡れないのか」
佐山の最奥の辺りを再び指先で触れながら、秋口がひとりごとのように呟いた。佐山の胸が締めつけられたように痛くなる。自分の体は女とは違う。反応が違っていて当然だ。
「持ってきてよかった」
これも誰に聞かせるでもない言葉だったが、佐山はつられるように秋口の方を振り返り、その手に小振りで細長いプラスチックの容器をみつける。
「……何……」
「薬局で売ってたローション。女用だけど、別に男に使っちゃいけないわけじゃないだろうし」
「……」
佐山は言葉を失って、今からでもこの場を逃げ出した方がいいのだろうかとぼんやり考えた。
逡巡しているうち、濡れた手が内腿に触れる。咄嗟に逃げだそうとする佐山の体を秋口の片手が押さえつけ、佐山は冷たく濡れた感触が体の中に滑り込むのを感じた。
「ぁ……ッ」
秋口の指先は容赦なく佐山の中へと潜り込んできた。ゆっくり体の中を掻き回される未知の感触に、佐山はドアに縋ることしかできなくなる。痛みよりも違和感が強い。こんな行為が快楽に繋がるなんて理解できなかった。濡れた感触と音が佐山を落ち着かなくさせる。
「力、入れないで下さいよ。動かし辛い」
囁く秋口の声音はどこか佐山をからかうようなものにも聞こえた。佐山は泣きたい気分でどうにか体に籠もってしまう力を抜こうと試みるが、徒労に終わった。緊張でどうしても体が強張ってしまう。
「あ……きぐち、ごめん、まだ無理……」
ただお互いの手や口で体を愛撫しあうだけの行為と、これは確実に一線を画すやり方だ。秋口と触れ合うようになってから、こういう事態を佐山が想像しなかったわけではないが、実際こんな状態になってみて感じるのは手ひどい拒否感だった。指だけだって受け入れることがこんなに不自然な感触なのに、これ以上のことなんて想像もつかない。
「どうして?」
止めることもなく指を動かし続けながら優しく問いかける秋口の声が、上っ面だけのものだなんてわかっていたのに、佐山はそれでもその優しさに縋りたくなった。
「きゅ……急に、全部は」
「御幸さんとは平気なのに?」
「……え……、……ッ」
ぐっと、さらに奥までねじ込まれた秋口の指が、中で動いて内壁を擦る。佐山は顔を歪めて声を押し殺した。
「御幸さんとは、したんでしょう? 昨日」
「んっ、……みゆ……、何……?」
濡れた音を立てて、秋口が佐山の中で指を出し入れしている。速さを増す動きに思考まで掻き乱されたように、佐山はうまく秋口の言葉について考えることができない。
――考えたくなかったのかもしれない。
「そりゃ、俺が他の女と寝てることとやかく言うわけがないよな。あんただって、他の男とこういうことしてるんだから」
「……っ……あ……ッ」
荒っぽく指が引き抜かれ、震えて頽れそうになる佐山の体は秋口の腕に抱え込まれて無理矢理に立たされた。薄い尻の肉を掴んで押し広げられる。さっきまで指でさんざんに掻き回された場所に、今度は別の、もっと大きな熱の塊が押し当てられた。
「秋……ッ」
嫌だ、と言おうとしたのかもしれない。自分でも何を言うつもりかわからなかった佐山の声は一瞬呼吸と共に飲み込まれ、喉で押し殺した悲鳴になった。
「……ッ……く……、……ん」
ねじ込まれる熱に、悲鳴すらうまく音にならない。
咳き込むように喘ぐ佐山の苦痛にはお構いなしに、秋口は強引に身を進めた。逃げようとする佐山の腰を抱え込み、その中に自分自身を押し込む。
あとはもう、佐山にはわけがわからなくなった。体の中を押し広げられ、熱いものが内壁を擦っている。痛いのか熱いのか苦しいのか、誰がこんな感触を自分に与えているのか、
(秋口)
佐山はただその存在だけに心で縋った。秋口がそう望んでしていることだと、辛くはないと、ぐちゃぐちゃになった頭の中で必死に思う。
到底気持ちが繋がっているだなんて思えないのに、体だけ無理矢理に繋げられる苦痛と惨めさをやり過ごそうとする。
秋口に強い力で体の中を貫かれ、途中から佐山は何も考えられなくなった。秋口の手に痛みで萎えかけた性器を掴まれ、擦られて、力ずくで快楽を揺り動かされる。
「……っ……ッ!」
まるで暴力のようだった。抱き締められるのではなく、押さえつけられたまま、無理矢理に体の中を犯される。呻き声を殺すために佐山はきつく歯を噛み締めた。がくがくと揺れる体は自分のものじゃないような気がした。
何度も佐山の中を突き上げた秋口が、不意に自身を外へ抜き出した。生温い感触が佐山の腰や腿に掛かる。
イッたんだ、とわかった刹那、佐山はその場に座り込みたくなったが、秋口はまだ佐山の体を抱えていて、両腕を使い張りつめたペニスをきつく扱いた。
「あっ……ぁ……」
声を洩らし、佐山も秋口の手の中で達した。
気がつくと、後ろから秋口に抱きすくめられる格好になっている。耳許で秋口が荒い息を繰り返していた。
佐山は秋口の体の温かさを感じながら、どの理由でかわからない涙を飲み込み、小さく啜り上げた。
その小さな音に驚いたような、怯えたような動きで秋口の体が震え、佐山の体を抱く力が弱まる。
佐山は座り込みたい気分を堪え、ドアに凭れて呼吸を整えるため大きく深呼吸した。
(――ハンカチ)
床に落ちたズボンのポケットに入っているハンカチをのろのろと拾い上げ、佐山はなるべく何も考えないよう頭を真っ白にして、あちこち濡れた自分の体をそれで拭った。
秋口も多分、億劫げな動きで乱れた自分の衣服を整えている。
佐山は鈍く痛む体を叱咤して動かし、ドアの前から身をずらした。
「先……」
振り返らないまま、秋口に告げる。
「戻っていいよ、ちょっと休んでく」
本当は今すぐにでも床に横たわってしまいたい状態だったが、そんな姿を秋口に見せるのが嫌で、佐山は努めて普通の声音でそう言った。
後ろで秋口が大きく溜息をついたのがわかり、佐山は悪寒を感じた。
決していい雰囲気なんかじゃない。そんなもの欠片もない。
「……やっぱり、女の方がよっぽど楽だ」
「……」
佐山はいっそ、笑い出したい気分になった。
「……面倒臭ぇ」
それだけ言い残して、秋口は佐山の横を擦り抜け、資材倉庫を出て行った。
「……」
ふ、と短く佐山の口から笑いが零れる。
一度笑い出すと止まらなくなって、それはいつの間にか嗚咽に変わり、佐山は床にへたり込んだ。
◇◇◇
やるべき仕事がなかったわけではないが、佐山はそれらすべてを放棄して、医務室へと転がり込んだ。
どこが痛いとか、辛いとか、自分でも判別がつかず、本当に転がり込むという表現が相応しい状態でベッドに入り、睡眠を誘発する鎮痛剤を山ほど飲んで眠った。
考えるのが、もう面倒だった。
本当はひとつ、気づいてしまったことがあったのだけれど。
(うるさい……)
自分の思考に蓋をして、佐山は誰もいない医務室の中で眠りについた。
目が覚めた時には夕方だった。外していた眼鏡をかけて時計を確認すると、もうそろそろ終業時間が迫ろうとしている。かなり長い時間眠ってしまったらしい。
ものすごい頭痛と胃痛と体の痛み。最低な目覚めだった。それでもいい加減仕事の続きをしなければと思い至り、佐山はふらつきながらベッドを下り、水道から直接水を飲み、顔を洗って、ついでに頭から水を被った。医務室備え付けのタオルを勝手に借りて、髪を拭きながら廊下に出る。
「佐山さん……? どうしたの、その格好」
廊下の途中で驚いた声に名前を呼ばれ、佐山はタオルを頭に被せたまま振り返った。書類を抱えた沙和子が目を見開いて立っている。ぼたぼたと水滴を上着や廊下に落としながら歩いている佐山の方へ、慌てたように駆け寄った。
「びしょ濡れじゃない、ちょっと止まって、ちゃんと拭いた方がいいわ」
面倒な気分になっていたので、佐山は沙和子にされるままタオルで髪を拭かれた。それなりに水滴を払って医務室を出たつもりだったのに、気づけば顔も服もびしょ濡れだ。
「スプリンクラーでも壊れたの?」
怪訝そうな沙和子の言葉ももっともで、佐山はつい笑ってしまう。
笑った佐山の気配に気づいて、その髪から顔に視線を移した沙和子が、表情を曇らせた。
「顔色、ひどいわ。医務室にいたのね?」
「だいぶマシになったよ。いい加減仕事に戻らないと」
「開発課まで一緒に行くわ」
有無を言わさぬ調子で沙和子が言って、佐山の背中を支えた。あの雛川佐和子と寄り添い合って歩いている姿なんて見られたら、社内でいらぬ噂が立つだろうと頭の端でちらりと考えたが、佐山は何だかどうでもよくなって大人しく彼女と一緒に歩いた。
沙和子は佐山が口を開くのも辛いと察してか、いろいろ訊ねてくることもなく、ただ気遣うようにゆっくりと歩きながらその様子を見守っている。
本当に、沙和子ともう一度恋人としてやっていけるのなら、どんなにいいだろうかと思いながら、佐山はやけに遠く感じる開発課までの道のりを歩いた。
「ごめん――ちょっと、飲み物飲んでいっていいかな」
「座ってて、お茶でいい?」
開発課に戻る手前の休憩所で、佐山はベンチの腰を下ろした。体が軋むように痛んだが、その痛みをやり過ごしてどうにか腰を下ろす。沙和子が冷たいジャスミンティを買ってくれた。
「少し気分がすっきりするから」
「ありがとう」
沙和子の気遣いが、こんな時によりいっそうありがたくて、佐山は微笑んで紙カップを受け取った。沙和子もお茶を手に、佐山の隣に座る。
「よかった……」
「え?」
溜息のように呟いた沙和子の声に、佐山は彼女の方を見て首を傾げた。
「佐山さん、すごい顔してたから。顔色もひどかったけど、何ていうか表情が……荒んでるっていうか」
遠慮がちな沙和子の声に、佐山は今度苦笑する。
「ちょっとね。腹の立つことがあって」
答えると、沙和子が驚いたように小さく目を見開いた。
「佐山さんが怒るって、どんなすごいことがあったの?」
佐山は滅多なことでは怒らないし、それを口にすることなんてほんとんどないことを沙和子は知っている。だから彼女が驚くのも当然だ。
「何だろうなあ……嫌われていやがらせをされたり、面と向かって罵倒されたりする分には、悲しいと思いこそすれそれほど腹は立たないんだけど――」
自分でもまだうまくまとまらない気持ちを考え考え口にしていた佐山は、不意に視界が蔭ったことに気づいて、何気なく顔を上げた。
「秋口君」
同じように顔を上げ、ベンチの前に人が立っていることに気づいた沙和子が声を上げる。
彼女が驚いた声音になっていたのは、そこにいた秋口の表情が、先刻の佐山の何倍も、何十倍も荒みきっていたからだ。
「……佐山さん、ちょっといいですか」
訊ねる形は取っていたが、秋口の語調は有無を言わせぬものだった。佐山は腕をきつく握られ、体をベンチから引っ張り上げられて、顔を顰めた。
「用なら、ここで言えばいいだろ」
体格でも力でも秋口には敵わない。佐山は休憩所から引き摺られるように歩かされながら、ベンチの方を振り返った。立ち上がった沙和子が、戸惑った様子で佐山と秋口を見ている。
「待って、秋口君、佐山さん具合が悪いのよ」
心配げな声で沙和子が言うが、秋口は振り返りもせず鼻先で嗤っただけだった。
「だからって、別に雛川さんと一緒にいればよくなるわけでもないでしょ」
そこで、佐山の限界が来た。
「秋口」
掴まれたままの腕を、掴み返す。秋口が少し驚いたように振り返り、自分のことを見返す様子を、佐山はひどく冷静な頭でみつめた。
「え――」
それから、秋口の目が、さらに驚いたように見開かれる様子を。
「……ッ」
秋口の踵の上を横から蹴りつけると、その体がバランスを崩してよろめく。倒れて低くなった秋口の顔めがけて、佐山は握った拳を渾身叩きつけた。上から下へ、体重を乗せて繰り出された佐山の拳に、秋口の体が勢いよく床に倒れて弾んだ。
「い……ッ……ってェ……!!」
殴られた頬を掌で覆い、秋口が呻き声を洩らした。何が起こったのか理解できていない、ただ痛みだけに反応した吐き出すような声。
佐山は佐山で痛む拳を反対の掌で握り込み、床に倒れたままの秋口を見下ろす。
後ろできっと沙和子が驚いているだろうが、佐山は気に止めなかった。
「秋口のことは好きだけど」
見開いたままの瞳で自分を見上げる秋口を見て、佐山は微かに目を細める。
「全部おまえの思いどおりになんてならないよ」
それだけ言って、踵を返す。一連の様子を見て、体を強張らせている沙和子の方へと戻った。
「沙和子、悪いけど手を切ったみたいだから、医務室に一緒に来てくれるか」
「え……ええ、構わないけど……」
彼女にも、治療が必要なのは秋口も同じだとわかっていただろうが、今の佐山に彼を一緒に連れて行くことなんて提案できるわけがない。
おそるおそる沙和子が振り返った先で、ようやく体を起こした秋口が、呆然と頬を押さえたまま佐山の背中を見ていた。
佐山は振り返りもしなかった。
どこが痛いとか、辛いとか、自分でも判別がつかず、本当に転がり込むという表現が相応しい状態でベッドに入り、睡眠を誘発する鎮痛剤を山ほど飲んで眠った。
考えるのが、もう面倒だった。
本当はひとつ、気づいてしまったことがあったのだけれど。
(うるさい……)
自分の思考に蓋をして、佐山は誰もいない医務室の中で眠りについた。
目が覚めた時には夕方だった。外していた眼鏡をかけて時計を確認すると、もうそろそろ終業時間が迫ろうとしている。かなり長い時間眠ってしまったらしい。
ものすごい頭痛と胃痛と体の痛み。最低な目覚めだった。それでもいい加減仕事の続きをしなければと思い至り、佐山はふらつきながらベッドを下り、水道から直接水を飲み、顔を洗って、ついでに頭から水を被った。医務室備え付けのタオルを勝手に借りて、髪を拭きながら廊下に出る。
「佐山さん……? どうしたの、その格好」
廊下の途中で驚いた声に名前を呼ばれ、佐山はタオルを頭に被せたまま振り返った。書類を抱えた沙和子が目を見開いて立っている。ぼたぼたと水滴を上着や廊下に落としながら歩いている佐山の方へ、慌てたように駆け寄った。
「びしょ濡れじゃない、ちょっと止まって、ちゃんと拭いた方がいいわ」
面倒な気分になっていたので、佐山は沙和子にされるままタオルで髪を拭かれた。それなりに水滴を払って医務室を出たつもりだったのに、気づけば顔も服もびしょ濡れだ。
「スプリンクラーでも壊れたの?」
怪訝そうな沙和子の言葉ももっともで、佐山はつい笑ってしまう。
笑った佐山の気配に気づいて、その髪から顔に視線を移した沙和子が、表情を曇らせた。
「顔色、ひどいわ。医務室にいたのね?」
「だいぶマシになったよ。いい加減仕事に戻らないと」
「開発課まで一緒に行くわ」
有無を言わさぬ調子で沙和子が言って、佐山の背中を支えた。あの雛川佐和子と寄り添い合って歩いている姿なんて見られたら、社内でいらぬ噂が立つだろうと頭の端でちらりと考えたが、佐山は何だかどうでもよくなって大人しく彼女と一緒に歩いた。
沙和子は佐山が口を開くのも辛いと察してか、いろいろ訊ねてくることもなく、ただ気遣うようにゆっくりと歩きながらその様子を見守っている。
本当に、沙和子ともう一度恋人としてやっていけるのなら、どんなにいいだろうかと思いながら、佐山はやけに遠く感じる開発課までの道のりを歩いた。
「ごめん――ちょっと、飲み物飲んでいっていいかな」
「座ってて、お茶でいい?」
開発課に戻る手前の休憩所で、佐山はベンチの腰を下ろした。体が軋むように痛んだが、その痛みをやり過ごしてどうにか腰を下ろす。沙和子が冷たいジャスミンティを買ってくれた。
「少し気分がすっきりするから」
「ありがとう」
沙和子の気遣いが、こんな時によりいっそうありがたくて、佐山は微笑んで紙カップを受け取った。沙和子もお茶を手に、佐山の隣に座る。
「よかった……」
「え?」
溜息のように呟いた沙和子の声に、佐山は彼女の方を見て首を傾げた。
「佐山さん、すごい顔してたから。顔色もひどかったけど、何ていうか表情が……荒んでるっていうか」
遠慮がちな沙和子の声に、佐山は今度苦笑する。
「ちょっとね。腹の立つことがあって」
答えると、沙和子が驚いたように小さく目を見開いた。
「佐山さんが怒るって、どんなすごいことがあったの?」
佐山は滅多なことでは怒らないし、それを口にすることなんてほんとんどないことを沙和子は知っている。だから彼女が驚くのも当然だ。
「何だろうなあ……嫌われていやがらせをされたり、面と向かって罵倒されたりする分には、悲しいと思いこそすれそれほど腹は立たないんだけど――」
自分でもまだうまくまとまらない気持ちを考え考え口にしていた佐山は、不意に視界が蔭ったことに気づいて、何気なく顔を上げた。
「秋口君」
同じように顔を上げ、ベンチの前に人が立っていることに気づいた沙和子が声を上げる。
彼女が驚いた声音になっていたのは、そこにいた秋口の表情が、先刻の佐山の何倍も、何十倍も荒みきっていたからだ。
「……佐山さん、ちょっといいですか」
訊ねる形は取っていたが、秋口の語調は有無を言わせぬものだった。佐山は腕をきつく握られ、体をベンチから引っ張り上げられて、顔を顰めた。
「用なら、ここで言えばいいだろ」
体格でも力でも秋口には敵わない。佐山は休憩所から引き摺られるように歩かされながら、ベンチの方を振り返った。立ち上がった沙和子が、戸惑った様子で佐山と秋口を見ている。
「待って、秋口君、佐山さん具合が悪いのよ」
心配げな声で沙和子が言うが、秋口は振り返りもせず鼻先で嗤っただけだった。
「だからって、別に雛川さんと一緒にいればよくなるわけでもないでしょ」
そこで、佐山の限界が来た。
「秋口」
掴まれたままの腕を、掴み返す。秋口が少し驚いたように振り返り、自分のことを見返す様子を、佐山はひどく冷静な頭でみつめた。
「え――」
それから、秋口の目が、さらに驚いたように見開かれる様子を。
「……ッ」
秋口の踵の上を横から蹴りつけると、その体がバランスを崩してよろめく。倒れて低くなった秋口の顔めがけて、佐山は握った拳を渾身叩きつけた。上から下へ、体重を乗せて繰り出された佐山の拳に、秋口の体が勢いよく床に倒れて弾んだ。
「い……ッ……ってェ……!!」
殴られた頬を掌で覆い、秋口が呻き声を洩らした。何が起こったのか理解できていない、ただ痛みだけに反応した吐き出すような声。
佐山は佐山で痛む拳を反対の掌で握り込み、床に倒れたままの秋口を見下ろす。
後ろできっと沙和子が驚いているだろうが、佐山は気に止めなかった。
「秋口のことは好きだけど」
見開いたままの瞳で自分を見上げる秋口を見て、佐山は微かに目を細める。
「全部おまえの思いどおりになんてならないよ」
それだけ言って、踵を返す。一連の様子を見て、体を強張らせている沙和子の方へと戻った。
「沙和子、悪いけど手を切ったみたいだから、医務室に一緒に来てくれるか」
「え……ええ、構わないけど……」
彼女にも、治療が必要なのは秋口も同じだとわかっていただろうが、今の佐山に彼を一緒に連れて行くことなんて提案できるわけがない。
おそるおそる沙和子が振り返った先で、ようやく体を起こした秋口が、呆然と頬を押さえたまま佐山の背中を見ていた。
佐山は振り返りもしなかった。
◇◇◇
頬を腫らし、憮然とした顔で業務を行う秋口を、皆遠巻きに見ている。
明らかにそれとわかる殴られた痕だったが、理由を問う者も怪我を慮る者もいない。営業課にいる誰もが、「おおかた、えげつないやり方で誰かの女を寝取って殴られたのだろう」と思っている。
(くそ、痛え)
苛々と、秋口は乱暴な仕種でパソコンのキーボードを叩いた。夕方から外回りをする予定は全部消えた。こんな顔でのこのこと客のところへ行けるわけがない。打ち合わせを日延べしてもらったり、電話ですませたりしたから、自分に対する評価はすっかり下がってしまったことだろう。プレゼンテーションなどがなかったことだけが幸いだ。
佐山が沙和子と医務室へ消えてしまって、しばらくしてから、茫然自失していた秋口はやっと我に返った。
佐山に殴られたのだ、とわかるまでに大分時間がかかった。
営業課の同僚がおそるおそる「具合でも悪いのか」と声をかけてきて、秋口はようやく自分が殴られた頬を押さえたまま廊下にへたり込んでいたことに気づいたのだ。手を貸そうとする同僚を大丈夫だからと振り払い、とにかく頬を冷やそうとトイレに向かった。口の中が鉄臭いからうがいをしたら、吐き出した水が真っ赤に染まっていてぎょっとした。口の中を歯で切ってしまったらしい。あんな小柄で細身で頼りなく見えるのに、佐山の拳は秋口に充分ダメージを与えた。油断していたこともあるが、誰かに殴られて地面に倒れ込んだのなんて生まれて初めてだった。
濡らしたハンカチで頬を冷やし、秋口は誰へともなく悪態をつきながらトイレの壁を蹴りつけた。
腹が立って腹が立って仕方がないのに、その怒りを誰にぶつけていいのか秋口にはわからなかった。殴られて転がった自分にも腹が立つし、沙和子と医務室に行った佐山にも腹が立つし、御幸と寝ていた佐山にも腹が立つ。
自分を好きだといいながら他の人間にも笑いかける佐山に腹が立つから、それをぶちまけようとしたら殴られた。
秋口には佐山の気持ちがさっぱりわけがわからない。
自分が他の女と寝ていることを知っても怒りもしなかったくせに、どうしてふたりきりになろうとすると怒るのか。
(……もしかして、最初からからかわれてたのか、俺は?)
営業課に戻っても、悶々とそんな考えが頭をめぐり、仕事にならなかった。
今頃佐山と沙和子が医務室で何を話して、何をしているのかと、考えるほど神経が焼き切れそうなひどい気持ちになったが、だからといってまたふたりのところに割り込んで、同じ目に遇うのは御免だ。それはきっとひどく惨めで情けないことだろう。
同じオフィスにいる人間の、遠巻きな視線と囁きに耐えかね、秋口は苛立ったまま席を立った。いつもだったら自分を取り巻くどんな噂も中傷も気にならなかったし、自分が話題の中心になっていることに快感を覚え、やっかみ陰口を叩くことにしか能のない奴らを蔑みこそすれ、それに引け目を感じたことなどなかったのに。
廊下に出て休憩所の方へ向かった秋口は、そこに先刻座って身を寄せるように会話をしていた佐山と沙和子のことを思い出し、腹の中で何かがねじれてちぎれそうな感じを持て余した。
乱暴にベンチへ腰かけ、ポケットから煙草を取り出して咥える時、切れた口腔が痛んで顔を顰める。
忌々しい気分でライターを取り出すが、ガス切れらしく火がつかない。ライターを床に叩きつけたくなったが、人が近づいてくる気配に辛うじてその衝動を抑えた。
「ああ、本当だ。悲惨だな」
そんな呟きが聞こえ、秋口が顔を上げると、感心したような表情の御幸がそばにいた。
「……何ですか」
「秋口が男前になってるっていうから、様子を見に来たんだよ」
いつもと変わらぬ穏和な口調で言って、御幸も立ったまま煙草を咥えた。まだ火のつかないライターと格闘している秋口を眺めながら、悠然と自分のライターで煙草に火をつけ、ポケットにしまいこんでいる。
火を貸してくれ、と頼むのも癪に触るので、秋口は諦めて煙草を握り潰すとそのまま灰皿に捨てた。
「何か用ですか、俺に」
御幸の顔を見れば、ゆうべのことを思い出して胃がムカムカしてくる。相手を見ないようにしながら、秋口は突慳貪な口調でそう訊ねた。
「だから言ったろ、おまえの姿を眺めに来たんだって」
「佐山さんに殴られてみっともない顔してる俺のこと、わざわざ馬鹿にしに来たんですか」
「やっぱり、佐山がやったのか」
御幸の呟きが聞こえ、秋口は舌打ちした。語るに落ちたというのか。
佐山も沙和子も事実を吹聴して回るようなタイプじゃないから、自分さえ黙っていれば、より惨めな気分になることなどなかったのに。
「何やって佐山を怒らせたんだか。あいつが自分から手を出すなんて、相当だぞ」
御幸の「佐山のことはよくわかっている」という口ぶりが、秋口の神経を逆撫でする。
「まさか秋口の方から佐山に暴力ふるうってとこまで最悪な事態にはなってないだろうし――」
「そんなことするわけないでしょう。いきなり殴られたんですよ。しかも足払いまでかけられましたよ、こっちが体勢崩したとこ狙って力一杯」
先刻の状況を思い出しながら秋口が仏頂面で説明すると、御幸が声を上げて笑った。
「よしよし、よくやった」
嬉しそうな声だ。
「一発ですんだんなら佐山に感謝するんだな。あいつが本気出したら、おまえ今頃自力で立てなくなってるぞ」
「……何ですか、それ」
「ああ見えて佐山は場数踏んでるってこと。あの外見に油断してる奴が相手なら、勝負にならないから」
秋口は顔を顰めて、自分の頬に指先で触れた。トイレで充分冷やしたはずなのに、腫れはひいていない。
「ま、さすがに会社ではそこまでやらないかな」
「会社ではって……他ではやってるみたいな口ぶりみたいですけど」
つい顔を上げると、御幸がじっとこちらを見下ろしていて、秋口は居心地の悪い気分になった。
「異常に絡まれやすいんだよ、佐山。別に絡んで来る相手をいちいち叩きのめしてるわけじゃないけどな、しばらく動けない程度にダメージ与えて隙を作って、全力で逃げるのがコツなんだって言ってた」
「……想像がつかない」
酔っ払いにでも絡まれたら、困りますとただ呟いて、周りが助けてくれるのを待っているような印象があるのだ。秋口にとっての佐山は。
「性格的には暴力沙汰とはまるで縁遠いからな。ただ――佐山はちょっと家庭が複雑で、小さい頃から周りに理不尽な暴力、言葉でも拳でも、そういうのを受けてきた奴だから。自分の身は自分で守るっていうのがあたりまえになってるんだよ」
「……」
淡々と語る御幸のことを、眉根を寄せて秋口は見遣った。
「俺は話を聞いて想像するしかないけどな。体もそう丈夫じゃなかったっていうから、同じ年代の子供の標的になりやすかったんだろうって想像はつく。それで、そういう状況を自分の力で振り払って、今の佐山があるってことだ」
御幸は二本目の煙草に手をつけた。秋口にはやっばり火を貸してくれなかった。
「そういう佐山が忍耐強くおまえとつき合って、とうとうキレたってことについて、ちょっとは考えるべきだな。秋口は」
「回りくどい嫌味なんて言わないで下さいよ」
「嫌味?」
御幸が軽く眉を上げる。
秋口はその表情を、また神経が焼き切れそうな気分で睨みつけた。
「俺が佐山さんに近づいたから、頭に来てるんでしょう。できれば遠ざけたいと思ってる。だからこんなふうにわざわざ俺のとこに来て」
「前にも言わなかったか、佐山と秋口の問題なら俺が怒る筋合いじゃないって」
「佐山さんと御幸さんの問題に俺が割り込めば、それは御幸さんの問題ってことになるじゃないですか」
「……おまえが割り込む、ねえ」
ふと、そこで御幸が笑いの質を変えた。
「おまえの恋愛感情が割り込めるほど、俺と佐山の間にある純然たる友情は脆くないぞ?」
「友情って」
秋口も嗤いを洩らし、御幸から目を逸らす。
「御幸さん言うところの友情は、男同士でも寝るような関係なんですか」
「佐山の部屋、知ってるだろ、客間もないし客用布団を敷けるスペースもないし」
「誤魔化すなよ、昨日あんなところ見せておいて」
「おまえが見たのは」
いきり立ってベンチから立ち上がる秋口を、御幸は冷静に見遣っている。
「酔いつぶれてベッドに転がる佐山と、その酔っ払いの吐いたもので服を汚されてシャワーを浴びてた可哀想な俺。佐山の服も汚れたから俺が脱がせた」
「――」
「いい大人が我をなくすほど酔っぱらうなんてみっともないから、会社の奴らには言うなって頼んだだろ?」
そこで笑った御幸を見て、秋口は彼がわざと誤解を招くような言い方をしていたのだと――つまりは佐山と彼の間にあるのが、本当に純然たる友情だということに思い至った。
(じゃあ)
ぐらりと、目の前が揺れた気がする。
(俺は勘違いして、佐山さんに無理矢理)
「どうして……」
自分がとんでもないことをしてしまったのだと、荒っぽく心臓が鳴り出した。秋口は強張る声で御幸を問い質す。
「どうしてそんな嘘」
「嘘はついてないさ、本当のことを説明してやる義理がなかっただけで」
「……」
「それとも俺は、笑っておまえに『どうぞ佐山をよろしく』なんて、大事な親友を預けなきゃいけなかったのか? 冗談だろ」
秋口は再びベンチに座り込み、思わず頭を抱えた。
先刻までの苛立ちが、同じ重さの後悔になって返ってくる。
「佐山はどんな困難があっても、自分でどうにかするって信頼はしてるけど、俺から進んで困難にぶつけるつもりもないからな。それでもあの時、怒って俺を殴りでもしたら上等、佐山を叩き起こして責めるならまだマシ、そう思ってたけど、おまえは結局何も言わずに逃げ出すし。それを追いかけていって弁解する義理も俺にはない、と」
「もういいです」
御幸の言葉を聞いていられず、秋口は頭を抱えたまま強引にその台詞を遮った。
「もういいです。……俺が馬鹿だった」
自分がどれだけひどいことを佐山に言って、どれだけひどいことを佐山にしたのか、秋口は思い出したくもなかった。
ゆうべ御幸といる佐山を見てから――それ以前にも彼といる佐山を、沙和子といる佐山を目にしてしまえば、秋口はとっくに冷静ではいられなくなっていたのだ。
他の女なら、自分が声をかければ簡単に喜ぶ。ましてや自分に気がある相手なら、秋口から何をしなくてもたやすく体を開いたし、呆れるほど自分に夢中になって、自分だけを見て、他の女を押し退け、自分だけと一緒にいようとしたのに。
なぜ佐山はそうではないのか、理解できなかった。
簡単に自分に甘えて、感情をぶつけてはこない佐山が、もどかしかった。
(それが面倒だと思ったんだ。俺は)
何の苦労もなく手に入る程度のものなら、こんなふうに気持ちを乱されたりはしないと、どこかで理解しながら。
(離れる気なんかなかったくせに突き放すふりして、俺のせいで泣くところが見たくて、それでも許されるなんて思い上がって)
頭上から微かな溜息が聞こえても、秋口は身動きひとつ取ることができない。
「だから、あとで痛い目に遇わないようにって忠告してやったのに」
そんな御幸の声と共に、秋口の座るベンチに小さく固いものが当たる音がした。
のろのろと秋口が視線を巡らせると、ベンチの上にライターが転がっていた。
御幸は灰皿に煙草を捨てて去っていき、秋口は煙草を吸う気なんてまったく起きなかった。
明らかにそれとわかる殴られた痕だったが、理由を問う者も怪我を慮る者もいない。営業課にいる誰もが、「おおかた、えげつないやり方で誰かの女を寝取って殴られたのだろう」と思っている。
(くそ、痛え)
苛々と、秋口は乱暴な仕種でパソコンのキーボードを叩いた。夕方から外回りをする予定は全部消えた。こんな顔でのこのこと客のところへ行けるわけがない。打ち合わせを日延べしてもらったり、電話ですませたりしたから、自分に対する評価はすっかり下がってしまったことだろう。プレゼンテーションなどがなかったことだけが幸いだ。
佐山が沙和子と医務室へ消えてしまって、しばらくしてから、茫然自失していた秋口はやっと我に返った。
佐山に殴られたのだ、とわかるまでに大分時間がかかった。
営業課の同僚がおそるおそる「具合でも悪いのか」と声をかけてきて、秋口はようやく自分が殴られた頬を押さえたまま廊下にへたり込んでいたことに気づいたのだ。手を貸そうとする同僚を大丈夫だからと振り払い、とにかく頬を冷やそうとトイレに向かった。口の中が鉄臭いからうがいをしたら、吐き出した水が真っ赤に染まっていてぎょっとした。口の中を歯で切ってしまったらしい。あんな小柄で細身で頼りなく見えるのに、佐山の拳は秋口に充分ダメージを与えた。油断していたこともあるが、誰かに殴られて地面に倒れ込んだのなんて生まれて初めてだった。
濡らしたハンカチで頬を冷やし、秋口は誰へともなく悪態をつきながらトイレの壁を蹴りつけた。
腹が立って腹が立って仕方がないのに、その怒りを誰にぶつけていいのか秋口にはわからなかった。殴られて転がった自分にも腹が立つし、沙和子と医務室に行った佐山にも腹が立つし、御幸と寝ていた佐山にも腹が立つ。
自分を好きだといいながら他の人間にも笑いかける佐山に腹が立つから、それをぶちまけようとしたら殴られた。
秋口には佐山の気持ちがさっぱりわけがわからない。
自分が他の女と寝ていることを知っても怒りもしなかったくせに、どうしてふたりきりになろうとすると怒るのか。
(……もしかして、最初からからかわれてたのか、俺は?)
営業課に戻っても、悶々とそんな考えが頭をめぐり、仕事にならなかった。
今頃佐山と沙和子が医務室で何を話して、何をしているのかと、考えるほど神経が焼き切れそうなひどい気持ちになったが、だからといってまたふたりのところに割り込んで、同じ目に遇うのは御免だ。それはきっとひどく惨めで情けないことだろう。
同じオフィスにいる人間の、遠巻きな視線と囁きに耐えかね、秋口は苛立ったまま席を立った。いつもだったら自分を取り巻くどんな噂も中傷も気にならなかったし、自分が話題の中心になっていることに快感を覚え、やっかみ陰口を叩くことにしか能のない奴らを蔑みこそすれ、それに引け目を感じたことなどなかったのに。
廊下に出て休憩所の方へ向かった秋口は、そこに先刻座って身を寄せるように会話をしていた佐山と沙和子のことを思い出し、腹の中で何かがねじれてちぎれそうな感じを持て余した。
乱暴にベンチへ腰かけ、ポケットから煙草を取り出して咥える時、切れた口腔が痛んで顔を顰める。
忌々しい気分でライターを取り出すが、ガス切れらしく火がつかない。ライターを床に叩きつけたくなったが、人が近づいてくる気配に辛うじてその衝動を抑えた。
「ああ、本当だ。悲惨だな」
そんな呟きが聞こえ、秋口が顔を上げると、感心したような表情の御幸がそばにいた。
「……何ですか」
「秋口が男前になってるっていうから、様子を見に来たんだよ」
いつもと変わらぬ穏和な口調で言って、御幸も立ったまま煙草を咥えた。まだ火のつかないライターと格闘している秋口を眺めながら、悠然と自分のライターで煙草に火をつけ、ポケットにしまいこんでいる。
火を貸してくれ、と頼むのも癪に触るので、秋口は諦めて煙草を握り潰すとそのまま灰皿に捨てた。
「何か用ですか、俺に」
御幸の顔を見れば、ゆうべのことを思い出して胃がムカムカしてくる。相手を見ないようにしながら、秋口は突慳貪な口調でそう訊ねた。
「だから言ったろ、おまえの姿を眺めに来たんだって」
「佐山さんに殴られてみっともない顔してる俺のこと、わざわざ馬鹿にしに来たんですか」
「やっぱり、佐山がやったのか」
御幸の呟きが聞こえ、秋口は舌打ちした。語るに落ちたというのか。
佐山も沙和子も事実を吹聴して回るようなタイプじゃないから、自分さえ黙っていれば、より惨めな気分になることなどなかったのに。
「何やって佐山を怒らせたんだか。あいつが自分から手を出すなんて、相当だぞ」
御幸の「佐山のことはよくわかっている」という口ぶりが、秋口の神経を逆撫でする。
「まさか秋口の方から佐山に暴力ふるうってとこまで最悪な事態にはなってないだろうし――」
「そんなことするわけないでしょう。いきなり殴られたんですよ。しかも足払いまでかけられましたよ、こっちが体勢崩したとこ狙って力一杯」
先刻の状況を思い出しながら秋口が仏頂面で説明すると、御幸が声を上げて笑った。
「よしよし、よくやった」
嬉しそうな声だ。
「一発ですんだんなら佐山に感謝するんだな。あいつが本気出したら、おまえ今頃自力で立てなくなってるぞ」
「……何ですか、それ」
「ああ見えて佐山は場数踏んでるってこと。あの外見に油断してる奴が相手なら、勝負にならないから」
秋口は顔を顰めて、自分の頬に指先で触れた。トイレで充分冷やしたはずなのに、腫れはひいていない。
「ま、さすがに会社ではそこまでやらないかな」
「会社ではって……他ではやってるみたいな口ぶりみたいですけど」
つい顔を上げると、御幸がじっとこちらを見下ろしていて、秋口は居心地の悪い気分になった。
「異常に絡まれやすいんだよ、佐山。別に絡んで来る相手をいちいち叩きのめしてるわけじゃないけどな、しばらく動けない程度にダメージ与えて隙を作って、全力で逃げるのがコツなんだって言ってた」
「……想像がつかない」
酔っ払いにでも絡まれたら、困りますとただ呟いて、周りが助けてくれるのを待っているような印象があるのだ。秋口にとっての佐山は。
「性格的には暴力沙汰とはまるで縁遠いからな。ただ――佐山はちょっと家庭が複雑で、小さい頃から周りに理不尽な暴力、言葉でも拳でも、そういうのを受けてきた奴だから。自分の身は自分で守るっていうのがあたりまえになってるんだよ」
「……」
淡々と語る御幸のことを、眉根を寄せて秋口は見遣った。
「俺は話を聞いて想像するしかないけどな。体もそう丈夫じゃなかったっていうから、同じ年代の子供の標的になりやすかったんだろうって想像はつく。それで、そういう状況を自分の力で振り払って、今の佐山があるってことだ」
御幸は二本目の煙草に手をつけた。秋口にはやっばり火を貸してくれなかった。
「そういう佐山が忍耐強くおまえとつき合って、とうとうキレたってことについて、ちょっとは考えるべきだな。秋口は」
「回りくどい嫌味なんて言わないで下さいよ」
「嫌味?」
御幸が軽く眉を上げる。
秋口はその表情を、また神経が焼き切れそうな気分で睨みつけた。
「俺が佐山さんに近づいたから、頭に来てるんでしょう。できれば遠ざけたいと思ってる。だからこんなふうにわざわざ俺のとこに来て」
「前にも言わなかったか、佐山と秋口の問題なら俺が怒る筋合いじゃないって」
「佐山さんと御幸さんの問題に俺が割り込めば、それは御幸さんの問題ってことになるじゃないですか」
「……おまえが割り込む、ねえ」
ふと、そこで御幸が笑いの質を変えた。
「おまえの恋愛感情が割り込めるほど、俺と佐山の間にある純然たる友情は脆くないぞ?」
「友情って」
秋口も嗤いを洩らし、御幸から目を逸らす。
「御幸さん言うところの友情は、男同士でも寝るような関係なんですか」
「佐山の部屋、知ってるだろ、客間もないし客用布団を敷けるスペースもないし」
「誤魔化すなよ、昨日あんなところ見せておいて」
「おまえが見たのは」
いきり立ってベンチから立ち上がる秋口を、御幸は冷静に見遣っている。
「酔いつぶれてベッドに転がる佐山と、その酔っ払いの吐いたもので服を汚されてシャワーを浴びてた可哀想な俺。佐山の服も汚れたから俺が脱がせた」
「――」
「いい大人が我をなくすほど酔っぱらうなんてみっともないから、会社の奴らには言うなって頼んだだろ?」
そこで笑った御幸を見て、秋口は彼がわざと誤解を招くような言い方をしていたのだと――つまりは佐山と彼の間にあるのが、本当に純然たる友情だということに思い至った。
(じゃあ)
ぐらりと、目の前が揺れた気がする。
(俺は勘違いして、佐山さんに無理矢理)
「どうして……」
自分がとんでもないことをしてしまったのだと、荒っぽく心臓が鳴り出した。秋口は強張る声で御幸を問い質す。
「どうしてそんな嘘」
「嘘はついてないさ、本当のことを説明してやる義理がなかっただけで」
「……」
「それとも俺は、笑っておまえに『どうぞ佐山をよろしく』なんて、大事な親友を預けなきゃいけなかったのか? 冗談だろ」
秋口は再びベンチに座り込み、思わず頭を抱えた。
先刻までの苛立ちが、同じ重さの後悔になって返ってくる。
「佐山はどんな困難があっても、自分でどうにかするって信頼はしてるけど、俺から進んで困難にぶつけるつもりもないからな。それでもあの時、怒って俺を殴りでもしたら上等、佐山を叩き起こして責めるならまだマシ、そう思ってたけど、おまえは結局何も言わずに逃げ出すし。それを追いかけていって弁解する義理も俺にはない、と」
「もういいです」
御幸の言葉を聞いていられず、秋口は頭を抱えたまま強引にその台詞を遮った。
「もういいです。……俺が馬鹿だった」
自分がどれだけひどいことを佐山に言って、どれだけひどいことを佐山にしたのか、秋口は思い出したくもなかった。
ゆうべ御幸といる佐山を見てから――それ以前にも彼といる佐山を、沙和子といる佐山を目にしてしまえば、秋口はとっくに冷静ではいられなくなっていたのだ。
他の女なら、自分が声をかければ簡単に喜ぶ。ましてや自分に気がある相手なら、秋口から何をしなくてもたやすく体を開いたし、呆れるほど自分に夢中になって、自分だけを見て、他の女を押し退け、自分だけと一緒にいようとしたのに。
なぜ佐山はそうではないのか、理解できなかった。
簡単に自分に甘えて、感情をぶつけてはこない佐山が、もどかしかった。
(それが面倒だと思ったんだ。俺は)
何の苦労もなく手に入る程度のものなら、こんなふうに気持ちを乱されたりはしないと、どこかで理解しながら。
(離れる気なんかなかったくせに突き放すふりして、俺のせいで泣くところが見たくて、それでも許されるなんて思い上がって)
頭上から微かな溜息が聞こえても、秋口は身動きひとつ取ることができない。
「だから、あとで痛い目に遇わないようにって忠告してやったのに」
そんな御幸の声と共に、秋口の座るベンチに小さく固いものが当たる音がした。
のろのろと秋口が視線を巡らせると、ベンチの上にライターが転がっていた。
御幸は灰皿に煙草を捨てて去っていき、秋口は煙草を吸う気なんてまったく起きなかった。
◇◇◇
自分がどうしたかったのかとか、そんなものはとっくに見失っていた。
以前に医務室で沙和子と一緒にいた佐山を見た時、理性が焼き切れて、無理矢理押さえつけてその体を愛撫した。
あの時も、ひどいことをしたと後悔して、それでも佐山が許してくれたから――だから余計に、どうしたらいいのかわからなくなった。
(佐山さんのせいかよ)
この期に及んで、まだ佐山に責任を押しつけたがっている自分に気づいて、秋口はますます惨めな気分になった。
(俺は、佐山さんにどうして欲しかったんだ?)
御幸が去っていった休憩所で、ひとり座りながら秋口は考える。
(俺のこと好きだってわかって……それで、それ以上どうして欲しかったんだ?)
どこで道を間違ってしまったのか、簡単なことな気がするのに、秋口には思いつかない。
多分、ずっと好きでいて欲しかったのだ。佐山が自分のことを好きなのだと思えば、今までに感じたことがないくらい、本当は、嬉しかった。
(……俺のことだけ見て欲しかったんだ)
だから沙和子といる佐山が、御幸といる佐山が、腹立たしかった。
裏切られたと思った。
(自分では何もしなかったくせに)
自分が好きだと言ったその口で、その体で、御幸のことも受け入れたのかと思うと、正気ではいられなくなりそうだった。本当はゆうべ、裸でいた佐山と御幸を見た時、ふたりとも殴り殺してやりたいくらいの気分になっていたのに。
そうしなかったのは、どこかで逃げ道を捜していたからだ。
必死になる自分が恥ずかしくて、口惜しかった。そんな取り乱したところを他人に見せたことなんて一度もない。
(そうだ、そんなことしたら)
――自分がまるで佐山のことを好きみたいだと思って、それがばれるのか怖かったのだ。
今まで自分を取り合って、自分に捨てられて、縋ってくる女たちを醜いと思った。鬱陶しいし、邪魔だと思った。
自分がそれと同列になるのが、どうしても許し難かった。
佐山はたとえ自分が他の女と寝ていることを知ったって、取り乱さないことができた。そんな佐山に、自分から好きになって、自分のことだけを見るように願うのは負けることだと、そうどこかで感じていた。
結局、自己保身だ。
(自分を守るために佐山さんのこと傷つけたのか、俺は)
それでも佐山が許してくれるだろうと、どこかで甘えていたことに秋口はようやく気づく。
それから、今でも佐山に許されたいと願っていることを。
以前に医務室で沙和子と一緒にいた佐山を見た時、理性が焼き切れて、無理矢理押さえつけてその体を愛撫した。
あの時も、ひどいことをしたと後悔して、それでも佐山が許してくれたから――だから余計に、どうしたらいいのかわからなくなった。
(佐山さんのせいかよ)
この期に及んで、まだ佐山に責任を押しつけたがっている自分に気づいて、秋口はますます惨めな気分になった。
(俺は、佐山さんにどうして欲しかったんだ?)
御幸が去っていった休憩所で、ひとり座りながら秋口は考える。
(俺のこと好きだってわかって……それで、それ以上どうして欲しかったんだ?)
どこで道を間違ってしまったのか、簡単なことな気がするのに、秋口には思いつかない。
多分、ずっと好きでいて欲しかったのだ。佐山が自分のことを好きなのだと思えば、今までに感じたことがないくらい、本当は、嬉しかった。
(……俺のことだけ見て欲しかったんだ)
だから沙和子といる佐山が、御幸といる佐山が、腹立たしかった。
裏切られたと思った。
(自分では何もしなかったくせに)
自分が好きだと言ったその口で、その体で、御幸のことも受け入れたのかと思うと、正気ではいられなくなりそうだった。本当はゆうべ、裸でいた佐山と御幸を見た時、ふたりとも殴り殺してやりたいくらいの気分になっていたのに。
そうしなかったのは、どこかで逃げ道を捜していたからだ。
必死になる自分が恥ずかしくて、口惜しかった。そんな取り乱したところを他人に見せたことなんて一度もない。
(そうだ、そんなことしたら)
――自分がまるで佐山のことを好きみたいだと思って、それがばれるのか怖かったのだ。
今まで自分を取り合って、自分に捨てられて、縋ってくる女たちを醜いと思った。鬱陶しいし、邪魔だと思った。
自分がそれと同列になるのが、どうしても許し難かった。
佐山はたとえ自分が他の女と寝ていることを知ったって、取り乱さないことができた。そんな佐山に、自分から好きになって、自分のことだけを見るように願うのは負けることだと、そうどこかで感じていた。
結局、自己保身だ。
(自分を守るために佐山さんのこと傷つけたのか、俺は)
それでも佐山が許してくれるだろうと、どこかで甘えていたことに秋口はようやく気づく。
それから、今でも佐山に許されたいと願っていることを。
◇◇◇
エスカレータから右手に白い包帯を巻いた佐山が下りてくるのをみとめて、秋口は寄り掛かっていた壁から身を起こした。
「――佐山さん」
決死の覚悟とか、悲愴な覚悟とか、そういう言葉がまったく相応しい気分で秋口はそう声をかける。
また殴られるか、罵られるか、無視して逃げられるか。
そのどれをされても話を聞いてもらう覚悟で。
緊張して強張った顔で、エスカレータから下りて自分に近づく佐山を見遣った秋口は、その表情が彼らしくやわらかくほころんだことを確認して、正直なところ一瞬深く安堵した。
(許してくれるのかもしれない)
少しだけ緊張を解いて自分からも近づいた秋口を、佐山が笑ったまま見上げる。
「お疲れ様、また明日」
「え」
社交辞令としか表現しようのない、だが完璧な笑顔でそう言って歩き去って行く佐山を、愚かなことに秋口は立ちつくして見送ってしまった。
佐山が自動ドアを越え、社外に出て行ったところでやっと我に返る。
「佐山さん、あの」
走って声をかけると、佐山は不思議そうな表情で振り返ったが、足は留めなかった。
「どうした?」
「時間、ありませんか。話がしたくて」
「打ち合わせなら、明日でも大丈夫だろ。T社の次の納品はまだ大分先だし」
「いや、仕事の話じゃなくて」
佐山は笑っているのに、秋口はその態度に強烈な違和感を覚えた。
自分の言葉がまったく通じていない。以前、もっと自分たちの関係が穏やかだった頃、自分が『捨てるぞ』なんて脅し文句を言った後でさえも、佐山はちゃんとこちらに向けて笑いかけてくれていた。
だが、違う。今は確実に違う。
その事実に、秋口はどうしようもなく焦燥感を覚えた。
焦る秋口に、佐山は申し訳なさそうな表情で微笑んで見せる。
「ごめん、今日はちょっと人と約束があるんだ。また今度」
やんわりと、だが確実に秋口を拒絶すると、思わず足を留める秋口を置いて佐山は駅の方へと去っていってしまった。
(約束――誰と?)
それが自分の誘いを断る口実なのか、それとも本当に誰かと会う約束があるのか、そんなことを考えて秋口はもう身動きが取れなくなる。御幸か沙和子なら一緒に会社を出るだろう。自分の知らない奴か、それとも。
(……そんなの今考えることじゃない)
今の自分に、そんなことを詮索して佐山を問いつめる資格がないことぐらい、秋口にもわかった。
それでも諦めきれずに、帰宅した後携帯電話から連絡してみたが繋がらず、メールの返事も来なかった。これも当然だ、と落胆しながら秋口は思った。
これまで自分のしてきたことを思い返すにつけ、どうして今日の昼間まででも佐山が自分につき合ってくれていたのか、その方が不思議だ。
(……どうして好きでいてくれたんだろう)
そう考えてから、秋口の中でもうそれが過去形になっていることに自分で気づいた。
これでもまだ佐山が自分に好意を持ってくれているなどと、思い上がることはできなくなってしまった。
そしてこんな状況にでもならなければ、自分が佐山と一緒にいられないことがどうしても辛いと、そう自覚できなったことも、理解する。
(どうしようもない)
こんなどうしようもない男に、佐山が二度と笑いかけてくれる可能性なんて、ゼロに等しい。
今の秋口にはそれしかわからなかった。
「――佐山さん」
決死の覚悟とか、悲愴な覚悟とか、そういう言葉がまったく相応しい気分で秋口はそう声をかける。
また殴られるか、罵られるか、無視して逃げられるか。
そのどれをされても話を聞いてもらう覚悟で。
緊張して強張った顔で、エスカレータから下りて自分に近づく佐山を見遣った秋口は、その表情が彼らしくやわらかくほころんだことを確認して、正直なところ一瞬深く安堵した。
(許してくれるのかもしれない)
少しだけ緊張を解いて自分からも近づいた秋口を、佐山が笑ったまま見上げる。
「お疲れ様、また明日」
「え」
社交辞令としか表現しようのない、だが完璧な笑顔でそう言って歩き去って行く佐山を、愚かなことに秋口は立ちつくして見送ってしまった。
佐山が自動ドアを越え、社外に出て行ったところでやっと我に返る。
「佐山さん、あの」
走って声をかけると、佐山は不思議そうな表情で振り返ったが、足は留めなかった。
「どうした?」
「時間、ありませんか。話がしたくて」
「打ち合わせなら、明日でも大丈夫だろ。T社の次の納品はまだ大分先だし」
「いや、仕事の話じゃなくて」
佐山は笑っているのに、秋口はその態度に強烈な違和感を覚えた。
自分の言葉がまったく通じていない。以前、もっと自分たちの関係が穏やかだった頃、自分が『捨てるぞ』なんて脅し文句を言った後でさえも、佐山はちゃんとこちらに向けて笑いかけてくれていた。
だが、違う。今は確実に違う。
その事実に、秋口はどうしようもなく焦燥感を覚えた。
焦る秋口に、佐山は申し訳なさそうな表情で微笑んで見せる。
「ごめん、今日はちょっと人と約束があるんだ。また今度」
やんわりと、だが確実に秋口を拒絶すると、思わず足を留める秋口を置いて佐山は駅の方へと去っていってしまった。
(約束――誰と?)
それが自分の誘いを断る口実なのか、それとも本当に誰かと会う約束があるのか、そんなことを考えて秋口はもう身動きが取れなくなる。御幸か沙和子なら一緒に会社を出るだろう。自分の知らない奴か、それとも。
(……そんなの今考えることじゃない)
今の自分に、そんなことを詮索して佐山を問いつめる資格がないことぐらい、秋口にもわかった。
それでも諦めきれずに、帰宅した後携帯電話から連絡してみたが繋がらず、メールの返事も来なかった。これも当然だ、と落胆しながら秋口は思った。
これまで自分のしてきたことを思い返すにつけ、どうして今日の昼間まででも佐山が自分につき合ってくれていたのか、その方が不思議だ。
(……どうして好きでいてくれたんだろう)
そう考えてから、秋口の中でもうそれが過去形になっていることに自分で気づいた。
これでもまだ佐山が自分に好意を持ってくれているなどと、思い上がることはできなくなってしまった。
そしてこんな状況にでもならなければ、自分が佐山と一緒にいられないことがどうしても辛いと、そう自覚できなったことも、理解する。
(どうしようもない)
こんなどうしようもない男に、佐山が二度と笑いかけてくれる可能性なんて、ゼロに等しい。
今の秋口にはそれしかわからなかった。
◇◇◇
翌日になっても、佐山は秋口のことを無視し続けた。
声をかければ応えるし、笑ってもくれるのに、それは確実に無視であり自分に対する否定だと、秋口にも伝わった。
仕事に託けて会いに行っても、本当に仕事のことしか話してくれない。昼食を誘っても、夕食を誘っても、休憩所に誘っても、穏やかに断られる。仕方なく声をひそめて開発課の佐山のデスク近くで話そうとすれば、仕事中だからと申し訳なさそうに退室を促される。
電話もメールも相変わらず繋がらないし、秋口はとうとう本当にどうしたらいいのかわからなくなってしまった。
「――で、俺に仲裁を頼むのか」
三日間佐山に無視続けられて、四日目に秋口は御幸に泣きついた。
就業時間中、急に廊下の隅へ呼び出されて『佐山と自分が話をできるように取り持って欲しい』と頼まれた御幸はすっかり呆れ顔で、その反応を予測していても秋口は居たたまれない気分になる。
「他に思いつかないんです、御幸さんの言うことなら、佐山さんも聞いてくれるかもしれないし……」
誰が見てもすっかり消耗している秋口を眺め、御幸がおかしそうに笑いを零した。
「佐山は、ああ見えて頑固だからなあ」
すっかり楽しんでいる風情だ。
「こうって決めたらてこでも動かないから、俺が何言ったって、本人が納得しない限り無駄だと思うぞ」
「だから、そこを説得してもらって」
「俺がその労力を割く理由がどこにあるのか、まずおまえが俺を説得できないとな」
大体、と御幸が言を継ぐ。
「何かするっていうなら、そんなことよりおまえに傷つけられた佐山を慰める方を選ぶに決まってるだろ」
秋口が反駁できないほどの正論だ。
「それに、おまえが佐山を傷つけたことを謝ったとして、同じことを繰り返さないなんて信頼が俺には一切ないわけだから。そもそもこういう問題を他力本願で解決しようなんて人間に、まともな謝罪とか償い自体ができるとも思わないし」
ひどい言われようだが、やはり秋口には反論の余地がない。
「そんなに話を聞いてもらいたいんなら、佐山を呼び出してふたりきりで話すなんて悠長なこと言わずに、人前で土下座なり泣き喚くなりすればあいつは聞いてくれるだろ。――秋口にそれができるとも思えないけど」
そう、その通りだ。結局のところ、佐山の仕事場や社内で強引に相手を呼び止めることができないのは、愁嘆場を演じているところを他人に見られることが許せない自分のプライドのせいだろう。
それがわかって、秋口はますます落ち込んだ。
「言っておくけどな」
黙り込む秋口に、御幸が冷たい声音で言う。
「俺が大事なのは佐山であって、佐山とおまえの関係じゃない。だから口出ししないって言った。その違いはわかれよ、俺だって何でわざわざおまえみたいのがいいのかは理解できないんだ。お門違いな頼み事はするもんじゃないよ」
「……ひとつわからないんですけど」
言うだけ言って去っていこうとする御幸に、秋口はやけくそ気味に訊ねた。
「そこまで俺がろくでもない相手だってわかっておきながら、どうして御幸さんは積極的に邪魔しなかったんですか。話聞いてるとやっぱり、御幸さんは特別佐山さんのことが好きだっていうふうにしか見えないし、おかしくありませんか」
そこで御幸が、盛大な溜息をついた。やれやれ、と表現するのが一番ぴったりな仕種だった。
「重症だ、どうしてそれで上手くいかないのか理解できない」
「……? 何がです?」
「自分がそうだからって他人まで同じだと決めつけるなって話だよ」
「はあ……」
御幸は最初に仲裁して欲しいと秋口が切りだした時よりも、遙かに呆れきった表情になっている。
「佐山のことを好きか嫌いかって言ったら、俺は愛してるけど」
やっぱり、と秋口は顔を強張らせる。御幸がまじめな表情でそんな秋口を見遣った。
「でもそれは、自分の家族に対するものと同じようなものなんだ。俺にとって佐山は尊敬に値する人間で、ある意味憧れてるって言っていい。もしくはコンプレックスを持ってるって表現した方が正しいか。こんな言葉、本当は使いたくないんだけどな」
「憧れ……コンプレックス?」
御幸こそが、周囲の人間に憧れられるほどの容姿を持ち、仕事の腕を持つ人間だから、秋口はその言葉がぴんとこなかった。
「おまえよりも長い間、ずいぶん深いところで佐山の存在が俺に関わってるってことだよ」
突き放されるようにそう言われて、秋口は自分でも手出しできない部分に御幸と佐山の関係があることを悟って、またいいしれない焦燥感を抱く。どうしようもない嫉妬心だ。
これ以上言うことはない、と言外に告げる態度で今度こそ踵を返した御幸の背に、秋口は苛立った声を叩きつけた。
「ますますおかしいですよ、じゃあどうして、そこまで大事な佐山さんに俺がちょっかいかけるのを、黙って見てられたのか」
御幸がまた足を留め、秋口の方を振り返る。苛立ちと焦りを隠しきれない秋口のことをしばらく眺めてから口を開いた。
「もし自分の大事な家族が、ブサイクで頭の悪い犬を拾って来たとして――」
自分を睨んでいる秋口に向けて、御幸は優しく慈愛に満ちた、貴公子然とした表情で微笑んで見せた。
「まさか『その犬はブサイクで頭が悪いから捨てて来なさい』なんて言えないだろう?」
「……」
「最終的に本人のあずかり知らぬところで保健所に連れて行くことはできるんだ。しばらくはそのバカ犬が言うことを聞くようになるのか黙って見守るよ」
秋口が二の句を継ぐことができないうちに、今度こそ御幸は自分のオフィスに戻っていった。
声をかければ応えるし、笑ってもくれるのに、それは確実に無視であり自分に対する否定だと、秋口にも伝わった。
仕事に託けて会いに行っても、本当に仕事のことしか話してくれない。昼食を誘っても、夕食を誘っても、休憩所に誘っても、穏やかに断られる。仕方なく声をひそめて開発課の佐山のデスク近くで話そうとすれば、仕事中だからと申し訳なさそうに退室を促される。
電話もメールも相変わらず繋がらないし、秋口はとうとう本当にどうしたらいいのかわからなくなってしまった。
「――で、俺に仲裁を頼むのか」
三日間佐山に無視続けられて、四日目に秋口は御幸に泣きついた。
就業時間中、急に廊下の隅へ呼び出されて『佐山と自分が話をできるように取り持って欲しい』と頼まれた御幸はすっかり呆れ顔で、その反応を予測していても秋口は居たたまれない気分になる。
「他に思いつかないんです、御幸さんの言うことなら、佐山さんも聞いてくれるかもしれないし……」
誰が見てもすっかり消耗している秋口を眺め、御幸がおかしそうに笑いを零した。
「佐山は、ああ見えて頑固だからなあ」
すっかり楽しんでいる風情だ。
「こうって決めたらてこでも動かないから、俺が何言ったって、本人が納得しない限り無駄だと思うぞ」
「だから、そこを説得してもらって」
「俺がその労力を割く理由がどこにあるのか、まずおまえが俺を説得できないとな」
大体、と御幸が言を継ぐ。
「何かするっていうなら、そんなことよりおまえに傷つけられた佐山を慰める方を選ぶに決まってるだろ」
秋口が反駁できないほどの正論だ。
「それに、おまえが佐山を傷つけたことを謝ったとして、同じことを繰り返さないなんて信頼が俺には一切ないわけだから。そもそもこういう問題を他力本願で解決しようなんて人間に、まともな謝罪とか償い自体ができるとも思わないし」
ひどい言われようだが、やはり秋口には反論の余地がない。
「そんなに話を聞いてもらいたいんなら、佐山を呼び出してふたりきりで話すなんて悠長なこと言わずに、人前で土下座なり泣き喚くなりすればあいつは聞いてくれるだろ。――秋口にそれができるとも思えないけど」
そう、その通りだ。結局のところ、佐山の仕事場や社内で強引に相手を呼び止めることができないのは、愁嘆場を演じているところを他人に見られることが許せない自分のプライドのせいだろう。
それがわかって、秋口はますます落ち込んだ。
「言っておくけどな」
黙り込む秋口に、御幸が冷たい声音で言う。
「俺が大事なのは佐山であって、佐山とおまえの関係じゃない。だから口出ししないって言った。その違いはわかれよ、俺だって何でわざわざおまえみたいのがいいのかは理解できないんだ。お門違いな頼み事はするもんじゃないよ」
「……ひとつわからないんですけど」
言うだけ言って去っていこうとする御幸に、秋口はやけくそ気味に訊ねた。
「そこまで俺がろくでもない相手だってわかっておきながら、どうして御幸さんは積極的に邪魔しなかったんですか。話聞いてるとやっぱり、御幸さんは特別佐山さんのことが好きだっていうふうにしか見えないし、おかしくありませんか」
そこで御幸が、盛大な溜息をついた。やれやれ、と表現するのが一番ぴったりな仕種だった。
「重症だ、どうしてそれで上手くいかないのか理解できない」
「……? 何がです?」
「自分がそうだからって他人まで同じだと決めつけるなって話だよ」
「はあ……」
御幸は最初に仲裁して欲しいと秋口が切りだした時よりも、遙かに呆れきった表情になっている。
「佐山のことを好きか嫌いかって言ったら、俺は愛してるけど」
やっぱり、と秋口は顔を強張らせる。御幸がまじめな表情でそんな秋口を見遣った。
「でもそれは、自分の家族に対するものと同じようなものなんだ。俺にとって佐山は尊敬に値する人間で、ある意味憧れてるって言っていい。もしくはコンプレックスを持ってるって表現した方が正しいか。こんな言葉、本当は使いたくないんだけどな」
「憧れ……コンプレックス?」
御幸こそが、周囲の人間に憧れられるほどの容姿を持ち、仕事の腕を持つ人間だから、秋口はその言葉がぴんとこなかった。
「おまえよりも長い間、ずいぶん深いところで佐山の存在が俺に関わってるってことだよ」
突き放されるようにそう言われて、秋口は自分でも手出しできない部分に御幸と佐山の関係があることを悟って、またいいしれない焦燥感を抱く。どうしようもない嫉妬心だ。
これ以上言うことはない、と言外に告げる態度で今度こそ踵を返した御幸の背に、秋口は苛立った声を叩きつけた。
「ますますおかしいですよ、じゃあどうして、そこまで大事な佐山さんに俺がちょっかいかけるのを、黙って見てられたのか」
御幸がまた足を留め、秋口の方を振り返る。苛立ちと焦りを隠しきれない秋口のことをしばらく眺めてから口を開いた。
「もし自分の大事な家族が、ブサイクで頭の悪い犬を拾って来たとして――」
自分を睨んでいる秋口に向けて、御幸は優しく慈愛に満ちた、貴公子然とした表情で微笑んで見せた。
「まさか『その犬はブサイクで頭が悪いから捨てて来なさい』なんて言えないだろう?」
「……」
「最終的に本人のあずかり知らぬところで保健所に連れて行くことはできるんだ。しばらくはそのバカ犬が言うことを聞くようになるのか黙って見守るよ」
秋口が二の句を継ぐことができないうちに、今度こそ御幸は自分のオフィスに戻っていった。
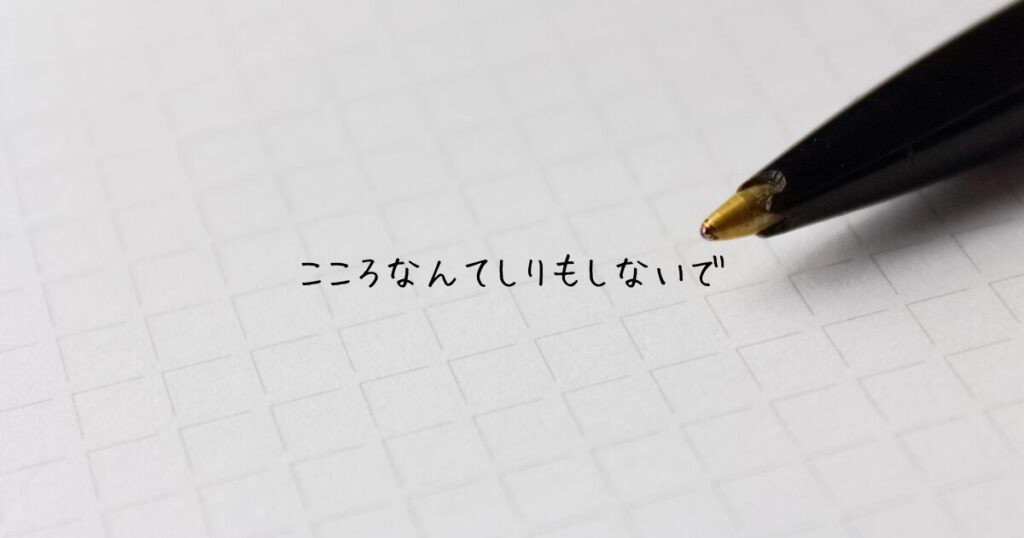
サラリーマン×サラリーマン

商業誌番外編

商業誌番外編

商業誌番外編
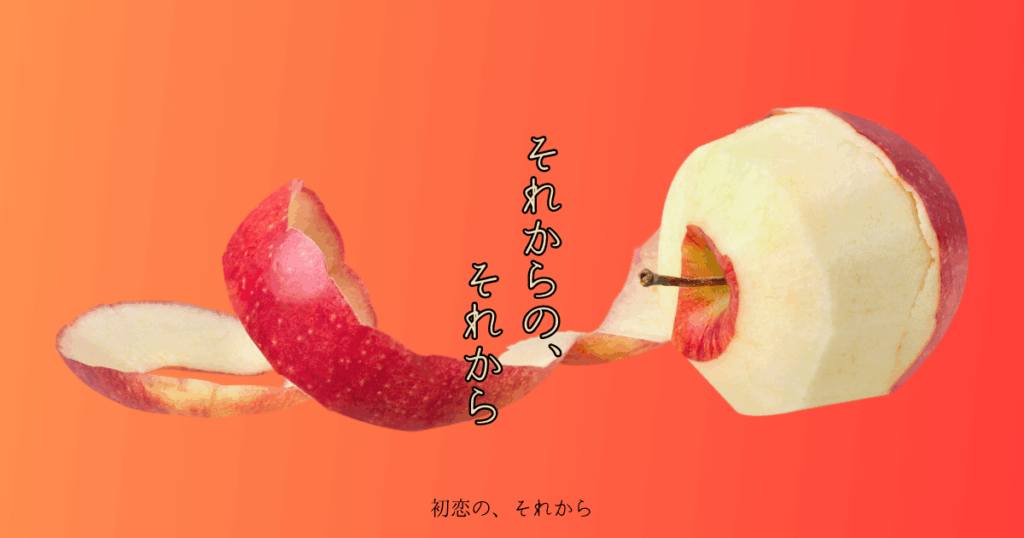
商業誌番外編
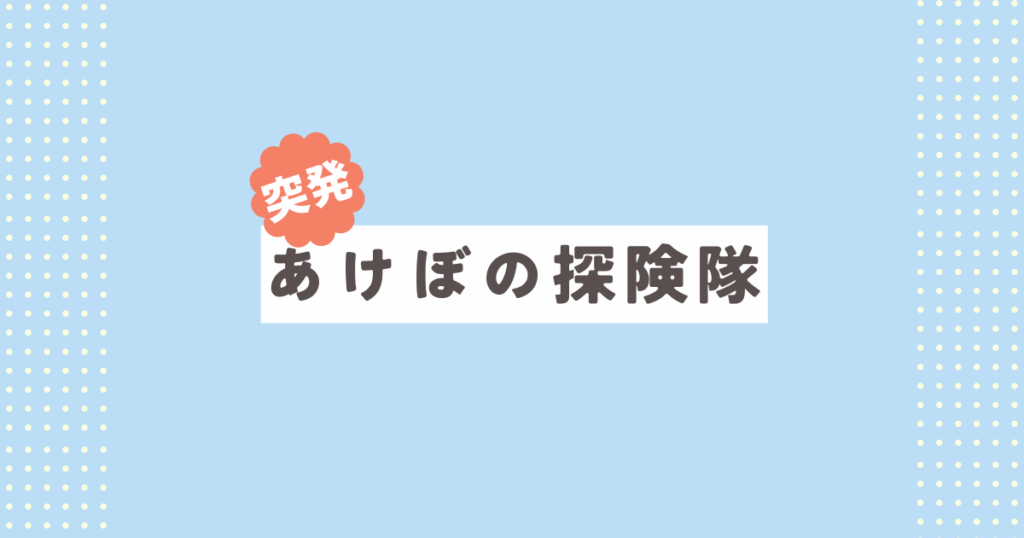
同人誌シリーズ番外編

高校生の恋未満読み切り