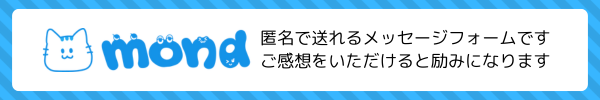九月に入ると、佐山は三日間だけ夏休みを取った。御幸は土日と有給を利用してもっと長い休みを取るよう主張したが、仕事が詰まっていることを理由に、佐山は結局短い休みだけを手に入れた。
暦の上ではもう秋とはいえ、まだ陽射しも厳しく蒸し暑い平日の午後、佐山はやかましく鳴く蝉の声を聞きながら、ひとつの建物の中にいた。
窓から見える景色はひどく牧歌的だ。畑があって、森がある。水のせせらぎも聞こえた。近くに川があるのだ。空はよく晴れ渡っていて、真っ青な色の中にぽっかりと白い雲が浮かんでいる。東京では到底お目にかかれない景色だった。
「あら、佐山さん、こんにちは」
廊下を通り掛かった白衣姿の女性看護師が、窓の外を眺めながらゆっくり廊下を進む佐山の姿をみとめ、そう声をかけてきた。佐山はその年配の看護師に小さく頭を下げる。
「こんにちは。暑いですね」
「でも東京に較べればずいぶん過ごしやすいでしょう。夏バテしてらっしゃるんじゃないの、少し顔色がお悪いわ」
優しい口調で言いながら、看護師が軽く首を傾げる。いえ、と佐山は曖昧に笑って済ませた。それから看護師の向こう、廊下の先へと視線を移す。
「今日は、具合がいいと電話でうかがったものですから」
「そうですね、ここのところだいぶいいみたいだから、お会いになっていかれたらいいと思いますよ。先生に許可をもらって下さいね」
看護婦に頭を下げ、佐山は再び廊下を歩き出した。
受付に寄り、もう長い間世話になっている医者と少し話をして、手続きをした後に、佐山は医者と一緒に入院病棟へと向かった。
歩きながら、佐山は少しずつ緊張していく。いつでもそうだ。この場所に訪れるたび。
『佐山治子』とプレートのかかったドアの前で、ふたり同時に立ち止まる。医者が先にその病室のドアをノックして、開いた。
「こんにちは、佐山さん、お客さんですよ」
さほど広くはない病室の窓際に白いベッド。体を起こして背中をベッドヘッドに凭れた浴衣姿の女性が、ゆっくりと振り返り、佐山の姿を見つけると目許に皺を寄せて微笑んだ。
「まあ……今日は来てくれると思ったのよ、夢が当たったわ」
「夢を見たの?」
微笑み返しながら、佐山はゆっくりベッドの方へ近づいた。医者は入口のところで待っている。佐山はベッドの側にある椅子へと腰を下ろした。治子の枯れ枝のように細い腕が伸びてきて、佐山の右手に触れる。その軽さに胸を痛めながら、佐山はもう一度彼女に笑い返した。
「ええ、今日はとても気分がいいし、きっといいことがあるって信じてたの」
治子が少女のようなはにかむ口調で言った。
「こんな格好で、ごめんなさいね。髪も梳いていないし……」
「病気なんだから、仕方ないよ。窓を開けていて大丈夫ですか。暑くはない?」
「夏は好きだもの。あら、今日は翼《つばさ》は一緒じゃないの?」
彼女の顔が見られず、点滴の針の刺さった細い腕を見られず、結局窓の外へと視線を向けた佐山は、緩い風に身を揺らす青い稲穂を眺めたまま少し動きを止めた。
「今日は、留守番」
一度息を吸い込んでから、声が強張らないように、掠れないように、精一杯優しい口調でそう告げる。
そう、と治子は残念そうに俯いた。
「あの子には寂しい思いをさせるわね。ねえあなた、翼のことお願いね。母親のわたしがいなくって、きっとひとりで泣いているわ。だからなるべく一緒にいてあげてね。ねえお父さん」
悲しげに懇願する彼女の掌を、佐山は安心させるように優しく握った。
暦の上ではもう秋とはいえ、まだ陽射しも厳しく蒸し暑い平日の午後、佐山はやかましく鳴く蝉の声を聞きながら、ひとつの建物の中にいた。
窓から見える景色はひどく牧歌的だ。畑があって、森がある。水のせせらぎも聞こえた。近くに川があるのだ。空はよく晴れ渡っていて、真っ青な色の中にぽっかりと白い雲が浮かんでいる。東京では到底お目にかかれない景色だった。
「あら、佐山さん、こんにちは」
廊下を通り掛かった白衣姿の女性看護師が、窓の外を眺めながらゆっくり廊下を進む佐山の姿をみとめ、そう声をかけてきた。佐山はその年配の看護師に小さく頭を下げる。
「こんにちは。暑いですね」
「でも東京に較べればずいぶん過ごしやすいでしょう。夏バテしてらっしゃるんじゃないの、少し顔色がお悪いわ」
優しい口調で言いながら、看護師が軽く首を傾げる。いえ、と佐山は曖昧に笑って済ませた。それから看護師の向こう、廊下の先へと視線を移す。
「今日は、具合がいいと電話でうかがったものですから」
「そうですね、ここのところだいぶいいみたいだから、お会いになっていかれたらいいと思いますよ。先生に許可をもらって下さいね」
看護婦に頭を下げ、佐山は再び廊下を歩き出した。
受付に寄り、もう長い間世話になっている医者と少し話をして、手続きをした後に、佐山は医者と一緒に入院病棟へと向かった。
歩きながら、佐山は少しずつ緊張していく。いつでもそうだ。この場所に訪れるたび。
『佐山治子』とプレートのかかったドアの前で、ふたり同時に立ち止まる。医者が先にその病室のドアをノックして、開いた。
「こんにちは、佐山さん、お客さんですよ」
さほど広くはない病室の窓際に白いベッド。体を起こして背中をベッドヘッドに凭れた浴衣姿の女性が、ゆっくりと振り返り、佐山の姿を見つけると目許に皺を寄せて微笑んだ。
「まあ……今日は来てくれると思ったのよ、夢が当たったわ」
「夢を見たの?」
微笑み返しながら、佐山はゆっくりベッドの方へ近づいた。医者は入口のところで待っている。佐山はベッドの側にある椅子へと腰を下ろした。治子の枯れ枝のように細い腕が伸びてきて、佐山の右手に触れる。その軽さに胸を痛めながら、佐山はもう一度彼女に笑い返した。
「ええ、今日はとても気分がいいし、きっといいことがあるって信じてたの」
治子が少女のようなはにかむ口調で言った。
「こんな格好で、ごめんなさいね。髪も梳いていないし……」
「病気なんだから、仕方ないよ。窓を開けていて大丈夫ですか。暑くはない?」
「夏は好きだもの。あら、今日は翼《つばさ》は一緒じゃないの?」
彼女の顔が見られず、点滴の針の刺さった細い腕を見られず、結局窓の外へと視線を向けた佐山は、緩い風に身を揺らす青い稲穂を眺めたまま少し動きを止めた。
「今日は、留守番」
一度息を吸い込んでから、声が強張らないように、掠れないように、精一杯優しい口調でそう告げる。
そう、と治子は残念そうに俯いた。
「あの子には寂しい思いをさせるわね。ねえあなた、翼のことお願いね。母親のわたしがいなくって、きっとひとりで泣いているわ。だからなるべく一緒にいてあげてね。ねえお父さん」
悲しげに懇願する彼女の掌を、佐山は安心させるように優しく握った。
◇◇◇
病院の建物を出ると、灼けつくような陽射しが落ちてきて、佐山は咄嗟に目を細めた。病院の建物から細い道を挟んだ向かい、駐車場のコンクリートの上には陽炎が揺れている。
掌を目の上に翳し、眼鏡の奥の目を陽射しから庇いながら、佐山はその陽炎の方へ向かって歩いた。道を通り過ぎる車はひとつもない。都心から、駅からずいぶんと離れた場所にあるこの土地を訪れる者は、この近くに住む人間の他は、病院に用のある患者か見舞い客しかいないのだ。
土地が余っているためかずいぶん広い駐車場には、数えるほどの車しか停まっていなかった。そのうち敷地の真ん中にぽつんと止められた青い車に、寄り掛かるように立っている友人の姿をみつけて、佐山は少し早足になった。
近づいてくる佐山に気づいて、御幸が片手を上げた。
「やっぱり外にいたのか、待合室にいないから」
「ちょっとその辺歩いてたんだよ。向こうにコンビニできててびっくりした、ほらこれ」
御幸が投げたミネラルウォーターのペットボトルを佐山は受け取った。
「もういいのか?」
訊ねられて頷いた佐山に頷きを返し、御幸が車の運転席のドアを開ける。佐山も助手席の方へ回り、シートに収まると、車が静かに発進した。
まだ陽が高い。擦れ違う車もない細い道で、御幸が黙ってハンドルを握っている。佐山も特に口を開かず、シートに深く凭れて目を閉じた。
ひどく疲労している。いつものことだ。胸に詰まる重い感触をやり過ごそうとするのに、病室での遣り取りを思い出しては深い溜息が漏れそうになった。
「いい天気だな」
ひとりごとのようにぽつりと言った御幸の言葉につられるように、佐山は瞼を開いた。
「窓開けていいか?」
訊ねると、自動で窓が開いた。生温い風を受けながら、佐山は開いた窓に頬杖をついて外の景色を眺める。
本当にいい天気だった。朝から快晴。いっそ雨が降ってくれればここに来ない言い訳になったのに、と考えてしまう自分を佐山は恥じた。
外をみつめる佐山の目から涙が伝っていることに、多分御幸は気づいていたが、何も言わなかった。そうすることが暗黙のルールだった。
高速道路を使っても三時間以上掛かる道のりを、佐山と御幸はほぼ無言で過ごした。高速を下りて、馴染んだ景色、ビルの建ち並ぶ通りへと差し掛かってから佐山はようやく口を開く。
「夕食、奢るよ。何がいい」
「そうだなあ、和食かな、美味い魚が食べたい」
不意に訊ねた佐山にすぐ応え、御幸が屈託のない口調で言った。こうして御幸が佐山の休暇に合わせて自分も有給を取り、車で遠い病院まで送り迎えした後は、佐山が食事を奢るのがここ数年来の恒例になっている。
御幸のリクエストした和食を出す店へと向かい、ふたりでゆっくりと座敷に座った。平日の夕方、店を訪れる客はそう多くない。
運ばれてきた料理に佐山はほとんど手を着けなかったが、御幸はそれについても何も言わず、自分は美味い美味いと上機嫌そうに言いながらすべて平らげた。
「佐山と外でゆっくり飯喰うのも、久しぶりだな」
食事の途中に御幸がそう言った。そういえばそうだ、と佐山も頷く。
「ここのところ、会っても食堂か休憩所だけだったしな。今日はわざわざありがとう、休み合わせてもらって、悪いな」
「ドライブに行く約束してただろ」
今日は水曜日だったから、連休にもならない単発の休みだ。申し訳ないと思いながらも、こうして自分のために時間を取ってくれる友人が佐山には心底からありがたかった。
「まだ時間、早いな。これからどうする」
食事を終えても、まだ午後八時前だった。佐山が会計をすませ、ふたりで駐車場に戻りながら、御幸が訊ねた。
「長い時間運転して、疲れただろ。移動するのは面倒じゃないか?」
「そうだな、駐車場捜すのも面倒だし……そうだ、久しぶりに佐山の家に行こうかな」
提案した御幸に、佐山は一瞬ぎくりと声を詰まらせた。
自分の部屋を思った時、浮かんだのは暗い部屋、軋むベッド、荒い息づかいと小さく漏れる声。ベッドの上にいるのはひとりじゃない。
「ああ、都合が悪ければ断っていいんだぞ?」
佐山の絶句をどう解釈したか、御幸が首を傾げてそう言った。
佐山は生々しい記憶を振り払うように、御幸に向かってぎこちなく笑って見せる。
「いいよ、散らかってるけど――」
「片付いてる佐山の部屋なんて、行ったことないだろ俺は」
「そうだ、その前に、悪いけどいったん会社に行ってもらえるか? 取ってきたい書類があるんだ」
そう頼んだ佐山に、御幸がわずかに眉根を寄せた。
「休みの時くらい、仕事のことなんか忘れろって。ただでさえ短い休暇なんだから」
「仕事してる方が気が紛れるんだよ」
佐山が答えると、御幸はもう何も言わなかった。きっと病院に行った自分の心境を気遣ってくれているのだろうと察して、佐山はひどく御幸に申し訳のない気分になった。それからわずかな自己嫌悪も味わう。
自分が一番考えなくてはならないのは、あの病室にいる寂しい女性のことなのに、病院から会社へと思いを馳せればもうそのことは忘れて、別の人のことで頭がいっぱいになっている。
せめてその相手のことを考えて幸福な気分を味わうことができるのならばまだ救いはあるのだが、状況はまったく逆だ。
(この時間なら、秋口はもう帰ってるかな)
そのことに、自分ががっかりしているのか、安堵しているのか、自分でもわからないまま佐山は御幸の車で会社に向かった。
夏休みのことを、佐山は何となく秋口に言いそびれていた。そんな話をするタイミングを掴めず休暇を迎えてしまった。
相変わらず、会社帰りに時間が合えば佐山の部屋でお互いの体に触れ合っているというのに、会話が弾む気配なんて微塵もないままだ。
佐山の休暇は明日で終わりだった。
(御幸の言うとおり、二週間くらい休みを取って、旅行にでも行けばよかったかも)
後悔は今さらだった。冷静に考える時間が欲しいと願いつつ、秋口に何日も会えないことが佐山にそれをためらわせた。
会いたいし、会いたくない。秋口は忙しいのか、昨日も今日もメールは来なかった。自分が会社にいないことに気づいているのか、いないのか、それすらも佐山にはわからない。
「佐山、着いたぞ」
ぼんやり物思いに耽っていると、御幸の声に呼ばれて佐山は我に返った。車は会社から少し離れた路肩に停められていた。御幸を車中に待たせておいてビルに向かう。開発課のオフィスに入ると、休みなのにわざわざ顔を見せるきまじめさを残業中の同僚に笑われた。
自分の机から書類を取って、再び社員用の通用口を抜けるまでの間は誰にも会わなかった。定時はとっくに過ぎている。秋口はもう帰宅したか、それとも残業しているのか。どっちにしろ顔を合わせたって、交わす話題もない。そう諦め、御幸を待たせては悪いと急ぎ足で表に出た佐山は、名前を呼ばれて竦むように足取りを止めた。
「佐山さん?」
はっとして、振り返る。御幸の車のある方、佐山が進もうとした道の反対側から、秋口が歩いてくるところだった。
「あれ、今日……休みじゃなかったです?」
「うん、ちょっと仕事取りに」
秋口は外回りからの帰りなのか、それとも買い出しにでもでかけていたのか、上着を手に少し驚いた顔で佐山のことを見ていた。手にした書類袋を佐山が見せると、秋口が軽く苦笑のような表情になる。
「何も夏休み中にまで会社に来ることないのに」
「明後日にはもう出社だから、気になるところは家でやっておきたくて」
「損するなあ」
秋口は呆れた様子ではあったが、佐山は彼と普通に言葉を交わせたことが嬉しかった。不意打ちで顔を合わせたことがむしろよかったのかもしれない。気構える暇もなかった。
「半端な時期だし、もうちょっと長く休めるように日程組めばいいのに」
「いいんだ、消化しないといけないから休んだだけだし」
笑って答えながら、佐山は少し胸が痛かった。昨日は一日秋口に会えず、自分はそのせいで湧き起こる感情を持て余していたというのに、秋口の方は平然と『もうちょっと長く休めばいいのに』などと言う。
(当然か)
気にする方がきっとおかしいのだ。
「今日は携帯、持ってないんですか?」
「え?」
もやもやと胸を覆う感情に力ずくで蓋をしようとあがいていた佐山は、秋口の問いに首を傾げた。
「いや、あるけど、ここに」
携帯電話はポケットに入れっぱなしだ。今日は朝出かける前に御幸と連絡を取ったきりで、後は着信音の鳴った覚えがない。
「電源切ってましたか。メール、入れたんだけど」
笑って訊ねる秋口に、佐山は慌てて携帯電話の液晶画面を見た。だがメールが届いた様子はない。
「ああ……圏外だったから、センターで止まっちゃってるのかも」
「携帯通じないようなところに行ってたんですか」
病院では電源を切っていたし、あの周辺は佐山の使っている携帯電話は通じない。
「うん、ちょっと、遠出して」
「どこに?」
おそらく世間話のついでのような秋口の問いに、佐山は咄嗟に返事をすることができなかった。
昼間見た青い空に浮かぶ雲や、病院の中の冷えた廊下、白い部屋、白いベッド、細い腕を思い出す。
それから――
『翼は一緒じゃないの?』
無邪気に問いかける掠れた声を。
「佐山さん?」
黙り込んでしまった佐山に、怪訝そうな秋口の声がかかる。
「ああ、うん、ちょっと……本当にちょっと、そこまで」
言葉を濁した佐山に、秋口がまた少し笑った。
「御幸さんと?」
気づくと、御幸の車がすぐそこまで来ていた。パワーウインドを下げ、運転席から顔を覗かせている。秋口と視線が合って、軽く手を挙げ挨拶をしていた。
「あっち、待たせてるんだ。それじゃあな」
逃げるように、佐山は秋口に背を向け御幸の車へと向かった。
秋口は何も言わず佐山の姿を見ていた。
掌を目の上に翳し、眼鏡の奥の目を陽射しから庇いながら、佐山はその陽炎の方へ向かって歩いた。道を通り過ぎる車はひとつもない。都心から、駅からずいぶんと離れた場所にあるこの土地を訪れる者は、この近くに住む人間の他は、病院に用のある患者か見舞い客しかいないのだ。
土地が余っているためかずいぶん広い駐車場には、数えるほどの車しか停まっていなかった。そのうち敷地の真ん中にぽつんと止められた青い車に、寄り掛かるように立っている友人の姿をみつけて、佐山は少し早足になった。
近づいてくる佐山に気づいて、御幸が片手を上げた。
「やっぱり外にいたのか、待合室にいないから」
「ちょっとその辺歩いてたんだよ。向こうにコンビニできててびっくりした、ほらこれ」
御幸が投げたミネラルウォーターのペットボトルを佐山は受け取った。
「もういいのか?」
訊ねられて頷いた佐山に頷きを返し、御幸が車の運転席のドアを開ける。佐山も助手席の方へ回り、シートに収まると、車が静かに発進した。
まだ陽が高い。擦れ違う車もない細い道で、御幸が黙ってハンドルを握っている。佐山も特に口を開かず、シートに深く凭れて目を閉じた。
ひどく疲労している。いつものことだ。胸に詰まる重い感触をやり過ごそうとするのに、病室での遣り取りを思い出しては深い溜息が漏れそうになった。
「いい天気だな」
ひとりごとのようにぽつりと言った御幸の言葉につられるように、佐山は瞼を開いた。
「窓開けていいか?」
訊ねると、自動で窓が開いた。生温い風を受けながら、佐山は開いた窓に頬杖をついて外の景色を眺める。
本当にいい天気だった。朝から快晴。いっそ雨が降ってくれればここに来ない言い訳になったのに、と考えてしまう自分を佐山は恥じた。
外をみつめる佐山の目から涙が伝っていることに、多分御幸は気づいていたが、何も言わなかった。そうすることが暗黙のルールだった。
高速道路を使っても三時間以上掛かる道のりを、佐山と御幸はほぼ無言で過ごした。高速を下りて、馴染んだ景色、ビルの建ち並ぶ通りへと差し掛かってから佐山はようやく口を開く。
「夕食、奢るよ。何がいい」
「そうだなあ、和食かな、美味い魚が食べたい」
不意に訊ねた佐山にすぐ応え、御幸が屈託のない口調で言った。こうして御幸が佐山の休暇に合わせて自分も有給を取り、車で遠い病院まで送り迎えした後は、佐山が食事を奢るのがここ数年来の恒例になっている。
御幸のリクエストした和食を出す店へと向かい、ふたりでゆっくりと座敷に座った。平日の夕方、店を訪れる客はそう多くない。
運ばれてきた料理に佐山はほとんど手を着けなかったが、御幸はそれについても何も言わず、自分は美味い美味いと上機嫌そうに言いながらすべて平らげた。
「佐山と外でゆっくり飯喰うのも、久しぶりだな」
食事の途中に御幸がそう言った。そういえばそうだ、と佐山も頷く。
「ここのところ、会っても食堂か休憩所だけだったしな。今日はわざわざありがとう、休み合わせてもらって、悪いな」
「ドライブに行く約束してただろ」
今日は水曜日だったから、連休にもならない単発の休みだ。申し訳ないと思いながらも、こうして自分のために時間を取ってくれる友人が佐山には心底からありがたかった。
「まだ時間、早いな。これからどうする」
食事を終えても、まだ午後八時前だった。佐山が会計をすませ、ふたりで駐車場に戻りながら、御幸が訊ねた。
「長い時間運転して、疲れただろ。移動するのは面倒じゃないか?」
「そうだな、駐車場捜すのも面倒だし……そうだ、久しぶりに佐山の家に行こうかな」
提案した御幸に、佐山は一瞬ぎくりと声を詰まらせた。
自分の部屋を思った時、浮かんだのは暗い部屋、軋むベッド、荒い息づかいと小さく漏れる声。ベッドの上にいるのはひとりじゃない。
「ああ、都合が悪ければ断っていいんだぞ?」
佐山の絶句をどう解釈したか、御幸が首を傾げてそう言った。
佐山は生々しい記憶を振り払うように、御幸に向かってぎこちなく笑って見せる。
「いいよ、散らかってるけど――」
「片付いてる佐山の部屋なんて、行ったことないだろ俺は」
「そうだ、その前に、悪いけどいったん会社に行ってもらえるか? 取ってきたい書類があるんだ」
そう頼んだ佐山に、御幸がわずかに眉根を寄せた。
「休みの時くらい、仕事のことなんか忘れろって。ただでさえ短い休暇なんだから」
「仕事してる方が気が紛れるんだよ」
佐山が答えると、御幸はもう何も言わなかった。きっと病院に行った自分の心境を気遣ってくれているのだろうと察して、佐山はひどく御幸に申し訳のない気分になった。それからわずかな自己嫌悪も味わう。
自分が一番考えなくてはならないのは、あの病室にいる寂しい女性のことなのに、病院から会社へと思いを馳せればもうそのことは忘れて、別の人のことで頭がいっぱいになっている。
せめてその相手のことを考えて幸福な気分を味わうことができるのならばまだ救いはあるのだが、状況はまったく逆だ。
(この時間なら、秋口はもう帰ってるかな)
そのことに、自分ががっかりしているのか、安堵しているのか、自分でもわからないまま佐山は御幸の車で会社に向かった。
夏休みのことを、佐山は何となく秋口に言いそびれていた。そんな話をするタイミングを掴めず休暇を迎えてしまった。
相変わらず、会社帰りに時間が合えば佐山の部屋でお互いの体に触れ合っているというのに、会話が弾む気配なんて微塵もないままだ。
佐山の休暇は明日で終わりだった。
(御幸の言うとおり、二週間くらい休みを取って、旅行にでも行けばよかったかも)
後悔は今さらだった。冷静に考える時間が欲しいと願いつつ、秋口に何日も会えないことが佐山にそれをためらわせた。
会いたいし、会いたくない。秋口は忙しいのか、昨日も今日もメールは来なかった。自分が会社にいないことに気づいているのか、いないのか、それすらも佐山にはわからない。
「佐山、着いたぞ」
ぼんやり物思いに耽っていると、御幸の声に呼ばれて佐山は我に返った。車は会社から少し離れた路肩に停められていた。御幸を車中に待たせておいてビルに向かう。開発課のオフィスに入ると、休みなのにわざわざ顔を見せるきまじめさを残業中の同僚に笑われた。
自分の机から書類を取って、再び社員用の通用口を抜けるまでの間は誰にも会わなかった。定時はとっくに過ぎている。秋口はもう帰宅したか、それとも残業しているのか。どっちにしろ顔を合わせたって、交わす話題もない。そう諦め、御幸を待たせては悪いと急ぎ足で表に出た佐山は、名前を呼ばれて竦むように足取りを止めた。
「佐山さん?」
はっとして、振り返る。御幸の車のある方、佐山が進もうとした道の反対側から、秋口が歩いてくるところだった。
「あれ、今日……休みじゃなかったです?」
「うん、ちょっと仕事取りに」
秋口は外回りからの帰りなのか、それとも買い出しにでもでかけていたのか、上着を手に少し驚いた顔で佐山のことを見ていた。手にした書類袋を佐山が見せると、秋口が軽く苦笑のような表情になる。
「何も夏休み中にまで会社に来ることないのに」
「明後日にはもう出社だから、気になるところは家でやっておきたくて」
「損するなあ」
秋口は呆れた様子ではあったが、佐山は彼と普通に言葉を交わせたことが嬉しかった。不意打ちで顔を合わせたことがむしろよかったのかもしれない。気構える暇もなかった。
「半端な時期だし、もうちょっと長く休めるように日程組めばいいのに」
「いいんだ、消化しないといけないから休んだだけだし」
笑って答えながら、佐山は少し胸が痛かった。昨日は一日秋口に会えず、自分はそのせいで湧き起こる感情を持て余していたというのに、秋口の方は平然と『もうちょっと長く休めばいいのに』などと言う。
(当然か)
気にする方がきっとおかしいのだ。
「今日は携帯、持ってないんですか?」
「え?」
もやもやと胸を覆う感情に力ずくで蓋をしようとあがいていた佐山は、秋口の問いに首を傾げた。
「いや、あるけど、ここに」
携帯電話はポケットに入れっぱなしだ。今日は朝出かける前に御幸と連絡を取ったきりで、後は着信音の鳴った覚えがない。
「電源切ってましたか。メール、入れたんだけど」
笑って訊ねる秋口に、佐山は慌てて携帯電話の液晶画面を見た。だがメールが届いた様子はない。
「ああ……圏外だったから、センターで止まっちゃってるのかも」
「携帯通じないようなところに行ってたんですか」
病院では電源を切っていたし、あの周辺は佐山の使っている携帯電話は通じない。
「うん、ちょっと、遠出して」
「どこに?」
おそらく世間話のついでのような秋口の問いに、佐山は咄嗟に返事をすることができなかった。
昼間見た青い空に浮かぶ雲や、病院の中の冷えた廊下、白い部屋、白いベッド、細い腕を思い出す。
それから――
『翼は一緒じゃないの?』
無邪気に問いかける掠れた声を。
「佐山さん?」
黙り込んでしまった佐山に、怪訝そうな秋口の声がかかる。
「ああ、うん、ちょっと……本当にちょっと、そこまで」
言葉を濁した佐山に、秋口がまた少し笑った。
「御幸さんと?」
気づくと、御幸の車がすぐそこまで来ていた。パワーウインドを下げ、運転席から顔を覗かせている。秋口と視線が合って、軽く手を挙げ挨拶をしていた。
「あっち、待たせてるんだ。それじゃあな」
逃げるように、佐山は秋口に背を向け御幸の車へと向かった。
秋口は何も言わず佐山の姿を見ていた。
◇◇◇
佐山の家に遊びに来た御幸は、部屋の掃除をしながら長い間話し込み、夜遅くになって車で帰っていった。
翌日佐山は一日寝て過ごした。それほど疲れた自覚はなかったのに、頭も体も疲労しきっていたようで、御幸が帰ったあとすぐベッドに潜り、目が覚めた時にはすでに陽が傾いていて驚いた。
さらに翌日、短い休暇を終えて佐山はまたいつもどおり会社へ向かった。
家にも資料を持ち帰ったせいで、滞りなく進む業務の合間、佐山は何度も携帯電話の画面を見た。
『昨日から姿が見えないので、風邪でもひいたのかと思っていました。夏休みなんですね。今何をしていますか』
送信者は秋口航。水曜日の昼過ぎ、ちょうど佐山が病院にいた時刻に送られて来たものだ。一昨日の夜、御幸の車で会社から自宅に戻る途中に届いた。
件名はなかったが、珍しく、ずいぶん長い本文だった。メールをすぐ受け取れなかったことを佐山は悔やんだが、どっちにしろその時『今何をしている』かなんて答えようがなかった。
(実の母親に、笑って人違いをされています――とか)
馬鹿正直に書くわけにもいかなかったし、嘘をつくのも気がひけた。
『昨日は返信できなくてごめん、やっぱりメールが止まっていたようで』
そう文字を打ちかけた途中で、佐山はそのメールを破棄した。メールが届かなかった事情なら昨日会って直接話したから、今さら繰り返すのも間が抜けている。かと言って、何ごともなかったかのように他の話題を送ることは難しかったし、そもそもそんなふうにメールで世間話をしたことはないのだ。
ただいつも、秋口から送られてくる、就業時間の連絡を待つだけで。
「……」
少し考えた後、佐山はひとつ決意して、昼休みを迎えた。時刻を報せる音楽放送を聞いてから、すぐに開発課のオフィスを出て、営業課の方へ向かう。
「秋口」
食堂に向かうために廊下へ出てきた秋口に呼びかけ、佐山は彼の方へ近づいた。
「はい」
足を止める秋口の前で自分も立ち止まり、佐山はその顔を見上げる。
「これから食事か?」
「外でね。接待ついでですよ」
秋口はちょっと肩を竦めるような格好をした。
「そうか……今日は、その、仕事は何時に終わるかな」
思い切って訊ねてみた佐山に、秋口は一瞬驚いたように目を瞠ってから、すぐに苦笑じみた表情になった。
「今日はちょっと。すみませんけど」
答えながら、秋口は腕時計を見てまた佐山に視線を戻した。
「もう行かないといけないので」「
「ああ、悪いな、呼び止めて」
秋口は小さく佐山に頭を下げると、廊下を歩いていってしまった。
「……」
その後ろ姿を見遣って、佐山はそっと溜息をつく。メールでは味気ないと思って直接訊ねてみたが、結果は空振りだ。
昨日の夕方に起き出してから、つい先刻まで、長い間考え続けて『やっぱり一度秋口ときちんと話をするべきだ』と答えを出した。別に自分たちの関係が何なのかとか、どうしてこんなことを続けるのかとか、そういう話をしたいわけじゃない。ただ、一昨日偶然会った時のように普通に会話ができるのなら、そうしたいと思っただけだ。
黙って、ただお互いの快楽を貪るような真似だけするのでは、あまりに虚しいと。
(まあ……どっちにしろ今日は会わないわけだし)
次の機会を捜そうと、佐山はとりあえず諦めた。
その日の定時を過ぎた後、佐山は御幸と落ち合って会社を出た。佐山に今日用事がないと知ると、御幸の方から食事に誘ったのだ。おそらく自分の心配をしてくれているのだろうと、佐山はすぐに察した。一昨日のように病院に向かった後、佐山が表に出さないようにしながらも、しばらくは塞ぎ込んでしまうことを御幸は知っているのだ。
御幸のおかげで気が紛れ、彼と食事をしている間は秋口のことも、病院でのことも考えずにすみ佐山は安堵した。ただ『今は考えずにいられた』と気づいた瞬間に、何かしらの思考を巡らせて塞ぎ込んでしまったりはするのだが、御幸が何も言わずそばにいてくれたので、やっぱりそれがありがたかった。
御幸に明日の朝一番で大きなプレゼンテーションがあると知って、そう遅くならない時間に佐山の方から帰宅を申し出た。会社の最寄り駅から少し離れた駅前で飲んでいたふたりは(佐山はいつもどおりお茶ですませたが)、店を出ると駅へ向かって歩き出した。
御幸が立ち止まったのは、その駅へと辿り着く少し手前の道半ばだった。
「あれ……」
「どうした?」
隣を歩いていた御幸が立ち止まってしまったので、つられて、佐山も足を留め相手を振り返る。
御幸は駅へ向かう大きな通りから、歓楽街へと続く路地の方を見遣っていた。
「御幸?」
「――いや、何でもない。ちょっと、知り合いに似てるのがいたと思ったけど、違ったみたいだ」
「そうか?」
御幸は何ごともなかったかのように佐山の隣に並び、佐山も彼と一緒に再び歩き出した。
改札を抜けて、それぞれ上りと下りのホームへ別れるまでの間、御幸は少し不機嫌そうに黙り込んでいた。他人を気遣うことの上手い御幸がそんな態度なのが珍しく、佐山は理由を問えずにいた。御幸から話さないのなら、自分が聞くべきことでもないだろうと判断する。
「それじゃ、またな」
別れる間際には、いつもの御幸らしい笑顔でそう言って手を振ったので、佐山はほっとして自分も手を上げて応えた。
御幸が駅前で誰を見たのかなんて、その時の佐山は思いつきもしなかった。
翌日佐山は一日寝て過ごした。それほど疲れた自覚はなかったのに、頭も体も疲労しきっていたようで、御幸が帰ったあとすぐベッドに潜り、目が覚めた時にはすでに陽が傾いていて驚いた。
さらに翌日、短い休暇を終えて佐山はまたいつもどおり会社へ向かった。
家にも資料を持ち帰ったせいで、滞りなく進む業務の合間、佐山は何度も携帯電話の画面を見た。
『昨日から姿が見えないので、風邪でもひいたのかと思っていました。夏休みなんですね。今何をしていますか』
送信者は秋口航。水曜日の昼過ぎ、ちょうど佐山が病院にいた時刻に送られて来たものだ。一昨日の夜、御幸の車で会社から自宅に戻る途中に届いた。
件名はなかったが、珍しく、ずいぶん長い本文だった。メールをすぐ受け取れなかったことを佐山は悔やんだが、どっちにしろその時『今何をしている』かなんて答えようがなかった。
(実の母親に、笑って人違いをされています――とか)
馬鹿正直に書くわけにもいかなかったし、嘘をつくのも気がひけた。
『昨日は返信できなくてごめん、やっぱりメールが止まっていたようで』
そう文字を打ちかけた途中で、佐山はそのメールを破棄した。メールが届かなかった事情なら昨日会って直接話したから、今さら繰り返すのも間が抜けている。かと言って、何ごともなかったかのように他の話題を送ることは難しかったし、そもそもそんなふうにメールで世間話をしたことはないのだ。
ただいつも、秋口から送られてくる、就業時間の連絡を待つだけで。
「……」
少し考えた後、佐山はひとつ決意して、昼休みを迎えた。時刻を報せる音楽放送を聞いてから、すぐに開発課のオフィスを出て、営業課の方へ向かう。
「秋口」
食堂に向かうために廊下へ出てきた秋口に呼びかけ、佐山は彼の方へ近づいた。
「はい」
足を止める秋口の前で自分も立ち止まり、佐山はその顔を見上げる。
「これから食事か?」
「外でね。接待ついでですよ」
秋口はちょっと肩を竦めるような格好をした。
「そうか……今日は、その、仕事は何時に終わるかな」
思い切って訊ねてみた佐山に、秋口は一瞬驚いたように目を瞠ってから、すぐに苦笑じみた表情になった。
「今日はちょっと。すみませんけど」
答えながら、秋口は腕時計を見てまた佐山に視線を戻した。
「もう行かないといけないので」「
「ああ、悪いな、呼び止めて」
秋口は小さく佐山に頭を下げると、廊下を歩いていってしまった。
「……」
その後ろ姿を見遣って、佐山はそっと溜息をつく。メールでは味気ないと思って直接訊ねてみたが、結果は空振りだ。
昨日の夕方に起き出してから、つい先刻まで、長い間考え続けて『やっぱり一度秋口ときちんと話をするべきだ』と答えを出した。別に自分たちの関係が何なのかとか、どうしてこんなことを続けるのかとか、そういう話をしたいわけじゃない。ただ、一昨日偶然会った時のように普通に会話ができるのなら、そうしたいと思っただけだ。
黙って、ただお互いの快楽を貪るような真似だけするのでは、あまりに虚しいと。
(まあ……どっちにしろ今日は会わないわけだし)
次の機会を捜そうと、佐山はとりあえず諦めた。
その日の定時を過ぎた後、佐山は御幸と落ち合って会社を出た。佐山に今日用事がないと知ると、御幸の方から食事に誘ったのだ。おそらく自分の心配をしてくれているのだろうと、佐山はすぐに察した。一昨日のように病院に向かった後、佐山が表に出さないようにしながらも、しばらくは塞ぎ込んでしまうことを御幸は知っているのだ。
御幸のおかげで気が紛れ、彼と食事をしている間は秋口のことも、病院でのことも考えずにすみ佐山は安堵した。ただ『今は考えずにいられた』と気づいた瞬間に、何かしらの思考を巡らせて塞ぎ込んでしまったりはするのだが、御幸が何も言わずそばにいてくれたので、やっぱりそれがありがたかった。
御幸に明日の朝一番で大きなプレゼンテーションがあると知って、そう遅くならない時間に佐山の方から帰宅を申し出た。会社の最寄り駅から少し離れた駅前で飲んでいたふたりは(佐山はいつもどおりお茶ですませたが)、店を出ると駅へ向かって歩き出した。
御幸が立ち止まったのは、その駅へと辿り着く少し手前の道半ばだった。
「あれ……」
「どうした?」
隣を歩いていた御幸が立ち止まってしまったので、つられて、佐山も足を留め相手を振り返る。
御幸は駅へ向かう大きな通りから、歓楽街へと続く路地の方を見遣っていた。
「御幸?」
「――いや、何でもない。ちょっと、知り合いに似てるのがいたと思ったけど、違ったみたいだ」
「そうか?」
御幸は何ごともなかったかのように佐山の隣に並び、佐山も彼と一緒に再び歩き出した。
改札を抜けて、それぞれ上りと下りのホームへ別れるまでの間、御幸は少し不機嫌そうに黙り込んでいた。他人を気遣うことの上手い御幸がそんな態度なのが珍しく、佐山は理由を問えずにいた。御幸から話さないのなら、自分が聞くべきことでもないだろうと判断する。
「それじゃ、またな」
別れる間際には、いつもの御幸らしい笑顔でそう言って手を振ったので、佐山はほっとして自分も手を上げて応えた。
御幸が駅前で誰を見たのかなんて、その時の佐山は思いつきもしなかった。
◇◇◇
夏休み明けの金曜日に一度出社すると、土曜日は午後から仕事をして、日曜日は休み、といささか中途半端なスケジュールになった。土曜日、秋口の出社予定はなかったようで、また二日間、佐山は彼に会うことができなかった。
月曜日の朝、佐山は秋口とまた直接顔を合わせるか、それともメールでとりあえず会って話がしたいということだけ伝えてみるかと迷いながら、結局そのどちらもできずに午前中の業務を終えた。
昼食を摂って午後、迷ってばかりの頭ではいまいち仕事がはかどらず、顔を洗って飲み物でも買って来るかと席を立ち、廊下に出る。
煙草が吸いたかったので休憩所に向かったが、数人の女子社員たちが場を占拠して煙を吐き出していたので、中に入っていくのが憚られた。自分も喫煙者ではありつつ、集団で煙草を吸う女性というのが佐山はどうも苦手だった。飲み物だけ買って外で一服するかと、他の課、顔見知りではない四、五人の女子社員の邪魔にならないように佐山は休憩所に入り、飲み物の自動販売機の前に立った。
「えー、じゃあ金曜、マジであんた秋口さんとあのまま一緒だったわけ?」
小銭がみつからず、千円札を自販機に入れた時、後ろの女子社員から聞こえた言葉に佐山は思わず動きを止めた。
すぐに小さく悲鳴のような笑い声が上がる。彼女たちは別の男性社員が現れたことには気づいて、声を少しひそめはしたものの、話すことをやめようとはしなかった。
「うっそ、やったじゃん、最近秋口さんつき合い悪くて声かけても全然遊びに連れてってくれなかったのに。何か口惜《くや》しー」
紙幣を受け入れ、商品を選ぶよう自販機のボタンが点灯する。ぽつんと赤い光を眺めながら、佐山はそのボタンのひとつを押した。
(あれ、コーヒーだな、これ)
ボタンを押してから、佐山は自分が飲めないものを選んでしまったことに気づいた。
(せめてミルクを入れればよかった)
後悔しても遅い。紙カップはもう下りてきて、注ぎ口からは琥珀色の液体が流れ落ちている。
「で? 次の日休みだったんだから当然」
からかうような、探るような女の声。別に今すぐこの場を立ち去ったってよかったのに、佐山は(まだコーヒーが入り終わっていない)と、自分が飲めもしない飲み物が出てくるのを馬鹿正直に待っている。
小さく、別の女の含み笑いが聞こえた。
「あたりまえ。ホテルご一泊コースに決まってるでしょ」
「ずるーい、今度あたしも誘ってみよ、あんたでオッケーならあたしだって行けるよ」
「うわムカつく、何だその言い種」
「でもそしたらこの辺みんな姉妹になっちゃうんじゃない?」
「え、そんなの今さらだって」
取り出し可能の電子音が短く響き、次におつりの小銭が落ちてくる音。先に小銭を拾ってしまおうと身を屈め、取り出し口に指先を入れるが、強張っていて上手く動かない。しまった、と思った時には、床へ小銭を散らしてしまった。
「あれ、大丈夫ですか」
音に気づいて振り返った女子社員が、佐山の姿を見て咄嗟にばつの悪そうな顔になった。「開発課の」「秋口さんと仲のいい」とひそひそ耳打ちしあう声を聞きながら、佐山は「秋口と仲なんかよかったっけ?」と疑問を浮かべ、落ちた小銭を拾った。
「はい、こっちにも落ちてましたよ」
「ありがとう」
小銭をいくつか拾ってくれた女子社員は、礼を言った佐山の顔を上目遣いに見上げると、いたずらっぽい口調で囁いてきた。
「こんなとこで秋口さんのこと話してたって、内緒にしておいて下さいね」
本当に困っている様子もなくそう告げる彼女に、佐山は心得たような笑いを返し、コーヒーカップを取り出すと休憩所を離れた。
歩きながら、妙に大きく鳴っている心臓を持て余す。何もしていないのに視界が揺れているようで気持ちが悪い。固い床が柔らかく波打っているようにも思えた。
その場にしゃがみ込んでしまいたい体をどうにか動かし、非常口から建物の外へと出て行く。狭い外階段の踊り場には誰もいない。ドアを閉めると、佐山はその鉄扉に背中で凭れ、目を閉じた。
(別に)
落ち着こうと吸った息が震えているのが自分でわかった。
(約束があったわけじゃないし)
悲しいでも腹が立つでもなく、ただ、立っているのも辛いほどに心を重い鉛で押さえつけられてしまったような感じだった。
(そもそもあの秋口が、俺以外と何もしないなんて思う方がどうかしてたわけだし)
どうしてここ最近の自分が、そんな可能性にすら思い至っていなかったのか、その方が不思議だった。もしかしたらあえて考えないようにしていたのかもしれないと自分で気づく。
(そんなこと承知の上で、秋口のこと好きになったんだろ)
好きな心が止められず、諦めようとしていたのにそれもできずに、何度も秋口と会って、何度も――
(でもせめて、俺の耳に届かないところであって欲しかった)
多分それは自分にとって贅沢な願いだったんだろうと、佐山はぼんやり笑いを浮かべながら、手に持ったままのコーヒーに口をつけた。
月曜日の朝、佐山は秋口とまた直接顔を合わせるか、それともメールでとりあえず会って話がしたいということだけ伝えてみるかと迷いながら、結局そのどちらもできずに午前中の業務を終えた。
昼食を摂って午後、迷ってばかりの頭ではいまいち仕事がはかどらず、顔を洗って飲み物でも買って来るかと席を立ち、廊下に出る。
煙草が吸いたかったので休憩所に向かったが、数人の女子社員たちが場を占拠して煙を吐き出していたので、中に入っていくのが憚られた。自分も喫煙者ではありつつ、集団で煙草を吸う女性というのが佐山はどうも苦手だった。飲み物だけ買って外で一服するかと、他の課、顔見知りではない四、五人の女子社員の邪魔にならないように佐山は休憩所に入り、飲み物の自動販売機の前に立った。
「えー、じゃあ金曜、マジであんた秋口さんとあのまま一緒だったわけ?」
小銭がみつからず、千円札を自販機に入れた時、後ろの女子社員から聞こえた言葉に佐山は思わず動きを止めた。
すぐに小さく悲鳴のような笑い声が上がる。彼女たちは別の男性社員が現れたことには気づいて、声を少しひそめはしたものの、話すことをやめようとはしなかった。
「うっそ、やったじゃん、最近秋口さんつき合い悪くて声かけても全然遊びに連れてってくれなかったのに。何か口惜《くや》しー」
紙幣を受け入れ、商品を選ぶよう自販機のボタンが点灯する。ぽつんと赤い光を眺めながら、佐山はそのボタンのひとつを押した。
(あれ、コーヒーだな、これ)
ボタンを押してから、佐山は自分が飲めないものを選んでしまったことに気づいた。
(せめてミルクを入れればよかった)
後悔しても遅い。紙カップはもう下りてきて、注ぎ口からは琥珀色の液体が流れ落ちている。
「で? 次の日休みだったんだから当然」
からかうような、探るような女の声。別に今すぐこの場を立ち去ったってよかったのに、佐山は(まだコーヒーが入り終わっていない)と、自分が飲めもしない飲み物が出てくるのを馬鹿正直に待っている。
小さく、別の女の含み笑いが聞こえた。
「あたりまえ。ホテルご一泊コースに決まってるでしょ」
「ずるーい、今度あたしも誘ってみよ、あんたでオッケーならあたしだって行けるよ」
「うわムカつく、何だその言い種」
「でもそしたらこの辺みんな姉妹になっちゃうんじゃない?」
「え、そんなの今さらだって」
取り出し可能の電子音が短く響き、次におつりの小銭が落ちてくる音。先に小銭を拾ってしまおうと身を屈め、取り出し口に指先を入れるが、強張っていて上手く動かない。しまった、と思った時には、床へ小銭を散らしてしまった。
「あれ、大丈夫ですか」
音に気づいて振り返った女子社員が、佐山の姿を見て咄嗟にばつの悪そうな顔になった。「開発課の」「秋口さんと仲のいい」とひそひそ耳打ちしあう声を聞きながら、佐山は「秋口と仲なんかよかったっけ?」と疑問を浮かべ、落ちた小銭を拾った。
「はい、こっちにも落ちてましたよ」
「ありがとう」
小銭をいくつか拾ってくれた女子社員は、礼を言った佐山の顔を上目遣いに見上げると、いたずらっぽい口調で囁いてきた。
「こんなとこで秋口さんのこと話してたって、内緒にしておいて下さいね」
本当に困っている様子もなくそう告げる彼女に、佐山は心得たような笑いを返し、コーヒーカップを取り出すと休憩所を離れた。
歩きながら、妙に大きく鳴っている心臓を持て余す。何もしていないのに視界が揺れているようで気持ちが悪い。固い床が柔らかく波打っているようにも思えた。
その場にしゃがみ込んでしまいたい体をどうにか動かし、非常口から建物の外へと出て行く。狭い外階段の踊り場には誰もいない。ドアを閉めると、佐山はその鉄扉に背中で凭れ、目を閉じた。
(別に)
落ち着こうと吸った息が震えているのが自分でわかった。
(約束があったわけじゃないし)
悲しいでも腹が立つでもなく、ただ、立っているのも辛いほどに心を重い鉛で押さえつけられてしまったような感じだった。
(そもそもあの秋口が、俺以外と何もしないなんて思う方がどうかしてたわけだし)
どうしてここ最近の自分が、そんな可能性にすら思い至っていなかったのか、その方が不思議だった。もしかしたらあえて考えないようにしていたのかもしれないと自分で気づく。
(そんなこと承知の上で、秋口のこと好きになったんだろ)
好きな心が止められず、諦めようとしていたのにそれもできずに、何度も秋口と会って、何度も――
(でもせめて、俺の耳に届かないところであって欲しかった)
多分それは自分にとって贅沢な願いだったんだろうと、佐山はぼんやり笑いを浮かべながら、手に持ったままのコーヒーに口をつけた。
◇◇◇
送信完了、のメッセージを確認してから、秋口は携帯電話を折りたたんで机の上に置く。
営業一課の自分の席に座り、まったく頭に入らない書類を眺め、我知らず溜息のような吐息を洩らした。
途端、携帯電話がメール着信のランプを点灯させて、秋口は慌てて再び電話を手に取った。画面を確認すると、別の課の女子社員からだった。
『週末は楽しかったです! また近々誘ってくださいね』
女の子らしく、絵文字を使った可愛いメールに、秋口は顔を顰めると簡単な操作でそのメールを削除した。反射的にそうしてしまってから、また溜息をついてしまう。
(何やってんだか)
週末、金曜の夜から秋口の胸を占めるのは、苦すぎる後悔の味ばかりだった。
(つまらないことした)
会社帰り、声をかけてきた女子社員とそのまま出かけた。最近ならもうずっとそういう誘いは断っていたのに、了承した自分の心理を秋口はおぼろげに自分でも理解している。
――多分、腹を立てていたのだ。
先週の火曜日から、佐山の姿が社内に見あたらず、メールを送ってみたのに返信もなかった。具合でも悪くしたのか、あの部屋にひとりで病に伏しているのでは気の毒だと、会社から電話をしようと思った時、二課の御幸も休んでいることに気づいた。
気になって同じ課の社員に訊ねれば御幸は有給休暇、佐山は夏休みだという。
まるで申し合わせたかのような休暇。まるで、ではなくてそのとおりなのだろう。ふたりの親しさは秋口も承知している。あの部屋、佐山の散らかりきった部屋を御幸は訪れて、掃除までして行くのだ。
自分が佐山の部屋を訪れるよりもずっと昔から。
そう思うと、秋口は何だか胸がもやもやして収まらなかった。佐山と御幸のことを考えると以前からそうだったが、より強いその感じに、もう誤魔化しが効かなくなっている。
自分には休みの日程も教えなかったくせに、御幸とは休みを示し合わせているのだ。きっと、一緒にどこかへ出かけているのだろう。
それに自分が腹を立てる必要はないことだった。そう思うのに、苛々して止まらない。
独占欲、なんて馬鹿げた単語が頭に浮かんだ時、秋口はうろたえた。今までどんな上等の女とつき合ったって味わったことのない、嫌な感触。相手に対してわずかな執着だって感じたことはない。たとえば沙和子に対する感情だって、彼女を好きだから他の男に渡したくないというよりも、この自分が声をかけたのに袖にするなんて許し難いと、そういうプライドが先立っていた。
佐山に対する自分の執着心に気づいた時、秋口はただうろたえて、なすすべを失った。
自分から電話の一本でもかけて、今どこにいるのかとか――会いたいのだとか、そういうことを伝えればいいのではと頭の片隅に方法は浮かんだのに、つまらない自尊心が邪魔をしてそれを正視できなかった。
おまけに、休暇中の佐山と偶然会社の前で会えた時、嬉しかったのに、その分やはり彼が御幸と一緒だったということを知って、どうしようもなく落胆して、やがてそれは理不尽な怒りに変わった。
だから休み明けに、珍しく佐山から誘われた時、断ってしまった。断ってすぐ後悔したが、『やっぱり一緒に帰りましょう』とは言えなかった。負ける気がして口惜しかったのだ。
それですぐ引き下がった佐山にも、『俺のことを好きなんだからもっと喰い下がればいいのに』などと八つ当たり気味に思い、その気分のまま女子社員に誘われて、出かけてしまった。
一緒に食事を摂って、酒を飲んで、その後はお定まりのコース。同じ会社の人間の目につかないよう、少し離れた駅のホテルで一夜を過ごした。
この夜が今までになく苦い時間で、秋口は狼狽を通り越して途方に暮れた。
柔らかい女の髪を撫でて、匂いを覚えて、体を抱いたのに、まるっきり充足感がなかったのだ。高い声を上げる女の喘ぎをうるさいと感じて、義務のように愛撫を繰り返して、ただ射精した。それだけだ。
キスをした時に感じた煙草の味は、秋口の嫌いなメンソールで、すぐにそれ以外の煙草の匂いを思い出し恋しい気分になった。
佐山との時は、触れ合って相手をいかせるだけで、秋口の認識では決してセックスと呼べるようなものではなかった。
なのに、佐山にはしない挿入もあった女に対する方が、味気なくて、つまらないと感じるなんて、どうかしている。
彼女を抱けば抱くほど、ここにはいない別の人に触れたいとか、匂いを感じたいとか、抱き締めたいとか――そんなことを思ってしまって、それを打ち消すのに苦労した。
彼女と土曜の朝に別れた時は、すっかり気疲れしてしまったほどだ。
家に帰るまで、帰ってからも、何度も携帯電話を開いては閉じる動きを繰り返した。多分自分が会いたいと佐山に連絡を取れば、佐山はすぐに了承してくれるだろう。それがわかっているのにできなかった。自分からそんなことをするのはどうしても許せなかった。
(佐山さんが俺のことを好きなんだから、佐山さんから動けばいい)
どうしてこの自分から、佐山と会いたいとか、別の人といるより自分を選んで欲しいとか、そんなことを懇願できるのか。相手は男で、しかも眼鏡で腕カバーで。そう侮るように思わなくては、今すぐにでも佐山のところに行って、あらぬことを口走ってしまいそうになる。それが秋口には怖かったし、これまでの人生を覆すようなことになりそうで、許容できなかった。
理性の片隅では、そんなプライドが馬鹿みたいにくだらないことだと、ちゃんとわかっているのに。
それをやっぱり正面から見ることができなくて、秋口はただいつものように、今日の仕事が終わる時間だけをメールする。
早く返事が来ないかと、音も鳴らない携帯電話を何度も見てしまう自分を、本当に馬鹿みたいだと思った。
営業一課の自分の席に座り、まったく頭に入らない書類を眺め、我知らず溜息のような吐息を洩らした。
途端、携帯電話がメール着信のランプを点灯させて、秋口は慌てて再び電話を手に取った。画面を確認すると、別の課の女子社員からだった。
『週末は楽しかったです! また近々誘ってくださいね』
女の子らしく、絵文字を使った可愛いメールに、秋口は顔を顰めると簡単な操作でそのメールを削除した。反射的にそうしてしまってから、また溜息をついてしまう。
(何やってんだか)
週末、金曜の夜から秋口の胸を占めるのは、苦すぎる後悔の味ばかりだった。
(つまらないことした)
会社帰り、声をかけてきた女子社員とそのまま出かけた。最近ならもうずっとそういう誘いは断っていたのに、了承した自分の心理を秋口はおぼろげに自分でも理解している。
――多分、腹を立てていたのだ。
先週の火曜日から、佐山の姿が社内に見あたらず、メールを送ってみたのに返信もなかった。具合でも悪くしたのか、あの部屋にひとりで病に伏しているのでは気の毒だと、会社から電話をしようと思った時、二課の御幸も休んでいることに気づいた。
気になって同じ課の社員に訊ねれば御幸は有給休暇、佐山は夏休みだという。
まるで申し合わせたかのような休暇。まるで、ではなくてそのとおりなのだろう。ふたりの親しさは秋口も承知している。あの部屋、佐山の散らかりきった部屋を御幸は訪れて、掃除までして行くのだ。
自分が佐山の部屋を訪れるよりもずっと昔から。
そう思うと、秋口は何だか胸がもやもやして収まらなかった。佐山と御幸のことを考えると以前からそうだったが、より強いその感じに、もう誤魔化しが効かなくなっている。
自分には休みの日程も教えなかったくせに、御幸とは休みを示し合わせているのだ。きっと、一緒にどこかへ出かけているのだろう。
それに自分が腹を立てる必要はないことだった。そう思うのに、苛々して止まらない。
独占欲、なんて馬鹿げた単語が頭に浮かんだ時、秋口はうろたえた。今までどんな上等の女とつき合ったって味わったことのない、嫌な感触。相手に対してわずかな執着だって感じたことはない。たとえば沙和子に対する感情だって、彼女を好きだから他の男に渡したくないというよりも、この自分が声をかけたのに袖にするなんて許し難いと、そういうプライドが先立っていた。
佐山に対する自分の執着心に気づいた時、秋口はただうろたえて、なすすべを失った。
自分から電話の一本でもかけて、今どこにいるのかとか――会いたいのだとか、そういうことを伝えればいいのではと頭の片隅に方法は浮かんだのに、つまらない自尊心が邪魔をしてそれを正視できなかった。
おまけに、休暇中の佐山と偶然会社の前で会えた時、嬉しかったのに、その分やはり彼が御幸と一緒だったということを知って、どうしようもなく落胆して、やがてそれは理不尽な怒りに変わった。
だから休み明けに、珍しく佐山から誘われた時、断ってしまった。断ってすぐ後悔したが、『やっぱり一緒に帰りましょう』とは言えなかった。負ける気がして口惜しかったのだ。
それですぐ引き下がった佐山にも、『俺のことを好きなんだからもっと喰い下がればいいのに』などと八つ当たり気味に思い、その気分のまま女子社員に誘われて、出かけてしまった。
一緒に食事を摂って、酒を飲んで、その後はお定まりのコース。同じ会社の人間の目につかないよう、少し離れた駅のホテルで一夜を過ごした。
この夜が今までになく苦い時間で、秋口は狼狽を通り越して途方に暮れた。
柔らかい女の髪を撫でて、匂いを覚えて、体を抱いたのに、まるっきり充足感がなかったのだ。高い声を上げる女の喘ぎをうるさいと感じて、義務のように愛撫を繰り返して、ただ射精した。それだけだ。
キスをした時に感じた煙草の味は、秋口の嫌いなメンソールで、すぐにそれ以外の煙草の匂いを思い出し恋しい気分になった。
佐山との時は、触れ合って相手をいかせるだけで、秋口の認識では決してセックスと呼べるようなものではなかった。
なのに、佐山にはしない挿入もあった女に対する方が、味気なくて、つまらないと感じるなんて、どうかしている。
彼女を抱けば抱くほど、ここにはいない別の人に触れたいとか、匂いを感じたいとか、抱き締めたいとか――そんなことを思ってしまって、それを打ち消すのに苦労した。
彼女と土曜の朝に別れた時は、すっかり気疲れしてしまったほどだ。
家に帰るまで、帰ってからも、何度も携帯電話を開いては閉じる動きを繰り返した。多分自分が会いたいと佐山に連絡を取れば、佐山はすぐに了承してくれるだろう。それがわかっているのにできなかった。自分からそんなことをするのはどうしても許せなかった。
(佐山さんが俺のことを好きなんだから、佐山さんから動けばいい)
どうしてこの自分から、佐山と会いたいとか、別の人といるより自分を選んで欲しいとか、そんなことを懇願できるのか。相手は男で、しかも眼鏡で腕カバーで。そう侮るように思わなくては、今すぐにでも佐山のところに行って、あらぬことを口走ってしまいそうになる。それが秋口には怖かったし、これまでの人生を覆すようなことになりそうで、許容できなかった。
理性の片隅では、そんなプライドが馬鹿みたいにくだらないことだと、ちゃんとわかっているのに。
それをやっぱり正面から見ることができなくて、秋口はただいつものように、今日の仕事が終わる時間だけをメールする。
早く返事が来ないかと、音も鳴らない携帯電話を何度も見てしまう自分を、本当に馬鹿みたいだと思った。
◇◇◇
八時過ぎに仕事が終わる、と秋口からメールが来たのは、長い休憩を佐山が非常階段で過ごし、ようやく自分のデスクに戻ってきた時だった。
「……」
携帯電話の液晶画面を、佐山はうつろな気分で眺める。
(何でだろう)
秋口の気に入られようと必死になる、綺麗な女の子たちは他に山ほどいるのに、どうして秋口は今日も自分にこんなメールを送ってくるのか。
(まあ、俺が責める筋合いじゃないか)
むしろ、誘ってくれるのを喜ぶべきなのだと思う。どっちにしたって自分はまだ秋口が好きだ。他の人と会う代わりにでも自分を選んでくれるのなら、少なくともその間だけは、秋口は他の誰かと一緒にいることはない。
そう頭ではわかっていても、メールを見て純粋に喜べることなんてなく、佐山はそのまま携帯電話を閉じてしまった。
今日はまったく仕事が進んでいない。これではいけないと、佐山は手許の作業に頭を集中させるため図面を眺めた。仕事に没頭すれば余計なことを考えずにすむ。だが、休憩の後から胃の辺りが痛んで、落ち着いて椅子に座っていることも難しかった。医者にも止められているコーヒーを、しかもブラックで一杯綺麗に飲み干してしまったのだ。
こんな時に限って、常備していたはずの胃薬が切れている。残業をしなくてはならないと思っていたのに、この体調では仕方がない。佐山は定時のチャイムが鳴る少し前に席を立って、医務室へ向かおうと廊下に出た。
「佐山さん」
胃の上を無意識に手で押さえて廊下を歩いていると、後ろから声をかけられた。その聞き覚えのある声に、佐山は身の竦む思いで立ち止まる。態度に出さないよう、咄嗟に自分に言い聞かせながら振り返った。
「――顔色悪いですけど、具合でも?」
振り向いた佐山を見て、秋口がかすかに表情を曇らせた。佐山は苦笑気味に首を横に振ってみせる。いろいろ説明するのが面倒だった。
「大したことないんだ」
「そういう様子にも見えませんけど……」
話を早く打ち切りたくて、佐山は無理に笑顔を浮かべた。秋口は当惑した表情になったが、それ以上は何も言わなかった。代わりに、本来の用件であるらしいことを訊ねてくる。
「メール、届きませんでしたか」
「ああ……ごめん、忙しくて。今日は駄目だ、ごめん」
考えるより先にそう答えてから、佐山はそれが当てつけのように聞こえはしないかと背筋を冷やした。だがすぐに、秋口は自分が先刻の彼女たちの会話を聞いたことは知らないし、それにそう思われても別段どうでもいいかと考えるのをやめた。
「佐山さん、本当に具合が悪いんじゃないですか?」
曖昧な笑顔を浮かべ、腹を押さえたままの佐山に、秋口はますます眉根を寄せ、顔を覗き込んできた。
近づいて来た秋口から、微かに嗅ぎ慣れた匂いがする。煙草とか、整髪料とか、そして体温とか、それを間近に感じて、佐山は逃げ出したくなる。
この感触を、あの休憩所にいた彼女たちが、その他の女の子たちが、自分と同じように味わったのだと思うと、逃げ出したいのに身動きも取れないくらい体が強張った。
「佐山さん」
口許を掌で押さえる佐山に、秋口が驚いて肩を支えようと手を伸ばしてきた。
反射的に、佐山はその手を反対の手で押し退けた。驚いた顔になる秋口を見ていられず、佐山は俯いた。
「ごめん、ちょっと、吐き気がして……」
「医務室に行きますか」
「大丈夫、ひとりで行ける」
一緒に歩き出そうとする秋口を言葉で制し、佐山はよろめきそうな足許を叱咤して歩き出した。
秋口は何も言わなかったが、気懸かりそうな視線を佐山は自分の背に感じた。だが振り返らず、とにかく秋口の目に届かないところへ行こうと、早足で廊下を進んだ。
医務室は違うフロアの片隅にある。覚束ない足取りで階段を下り、医務室目指して廊下を進んでいると、次には別の声が聞こえた。
「佐山さん」
今度は誰だ、と俯きがちだった顔を上げると、書類を抱え、驚いた顔をしている沙和子の姿が佐山の目に映った。
医務室があるフロアには、彼女のいる総務部もあったことを佐山は思い出す。
「どうしたの、大丈夫。ひどい顔色よ」
沙和子はすぐに駆け寄ってくると、佐山の腕に細い手を置き、心配げに顔を覗き込んできた。それからポケットを探ってハンカチを取り出し、脂汗の浮かぶ佐山の額をそっと拭った。
「医務室へ行くのね。歩ける?」
「大丈夫、ひとりで行けるから」
「駄目、すぐそこだから、一緒に行くわ」
佐山の言葉に聞く耳を持たず、沙和子は佐山の体を支えて歩き出した。医務室までゆっくり進むと、沙和子が自分のIDカードでドアを開け、佐山と一緒に中へ入った。仮眠用のベッドとソファ、薬の置かれた棚があるだけの部屋には誰もいない。医務室といっても簡素なものだ。
「また胃が痛むの?」
とりあえず佐山をソファに座らせながら、沙和子がそう訊ねてくる。彼女とつき合っていた頃もこんなことがあった。佐山はそう思い出しながら苦笑いを浮かべ、頷く。
「コーヒー、飲んじゃって」
「飲んだら駄目って言われてるのに。無理しないで」
困った顔で言ってから、沙和子が薬品棚に向かい、胃薬を一包み取り出した。薬を佐山に渡すと、一度医務室を出て行ってから、すぐにミネラルウォーターを手に戻ってくる。
「ありがとう」
ありがたく、佐山は沙和子のくれた水で胃薬を飲み下し、ソファに深く凭れた。
沙和子が佐山の隣へ腰を下ろす。
「ごめん、沙和――雛川さんも、仕事中だろ。大丈夫だから戻っていいよ」
「急ぎの仕事はないから、平気」
答えてから、沙和子が小さく笑った。
「『沙和子』でいいのに」
「君を好きな人に悪いよ」
「いないわ」
沙和子は膝の上で指を組み、その指に視線を落として小さな声で言った。
「とっくに別れて、今は誰もいない」
「……」
どう答えていいのかわからず、佐山は黙り込んだ。沙和子も口を閉ざした。しばらくふたりして黙っていると、薬のお陰で少しずつ胃の痛みがひいてきて、佐山はほっと細い息を吐いた。
そのタイミングで、沙和子がまた口を開く。
「久しぶりね、ふたりでゆっくり話すの」
「そうか……そうだな」
別れてから数年、おそらく沙和子の方から佐山を避けていて、ふたりきりになることも、落ち着いて言葉を交わすこともなかった。
長い時間空白があるのに、思いのほか自然と彼女と話せるのが佐山には不思議だった。
「ずっと話したい、話したいって思ってたけど、何て言うか……気がひけて、なかなか声がかけられなかったの。わたし、佐山さんにずいぶんひどいことしたから」
「いいよ。俺も沙和子にはいろいろ大変なこと強いてたって、あとから大分反省した」
彼女とつき合っていた間のことを、佐山は思い出す。沙和子は綺麗で、頭がいいだけではなく、佐山にとって『都合のいい』相手だった。
理想の結婚相手、という意味で。
「断るのも辛かっただろうと思う、ごめん」
結婚して早く家庭を持ちたい佐山と、まだ結婚なんて現実味すら持てない沙和子と、そこが喰い違って結局別れた。
しかも佐山との結婚には普通とは言い難い事情がついて来る。沙和子ならばそれも受け入れてくれると信じてしまった自分のせいで、彼女には辛い思いをさせたと、彼女と別れた後も佐山にはそれが気に懸かっていた。
「この間、夏休みを取ったでしょう。――お母様のお見舞い、行ってきたの?」
おそらく佐山と同じことを考えていたのだろう、沙和子が遠慮がちにその話題を口に乗せた。
「うん。御幸がまた車出してくれたから」
「お加減、どうでした」
やはり遠慮がちな沙和子の口調に、佐山は少し笑って、ソファに凭れたまま医務室の天井を見上げた。
「体の方は割合調子がいいようだけど……相変わらず。俺の顔見て、翼はいないのかって聞いてきた」
「……」
ごめんなさい、と微かな声で呟いた沙和子に、佐山はもう一度笑って見せた。
「それで母が倖せならいいと思うんだ、久しぶりに直接顔を見られて運がよかったし。いつもなら面会はできないところを、数分間だけでも会えたんだから」
「そう……よかったわね」
優しく言う沙和子に、佐山が頷いた時、医務室の外でIDカードを認証する電子音が聞こえた。すぐにドアが開く。
現れた秋口に、佐山は目を見開いた。
「秋口――」
秋口は秋口で、佐山と一緒にいる沙和子を見て、驚いた顔になっていた。沙和子が佐山の腕に触れていた指先をそっと離す。
その様子に気づいた秋口が、皮肉っぽい表情で口端を持ち上げ、笑った。
「何だ。具合が悪いみたいだから心配して来たけど、お邪魔だったみたいですね」
「途中で会って、心配してついてきてくれたんだ。ごめん雛川さん、助かった。仕事に戻って」
いわれのないことで邪推されては沙和子が可哀想だと、佐山は秋口から目を逸らして彼女に言った。
「俺も戻るよ、どうもありがとう」
沙和子は戸惑った様子ながら、佐山にそう言われると頷き立ち上がった。秋口の方を気にするように見上げてから、出口のところで佐山のことを振り返る。
「また今度、ゆっくり話ができる?」
「うん。そのうちに」
ほっとしたように笑って、沙和子が医務室を出て行った。
笑みを消し、佐山は自分も出て行こうとソファから立ち上がってから、そばにあった備え付けのノートに、使った薬の名前と『開発課・佐山翼』とペンで書きつけ、印鑑を押す。
なるべく秋口の方を見ないように立ち去ろうと思っていたのに、ノートを閉じて出口へ向かった佐山の前には、無表情の秋口が立ちはだかっていた。
「ごめん、仕事に戻らないと。退いてくれるか」
「雛川さんとより、戻す気ですか」
秋口がドアの前から退いてくれないと外には出られない。困って立ちつくす佐山の前で、やはり身動きもせず、冷たい口調で秋口が訊ねた。急にそんなことを問われて、佐山はつい、混乱する。
「そんなつもりないよ、沙和子の方から別れたんだ、向こうにだってそんな気ないだろうし」
「その沙和子さんと、あんたはどういうつもりでこんなとこでふたりきりだったのかって訊いてるんですよ」
秋口の冷たい詰問口調に、佐山は胸をざわつかせた。
何だかとても不快な感覚だった。
「秋口が気にするところじゃないだろ」
ついそう吐き捨てると、乱暴に腕を掴まれ、佐山は驚いて秋口を見上げた。
「質問してるんだから、答えればいいんですよ。やましいことでもあるから誤魔化すんですか?」
「やましい――って、俺は別に」
なぜこんなことを訊かれなくてはならないのか、佐山はますます混乱した。秋口の言葉はまるで沙和子といた自分を責めているようで、だったらなぜ自分が彼にそんなことを責められればいけないのかと、何か口惜しい気分になる。
(自分だって)
浮かぶ思いは、それこそ自分の責める筋合いではないはずなのに、腹が立つ。
(他の人と一緒にいたのに)
秋口が何のつもりで今ここにいるのか、佐山は理解できなかった。
「秋口も仕事の途中だろ、心配してくれて嬉しいけど、薬も飲んだし、もう大丈夫だから」
「だから誤魔化すなって言ってんだよ」
さらにきつく腕を掴まれ、佐山は痛みに顔を歪め、秋口のことを睨むように見上げた。
腹が立って仕方がなかった。
「秋口だって先週、他の子と遊びに行ったんだろ」
怒った顔で自分を睨む佐山の表情と、その口から出た言葉に、秋口が虚をつかれたように表情を失くす。佐山はそのまま秋口から顔を逸らした。
「俺は、沙和子とは何もない。本当にたまたまとおりがかかったからここに連れてきてくれただけだ。……秋口の方は、ホテルまで行ったんだって女の子が話してるの聞いたけど」
秋口に掴まれた腕が痛い。振り払いたかったが、力で敵わなかった。
「他にあてがあるなら、何も俺なんかにわざわざつき合ってくれなくてもいいんだ。頼んだわけじゃない。周りにいくらでも相手をしてくれる人たちがいるんだから」
「俺のこと好きなくせに?」
「――」
吐き出された一言が信じられずに、佐山は強張った顔を秋口の方に向けた。
「当てつけみたいな女々しいこと言わないでくださいよ。俺が他に相手するのがいたら、何だっていうんですか」
秋口は笑っていた。笑っているのに、見上げた佐山の背筋が冷えるほどの怒りが見て取れた。何かが秋口の神経を逆撫でしたのはわかったが、それで自分が謝る必要はないと、佐山は唇をひき結んだまま秋口を見上げる。
その表情に、秋口は笑顔も消して、掴んだ佐山の腕を引いた。驚いた佐山が抵抗する間もなく、乱暴にソファの上に体を投げ出された。
「痛……ッ」
ソファの固いところに手足をぶつけ、顔を顰める佐山の上に、秋口が覆いかぶさって来る。佐山はその体を押し退けて立ち上がろうとするが、苛立った動きの秋口に肩を押さえつけられ、身動きが取れなかった。
「やめろよ」
ひどく惨めな気分で、佐山はただ手足をばたつかせた。秋口は佐山の抵抗など微塵も気に懸けない素振りで、佐山の眼鏡を外してしまった。
口惜しくて、情けなくて、涙の滲みかけた目では秋口の表情はわからない。その顔が近づいてきたとわかった時、精一杯首を逸らして逃げようとしたが、強く顎を掴まれて適わなかった。
「あんたとやるメリットなんて、孕まないことと、女みたいにぐちぐち言わないことなんだから。黙ってろよ、俺のこと好きなんだろ。余計なこと言うなら捨てるぞ」
間近で聞こえた声が信じられず、佐山は呆然とした頭で秋口の接吻けを受けた。
まなじりからこめかみを伝って流れる涙の感触を、他人事みたいに味わっていた。
「……」
携帯電話の液晶画面を、佐山はうつろな気分で眺める。
(何でだろう)
秋口の気に入られようと必死になる、綺麗な女の子たちは他に山ほどいるのに、どうして秋口は今日も自分にこんなメールを送ってくるのか。
(まあ、俺が責める筋合いじゃないか)
むしろ、誘ってくれるのを喜ぶべきなのだと思う。どっちにしたって自分はまだ秋口が好きだ。他の人と会う代わりにでも自分を選んでくれるのなら、少なくともその間だけは、秋口は他の誰かと一緒にいることはない。
そう頭ではわかっていても、メールを見て純粋に喜べることなんてなく、佐山はそのまま携帯電話を閉じてしまった。
今日はまったく仕事が進んでいない。これではいけないと、佐山は手許の作業に頭を集中させるため図面を眺めた。仕事に没頭すれば余計なことを考えずにすむ。だが、休憩の後から胃の辺りが痛んで、落ち着いて椅子に座っていることも難しかった。医者にも止められているコーヒーを、しかもブラックで一杯綺麗に飲み干してしまったのだ。
こんな時に限って、常備していたはずの胃薬が切れている。残業をしなくてはならないと思っていたのに、この体調では仕方がない。佐山は定時のチャイムが鳴る少し前に席を立って、医務室へ向かおうと廊下に出た。
「佐山さん」
胃の上を無意識に手で押さえて廊下を歩いていると、後ろから声をかけられた。その聞き覚えのある声に、佐山は身の竦む思いで立ち止まる。態度に出さないよう、咄嗟に自分に言い聞かせながら振り返った。
「――顔色悪いですけど、具合でも?」
振り向いた佐山を見て、秋口がかすかに表情を曇らせた。佐山は苦笑気味に首を横に振ってみせる。いろいろ説明するのが面倒だった。
「大したことないんだ」
「そういう様子にも見えませんけど……」
話を早く打ち切りたくて、佐山は無理に笑顔を浮かべた。秋口は当惑した表情になったが、それ以上は何も言わなかった。代わりに、本来の用件であるらしいことを訊ねてくる。
「メール、届きませんでしたか」
「ああ……ごめん、忙しくて。今日は駄目だ、ごめん」
考えるより先にそう答えてから、佐山はそれが当てつけのように聞こえはしないかと背筋を冷やした。だがすぐに、秋口は自分が先刻の彼女たちの会話を聞いたことは知らないし、それにそう思われても別段どうでもいいかと考えるのをやめた。
「佐山さん、本当に具合が悪いんじゃないですか?」
曖昧な笑顔を浮かべ、腹を押さえたままの佐山に、秋口はますます眉根を寄せ、顔を覗き込んできた。
近づいて来た秋口から、微かに嗅ぎ慣れた匂いがする。煙草とか、整髪料とか、そして体温とか、それを間近に感じて、佐山は逃げ出したくなる。
この感触を、あの休憩所にいた彼女たちが、その他の女の子たちが、自分と同じように味わったのだと思うと、逃げ出したいのに身動きも取れないくらい体が強張った。
「佐山さん」
口許を掌で押さえる佐山に、秋口が驚いて肩を支えようと手を伸ばしてきた。
反射的に、佐山はその手を反対の手で押し退けた。驚いた顔になる秋口を見ていられず、佐山は俯いた。
「ごめん、ちょっと、吐き気がして……」
「医務室に行きますか」
「大丈夫、ひとりで行ける」
一緒に歩き出そうとする秋口を言葉で制し、佐山はよろめきそうな足許を叱咤して歩き出した。
秋口は何も言わなかったが、気懸かりそうな視線を佐山は自分の背に感じた。だが振り返らず、とにかく秋口の目に届かないところへ行こうと、早足で廊下を進んだ。
医務室は違うフロアの片隅にある。覚束ない足取りで階段を下り、医務室目指して廊下を進んでいると、次には別の声が聞こえた。
「佐山さん」
今度は誰だ、と俯きがちだった顔を上げると、書類を抱え、驚いた顔をしている沙和子の姿が佐山の目に映った。
医務室があるフロアには、彼女のいる総務部もあったことを佐山は思い出す。
「どうしたの、大丈夫。ひどい顔色よ」
沙和子はすぐに駆け寄ってくると、佐山の腕に細い手を置き、心配げに顔を覗き込んできた。それからポケットを探ってハンカチを取り出し、脂汗の浮かぶ佐山の額をそっと拭った。
「医務室へ行くのね。歩ける?」
「大丈夫、ひとりで行けるから」
「駄目、すぐそこだから、一緒に行くわ」
佐山の言葉に聞く耳を持たず、沙和子は佐山の体を支えて歩き出した。医務室までゆっくり進むと、沙和子が自分のIDカードでドアを開け、佐山と一緒に中へ入った。仮眠用のベッドとソファ、薬の置かれた棚があるだけの部屋には誰もいない。医務室といっても簡素なものだ。
「また胃が痛むの?」
とりあえず佐山をソファに座らせながら、沙和子がそう訊ねてくる。彼女とつき合っていた頃もこんなことがあった。佐山はそう思い出しながら苦笑いを浮かべ、頷く。
「コーヒー、飲んじゃって」
「飲んだら駄目って言われてるのに。無理しないで」
困った顔で言ってから、沙和子が薬品棚に向かい、胃薬を一包み取り出した。薬を佐山に渡すと、一度医務室を出て行ってから、すぐにミネラルウォーターを手に戻ってくる。
「ありがとう」
ありがたく、佐山は沙和子のくれた水で胃薬を飲み下し、ソファに深く凭れた。
沙和子が佐山の隣へ腰を下ろす。
「ごめん、沙和――雛川さんも、仕事中だろ。大丈夫だから戻っていいよ」
「急ぎの仕事はないから、平気」
答えてから、沙和子が小さく笑った。
「『沙和子』でいいのに」
「君を好きな人に悪いよ」
「いないわ」
沙和子は膝の上で指を組み、その指に視線を落として小さな声で言った。
「とっくに別れて、今は誰もいない」
「……」
どう答えていいのかわからず、佐山は黙り込んだ。沙和子も口を閉ざした。しばらくふたりして黙っていると、薬のお陰で少しずつ胃の痛みがひいてきて、佐山はほっと細い息を吐いた。
そのタイミングで、沙和子がまた口を開く。
「久しぶりね、ふたりでゆっくり話すの」
「そうか……そうだな」
別れてから数年、おそらく沙和子の方から佐山を避けていて、ふたりきりになることも、落ち着いて言葉を交わすこともなかった。
長い時間空白があるのに、思いのほか自然と彼女と話せるのが佐山には不思議だった。
「ずっと話したい、話したいって思ってたけど、何て言うか……気がひけて、なかなか声がかけられなかったの。わたし、佐山さんにずいぶんひどいことしたから」
「いいよ。俺も沙和子にはいろいろ大変なこと強いてたって、あとから大分反省した」
彼女とつき合っていた間のことを、佐山は思い出す。沙和子は綺麗で、頭がいいだけではなく、佐山にとって『都合のいい』相手だった。
理想の結婚相手、という意味で。
「断るのも辛かっただろうと思う、ごめん」
結婚して早く家庭を持ちたい佐山と、まだ結婚なんて現実味すら持てない沙和子と、そこが喰い違って結局別れた。
しかも佐山との結婚には普通とは言い難い事情がついて来る。沙和子ならばそれも受け入れてくれると信じてしまった自分のせいで、彼女には辛い思いをさせたと、彼女と別れた後も佐山にはそれが気に懸かっていた。
「この間、夏休みを取ったでしょう。――お母様のお見舞い、行ってきたの?」
おそらく佐山と同じことを考えていたのだろう、沙和子が遠慮がちにその話題を口に乗せた。
「うん。御幸がまた車出してくれたから」
「お加減、どうでした」
やはり遠慮がちな沙和子の口調に、佐山は少し笑って、ソファに凭れたまま医務室の天井を見上げた。
「体の方は割合調子がいいようだけど……相変わらず。俺の顔見て、翼はいないのかって聞いてきた」
「……」
ごめんなさい、と微かな声で呟いた沙和子に、佐山はもう一度笑って見せた。
「それで母が倖せならいいと思うんだ、久しぶりに直接顔を見られて運がよかったし。いつもなら面会はできないところを、数分間だけでも会えたんだから」
「そう……よかったわね」
優しく言う沙和子に、佐山が頷いた時、医務室の外でIDカードを認証する電子音が聞こえた。すぐにドアが開く。
現れた秋口に、佐山は目を見開いた。
「秋口――」
秋口は秋口で、佐山と一緒にいる沙和子を見て、驚いた顔になっていた。沙和子が佐山の腕に触れていた指先をそっと離す。
その様子に気づいた秋口が、皮肉っぽい表情で口端を持ち上げ、笑った。
「何だ。具合が悪いみたいだから心配して来たけど、お邪魔だったみたいですね」
「途中で会って、心配してついてきてくれたんだ。ごめん雛川さん、助かった。仕事に戻って」
いわれのないことで邪推されては沙和子が可哀想だと、佐山は秋口から目を逸らして彼女に言った。
「俺も戻るよ、どうもありがとう」
沙和子は戸惑った様子ながら、佐山にそう言われると頷き立ち上がった。秋口の方を気にするように見上げてから、出口のところで佐山のことを振り返る。
「また今度、ゆっくり話ができる?」
「うん。そのうちに」
ほっとしたように笑って、沙和子が医務室を出て行った。
笑みを消し、佐山は自分も出て行こうとソファから立ち上がってから、そばにあった備え付けのノートに、使った薬の名前と『開発課・佐山翼』とペンで書きつけ、印鑑を押す。
なるべく秋口の方を見ないように立ち去ろうと思っていたのに、ノートを閉じて出口へ向かった佐山の前には、無表情の秋口が立ちはだかっていた。
「ごめん、仕事に戻らないと。退いてくれるか」
「雛川さんとより、戻す気ですか」
秋口がドアの前から退いてくれないと外には出られない。困って立ちつくす佐山の前で、やはり身動きもせず、冷たい口調で秋口が訊ねた。急にそんなことを問われて、佐山はつい、混乱する。
「そんなつもりないよ、沙和子の方から別れたんだ、向こうにだってそんな気ないだろうし」
「その沙和子さんと、あんたはどういうつもりでこんなとこでふたりきりだったのかって訊いてるんですよ」
秋口の冷たい詰問口調に、佐山は胸をざわつかせた。
何だかとても不快な感覚だった。
「秋口が気にするところじゃないだろ」
ついそう吐き捨てると、乱暴に腕を掴まれ、佐山は驚いて秋口を見上げた。
「質問してるんだから、答えればいいんですよ。やましいことでもあるから誤魔化すんですか?」
「やましい――って、俺は別に」
なぜこんなことを訊かれなくてはならないのか、佐山はますます混乱した。秋口の言葉はまるで沙和子といた自分を責めているようで、だったらなぜ自分が彼にそんなことを責められればいけないのかと、何か口惜しい気分になる。
(自分だって)
浮かぶ思いは、それこそ自分の責める筋合いではないはずなのに、腹が立つ。
(他の人と一緒にいたのに)
秋口が何のつもりで今ここにいるのか、佐山は理解できなかった。
「秋口も仕事の途中だろ、心配してくれて嬉しいけど、薬も飲んだし、もう大丈夫だから」
「だから誤魔化すなって言ってんだよ」
さらにきつく腕を掴まれ、佐山は痛みに顔を歪め、秋口のことを睨むように見上げた。
腹が立って仕方がなかった。
「秋口だって先週、他の子と遊びに行ったんだろ」
怒った顔で自分を睨む佐山の表情と、その口から出た言葉に、秋口が虚をつかれたように表情を失くす。佐山はそのまま秋口から顔を逸らした。
「俺は、沙和子とは何もない。本当にたまたまとおりがかかったからここに連れてきてくれただけだ。……秋口の方は、ホテルまで行ったんだって女の子が話してるの聞いたけど」
秋口に掴まれた腕が痛い。振り払いたかったが、力で敵わなかった。
「他にあてがあるなら、何も俺なんかにわざわざつき合ってくれなくてもいいんだ。頼んだわけじゃない。周りにいくらでも相手をしてくれる人たちがいるんだから」
「俺のこと好きなくせに?」
「――」
吐き出された一言が信じられずに、佐山は強張った顔を秋口の方に向けた。
「当てつけみたいな女々しいこと言わないでくださいよ。俺が他に相手するのがいたら、何だっていうんですか」
秋口は笑っていた。笑っているのに、見上げた佐山の背筋が冷えるほどの怒りが見て取れた。何かが秋口の神経を逆撫でしたのはわかったが、それで自分が謝る必要はないと、佐山は唇をひき結んだまま秋口を見上げる。
その表情に、秋口は笑顔も消して、掴んだ佐山の腕を引いた。驚いた佐山が抵抗する間もなく、乱暴にソファの上に体を投げ出された。
「痛……ッ」
ソファの固いところに手足をぶつけ、顔を顰める佐山の上に、秋口が覆いかぶさって来る。佐山はその体を押し退けて立ち上がろうとするが、苛立った動きの秋口に肩を押さえつけられ、身動きが取れなかった。
「やめろよ」
ひどく惨めな気分で、佐山はただ手足をばたつかせた。秋口は佐山の抵抗など微塵も気に懸けない素振りで、佐山の眼鏡を外してしまった。
口惜しくて、情けなくて、涙の滲みかけた目では秋口の表情はわからない。その顔が近づいてきたとわかった時、精一杯首を逸らして逃げようとしたが、強く顎を掴まれて適わなかった。
「あんたとやるメリットなんて、孕まないことと、女みたいにぐちぐち言わないことなんだから。黙ってろよ、俺のこと好きなんだろ。余計なこと言うなら捨てるぞ」
間近で聞こえた声が信じられず、佐山は呆然とした頭で秋口の接吻けを受けた。
まなじりからこめかみを伝って流れる涙の感触を、他人事みたいに味わっていた。
◇◇◇
医務室のソファは年季が入っていて、佐山が嫌がって身を捩るたびにぎしぎしとスプリングの軋む音がした。
秋口は佐山の抵抗を力でねじ伏せ、今までになく荒っぽい動きでその体を探った。
キスされて、首筋や肩に歯を立てられて、手でいかされた。秋口に今触れられるのはどうしても嫌だと思ったのに、ただ押さえつけられていたせいだけではなく、佐山は結局相手を振り解くほどの抵抗はできなかった。
触れ合っている時は、余計なことを考えずに快楽を味わうと。
そう自分で決めたことが、佐山を余計に混乱させた。気持ちいいと、感じながら、考えながら、別の場所で『どうしてこんなことになってしまったのか』と思っている。
手で扱かれている途中、耳許で荒い吐息混じりに「あんたもやれよ」と命令口調で言われて、佐山はもうわけもわからず、条件反射みたいに秋口の昂ぶりに手を伸ばした。
焦らされて焦らされて、恥も忘れて懇願しそうになった頃にやっと秋口の手に精を吐いて、我に返る間もなく立て続けにもう一度いかされた。
秋口もはだけた佐山の体に射精して、佐山はソファに仰向けになったまま、呆然と、そんな秋口を見上げていた。
どうせ眼鏡もないぼやけた視界のせいで、はっきりその顔も見えなかったけれど。
荒い呼吸を繰り返したまま、佐山は会社のソファなんてところでみっともなく服をはだけられて、半分脚が床にずり落ちるような格好で、ただ呆然とした。
終わった後は何も考えられなくなった。
ひどく噛まれた肩口や、ねじ切られるかと思った胸の先がずきずきと痛む。今まで何度こんなことをしたって、佐山の意志を無視することもなく秋口が乱暴な仕種をすることはなかった。
「……秋口……」
自分でも何を言うつもりかわからないまま、佐山は頼りなく掠れた声を洩らした。その呼びかけを聞いて、こちらも呆然とした様子で佐山の上にまだのしかかっていた秋口の体が、びくりと小さく揺れる。
「――」
秋口がどんな顔をしていたのか、やっぱり佐山にはわからない。眼鏡はどこだ、と一瞬意識を逸らした時、秋口が起き上がり、乱れた服を直すと、何も言わずに佐山に背を向けた。
一言もなく医務室を出た秋口のことを、佐山もやっぱり何も言うこともできず、黙って見送ってしまった。
秋口は佐山の抵抗を力でねじ伏せ、今までになく荒っぽい動きでその体を探った。
キスされて、首筋や肩に歯を立てられて、手でいかされた。秋口に今触れられるのはどうしても嫌だと思ったのに、ただ押さえつけられていたせいだけではなく、佐山は結局相手を振り解くほどの抵抗はできなかった。
触れ合っている時は、余計なことを考えずに快楽を味わうと。
そう自分で決めたことが、佐山を余計に混乱させた。気持ちいいと、感じながら、考えながら、別の場所で『どうしてこんなことになってしまったのか』と思っている。
手で扱かれている途中、耳許で荒い吐息混じりに「あんたもやれよ」と命令口調で言われて、佐山はもうわけもわからず、条件反射みたいに秋口の昂ぶりに手を伸ばした。
焦らされて焦らされて、恥も忘れて懇願しそうになった頃にやっと秋口の手に精を吐いて、我に返る間もなく立て続けにもう一度いかされた。
秋口もはだけた佐山の体に射精して、佐山はソファに仰向けになったまま、呆然と、そんな秋口を見上げていた。
どうせ眼鏡もないぼやけた視界のせいで、はっきりその顔も見えなかったけれど。
荒い呼吸を繰り返したまま、佐山は会社のソファなんてところでみっともなく服をはだけられて、半分脚が床にずり落ちるような格好で、ただ呆然とした。
終わった後は何も考えられなくなった。
ひどく噛まれた肩口や、ねじ切られるかと思った胸の先がずきずきと痛む。今まで何度こんなことをしたって、佐山の意志を無視することもなく秋口が乱暴な仕種をすることはなかった。
「……秋口……」
自分でも何を言うつもりかわからないまま、佐山は頼りなく掠れた声を洩らした。その呼びかけを聞いて、こちらも呆然とした様子で佐山の上にまだのしかかっていた秋口の体が、びくりと小さく揺れる。
「――」
秋口がどんな顔をしていたのか、やっぱり佐山にはわからない。眼鏡はどこだ、と一瞬意識を逸らした時、秋口が起き上がり、乱れた服を直すと、何も言わずに佐山に背を向けた。
一言もなく医務室を出た秋口のことを、佐山もやっぱり何も言うこともできず、黙って見送ってしまった。
◇◇◇
(ひどいことをした)
逃げるように医務室を出た後、秋口は一杯に混乱した頭を抱えて、無意識に営業部の方へ向かった。
(ひどいことをしてしまった)
後悔しているのか、腹を立てているのか、何に腹を立てているのか、考えも感情すらまとまらず、秋口は営業部の自分の机に戻った。
あんなふうに理性を手放したことなんて今まで一度もなかった。
佐山が医務室で沙和子といるのを見た瞬間、どうしようもない、度し難い怒りが全身を貫いて、自分でも制御できなくなってしまったのだ。
『沙和子が――』
佐山がその声で沙和子の名前を呼んだ時、それは以前に恋人同士のつき合いがあったのなら不思議でも何でもなかったのに、秋口には佐山のことが許せなくなった。
そんなものは勝手な感情だと、わかっていたのに無理矢理目を逸らした自分がいる。
頭に血が昇って、駄目だと思う間もなくひどいことを口走った。
あんなふうに嫌がる相手を力ずくでねじ伏せたのなんて、生まれて初めてだ。
(佐山さん、泣いてた)
当然だ。それだけのことを自分が言った。ひどいことをしているという自覚はあの時にだってあったのに、佐山の涙を見たって、それは秋口を止めるよりもむしろ逆の効果しかもたらさなかった。嫌がる態度がさらに秋口を逆上させた。どうせ俺のことが好きなくせに、俺に触られて嬉しいくせにと、同じことばかりを考えた。
(最低だ)
おまけにことがすんだ後、目を見開いてただ大きく息を繰り返す佐山を見て、いたたまれず、逃げ出してしまった。謝ることも言いつくろうこともできず、それはまさに逃げるという言葉に相応しい態度だった。
謝るべきだ、と仕事をする気にもならずパソコンのモニタを睨みながら秋口は思ったが、「どうやって」という自問に答えが出ない。
そもそも佐山が許してくれるかがわからなかった。あんな言葉を投げつけられて、嫌がっているのに強引にいかされて。
謝りもしなかった男を、一体誰が許すのか。
長い間そんなことを悶々と考え、何も手につかず、秋口は結局そのまま帰り支度を始めた。
なぜ自分がこんなにも、佐山にこだわってしまうのか。
秋口はまだ答えを出せずにいた。自分をこんなふうに思い悩ませる佐山のことが、次第に腹立たしくなってくる始末だ。
(もういい、俺が悩む必要なんてない。どうせ顔合わせ辛いし、当分会わなければほとぼりも冷めるし)
半ばやけくそのようにそう結論づけようとした秋口は、エスカレータでエントランスへ向けて下りる途中、その壁際に寄り掛かって立っている佐山の姿に気づき、ぎくりとした。
人待ち顔でいる佐山に、秋口は一番最初に自分が彼を誘った時のことを不意に思い出した。あの日も仕事の後、佐山がそうしてあそこで立っていた。
(御幸さんか、雛川さんを待ってるんだ)
秋口は咄嗟にそう思い、刹那、ぎゅっと心臓を握り潰されるような感覚を味わった。佐山が、自分ではない誰かを待っている。そのことが秋口を傷つけた。
佐山に見つからないよう、顔を伏せ足早にその場を去ってしまおうとした秋口は、エスカレータを下りたところですぐそばに誰かがやってきたことに気づき、ハッとして顔を上げた。
「秋口」
立っていたのは佐山だった。秋口はつい驚いて小さく目を見開く。
佐山は彼らしく控えめに笑って、秋口のことを見上げている。
「さっきは今晩無理って言ったけど、仕事切り上げて来たから。やっぱり飯、行かないか」
「……え……」
驚いて、秋口は笑っている佐山のことを見返した。一瞬、自分の行為を非難され罵声を浴びせかけられるのではと覚悟を決めかけたのに、佐山があまりに普段どおりだったので、上手く反応できなかった。
「あ、もちろん、都合が悪くなったのならいいんだけど」
「……いや――大丈夫ですけど」
自分ばかりが取り乱しているのはみっともないと、そう思った途端秋口は普段どおりに答えることができた。多少ぎこちなく、その上ぶっきらぼうな調子にはなってしまったが。
そうか、と佐山は笑ったまま頷いた。
佐山の態度が理解できないまま、秋口は会社を出て、佐山のリクエストで久しぶりに彼お気に入り料理屋へ向かった。雑誌で紹介された時の客足が少し落ち着いたのか、長い時間待たされることもなく、秋口と佐山は席に案内された。
「ここ、久しぶりだな」
佐山は嬉しそうにメニューを開き、秋口も到底食欲なんて湧かないまま適当に料理を注文した。
佐山はまったく普段と同じ表情で、口調で、秋口は彼の内心を疑いながらも、その理由を自分から問うわけにもいかず、自分も普段どおりに相槌を打ち、会話を交わした。
「佐山さん、すみませんけどそっちの塩、ちょっと取ってくれませんか」
「あ、うん」
何気なく頼んだ秋口に、佐山がテーブルの端に置かれた小瓶を取ってくれた。それを受け取ろうとした秋口の手が佐山の指先に触れた時、佐山が秋口が驚くほど素早くその手を引っ込めて、小瓶はテーブルの上に落ち、蓋がはずれて中身が散らばった。
「……」
「あ……あーあ、ごめん、店の人呼ばないと」
佐山が不自然なほどのんびりした口調で言って、苦笑した。
その笑い顔を見た刹那、秋口は頭の中を殴られたような気分で、気づいてしまった。
佐山はいつもどおりに振る舞おうと『している』のだ。秋口を責めもせず、本当は傷つきも怒りもして、不意に触れた秋口の指先にすら過剰に反応してしまうほどなのに、普段と同じ態度で笑って秋口と一緒にいる。
そうするために佐山が必死になっていることに、秋口は気づいてしまった。
(どうして)
秋口がそんなことを思うのも馬鹿らしい。自分自身が言ったからだ。
『あんたとやるメリットなんて、女みたいにぐちぐち言わないことなんだから――』
どうしてあんなひどいことが言えたのか、秋口にだってわからない。
「どうもやっぱり、トロいんだろうなあ……」
恥ずかしそうに小瓶を起こし、皿を退けておしぼりでテーブルの上を拭う佐山を見ながら、秋口は何だか泣きたい気分になってしまった。
どうして、と今度は違う疑問が秋口の脳裡に浮かぶ。
どうして、佐山は自分をこんなにまで好きなのか。
「ごめんな、テーブル散らかしちゃって」
困って笑いながら謝る佐山に、秋口はどうしても自分が謝ることなんてできなかった。
逃げるように医務室を出た後、秋口は一杯に混乱した頭を抱えて、無意識に営業部の方へ向かった。
(ひどいことをしてしまった)
後悔しているのか、腹を立てているのか、何に腹を立てているのか、考えも感情すらまとまらず、秋口は営業部の自分の机に戻った。
あんなふうに理性を手放したことなんて今まで一度もなかった。
佐山が医務室で沙和子といるのを見た瞬間、どうしようもない、度し難い怒りが全身を貫いて、自分でも制御できなくなってしまったのだ。
『沙和子が――』
佐山がその声で沙和子の名前を呼んだ時、それは以前に恋人同士のつき合いがあったのなら不思議でも何でもなかったのに、秋口には佐山のことが許せなくなった。
そんなものは勝手な感情だと、わかっていたのに無理矢理目を逸らした自分がいる。
頭に血が昇って、駄目だと思う間もなくひどいことを口走った。
あんなふうに嫌がる相手を力ずくでねじ伏せたのなんて、生まれて初めてだ。
(佐山さん、泣いてた)
当然だ。それだけのことを自分が言った。ひどいことをしているという自覚はあの時にだってあったのに、佐山の涙を見たって、それは秋口を止めるよりもむしろ逆の効果しかもたらさなかった。嫌がる態度がさらに秋口を逆上させた。どうせ俺のことが好きなくせに、俺に触られて嬉しいくせにと、同じことばかりを考えた。
(最低だ)
おまけにことがすんだ後、目を見開いてただ大きく息を繰り返す佐山を見て、いたたまれず、逃げ出してしまった。謝ることも言いつくろうこともできず、それはまさに逃げるという言葉に相応しい態度だった。
謝るべきだ、と仕事をする気にもならずパソコンのモニタを睨みながら秋口は思ったが、「どうやって」という自問に答えが出ない。
そもそも佐山が許してくれるかがわからなかった。あんな言葉を投げつけられて、嫌がっているのに強引にいかされて。
謝りもしなかった男を、一体誰が許すのか。
長い間そんなことを悶々と考え、何も手につかず、秋口は結局そのまま帰り支度を始めた。
なぜ自分がこんなにも、佐山にこだわってしまうのか。
秋口はまだ答えを出せずにいた。自分をこんなふうに思い悩ませる佐山のことが、次第に腹立たしくなってくる始末だ。
(もういい、俺が悩む必要なんてない。どうせ顔合わせ辛いし、当分会わなければほとぼりも冷めるし)
半ばやけくそのようにそう結論づけようとした秋口は、エスカレータでエントランスへ向けて下りる途中、その壁際に寄り掛かって立っている佐山の姿に気づき、ぎくりとした。
人待ち顔でいる佐山に、秋口は一番最初に自分が彼を誘った時のことを不意に思い出した。あの日も仕事の後、佐山がそうしてあそこで立っていた。
(御幸さんか、雛川さんを待ってるんだ)
秋口は咄嗟にそう思い、刹那、ぎゅっと心臓を握り潰されるような感覚を味わった。佐山が、自分ではない誰かを待っている。そのことが秋口を傷つけた。
佐山に見つからないよう、顔を伏せ足早にその場を去ってしまおうとした秋口は、エスカレータを下りたところですぐそばに誰かがやってきたことに気づき、ハッとして顔を上げた。
「秋口」
立っていたのは佐山だった。秋口はつい驚いて小さく目を見開く。
佐山は彼らしく控えめに笑って、秋口のことを見上げている。
「さっきは今晩無理って言ったけど、仕事切り上げて来たから。やっぱり飯、行かないか」
「……え……」
驚いて、秋口は笑っている佐山のことを見返した。一瞬、自分の行為を非難され罵声を浴びせかけられるのではと覚悟を決めかけたのに、佐山があまりに普段どおりだったので、上手く反応できなかった。
「あ、もちろん、都合が悪くなったのならいいんだけど」
「……いや――大丈夫ですけど」
自分ばかりが取り乱しているのはみっともないと、そう思った途端秋口は普段どおりに答えることができた。多少ぎこちなく、その上ぶっきらぼうな調子にはなってしまったが。
そうか、と佐山は笑ったまま頷いた。
佐山の態度が理解できないまま、秋口は会社を出て、佐山のリクエストで久しぶりに彼お気に入り料理屋へ向かった。雑誌で紹介された時の客足が少し落ち着いたのか、長い時間待たされることもなく、秋口と佐山は席に案内された。
「ここ、久しぶりだな」
佐山は嬉しそうにメニューを開き、秋口も到底食欲なんて湧かないまま適当に料理を注文した。
佐山はまったく普段と同じ表情で、口調で、秋口は彼の内心を疑いながらも、その理由を自分から問うわけにもいかず、自分も普段どおりに相槌を打ち、会話を交わした。
「佐山さん、すみませんけどそっちの塩、ちょっと取ってくれませんか」
「あ、うん」
何気なく頼んだ秋口に、佐山がテーブルの端に置かれた小瓶を取ってくれた。それを受け取ろうとした秋口の手が佐山の指先に触れた時、佐山が秋口が驚くほど素早くその手を引っ込めて、小瓶はテーブルの上に落ち、蓋がはずれて中身が散らばった。
「……」
「あ……あーあ、ごめん、店の人呼ばないと」
佐山が不自然なほどのんびりした口調で言って、苦笑した。
その笑い顔を見た刹那、秋口は頭の中を殴られたような気分で、気づいてしまった。
佐山はいつもどおりに振る舞おうと『している』のだ。秋口を責めもせず、本当は傷つきも怒りもして、不意に触れた秋口の指先にすら過剰に反応してしまうほどなのに、普段と同じ態度で笑って秋口と一緒にいる。
そうするために佐山が必死になっていることに、秋口は気づいてしまった。
(どうして)
秋口がそんなことを思うのも馬鹿らしい。自分自身が言ったからだ。
『あんたとやるメリットなんて、女みたいにぐちぐち言わないことなんだから――』
どうしてあんなひどいことが言えたのか、秋口にだってわからない。
「どうもやっぱり、トロいんだろうなあ……」
恥ずかしそうに小瓶を起こし、皿を退けておしぼりでテーブルの上を拭う佐山を見ながら、秋口は何だか泣きたい気分になってしまった。
どうして、と今度は違う疑問が秋口の脳裡に浮かぶ。
どうして、佐山は自分をこんなにまで好きなのか。
「ごめんな、テーブル散らかしちゃって」
困って笑いながら謝る佐山に、秋口はどうしても自分が謝ることなんてできなかった。
◇◇◇
自分のことを好きになる人間なんてこれまで掃いて捨てるほどいたし、その中に気に入った相手がいれば簡単に誘って簡単に寝たし、簡単に振る時に辛くなることなんて一度もなかった。
誰かのことを考えて、息苦しいような、何もかも手につかないような気分になることなんて、欠片もなかった。
秋口にとって、今のその感情がどうしようもなく苦痛だった。迷惑だとも思った。自分をこんな気持ちにさせる佐山の存在は迷惑だ。
いっそいなくなってくれたらすっきりするのに。
「それじゃあ俺、こっちだから」
店を出ると、佐山は笑ったまま道の向こうを指さした。
「佐山さん――」
咄嗟に、自分に背中を向ける佐山に声をかけてしまってから、秋口はハッと口を噤んだ。
「うん?」
佐山が振り返り、小首を傾げる。
『帰るんですか』
その質問を口に乗せようとした秋口は、頭の中で誰かに『どの面下げてそんなことを聞くのか』と罵倒されて、それを言葉にすることができず、ただ首を振った。
「いえ。おやすみなさい」
そう告げた秋口に、佐山は柔らかい笑顔を見せて、その表情がどうしてか秋口の呼吸をまた苦しくした。
「おやすみ、また会社で」
追いかけたい、と思う自分の気持ちが何なのか、秋口には理解できない。追いかけて、よくも自分をこんな気分にさせたなと罵りたいのか。
(そうじゃない)
ひどく混乱して、秋口はその場に立ちつくした。そうしている間に、佐山はまばらなネオンが散らばる宵闇の中へと消えていく。
今ここで佐山を追いかけたら、自分はどうなってしまうのだろう。
そう考えることが秋口には、どうしてかひどく怖かった。今まで知らなかった自分になることが無性に怖い。
沙和子を落とすためなんて言い訳を、白々しくてもう自分でも使えなくなってしまった。彼女と佐山が一緒にいるところなんて、二度と見たくないと思っているのだ。
沙和子と自分が恋人同士になれば、佐山が彼女とそうなることはない、などと考えてしまってから、そんな状態に陥った自分がやっぱり怖くなる。
佐山はもういないのに、秋口はその場から逃げるように駅へと向かって歩き出した。
誰かのことを考えて、息苦しいような、何もかも手につかないような気分になることなんて、欠片もなかった。
秋口にとって、今のその感情がどうしようもなく苦痛だった。迷惑だとも思った。自分をこんな気持ちにさせる佐山の存在は迷惑だ。
いっそいなくなってくれたらすっきりするのに。
「それじゃあ俺、こっちだから」
店を出ると、佐山は笑ったまま道の向こうを指さした。
「佐山さん――」
咄嗟に、自分に背中を向ける佐山に声をかけてしまってから、秋口はハッと口を噤んだ。
「うん?」
佐山が振り返り、小首を傾げる。
『帰るんですか』
その質問を口に乗せようとした秋口は、頭の中で誰かに『どの面下げてそんなことを聞くのか』と罵倒されて、それを言葉にすることができず、ただ首を振った。
「いえ。おやすみなさい」
そう告げた秋口に、佐山は柔らかい笑顔を見せて、その表情がどうしてか秋口の呼吸をまた苦しくした。
「おやすみ、また会社で」
追いかけたい、と思う自分の気持ちが何なのか、秋口には理解できない。追いかけて、よくも自分をこんな気分にさせたなと罵りたいのか。
(そうじゃない)
ひどく混乱して、秋口はその場に立ちつくした。そうしている間に、佐山はまばらなネオンが散らばる宵闇の中へと消えていく。
今ここで佐山を追いかけたら、自分はどうなってしまうのだろう。
そう考えることが秋口には、どうしてかひどく怖かった。今まで知らなかった自分になることが無性に怖い。
沙和子を落とすためなんて言い訳を、白々しくてもう自分でも使えなくなってしまった。彼女と佐山が一緒にいるところなんて、二度と見たくないと思っているのだ。
沙和子と自分が恋人同士になれば、佐山が彼女とそうなることはない、などと考えてしまってから、そんな状態に陥った自分がやっぱり怖くなる。
佐山はもういないのに、秋口はその場から逃げるように駅へと向かって歩き出した。
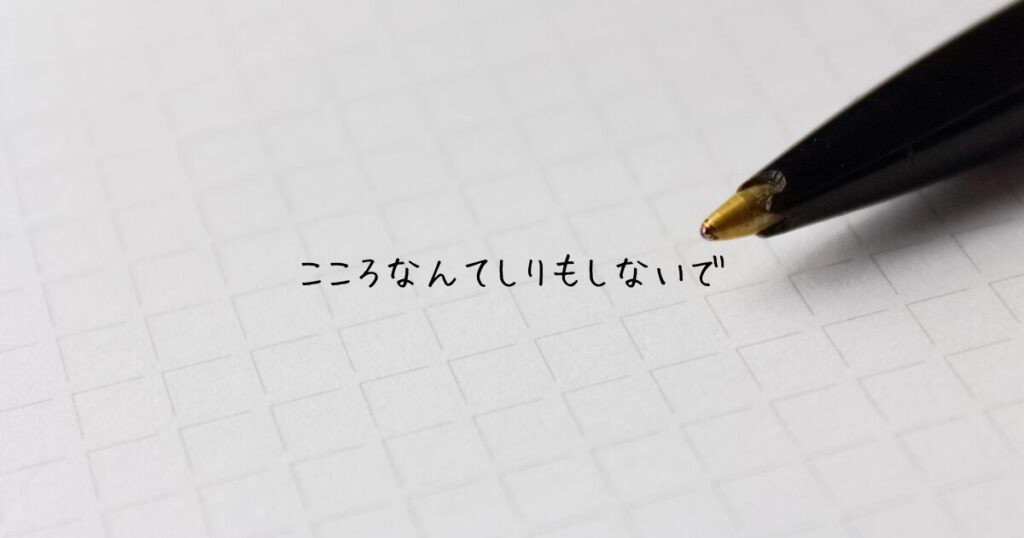
サラリーマン×サラリーマン

商業誌番外編

商業誌番外編

商業誌番外編
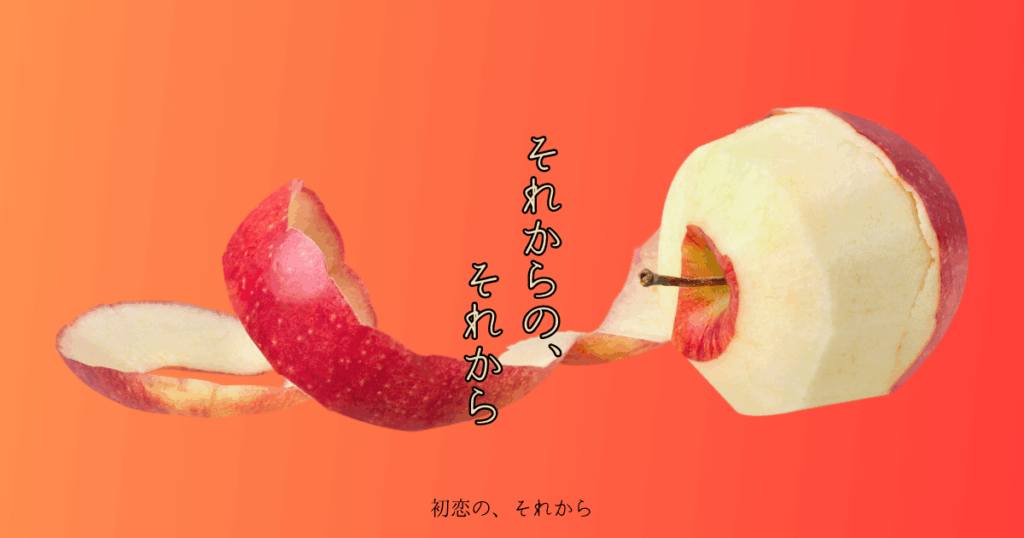
商業誌番外編
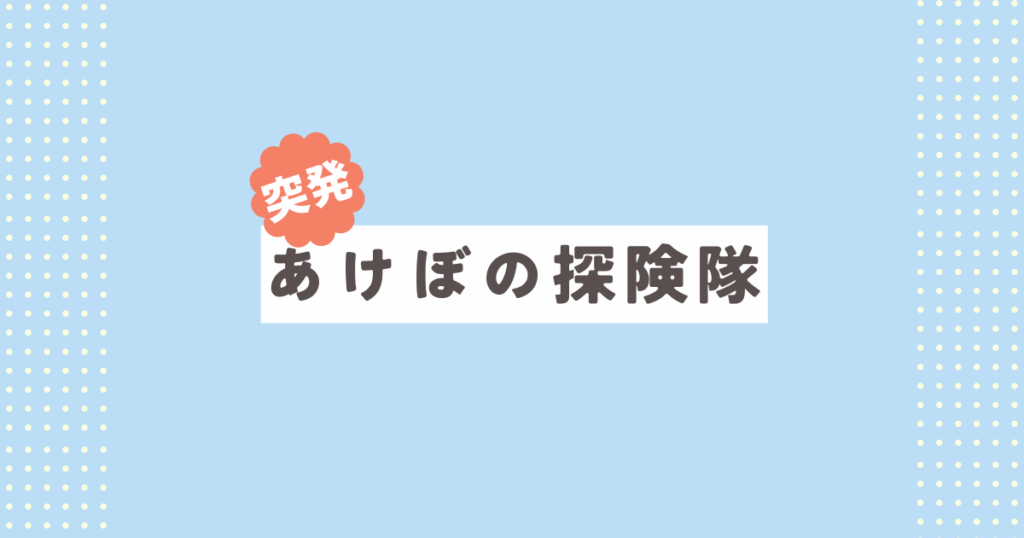
同人誌シリーズ番外編

高校生の恋未満読み切り