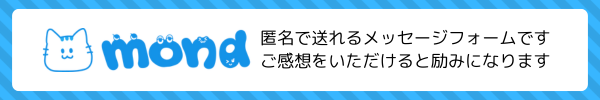(痛い)
鈍痛で目が覚めた。
ずきずきと、脈打つようにこめかみの辺りが痛んでいる。胃が重たくて、気持ち悪い。喉から胃液が逆流してきそうだ。
こんな感触には覚えがある。営業時代によく味わった、紛れもない宿酔いの状態。
「うー……」
体全体が怠くて、瞼は重くて、目が開かない。外がもう明るいことは、閉じた瞼越しにもわかった。一瞬、会社に遅れる、と思って肝が冷えたが、すぐに「今日は土曜日だ」ということを思い出す。午後から出社するつもりではあったが、基本的には休みの日だ。休んだって咎められることもない。
そこまでひどく間延びした思考で結論を出すと、佐山は少し落ち着いた気分でベッドのシーツに頬を擦りつけた。枕がなくて、横向きに丸まるような格好をしていた。うっすら目を開けて見ると、すぐそこにベッドのふちがある。何だって自分はこんな端っこで眠っていたのだろうか――と訝しみながら、佐山は軽く伸びをした。またこめかみで鈍痛が響くが、どうにかやりすごす。
カーテンから漏れる光で、すでに陽が高いことがわかり、佐山はいい加減起き出さなくてはと思いながら小さく身じろぎした。
と。
「え?」
動かした腕に、何か暖かいものが当たって佐山は眉を寄せる。暖かいくて、弾力のある、明らかに、
(……人肌?)
恐る恐る、佐山は背後へ首を巡らせた。
と。
「……ッ!」
驚きのあまり声も出ず、ただひたすらに、両目を見開いてしまう。
(な、何で)
口から心臓が飛び出るかと思った。なぜか、どういうわけだか、自分の隣では秋口が仰向けになって規則正しい寝息を立てているのだ。
おまけに、裸の肩が剥き出しだ。タオルケットが掛かっているから、全身素っ裸なのかまではわからない。佐山は慌てて自分の姿を確認した。辛うじて下着はつけているが、シャツは着ていない。また恐る恐る床を見ると、ふたり分のズボンと一枚分のシャツが、積み上げられた本の上にかけられている。そのの上に眼鏡。シャツ一枚だけが丸めて床に落としてあった。これが佐山のものだ。
痛む頭を押さえながら、佐山はどうにかベッドの上に起き上がった。とにかく眼鏡を拾って掛ける。
「……あれ……」
寝乱れた髪を押さえるように掻き上げながら、佐山は丸まったシャツと、秋口の寝姿を交互に見遣った。
必死になって、ゆうべのことを思い出す。
(いつもの店が閉まってて、買い物をしてうちに来て、それでメシ喰いながら、ちょっとだけ酒入れて――)
覚えているのは、そこまでだ。どうやら苦手な酒を飲んで、途中で潰れてしまったらしい。秋口に勧められたビールを一口二口飲んだ辺りから、すでに記憶が怪しくなっている。
(……変なこと、言ってないよな?)
おぼろげに覚えているのは、秋口がそこはかとなく苦笑する顔。自分は多分、彼に何かを言いつのり、だが何を言ったのかサッパリ覚えていない。
とにかく秋口が起きる前にベッドから抜け出そう、と佐山は痛む頭を押さえながらまた身じろぎした。こんな格好で秋口と顔を合わせるところなんて考えたくもない。
そう思ったのに、佐山がベッドを下りるよりも早く、秋口の目が開いた。フッと、前触れなく瞼が開いたのに、「寝起きがいいんだなあ」とこんな時なのに佐山は感心してしまう。
秋口は眠たそうに一度ぎゅっと目を閉じてから、佐山の方を見上げて、気怠そうに吐息した。
「……おはようございます」
寝起きの掠れた声に、佐山は頭の芯がぐらぐら揺れる感触を味わった。腰に来そうになって、慌ててその声を意識から追いやる。さり気ない素振りでタオルケットを引っ張り上げた。
「ええと……秋口、泊まったのか」
秋口から目を逸らしつつ、佐山がそう言うと、無言が返ってきた。
あれ、と思って秋口を見下ろしたら、思い切り曇った顔が見える。
「秋口? あの……悪い、俺、昨日のこと全然覚えてなくて」
「……ああ」
うわの空な様子で、秋口がやっと頷く。天井を見上げ、また大きく息を吐き出していた。
「そうか」
秋口はひどく不機嫌そうだった。そのことに佐山は慌てる。もしかしたら、酔っぱらって秋口の迷惑になるようなことをしてしまったのだろうか。
そう訊ねることもできず、どうしたものかと所在なくベッドの上で佐山が座ったままでいると、秋口が軽く目を閉じてまた口を開いた。
「すみませんけど、水か何かもらっていいですか」
「あ、う、うん」
急いでベッドから下りようとした佐山は、途端また鈍痛を感じて頭を押さえ、思わずうずくまった。呻き声を上げていると、隣で秋口が起き上がる気配がする。
「自分で取ってきます」
秋口がぶっきらぼうにそう言って、ベッドを下りる。
「あー……悪い、冷蔵庫にミネラルウォーターが入ってるから」
「佐山さんも飲みますか?」
「うん」
あちこちに積まれた荷物を乗り越えながら、隣のダイニングキッチンへ向かう秋口の後ろ姿を、佐山はそっと見遣った。秋口も下着ははいている。
男女じゃないんだから、たとえ素っ裸で寝ていたって、男同士なら妙なことになったと想像する方がおかしい。
そうわかってはいても、何しろ相手が秋口なものだから、佐山はうろたえずにはいられなかった。これがたとえば御幸あたりだったら、特に何も感じなかったに違いない。
秋口が戻って来たので、佐山は慌てて目を逸らした。頭痛に気を取られているふりで俯く。実際ひどく頭は痛み続けていた。
「どうぞ」
「あ、ありがとう」
目の前にぬっと出てきたペットボトルを佐山は受け取った。いただきます、と秋口が礼儀正しく言う声が聞こえる。佐山もキャップを開けて、水を一気に飲んだ。冷たい液体が喉を潤し、少し落ち着く。
「……すみません」
大きく息を吐いていると、そんな秋口の声が聞こえて、佐山は自然彼の方を見上げた。秋口はベッドの脇で、座りもせず、立ちっぱなしだ。
「え?」
「佐山さん眠っちゃったから、帰ろうと思ったんですけど、鍵の場所もわからないし、俺も眠たくて。床をお借りしようと思ったんですけど、その」
秋口がごちゃごちゃとものの積まれた床を見下ろし、佐山は恥じ入った。
「そうだよな、寝る場所ないよな、これじゃ」
「なんで俺も、ベッドをお借りして」
「うん」
「皺になると悪いと思ったんで、佐山さんもズボンだけ脱がせたんですけど、暑かったからシャツも脱いじゃったみたいですね」
秋口の言葉は、どこかいいわけめいた響きがあって、佐山には不思議だった。
「そっか、ありがとな。パジャマくらい出してやれればよかったんだけど……」
「いえ」
短く答え、秋口は一気に水を飲み干した。ペットボトルをテーブルの上に置いて、自分のシャツとズボンを手に取ると身にまとい出す。
「あ、ええと……帰るのか?」
「はい。泊まるつもりもなかったし」
答える秋口の言葉はやっぱりぶっきらぼうで、佐山はにわかに不安になった。
最初の頃、自分と顔を合わせるたびに呆れたり、小馬鹿にするような表情を見せていた秋口だが、最近は心なしか当たりがやわらかくなっていた気がする。少しは自分に気を許してくれたのだろうと、佐山はおぼろげに理解していたのだが。
(やっぱり、酔っぱらって、秋口の気に障ること口走ったんだろうか)
そのことについて訊ねるべきか、触らずにいるべきか迷っているうち、秋口はすっかり身支度を調えてしまった。
「それじゃあ、お邪魔しました」
「あ――秋口」
すぐに玄関口まで向かおうとする佐山は、とっさに秋口を呼び止めてしまった。秋口が無表情に振り返る。その顔を見たら、佐山の気持ちが竦んだ。
「いや……気をつけてな」
小さく頷くと、秋口はあとは何も言わず、佐山の部屋を出て行った。
「……」
佐山は呆けたようにベッドに座り込んだまま、それを見送る。静かにドアの閉まる音がした。
「……痛て……」
相変わらず頭は鈍く痛んでいる。
佐山はこれ以上考えるのが面倒になって、眼鏡をサイドテーブルに置くと、そのまま再びベッドへ横たわった。
鈍痛で目が覚めた。
ずきずきと、脈打つようにこめかみの辺りが痛んでいる。胃が重たくて、気持ち悪い。喉から胃液が逆流してきそうだ。
こんな感触には覚えがある。営業時代によく味わった、紛れもない宿酔いの状態。
「うー……」
体全体が怠くて、瞼は重くて、目が開かない。外がもう明るいことは、閉じた瞼越しにもわかった。一瞬、会社に遅れる、と思って肝が冷えたが、すぐに「今日は土曜日だ」ということを思い出す。午後から出社するつもりではあったが、基本的には休みの日だ。休んだって咎められることもない。
そこまでひどく間延びした思考で結論を出すと、佐山は少し落ち着いた気分でベッドのシーツに頬を擦りつけた。枕がなくて、横向きに丸まるような格好をしていた。うっすら目を開けて見ると、すぐそこにベッドのふちがある。何だって自分はこんな端っこで眠っていたのだろうか――と訝しみながら、佐山は軽く伸びをした。またこめかみで鈍痛が響くが、どうにかやりすごす。
カーテンから漏れる光で、すでに陽が高いことがわかり、佐山はいい加減起き出さなくてはと思いながら小さく身じろぎした。
と。
「え?」
動かした腕に、何か暖かいものが当たって佐山は眉を寄せる。暖かいくて、弾力のある、明らかに、
(……人肌?)
恐る恐る、佐山は背後へ首を巡らせた。
と。
「……ッ!」
驚きのあまり声も出ず、ただひたすらに、両目を見開いてしまう。
(な、何で)
口から心臓が飛び出るかと思った。なぜか、どういうわけだか、自分の隣では秋口が仰向けになって規則正しい寝息を立てているのだ。
おまけに、裸の肩が剥き出しだ。タオルケットが掛かっているから、全身素っ裸なのかまではわからない。佐山は慌てて自分の姿を確認した。辛うじて下着はつけているが、シャツは着ていない。また恐る恐る床を見ると、ふたり分のズボンと一枚分のシャツが、積み上げられた本の上にかけられている。そのの上に眼鏡。シャツ一枚だけが丸めて床に落としてあった。これが佐山のものだ。
痛む頭を押さえながら、佐山はどうにかベッドの上に起き上がった。とにかく眼鏡を拾って掛ける。
「……あれ……」
寝乱れた髪を押さえるように掻き上げながら、佐山は丸まったシャツと、秋口の寝姿を交互に見遣った。
必死になって、ゆうべのことを思い出す。
(いつもの店が閉まってて、買い物をしてうちに来て、それでメシ喰いながら、ちょっとだけ酒入れて――)
覚えているのは、そこまでだ。どうやら苦手な酒を飲んで、途中で潰れてしまったらしい。秋口に勧められたビールを一口二口飲んだ辺りから、すでに記憶が怪しくなっている。
(……変なこと、言ってないよな?)
おぼろげに覚えているのは、秋口がそこはかとなく苦笑する顔。自分は多分、彼に何かを言いつのり、だが何を言ったのかサッパリ覚えていない。
とにかく秋口が起きる前にベッドから抜け出そう、と佐山は痛む頭を押さえながらまた身じろぎした。こんな格好で秋口と顔を合わせるところなんて考えたくもない。
そう思ったのに、佐山がベッドを下りるよりも早く、秋口の目が開いた。フッと、前触れなく瞼が開いたのに、「寝起きがいいんだなあ」とこんな時なのに佐山は感心してしまう。
秋口は眠たそうに一度ぎゅっと目を閉じてから、佐山の方を見上げて、気怠そうに吐息した。
「……おはようございます」
寝起きの掠れた声に、佐山は頭の芯がぐらぐら揺れる感触を味わった。腰に来そうになって、慌ててその声を意識から追いやる。さり気ない素振りでタオルケットを引っ張り上げた。
「ええと……秋口、泊まったのか」
秋口から目を逸らしつつ、佐山がそう言うと、無言が返ってきた。
あれ、と思って秋口を見下ろしたら、思い切り曇った顔が見える。
「秋口? あの……悪い、俺、昨日のこと全然覚えてなくて」
「……ああ」
うわの空な様子で、秋口がやっと頷く。天井を見上げ、また大きく息を吐き出していた。
「そうか」
秋口はひどく不機嫌そうだった。そのことに佐山は慌てる。もしかしたら、酔っぱらって秋口の迷惑になるようなことをしてしまったのだろうか。
そう訊ねることもできず、どうしたものかと所在なくベッドの上で佐山が座ったままでいると、秋口が軽く目を閉じてまた口を開いた。
「すみませんけど、水か何かもらっていいですか」
「あ、う、うん」
急いでベッドから下りようとした佐山は、途端また鈍痛を感じて頭を押さえ、思わずうずくまった。呻き声を上げていると、隣で秋口が起き上がる気配がする。
「自分で取ってきます」
秋口がぶっきらぼうにそう言って、ベッドを下りる。
「あー……悪い、冷蔵庫にミネラルウォーターが入ってるから」
「佐山さんも飲みますか?」
「うん」
あちこちに積まれた荷物を乗り越えながら、隣のダイニングキッチンへ向かう秋口の後ろ姿を、佐山はそっと見遣った。秋口も下着ははいている。
男女じゃないんだから、たとえ素っ裸で寝ていたって、男同士なら妙なことになったと想像する方がおかしい。
そうわかってはいても、何しろ相手が秋口なものだから、佐山はうろたえずにはいられなかった。これがたとえば御幸あたりだったら、特に何も感じなかったに違いない。
秋口が戻って来たので、佐山は慌てて目を逸らした。頭痛に気を取られているふりで俯く。実際ひどく頭は痛み続けていた。
「どうぞ」
「あ、ありがとう」
目の前にぬっと出てきたペットボトルを佐山は受け取った。いただきます、と秋口が礼儀正しく言う声が聞こえる。佐山もキャップを開けて、水を一気に飲んだ。冷たい液体が喉を潤し、少し落ち着く。
「……すみません」
大きく息を吐いていると、そんな秋口の声が聞こえて、佐山は自然彼の方を見上げた。秋口はベッドの脇で、座りもせず、立ちっぱなしだ。
「え?」
「佐山さん眠っちゃったから、帰ろうと思ったんですけど、鍵の場所もわからないし、俺も眠たくて。床をお借りしようと思ったんですけど、その」
秋口がごちゃごちゃとものの積まれた床を見下ろし、佐山は恥じ入った。
「そうだよな、寝る場所ないよな、これじゃ」
「なんで俺も、ベッドをお借りして」
「うん」
「皺になると悪いと思ったんで、佐山さんもズボンだけ脱がせたんですけど、暑かったからシャツも脱いじゃったみたいですね」
秋口の言葉は、どこかいいわけめいた響きがあって、佐山には不思議だった。
「そっか、ありがとな。パジャマくらい出してやれればよかったんだけど……」
「いえ」
短く答え、秋口は一気に水を飲み干した。ペットボトルをテーブルの上に置いて、自分のシャツとズボンを手に取ると身にまとい出す。
「あ、ええと……帰るのか?」
「はい。泊まるつもりもなかったし」
答える秋口の言葉はやっぱりぶっきらぼうで、佐山はにわかに不安になった。
最初の頃、自分と顔を合わせるたびに呆れたり、小馬鹿にするような表情を見せていた秋口だが、最近は心なしか当たりがやわらかくなっていた気がする。少しは自分に気を許してくれたのだろうと、佐山はおぼろげに理解していたのだが。
(やっぱり、酔っぱらって、秋口の気に障ること口走ったんだろうか)
そのことについて訊ねるべきか、触らずにいるべきか迷っているうち、秋口はすっかり身支度を調えてしまった。
「それじゃあ、お邪魔しました」
「あ――秋口」
すぐに玄関口まで向かおうとする佐山は、とっさに秋口を呼び止めてしまった。秋口が無表情に振り返る。その顔を見たら、佐山の気持ちが竦んだ。
「いや……気をつけてな」
小さく頷くと、秋口はあとは何も言わず、佐山の部屋を出て行った。
「……」
佐山は呆けたようにベッドに座り込んだまま、それを見送る。静かにドアの閉まる音がした。
「……痛て……」
相変わらず頭は鈍く痛んでいる。
佐山はこれ以上考えるのが面倒になって、眼鏡をサイドテーブルに置くと、そのまま再びベッドへ横たわった。
◇◇◇
(――まいった)
土曜日、日曜日と、外に遊びに行く気にもならず悶々と自分の部屋で過ごす秋口の頭を占めていたのは、そんな気持ちばかりだった。
まさかあんな展開になるとは思わなかった。
まさか、佐山が、自分のことを好きだとは。
男なんてまるっきり趣味の範疇外だったから、そんな展開を考えたこともなかった。
なのに、なぜ……と考えると秋口はすっかり混乱してしまう。
(何で、俺は全然嫌な気分にならないんだ?)
昔別の男に言い寄られた時は、『虫酸が走る』という言葉を実体験したくらい、最低な気分になったのだ。言い寄ってきたふたりのうち片方は、佐山よりもずっと見た目のいい、妙に女性的なところのある男だった。胸があればそのまま女だと言い張れるくらいの美形だったが、秋口には生理的にその相手が許せなかった。
あれほどの美形でも許せなかったのに、なぜ、と秋口は途方に暮れる。
あんなに冴えない、やせっぽっちの男だというのに――
(でも、変に可愛いところがあったり)
気を抜くとそんなことを思ってしまい、そのたび秋口は慌てて佐山の酔っぱらって赤い顔や、小さく寝息を立てる寝顔を記憶から追い払おうとした。
なのに自分に寄り掛かってきた体の重みや温かさ、無防備に眠りこける表情は頭の中から消してしまえず、秋口を煩悶させる。服を脱いで寝たのは失敗だった。ふと素肌が触れて、夜中に何度も目を覚ましてしまった。寝返りも気軽に打てず、ろくろく眠ることもできなかった。佐山の方は、酒の力も手伝ってかぐっすりだったのが、恨めしいほど。
目が覚めるたび、自然と佐山の素肌に手が伸びそうになって、その都度秋口は自分の行動にぎょっとしなければならなかった。
何だかもう、わけがわからなかった。
(でも、そうだ)
そわそわする秋口の心をどうにか落ち着かせたのは、不意に浮かんだひとつの考えだった。
もし、本当に佐山が自分のことを好きだというのなら。
(佐山さんが俺のことを好きな限り、雛川さんになびくことがない)
その考えは、自分にとって大変な救いになるもののように、秋口には感じられた。
そう、利用してやればいいのだ。
自分は決してゲイなどではないのだから、せいぜい、そんな相手を利用してやればいいのだ。自分の目的はあくまで沙和子だ。彼女が佐山とよりを戻してしまわないよう、妨害するために佐山を食事に誘ってきた。
佐山が自分のことを好きだというのなら、それを利用してやればいいのだ。
いっそ自分にメロメロにさせて、その間に沙和子を自分のものにしてしまえばいい。そうしたら後は佐山に用なんてない。仕事の時に顔を合わせて、たったそれだけの関係になればいい。
「……そうだ、それがいいんだ」
秋口はそう決めると、やっと安心した。
自分が何を不安がっていたかなんて、考えるつもりはなかった。
土曜日、日曜日と、外に遊びに行く気にもならず悶々と自分の部屋で過ごす秋口の頭を占めていたのは、そんな気持ちばかりだった。
まさかあんな展開になるとは思わなかった。
まさか、佐山が、自分のことを好きだとは。
男なんてまるっきり趣味の範疇外だったから、そんな展開を考えたこともなかった。
なのに、なぜ……と考えると秋口はすっかり混乱してしまう。
(何で、俺は全然嫌な気分にならないんだ?)
昔別の男に言い寄られた時は、『虫酸が走る』という言葉を実体験したくらい、最低な気分になったのだ。言い寄ってきたふたりのうち片方は、佐山よりもずっと見た目のいい、妙に女性的なところのある男だった。胸があればそのまま女だと言い張れるくらいの美形だったが、秋口には生理的にその相手が許せなかった。
あれほどの美形でも許せなかったのに、なぜ、と秋口は途方に暮れる。
あんなに冴えない、やせっぽっちの男だというのに――
(でも、変に可愛いところがあったり)
気を抜くとそんなことを思ってしまい、そのたび秋口は慌てて佐山の酔っぱらって赤い顔や、小さく寝息を立てる寝顔を記憶から追い払おうとした。
なのに自分に寄り掛かってきた体の重みや温かさ、無防備に眠りこける表情は頭の中から消してしまえず、秋口を煩悶させる。服を脱いで寝たのは失敗だった。ふと素肌が触れて、夜中に何度も目を覚ましてしまった。寝返りも気軽に打てず、ろくろく眠ることもできなかった。佐山の方は、酒の力も手伝ってかぐっすりだったのが、恨めしいほど。
目が覚めるたび、自然と佐山の素肌に手が伸びそうになって、その都度秋口は自分の行動にぎょっとしなければならなかった。
何だかもう、わけがわからなかった。
(でも、そうだ)
そわそわする秋口の心をどうにか落ち着かせたのは、不意に浮かんだひとつの考えだった。
もし、本当に佐山が自分のことを好きだというのなら。
(佐山さんが俺のことを好きな限り、雛川さんになびくことがない)
その考えは、自分にとって大変な救いになるもののように、秋口には感じられた。
そう、利用してやればいいのだ。
自分は決してゲイなどではないのだから、せいぜい、そんな相手を利用してやればいいのだ。自分の目的はあくまで沙和子だ。彼女が佐山とよりを戻してしまわないよう、妨害するために佐山を食事に誘ってきた。
佐山が自分のことを好きだというのなら、それを利用してやればいいのだ。
いっそ自分にメロメロにさせて、その間に沙和子を自分のものにしてしまえばいい。そうしたら後は佐山に用なんてない。仕事の時に顔を合わせて、たったそれだけの関係になればいい。
「……そうだ、それがいいんだ」
秋口はそう決めると、やっと安心した。
自分が何を不安がっていたかなんて、考えるつもりはなかった。
◇◇◇
「佐山さん、今晩も空いてますか?」
月曜日、会社で顔を合わせるなり秋口に訊ねられ、佐山は頭の中で自分の予定を反芻してから、頷いた。
「また少し遅くなるけど、それからなら」
「俺も定時には終わらないですから、八時にいつものところで、どうですか。念のため予約入れておきました」
予約、という言葉に佐山は少し驚いた。その気配に気づいたのか、秋口が少し照れ臭そうな顔で笑う。
そんな秋口の表情に、佐山はつい見とれた。
「待つの面倒でしょう。本当は予約は取らないそうなんですけど、顔見知りになった店員に電話したら、時間どおりに必ず来るなら取っておくって」
「店員、女の子?」
軽口のつもりで訊ねた自分の言葉が、妙な具合に勘ぐっているように聞こえやしまいかと、佐山は内心ひやりとした。
秋口がかすかにばつの悪そうな苦笑いになったのを見て、佐山の焦りが募る。
「だよな、や、でも、助かった、秋口そういうところ、そつなくて」
言えば言うだけ深みにはまっている気がしないでもないが、とにかく、佐山は秋口と今日も夕食の約束をして別れた。
「ふうん、本当に仲よくなったんだな、おまえら」
「うわ」
秋口の後ろ姿を何となく見送っている時、背後、間近で聞こえた声に、佐山はぎょっとして振り返った。
「み、御幸、何だよ、驚かすなよ」
「たまたま通り掛かったんだよ、聞かれたくなかったんなら廊下で話してるおまえらが悪い」
友人はしれっと言って、佐山の隣に並んだ。始業後数時間経った昼休み少し前、佐山は備品を取りに倉庫へ向かうところ、御幸も資料を手にしているから、社内を移動する途中のようだ。
「別に、聞かれて困るってわけでもないけど……」
「恨まれてるぞ、おまえ、女子社員たちに。秋口を独り占めしてるってな」
からかう声音の御幸に、何とも答えがたく佐山は口を噤む。
「秋口も恨まれてるけどな、充分」
今度の御幸の言葉には、首を傾げた。
「恨まれてるって、誰に?」
「主に俺に。佐山君最近つき合い悪くって」
「って、別に俺、誘われてないよな?」
少し慌てた佐山を横目で見遣ってから、御幸が口端を持ち上げてにやっと笑った。
「野暮な真似したくないからな」
やっぱり佐山には、何と答えたものか、言葉が思いつかない。
御幸が佐山の耳許に唇を寄せ、声をひそめて訊ねた。
「で、うまくいってるのか?」
「うまく……? いってる? のか?」
「何だよ、煮え切らないなあ」
「だってただ単に、先輩後輩としてっていうか、仕事仲間として飲んでるだけだぞ。その……俺の下心、のようなもの、は知らないわけだし、向こうは」
「普通に店でメシ喰ってるだけ?」
「だいたいは。先週末は、いつも行ってる店が混んでたから、うちに来たけど……」
「嘘」
御幸は大仰なほど、驚いた顔で大きく目を見開いて見せた。
「おまえ、秋口をあの部屋に入れたのか? 俺以外の他人を?家族でもなく?」
「流れで、何となく」
「……ふーん……」
考え込む顔で、御幸が指先を自分の顎に当ててとんとんと叩いた。
それから、ふっと、苦笑のような笑みを浮かべる。
「おまえ、本当に好きなんだな。あいつのこと」
「……何、急に」
「佐山が自分の部屋に人招くなんてさ、なかっただろ? これまで。雛川さんの時も」
「そりゃあ、あれだけ散らかってれば、人呼ぶのなんて申し訳ないし」
「散らかってるとか、散らかってないとか、そういう問題じゃなくて――」
御幸がどことなく、まじめな顔になって佐山の目を覗き込んだ。
「おまえの部屋はさ、テリトリーだろ。殻っていうか……滅多なことじゃ踏み込ませない場所なわけだし」
「そこまで大袈裟なもんじゃないよ、現に御幸だって来るだろ」
「佐山、俺がおまえの部屋に入れてもらえるまで三年かかったって、わかってるか?」
「……そうだったっけ?」
「そうそう。俺たちがまともに自分たちのこと話すようになったのも、その辺だろ」
「……そうかも」
笑って、御幸が佐山の背中を叩いた。
「いい傾向いい傾向。佐山はもうちょっと自分ってもん他人に晒してけよ、そしたら、秋口だっておまえの価値に気づくさ」
「俺の価値、ねえ……」
御幸の言っていることは、佐山にはいまいちわからなかった。
何も隠しているつもりはないし、殻を作っているつもりもない。秋口にも、その他の人たちとも、自分なりにそれらしくつき合っているつもりだ。
「相手が秋口ってのがいささか不安だけどな……」
今度の御幸の言葉はひとりごとに近かったから、佐山は特別返事をしなかった。
「じゃ、空いてる時は俺も誘えよ」
御幸はもう一度佐山の背を叩き、廊下を歩いて行った。
夜になると、佐山は約束どおり秋口と落ち合い、いつもの店へ向かった。店は相変わらずの繁盛ぶりだったが、秋口が店員に自分の名前を耳打ちすると、店員は心得たように頷いて店の中へふたりを案内した。客で賑わうフロアを通り抜け、ついたてに隠されたドアを店員が開いて、急ぎ気味にふたりを手招く。佐山は秋口と一緒に、慌ててその中へ身を滑らせた。
「ここは貸し切りの時に使うお得意様用のフロアなんですけど。特別に」
年配の女性店員が、そう言って秋口に目配せした。もしかしたら彼女が店主なのかもしれない、と佐山はおぼろげに察する。メニューを置くと、彼女は一度部屋を下がっていった。
「いいのかな。あんなに混んでるのに、こんな広いところふたりだけで入っちゃって」
広い、と言っても、通常の客が使うフロアよりはぐっと狭まる。客は十人も入れば一杯になってしまうだろう。その代わり机や椅子はかなり上等そうなもので、飾り棚も、そこに並んだ皿やオブジェも、ぐっとグレードが上がっているように見える。本当に、賓客のための部屋なのだろう。
「ここまで開けて満杯にすると、料理の方が追いつかないからって言ってましたよ」
秋口は平然とした態度で上着を脱ぎ、椅子に腰かけた。佐山もそれに倣う。
「その代わりあまり面倒は見られないから、料理を運んだら放っておくって言われましたけど」
メニューを佐山に手渡しながら、秋口が笑う。佐山は彼がいかなる手段をもってこの部屋を借りるに至ったのか、訊ねようと思ってやめた。何となく落ち込む結果になりそうだと思った。
(そんなに心が狭い方でもないと思ってたんだけどな)
先刻の店員は、歳は多少いっているようだったが、それでも充分な美人だ。それに怜悧そうな顔立ちだった。秋口はああいう美人が好みなのかもしれない、などと思ってしまえば、自分との違いに落ち込むしかない。
考えないようにして、佐山はメニューから料理を選んだ。しばらく待つと先刻の女性が注文を聞きに来て、大分長い時間待たされた後やっと料理が来た。本当に忙しいらしくて、女性は遅くなったことを詫びたが、佐山はむしろ申し訳ない気分になった。
「やっぱり悪いな、混んでるのに」
女性が出て行った後、フォークを手に取りつつ佐山は呟いた。
「遅くてもよければって約束で、それに今回限りだから、そんなに気にしなくても大丈夫じゃないですか。結構待たされたけど、静かなところ借り切れてラッキーって思ってください」
そう言った秋口を、佐山は不思議な気分になって見遣った。
「どうしてわざわざ予約まで? この時間なら、今日はまだ他の店やってるだろうし……あ、もちろん、俺は嬉しいんだけど。この店はすごく気に入ったし」
「だからです」
「え?」
「佐山さん、この間ここに入れなくてがっかりしてたでしょう。次は春巻き食べてみるって楽しみにしてたのに」
秋口の言葉に、佐山はぎゅっと胸が締めつけられるような喜びを感じた。
「俺のために?」
「まあ――俺も来たかったですし」
秋口が憮然とした顔になったのを見て、佐山は今浮き上がった気分が急に沈んでしまった。一喜一憂とはこのことだろう。佐山にはなぜ秋口が不機嫌そうな顔になってしまったのかわからず、落ち着かない心地になった。
料理が来るまでは、仕事のことや他愛ない世間話でそれなりに話が弾んでいたのに、秋口が不機嫌になると、あっという間に部屋が静まりかえってしまった。秋口は黙って料理を口に運び、佐山も黙然とフォークを動かした。
(何か変なこと言ったか? 俺)
気になって、せっかくの料理の味がわからなくなってしまう。あまり食事という行為に興味がなかった自分が、こんなにも気に入るなんて、奇蹟みたいなもんだと思っていた料理なのに。
(料理のせいじゃないのかも)
もそもそと春巻きを噛みながら、佐山はそんなことに気づいた。
もちろん料理は絶品だとは思うが、それ以上に、一緒に食べる相手が秋口だから余計美味しくて、楽しいと思っていたのだ。多分。だって今はこんなに料理が味気ない。
どうにか会話のタイミングを掴もうとして、佐山は「この春巻き美味いな」とか、「このラッシーって今まで飲んだことなかったけど、結構癖になるな」とか笑って話しかけてみたのに、秋口は「はあ」とか「そうですか」とか気のない返事をするばかりだ。
佐山はどんどん胸が詰まってきて、春巻きを半分食べたところで、もう食欲がなくなってしまった。
自分の皿を見下ろしたまま黙々と料理を食べていた秋口が、すっかりフォークを持つ手を止めてしまった佐山に気づき、怪訝な顔になる。
「佐山さん? もういいんですか?」
「あ、いや……」
せっかく秋口が無理を言って部屋まで借りてくれたのに、食事を残すなんて彼にも店にも失礼だと思い直し、佐山は無理に春巻きを口に押し込んだ。
「……何か、機嫌悪いですか?」
「え」
探るように秋口から訊ねられ、佐山は手加減なくぎょっとした。おまえが言うのか、と言い返したいのを、ようよう堪える。
「いや、全然、そんなことは、ないけど」
「そうですか」
秋口はやっぱり憮然と、カクテルを飲み干した。テーブルの上のピッチャーを手に取り、手酌でお代わりしている。
「佐山さんって、結構人によって態度、変わる人です?」
「え……」
また佐山が驚くような台詞を秋口が言った。まるで責めているような口調だった。
「そんなこと、ないと思うけど。そりゃ、友達と取引先のお偉いさんの前じゃ変わるだろうけど……」
戸惑いつつ、そう答える。「ふうん」と頷いて、秋口がまたカクテルを口にした。
それから、グラスを片手に佐山の方を見て、軽く首を傾げる。
「俺の前で作ってません?」
「作ってる……って……」
佐山の脳裡に、昼間御幸に言われた言葉が浮かんだ。佐山はもうちょっと自分ってもん他人に晒してけよ、という。
「わざとやってるってことは、全然ないけど」
御幸にも秋口に言われるということは、もしかしたらそういう部分があるのかもしれないが、少なくとも意識しているわけではない。
だからそう答えた佐山に、秋口が小さく何度も頷いた。
「まあ、あの時は佐山さん、すっかり酔っぱらって正体失くしてたっぽいし」
「あの時? ……金曜日?」
「そうです」
記憶のない先週末の話を持ち出され、佐山はじんわりと背筋が冷える心地がした。
「もしかして俺、酔っぱらって、秋口に失礼なこと言ったりしたのか?」
それで秋口の機嫌が悪かったのかもしれない。わざわざひとけのないこの部屋を借りてくれたのも、自分の非を糾弾するためだったのかもしれない。
そこまで思い至って、佐山は蒼白になった。
「失礼……ってことは、ないと思いますけど」
秋口は含むような言い方をする。佐山はますます青くなった。
「ごめん、いや、何言ったかも思い出せないうちに謝るのはよくないと思うけど」
「まじめですよね、佐山さんは」
秋口が小さく微笑んだ。いつもならみとれてしまいそうなその笑顔に、佐山はどんどん肝が冷えていく心地だった。秋口は何も楽しくて笑っているという表情でもなかった。
「でも本当は、もう少しくだけた人なんじゃないですか? 酒入った時、佐山さんちょっと子供みたいだった。俺がもう帰るって言ったら、まだダメだって駄々っ子みたいに」
まるで覚えていない。佐山は恥ずかしくて目許を赤くした。青くなったり赤くなったり忙しい。
「悪い、記憶、ないんだ。困らせたよな、悪かった」
「俺に抱きついたのも覚えてない?」
「――ッ」
思わず、佐山は手にしていたフォークをテーブルの上に落とした。
「だ……抱きついた?」
「覚えてない?」
「……」
無言で、佐山はぶんぶんと必死で首を横に振った。まったく何ということをしてしまったのかと、自分を殴りつけたい気分だった。
「そっか……」
細く、秋口が溜息をつく。佐山はとにかく落ち着こうと水を飲んだ。
「その後俺に、好きだって言ったことも?」
「……ッ!」
今度は水の入ったグラスを取り落としそうになり、佐山は危うくのところでそれを堪えた。震える手でグラスをテーブルに置いたら、思いのほか大きな音がして自分で驚く。
「ああ、違うか。俺が訊いたんだ、佐山さんは俺のこと好きなのか、って」
「ごめん!」
佐山が立ち上がり、その勢いで椅子が後ろに倒れた。秋口が驚いたように佐山を見上げている。
そんな秋口の表情も見えないくらい混乱して、佐山は真っ白な頭でひたすら謝罪を口にした。もうまともに物を考えられなくなっていた。
「本当に、ごめん、違うんだ、そんな……言うつもりはなくて、全然、覚えてなくて、俺は」
自分でも何を言っているのかわからない。恥ずかしくて、目の前に涙が滲み、余計情けない気分になる。
酔っぱらって、秋口本人に、気持ちを告げてしまった。
そして秋口は気分を害して、きっと、とても怒っている。
「……ごめん!」
椅子にかけた上着を取り、佐山はそのまま部屋を駆け出そうとした。
それより早く、後ろから腕を掴まれる。驚いて振り返ると、すぐ間近に秋口がいた。広くはない部屋で、佐山の前にはもうドアがあったが、そのドアを秋口が腕で押さえてしまう。
(怒ってるんだ)
真剣な顔で自分を見下ろす秋口のことを見ていられず、佐山は咄嗟に顔を伏せた。酔った勢いで男に告白されて、それで嫌な気分にならない人間がいるはずがない。その上秋口はどんな美女でもよりどりみどりの男なのだ。
「ごめん、忘れてくれ、秋口のこと怒らせるつもりはなかったんだ」
とにかくこの場を逃げ出したい一心で秋口の腕を振り解こうとするのに、秋口は許さず、佐山はむしろその腕に体を押さえつけられるような格好になった。ドアに肩が当たってひどく痛む。だがそれに文句を言う権利なんてないと思う。どれだけ罵られたって、たとえ殴られたって文句なんて言えない。
「気持ちの悪い思いさせて、ごめん、そんなふうに言うつもりは本当に、なくて」
秋口を不快にさせたと思うと、自分がどうしようもなく情けなくて、堪えきれず佐山は涙をこぼした。それで余計にまた恥ずかしく居たたまれない気分になり、せめてみっともない泣き顔なんて見せてますます秋口を不愉快にさせたりはすまいと、顔を伏せる。
だが秋口は片手で佐山の腕をきつく掴み、反対の手で佐山の顎に手をかけると、顔を上向かせた。
謝る言葉も掠れて上手く出なくなってしまった佐山は、なすすべもなく小さく肩を揺らした。子供みたいにしゃくり上げる自分がなんてみっともないのだろうかと、消え入りたい気分で思った時、目の前に影が近づいてきたことに気づいて、反射的に顔を上げる。
(――え)
秋口にきつく押さえられた顎が痛む。
だがそんな痛みも一瞬でかき消えてしまいそうな、まったく別の感触。
「あ……きぐち?」
問う声は掠れて、ほとんど音になっていなかった。
その声を吸い込むように、秋口がもう一度、佐山の唇に唇で触れる。
キスをされているのだと、そう理解した瞬間、佐山は心臓を拳で殴られたような衝撃を味わった。
「ん……ッ」
驚いて、咄嗟に秋口の胸を押し遣ろうと、掴まれたままの腕を動かす。だが秋口の手がそれを封じ込め、佐山はそれで身じろぎひとつできなくなった。
本当はほんの数秒のできごとだったのかもしれない。
しかし佐山はずいぶんと長い間秋口に唇を重ねられていたような気がして、途中からはもう呆然と、ただなすがままになっていた。
大人しくなった佐山から、秋口がゆっくりと唇を離す。
「秋、口……」
わけを問おうとどうにか声を絞り出した佐山の間近で、秋口が眉根を寄せてそれを見返した。
「黙って」
そう言われて、もう言葉を発することすら佐山にはできなくなってしまう。
秋口にされるまま、眼鏡を奪われ、もう一度接吻けられた。
正気を保っていられなくて目を閉じる。瞼を下ろすと涙が落ちた。指先でそれを拭われる感触。どうして、とまた思ったが、佐山はやっぱりそれを秋口に訊ねることはできなかった。
何ひとつ思考なんてできない頭のまま、佐山は何度も秋口と唇を重ねた。
月曜日、会社で顔を合わせるなり秋口に訊ねられ、佐山は頭の中で自分の予定を反芻してから、頷いた。
「また少し遅くなるけど、それからなら」
「俺も定時には終わらないですから、八時にいつものところで、どうですか。念のため予約入れておきました」
予約、という言葉に佐山は少し驚いた。その気配に気づいたのか、秋口が少し照れ臭そうな顔で笑う。
そんな秋口の表情に、佐山はつい見とれた。
「待つの面倒でしょう。本当は予約は取らないそうなんですけど、顔見知りになった店員に電話したら、時間どおりに必ず来るなら取っておくって」
「店員、女の子?」
軽口のつもりで訊ねた自分の言葉が、妙な具合に勘ぐっているように聞こえやしまいかと、佐山は内心ひやりとした。
秋口がかすかにばつの悪そうな苦笑いになったのを見て、佐山の焦りが募る。
「だよな、や、でも、助かった、秋口そういうところ、そつなくて」
言えば言うだけ深みにはまっている気がしないでもないが、とにかく、佐山は秋口と今日も夕食の約束をして別れた。
「ふうん、本当に仲よくなったんだな、おまえら」
「うわ」
秋口の後ろ姿を何となく見送っている時、背後、間近で聞こえた声に、佐山はぎょっとして振り返った。
「み、御幸、何だよ、驚かすなよ」
「たまたま通り掛かったんだよ、聞かれたくなかったんなら廊下で話してるおまえらが悪い」
友人はしれっと言って、佐山の隣に並んだ。始業後数時間経った昼休み少し前、佐山は備品を取りに倉庫へ向かうところ、御幸も資料を手にしているから、社内を移動する途中のようだ。
「別に、聞かれて困るってわけでもないけど……」
「恨まれてるぞ、おまえ、女子社員たちに。秋口を独り占めしてるってな」
からかう声音の御幸に、何とも答えがたく佐山は口を噤む。
「秋口も恨まれてるけどな、充分」
今度の御幸の言葉には、首を傾げた。
「恨まれてるって、誰に?」
「主に俺に。佐山君最近つき合い悪くって」
「って、別に俺、誘われてないよな?」
少し慌てた佐山を横目で見遣ってから、御幸が口端を持ち上げてにやっと笑った。
「野暮な真似したくないからな」
やっぱり佐山には、何と答えたものか、言葉が思いつかない。
御幸が佐山の耳許に唇を寄せ、声をひそめて訊ねた。
「で、うまくいってるのか?」
「うまく……? いってる? のか?」
「何だよ、煮え切らないなあ」
「だってただ単に、先輩後輩としてっていうか、仕事仲間として飲んでるだけだぞ。その……俺の下心、のようなもの、は知らないわけだし、向こうは」
「普通に店でメシ喰ってるだけ?」
「だいたいは。先週末は、いつも行ってる店が混んでたから、うちに来たけど……」
「嘘」
御幸は大仰なほど、驚いた顔で大きく目を見開いて見せた。
「おまえ、秋口をあの部屋に入れたのか? 俺以外の他人を?家族でもなく?」
「流れで、何となく」
「……ふーん……」
考え込む顔で、御幸が指先を自分の顎に当ててとんとんと叩いた。
それから、ふっと、苦笑のような笑みを浮かべる。
「おまえ、本当に好きなんだな。あいつのこと」
「……何、急に」
「佐山が自分の部屋に人招くなんてさ、なかっただろ? これまで。雛川さんの時も」
「そりゃあ、あれだけ散らかってれば、人呼ぶのなんて申し訳ないし」
「散らかってるとか、散らかってないとか、そういう問題じゃなくて――」
御幸がどことなく、まじめな顔になって佐山の目を覗き込んだ。
「おまえの部屋はさ、テリトリーだろ。殻っていうか……滅多なことじゃ踏み込ませない場所なわけだし」
「そこまで大袈裟なもんじゃないよ、現に御幸だって来るだろ」
「佐山、俺がおまえの部屋に入れてもらえるまで三年かかったって、わかってるか?」
「……そうだったっけ?」
「そうそう。俺たちがまともに自分たちのこと話すようになったのも、その辺だろ」
「……そうかも」
笑って、御幸が佐山の背中を叩いた。
「いい傾向いい傾向。佐山はもうちょっと自分ってもん他人に晒してけよ、そしたら、秋口だっておまえの価値に気づくさ」
「俺の価値、ねえ……」
御幸の言っていることは、佐山にはいまいちわからなかった。
何も隠しているつもりはないし、殻を作っているつもりもない。秋口にも、その他の人たちとも、自分なりにそれらしくつき合っているつもりだ。
「相手が秋口ってのがいささか不安だけどな……」
今度の御幸の言葉はひとりごとに近かったから、佐山は特別返事をしなかった。
「じゃ、空いてる時は俺も誘えよ」
御幸はもう一度佐山の背を叩き、廊下を歩いて行った。
夜になると、佐山は約束どおり秋口と落ち合い、いつもの店へ向かった。店は相変わらずの繁盛ぶりだったが、秋口が店員に自分の名前を耳打ちすると、店員は心得たように頷いて店の中へふたりを案内した。客で賑わうフロアを通り抜け、ついたてに隠されたドアを店員が開いて、急ぎ気味にふたりを手招く。佐山は秋口と一緒に、慌ててその中へ身を滑らせた。
「ここは貸し切りの時に使うお得意様用のフロアなんですけど。特別に」
年配の女性店員が、そう言って秋口に目配せした。もしかしたら彼女が店主なのかもしれない、と佐山はおぼろげに察する。メニューを置くと、彼女は一度部屋を下がっていった。
「いいのかな。あんなに混んでるのに、こんな広いところふたりだけで入っちゃって」
広い、と言っても、通常の客が使うフロアよりはぐっと狭まる。客は十人も入れば一杯になってしまうだろう。その代わり机や椅子はかなり上等そうなもので、飾り棚も、そこに並んだ皿やオブジェも、ぐっとグレードが上がっているように見える。本当に、賓客のための部屋なのだろう。
「ここまで開けて満杯にすると、料理の方が追いつかないからって言ってましたよ」
秋口は平然とした態度で上着を脱ぎ、椅子に腰かけた。佐山もそれに倣う。
「その代わりあまり面倒は見られないから、料理を運んだら放っておくって言われましたけど」
メニューを佐山に手渡しながら、秋口が笑う。佐山は彼がいかなる手段をもってこの部屋を借りるに至ったのか、訊ねようと思ってやめた。何となく落ち込む結果になりそうだと思った。
(そんなに心が狭い方でもないと思ってたんだけどな)
先刻の店員は、歳は多少いっているようだったが、それでも充分な美人だ。それに怜悧そうな顔立ちだった。秋口はああいう美人が好みなのかもしれない、などと思ってしまえば、自分との違いに落ち込むしかない。
考えないようにして、佐山はメニューから料理を選んだ。しばらく待つと先刻の女性が注文を聞きに来て、大分長い時間待たされた後やっと料理が来た。本当に忙しいらしくて、女性は遅くなったことを詫びたが、佐山はむしろ申し訳ない気分になった。
「やっぱり悪いな、混んでるのに」
女性が出て行った後、フォークを手に取りつつ佐山は呟いた。
「遅くてもよければって約束で、それに今回限りだから、そんなに気にしなくても大丈夫じゃないですか。結構待たされたけど、静かなところ借り切れてラッキーって思ってください」
そう言った秋口を、佐山は不思議な気分になって見遣った。
「どうしてわざわざ予約まで? この時間なら、今日はまだ他の店やってるだろうし……あ、もちろん、俺は嬉しいんだけど。この店はすごく気に入ったし」
「だからです」
「え?」
「佐山さん、この間ここに入れなくてがっかりしてたでしょう。次は春巻き食べてみるって楽しみにしてたのに」
秋口の言葉に、佐山はぎゅっと胸が締めつけられるような喜びを感じた。
「俺のために?」
「まあ――俺も来たかったですし」
秋口が憮然とした顔になったのを見て、佐山は今浮き上がった気分が急に沈んでしまった。一喜一憂とはこのことだろう。佐山にはなぜ秋口が不機嫌そうな顔になってしまったのかわからず、落ち着かない心地になった。
料理が来るまでは、仕事のことや他愛ない世間話でそれなりに話が弾んでいたのに、秋口が不機嫌になると、あっという間に部屋が静まりかえってしまった。秋口は黙って料理を口に運び、佐山も黙然とフォークを動かした。
(何か変なこと言ったか? 俺)
気になって、せっかくの料理の味がわからなくなってしまう。あまり食事という行為に興味がなかった自分が、こんなにも気に入るなんて、奇蹟みたいなもんだと思っていた料理なのに。
(料理のせいじゃないのかも)
もそもそと春巻きを噛みながら、佐山はそんなことに気づいた。
もちろん料理は絶品だとは思うが、それ以上に、一緒に食べる相手が秋口だから余計美味しくて、楽しいと思っていたのだ。多分。だって今はこんなに料理が味気ない。
どうにか会話のタイミングを掴もうとして、佐山は「この春巻き美味いな」とか、「このラッシーって今まで飲んだことなかったけど、結構癖になるな」とか笑って話しかけてみたのに、秋口は「はあ」とか「そうですか」とか気のない返事をするばかりだ。
佐山はどんどん胸が詰まってきて、春巻きを半分食べたところで、もう食欲がなくなってしまった。
自分の皿を見下ろしたまま黙々と料理を食べていた秋口が、すっかりフォークを持つ手を止めてしまった佐山に気づき、怪訝な顔になる。
「佐山さん? もういいんですか?」
「あ、いや……」
せっかく秋口が無理を言って部屋まで借りてくれたのに、食事を残すなんて彼にも店にも失礼だと思い直し、佐山は無理に春巻きを口に押し込んだ。
「……何か、機嫌悪いですか?」
「え」
探るように秋口から訊ねられ、佐山は手加減なくぎょっとした。おまえが言うのか、と言い返したいのを、ようよう堪える。
「いや、全然、そんなことは、ないけど」
「そうですか」
秋口はやっぱり憮然と、カクテルを飲み干した。テーブルの上のピッチャーを手に取り、手酌でお代わりしている。
「佐山さんって、結構人によって態度、変わる人です?」
「え……」
また佐山が驚くような台詞を秋口が言った。まるで責めているような口調だった。
「そんなこと、ないと思うけど。そりゃ、友達と取引先のお偉いさんの前じゃ変わるだろうけど……」
戸惑いつつ、そう答える。「ふうん」と頷いて、秋口がまたカクテルを口にした。
それから、グラスを片手に佐山の方を見て、軽く首を傾げる。
「俺の前で作ってません?」
「作ってる……って……」
佐山の脳裡に、昼間御幸に言われた言葉が浮かんだ。佐山はもうちょっと自分ってもん他人に晒してけよ、という。
「わざとやってるってことは、全然ないけど」
御幸にも秋口に言われるということは、もしかしたらそういう部分があるのかもしれないが、少なくとも意識しているわけではない。
だからそう答えた佐山に、秋口が小さく何度も頷いた。
「まあ、あの時は佐山さん、すっかり酔っぱらって正体失くしてたっぽいし」
「あの時? ……金曜日?」
「そうです」
記憶のない先週末の話を持ち出され、佐山はじんわりと背筋が冷える心地がした。
「もしかして俺、酔っぱらって、秋口に失礼なこと言ったりしたのか?」
それで秋口の機嫌が悪かったのかもしれない。わざわざひとけのないこの部屋を借りてくれたのも、自分の非を糾弾するためだったのかもしれない。
そこまで思い至って、佐山は蒼白になった。
「失礼……ってことは、ないと思いますけど」
秋口は含むような言い方をする。佐山はますます青くなった。
「ごめん、いや、何言ったかも思い出せないうちに謝るのはよくないと思うけど」
「まじめですよね、佐山さんは」
秋口が小さく微笑んだ。いつもならみとれてしまいそうなその笑顔に、佐山はどんどん肝が冷えていく心地だった。秋口は何も楽しくて笑っているという表情でもなかった。
「でも本当は、もう少しくだけた人なんじゃないですか? 酒入った時、佐山さんちょっと子供みたいだった。俺がもう帰るって言ったら、まだダメだって駄々っ子みたいに」
まるで覚えていない。佐山は恥ずかしくて目許を赤くした。青くなったり赤くなったり忙しい。
「悪い、記憶、ないんだ。困らせたよな、悪かった」
「俺に抱きついたのも覚えてない?」
「――ッ」
思わず、佐山は手にしていたフォークをテーブルの上に落とした。
「だ……抱きついた?」
「覚えてない?」
「……」
無言で、佐山はぶんぶんと必死で首を横に振った。まったく何ということをしてしまったのかと、自分を殴りつけたい気分だった。
「そっか……」
細く、秋口が溜息をつく。佐山はとにかく落ち着こうと水を飲んだ。
「その後俺に、好きだって言ったことも?」
「……ッ!」
今度は水の入ったグラスを取り落としそうになり、佐山は危うくのところでそれを堪えた。震える手でグラスをテーブルに置いたら、思いのほか大きな音がして自分で驚く。
「ああ、違うか。俺が訊いたんだ、佐山さんは俺のこと好きなのか、って」
「ごめん!」
佐山が立ち上がり、その勢いで椅子が後ろに倒れた。秋口が驚いたように佐山を見上げている。
そんな秋口の表情も見えないくらい混乱して、佐山は真っ白な頭でひたすら謝罪を口にした。もうまともに物を考えられなくなっていた。
「本当に、ごめん、違うんだ、そんな……言うつもりはなくて、全然、覚えてなくて、俺は」
自分でも何を言っているのかわからない。恥ずかしくて、目の前に涙が滲み、余計情けない気分になる。
酔っぱらって、秋口本人に、気持ちを告げてしまった。
そして秋口は気分を害して、きっと、とても怒っている。
「……ごめん!」
椅子にかけた上着を取り、佐山はそのまま部屋を駆け出そうとした。
それより早く、後ろから腕を掴まれる。驚いて振り返ると、すぐ間近に秋口がいた。広くはない部屋で、佐山の前にはもうドアがあったが、そのドアを秋口が腕で押さえてしまう。
(怒ってるんだ)
真剣な顔で自分を見下ろす秋口のことを見ていられず、佐山は咄嗟に顔を伏せた。酔った勢いで男に告白されて、それで嫌な気分にならない人間がいるはずがない。その上秋口はどんな美女でもよりどりみどりの男なのだ。
「ごめん、忘れてくれ、秋口のこと怒らせるつもりはなかったんだ」
とにかくこの場を逃げ出したい一心で秋口の腕を振り解こうとするのに、秋口は許さず、佐山はむしろその腕に体を押さえつけられるような格好になった。ドアに肩が当たってひどく痛む。だがそれに文句を言う権利なんてないと思う。どれだけ罵られたって、たとえ殴られたって文句なんて言えない。
「気持ちの悪い思いさせて、ごめん、そんなふうに言うつもりは本当に、なくて」
秋口を不快にさせたと思うと、自分がどうしようもなく情けなくて、堪えきれず佐山は涙をこぼした。それで余計にまた恥ずかしく居たたまれない気分になり、せめてみっともない泣き顔なんて見せてますます秋口を不愉快にさせたりはすまいと、顔を伏せる。
だが秋口は片手で佐山の腕をきつく掴み、反対の手で佐山の顎に手をかけると、顔を上向かせた。
謝る言葉も掠れて上手く出なくなってしまった佐山は、なすすべもなく小さく肩を揺らした。子供みたいにしゃくり上げる自分がなんてみっともないのだろうかと、消え入りたい気分で思った時、目の前に影が近づいてきたことに気づいて、反射的に顔を上げる。
(――え)
秋口にきつく押さえられた顎が痛む。
だがそんな痛みも一瞬でかき消えてしまいそうな、まったく別の感触。
「あ……きぐち?」
問う声は掠れて、ほとんど音になっていなかった。
その声を吸い込むように、秋口がもう一度、佐山の唇に唇で触れる。
キスをされているのだと、そう理解した瞬間、佐山は心臓を拳で殴られたような衝撃を味わった。
「ん……ッ」
驚いて、咄嗟に秋口の胸を押し遣ろうと、掴まれたままの腕を動かす。だが秋口の手がそれを封じ込め、佐山はそれで身じろぎひとつできなくなった。
本当はほんの数秒のできごとだったのかもしれない。
しかし佐山はずいぶんと長い間秋口に唇を重ねられていたような気がして、途中からはもう呆然と、ただなすがままになっていた。
大人しくなった佐山から、秋口がゆっくりと唇を離す。
「秋、口……」
わけを問おうとどうにか声を絞り出した佐山の間近で、秋口が眉根を寄せてそれを見返した。
「黙って」
そう言われて、もう言葉を発することすら佐山にはできなくなってしまう。
秋口にされるまま、眼鏡を奪われ、もう一度接吻けられた。
正気を保っていられなくて目を閉じる。瞼を下ろすと涙が落ちた。指先でそれを拭われる感触。どうして、とまた思ったが、佐山はやっぱりそれを秋口に訊ねることはできなかった。
何ひとつ思考なんてできない頭のまま、佐山は何度も秋口と唇を重ねた。
◇◇◇
足許がふわふわする感覚、というのを生まれて初めて味わっている。
別にそのことばかりを考えているわけじゃないのに、いつでも気持ちが上擦って、落ち着かない。パソコンのキーボードを叩いていても、書類を眺めていても、喉が詰まったように熱くなって、そわそわしてしまう。
(……駄目だ)
溜息をつき、眼鏡を取ってこめかみを揉んだ。
「あれ、佐山、お疲れ?」
後ろを通り掛かった開発課の同期が、そんな佐山の様子を見て声をかけてくる。佐山は振り返って曖昧に笑った。
「かもしれない。ちょっと一服してくる」
急ぎの仕事がないのを幸い、佐山はデスクの上の煙草とライターを取って尻ポケットにねじ込み、席を立った。妙に頭が痛んだので、眼鏡はかけず、そのままシャツの胸ポケットに引っかける。
まだ午前中、休憩所の辺りに人影はなかった。佐山は自販機でホットミルクを買うと、カップを取り出し、立ったまま壁に寄り掛かった。
冷房の効いたビルの中、暖かいミルクを飲み込むと、少し落ち着いた。
だが一口目を飲んだだけであとは動きが止まり、そのまま、カップの中のミルクを眺める。湯気のせいと裸眼のせいで、ミルクはずいぶんぼんやりした、白い靄のように見えた。
「……」
そしてほんの少し動きを止めてしまうと、佐山の脳裡に浮かぶのはゆうべの晩秋口に触れられた状況ばかりだ。
(本当、駄目だ)
目を閉じて、頭も壁に預けてしまう。自分の顔が赤くなってしまわない自信がなかった。まるで恋を覚えたての子供みたいだと奇妙に気恥ずかしい心地になる。
ゆうべ、佐山は何度も秋口とキスを交わした。それは本当にただ触れるだけの接吻けで、ゆっくり、ゆっくりと、秋口の唇が触れては離れ、触れては離れと、した。
その時佐山の頭は真っ白で、どうして秋口が自分にそんなことをするのか、まったく答えが出なかった。
そして未だに、正解なんて捜せない。
秋口はみっともなく泣いてしまった自分に何度も唇で触れてから、そのうちにそっと体を離した。
『飯、喰いましょう。残ってるから、勿体ない』
言われた言葉の意味がその時の佐山にはよくわからなくて、曖昧な視線で秋口を見上げた。その時も佐山は眼鏡がなく裸眼で、秋口の姿がひどくぼやけて見えていた。だから彼がどんな顔をしていたのかわからなかった。
涙の伝う目尻や頬が痒くなって、その辺りに佐山が指で触れようとするより先に、視界に黒いものが飛び込んできた。驚いて身を引くと、背中のドアに頭をぶつけてしまった。
微かに秋口の輪郭が揺れて、笑われたのだとわかった。
『眼鏡。ないと見えないんでしょう』
笑った声で秋口はそう言って、佐山に眼鏡をかけてくれた。その眼鏡を佐山は一度取り外して、目許を拭ってからもう一度自分で掛け直した。
その時には、秋口はもう元の席に戻っていた。
佐山は上手く思考の働かない頭を持て余しながら、自分も秋口の向かいに座り直した。
秋口は普通の顔で食事を再開して、佐山も無理に春巻きを口の中へと押し込み、ラッシーでそれを飲み下した。味なんてさっぱりわからなかった。
秋口の真意を問うことが佐山にはできなかった。あまりに秋口が平然とした態度だったせいだと思う。平然としているのに何も喋らない。いつもだったら場を和ませるような会話を如才なく続けるのに。
秋口は結局それから最後まで、黙然と料理を口に運び続けた。佐山も黙ったまま食事を終え、ふたりで店を出た。
『それじゃ、また会社で』
いつものとおり、分かれ道でそう言うと、秋口は駅の方へと行ってしまった。
佐山は取り残された気分でそれを見送り、それから自分の家へと戻った。
眠れなかった。自分の部屋の自分のベッドに横たわるのに、秋口にされたキスの感触を思い出してしまって、明け方近くまで眠気なんて一欠片も起きなかった。
起きてからもその調子だ。
好きだと、自分の気持ちが当の秋口にばれて、それで秋口は自分にキスした。
でも秋口は何も言わなかった。
それがどういうことなのか、佐山はずっと、その意味について考えようとしている。
決してキスをされたこと自体に浮かれてしまわないように。
(秋口が、俺と同じ気持ちだなんてことは、ありえないんだから)
何度も何度も、そうやって自分を戒める。調子に乗って、秋口に嫌な思いをさせることにでもなったら最低だ。
(もしかしたら、いい歳して男なんかに告白した俺のことを、可哀想だと思って慰めてくれたのかもしれないし)
自分が女だったら、多分秋口の行動に説明はつくのだ。ごく簡単に。佐山にもそれはわかる。秋口は女の子の扱いが上手くて、彼が好んでつき合うのは物分かりがよくプライドも高く、後腐れのない大人の女性が多い。噂でそう聞いて、その相手として名前の挙がった女性数人は社内で佐山も知っている人だったから、納得もできた。
キスをされたくらいで、想いを返してもらえたなんて勘違いしてつきまとったりしたら、秋口には迷惑だろう。そういうタイプの女を秋口が相手にした話は聞いたことがない。
(だから、いちいち浮かれたら駄目なんだって)
もし秋口が女だったら、さちに話は簡単だった。誠意を尽くして気持ちを告げて、できれば恋人としてつき合ってほしいと言うだけだ。結果はどうあっても、自分の取るべき行動はひとつしかないし、そもそも、迷う理由も悩む理由もひとつだってない。
今の自分の前に立ちふさがるあたりまえの障害について思って、冷房で冷えた手をカップで温めながら、佐山は小さく溜息をついた。
「あれ――」
ぼやけた視界で揺れる湯気を眺めていると、間近で声が聞こえて佐山はぎょっと顔を上げた。いつの間にか斜め前に人がいて、自分の正面に近づきながら顔を覗き込んでいる。
声でわかった。秋口だ。
「佐山さん、眼鏡は?」
「ここ」
内心はひどくうろたえていたのに、佐山は何ともない素振りで自分の胸ポケットを指さして見せた。割合こういう態度が得意なのだ。昨日、秋口の前でみっともなく涙なんてこぼしてしまったのが異常なくらいで。
「俺の顔見えてます?」
間近に秋口の顔があった。まったく眼鏡を外していた自分は運がいい。その男らしく整った顔になるべく焦点を合わせないよう、目を細めながら佐山は首を横に振った。
「ぼやけてる」
本当は近視だから、近づいてくれれば充分見えるのだが。
「すげぇ顔」
秋口が小さく笑った。それから、不意に片手を佐山の頬へ伸ばしてくる。
「ちょっと、動かないで。睫ついてる」
「……」
佐山は大人しく動きを止めた。本当は体が強張って、動かなかったのだが。
秋口の指先が軽く目許に触れて、反射的に佐山は目を閉じた。
「取れたか?」
なかなか離れない秋口の指に困って、佐山は目を閉じたまま訊ねた。
「……秋口?」
そんなに頑固な睫なのかと、再び問おうとした佐山は、秋口の指先にそっと目許を撫でられて微かに眉根を寄せた。些細な感触だったのに、体が震えそうになって驚いた。
佐山はその動揺を隠すように瞼を開き、つい秋口に視線を凝らしてしまった。
秋口が真顔で佐山のことを見下ろしていた。
(……あれ、何か)
よくない感じだ、と佐山は肌で感じた。
今秋口とふたりきりでいるのは、多分よくない。
「そろそろ仕事、戻るな」
温くなったミルクを一気に飲み干し、秋口から顔を逸らすようにして空になったカップを捨て、休憩所を出ようと歩き出しかけた佐山は、手首を掴まれ驚いた。
見上げると秋口はもう自分の前を歩いていて、手を引っ張ったまま休憩所から廊下に進んでいる。
「あ――秋口?」
何のつもりかと、訊ねたつもりで呟いた言葉は無視された。廊下を歩く別の社員が、無表情の秋口と、それに手を引かれた佐山を怪訝そうに見ていたが秋口はお構いなしだ。どんどん佐山を引っ張って、廊下を奥の方へと進んでいる。
大股で歩く秋口の後を仕方なく小走りについていった佐山は、そのまま資材倉庫まで辿り着いた。資材倉庫とは名ばかりで、使い道はないが処分し辛い古びた備品や資料が押し込められた、狭いがらくた部屋だ。秋口はその部屋の中に佐山の手を引いて入ると、IDカードなんかなくても入れる壊れかけたドアを閉じた。
明かりはつけなかったが、ブラインドの掛かった窓から外の光が細く何条も漏れている。
佐山は何が起きたのかよくわからなくて、とにかく落ち着こうと、眼鏡に手を伸ばした。
それを、秋口のもう一本の手に止められた。両手を押さえるように掴まれ、佐山は顔が上げられなくなってしまった。自分の心音が奇妙に近い。まるで耳許に心臓があるみたいだ。
多分、きっと、期待してたと思う。
そして佐山の期待どおりに、秋口はそのまま身を屈め、そっと近づいてきた。佐山はやっぱり顔が上げられず、俯いたまま困り果てる。
どうして、と理由を問えば、秋口が逃げてしまう気がして何も言えなかった。秋口は俯いた佐山の顔を下から掬うように、ゆっくり唇を合わせてきた。佐山は少し迷ったあと目を閉じる。昨日みたいに、秋口に何度も接吻けられる間に少しずつ顎が上がった。気づいたら秋口にされっぱなしになっているわけではなく、自分からも唇を寄せて触れ合っているような格好になっていた。
(止まらない)
どこの世界に、好きな相手からキスされて、自分からその状況を手放せるような人間がいるのか。
佐山は面倒になって、もう理由なんて考えず秋口とキスを交わした。わけを聞くなら喋るために離れなくてはいけない。そんなの勿体ない。
秋口の舌が唇に触れると、佐山はほぼ無意識にそれを開いた。自分からも少し舌を差し出し、接吻けはすぐに深くなった。両手を戒めるように掴まれているのがわずかにもどかしい。でもどうせ両手が自由だって、自分から秋口の背を抱いたりすることはできなかっただろう。
秋口はどうしてか、佐山が逃げ出すことでも警戒するように、きつく手首を握っている。ちょっと痛かったが、佐山はそれに文句を言う気も起きなかった。
「……ん……」
息苦しいのと、気持ちいいので、微かに吐息に似た声を洩らしてしまう。その自分の声が部屋の中に響いたから、佐山は変に緊張した。つい夢中で舌を絡め合ったりしてしまったが、そういえばここは会社なのだと、いまさら思い出した。
それで無意識に佐山が少し身を引くと、濡れた音を立てて互いの舌と唇が離れた。その音がやたら淫らっぽくて佐山は頭がくらくらする。場所とか、相手のこととか、考えるだけで貧血でも起こしそうな気分になった。
血が下がっているのではなく、頭に昇っている方の眩暈なのかもしれない。
佐山は息が乱れているのを悟られたくなくて、ゆっくり深呼吸した。まだ間近にいる秋口からも吐息が漏れ、体が震えそうになるのをようやく堪える。
秋口はやっぱり何も言わなかった。佐山は声を出せばそれが上擦っていそうなのが怖くて、口が開けなかった。
黙ったままお互いそのまま向かい合い、しばらくの時が過ぎる。佐山は視線を落とし、薄暗がりの中で秋口の靴ばかりを見ていた。茶色い革靴。輪郭なんてぼやけてよくわからない。本当にそれが茶色いのかも。
「佐山さん、今日も夜」
不意に秋口の方から口を開き、佐山は小さく肩を揺らした。馬鹿みたいに驚いてしまって、それに秋口が気づかなければいいと必死に願った。
「空いてますか? また、飯でも」
佐山は少しの間を置いてから頷き、それではわからないかと、「うん」と小さな声で答えた。
「じゃ、終わったらメールか電話」
「わかった」
そう返事をしたのに、秋口はまだ佐山の手を離さなかった。
「……秋口、先出てくれ」
このまま秋口と一緒にこの部屋を出て、どういう顔をして自分のデスクに戻ればいいのか、佐山には見当もつかなかった。
秋口は頷くとやっと手を離し、あとは何も言わずにすぐ部屋を出て行った。
ドアが閉まる音をたしかめてから、佐山はその場にしゃがみ込み、項垂れて大きく溜息をついた。
別にそのことばかりを考えているわけじゃないのに、いつでも気持ちが上擦って、落ち着かない。パソコンのキーボードを叩いていても、書類を眺めていても、喉が詰まったように熱くなって、そわそわしてしまう。
(……駄目だ)
溜息をつき、眼鏡を取ってこめかみを揉んだ。
「あれ、佐山、お疲れ?」
後ろを通り掛かった開発課の同期が、そんな佐山の様子を見て声をかけてくる。佐山は振り返って曖昧に笑った。
「かもしれない。ちょっと一服してくる」
急ぎの仕事がないのを幸い、佐山はデスクの上の煙草とライターを取って尻ポケットにねじ込み、席を立った。妙に頭が痛んだので、眼鏡はかけず、そのままシャツの胸ポケットに引っかける。
まだ午前中、休憩所の辺りに人影はなかった。佐山は自販機でホットミルクを買うと、カップを取り出し、立ったまま壁に寄り掛かった。
冷房の効いたビルの中、暖かいミルクを飲み込むと、少し落ち着いた。
だが一口目を飲んだだけであとは動きが止まり、そのまま、カップの中のミルクを眺める。湯気のせいと裸眼のせいで、ミルクはずいぶんぼんやりした、白い靄のように見えた。
「……」
そしてほんの少し動きを止めてしまうと、佐山の脳裡に浮かぶのはゆうべの晩秋口に触れられた状況ばかりだ。
(本当、駄目だ)
目を閉じて、頭も壁に預けてしまう。自分の顔が赤くなってしまわない自信がなかった。まるで恋を覚えたての子供みたいだと奇妙に気恥ずかしい心地になる。
ゆうべ、佐山は何度も秋口とキスを交わした。それは本当にただ触れるだけの接吻けで、ゆっくり、ゆっくりと、秋口の唇が触れては離れ、触れては離れと、した。
その時佐山の頭は真っ白で、どうして秋口が自分にそんなことをするのか、まったく答えが出なかった。
そして未だに、正解なんて捜せない。
秋口はみっともなく泣いてしまった自分に何度も唇で触れてから、そのうちにそっと体を離した。
『飯、喰いましょう。残ってるから、勿体ない』
言われた言葉の意味がその時の佐山にはよくわからなくて、曖昧な視線で秋口を見上げた。その時も佐山は眼鏡がなく裸眼で、秋口の姿がひどくぼやけて見えていた。だから彼がどんな顔をしていたのかわからなかった。
涙の伝う目尻や頬が痒くなって、その辺りに佐山が指で触れようとするより先に、視界に黒いものが飛び込んできた。驚いて身を引くと、背中のドアに頭をぶつけてしまった。
微かに秋口の輪郭が揺れて、笑われたのだとわかった。
『眼鏡。ないと見えないんでしょう』
笑った声で秋口はそう言って、佐山に眼鏡をかけてくれた。その眼鏡を佐山は一度取り外して、目許を拭ってからもう一度自分で掛け直した。
その時には、秋口はもう元の席に戻っていた。
佐山は上手く思考の働かない頭を持て余しながら、自分も秋口の向かいに座り直した。
秋口は普通の顔で食事を再開して、佐山も無理に春巻きを口の中へと押し込み、ラッシーでそれを飲み下した。味なんてさっぱりわからなかった。
秋口の真意を問うことが佐山にはできなかった。あまりに秋口が平然とした態度だったせいだと思う。平然としているのに何も喋らない。いつもだったら場を和ませるような会話を如才なく続けるのに。
秋口は結局それから最後まで、黙然と料理を口に運び続けた。佐山も黙ったまま食事を終え、ふたりで店を出た。
『それじゃ、また会社で』
いつものとおり、分かれ道でそう言うと、秋口は駅の方へと行ってしまった。
佐山は取り残された気分でそれを見送り、それから自分の家へと戻った。
眠れなかった。自分の部屋の自分のベッドに横たわるのに、秋口にされたキスの感触を思い出してしまって、明け方近くまで眠気なんて一欠片も起きなかった。
起きてからもその調子だ。
好きだと、自分の気持ちが当の秋口にばれて、それで秋口は自分にキスした。
でも秋口は何も言わなかった。
それがどういうことなのか、佐山はずっと、その意味について考えようとしている。
決してキスをされたこと自体に浮かれてしまわないように。
(秋口が、俺と同じ気持ちだなんてことは、ありえないんだから)
何度も何度も、そうやって自分を戒める。調子に乗って、秋口に嫌な思いをさせることにでもなったら最低だ。
(もしかしたら、いい歳して男なんかに告白した俺のことを、可哀想だと思って慰めてくれたのかもしれないし)
自分が女だったら、多分秋口の行動に説明はつくのだ。ごく簡単に。佐山にもそれはわかる。秋口は女の子の扱いが上手くて、彼が好んでつき合うのは物分かりがよくプライドも高く、後腐れのない大人の女性が多い。噂でそう聞いて、その相手として名前の挙がった女性数人は社内で佐山も知っている人だったから、納得もできた。
キスをされたくらいで、想いを返してもらえたなんて勘違いしてつきまとったりしたら、秋口には迷惑だろう。そういうタイプの女を秋口が相手にした話は聞いたことがない。
(だから、いちいち浮かれたら駄目なんだって)
もし秋口が女だったら、さちに話は簡単だった。誠意を尽くして気持ちを告げて、できれば恋人としてつき合ってほしいと言うだけだ。結果はどうあっても、自分の取るべき行動はひとつしかないし、そもそも、迷う理由も悩む理由もひとつだってない。
今の自分の前に立ちふさがるあたりまえの障害について思って、冷房で冷えた手をカップで温めながら、佐山は小さく溜息をついた。
「あれ――」
ぼやけた視界で揺れる湯気を眺めていると、間近で声が聞こえて佐山はぎょっと顔を上げた。いつの間にか斜め前に人がいて、自分の正面に近づきながら顔を覗き込んでいる。
声でわかった。秋口だ。
「佐山さん、眼鏡は?」
「ここ」
内心はひどくうろたえていたのに、佐山は何ともない素振りで自分の胸ポケットを指さして見せた。割合こういう態度が得意なのだ。昨日、秋口の前でみっともなく涙なんてこぼしてしまったのが異常なくらいで。
「俺の顔見えてます?」
間近に秋口の顔があった。まったく眼鏡を外していた自分は運がいい。その男らしく整った顔になるべく焦点を合わせないよう、目を細めながら佐山は首を横に振った。
「ぼやけてる」
本当は近視だから、近づいてくれれば充分見えるのだが。
「すげぇ顔」
秋口が小さく笑った。それから、不意に片手を佐山の頬へ伸ばしてくる。
「ちょっと、動かないで。睫ついてる」
「……」
佐山は大人しく動きを止めた。本当は体が強張って、動かなかったのだが。
秋口の指先が軽く目許に触れて、反射的に佐山は目を閉じた。
「取れたか?」
なかなか離れない秋口の指に困って、佐山は目を閉じたまま訊ねた。
「……秋口?」
そんなに頑固な睫なのかと、再び問おうとした佐山は、秋口の指先にそっと目許を撫でられて微かに眉根を寄せた。些細な感触だったのに、体が震えそうになって驚いた。
佐山はその動揺を隠すように瞼を開き、つい秋口に視線を凝らしてしまった。
秋口が真顔で佐山のことを見下ろしていた。
(……あれ、何か)
よくない感じだ、と佐山は肌で感じた。
今秋口とふたりきりでいるのは、多分よくない。
「そろそろ仕事、戻るな」
温くなったミルクを一気に飲み干し、秋口から顔を逸らすようにして空になったカップを捨て、休憩所を出ようと歩き出しかけた佐山は、手首を掴まれ驚いた。
見上げると秋口はもう自分の前を歩いていて、手を引っ張ったまま休憩所から廊下に進んでいる。
「あ――秋口?」
何のつもりかと、訊ねたつもりで呟いた言葉は無視された。廊下を歩く別の社員が、無表情の秋口と、それに手を引かれた佐山を怪訝そうに見ていたが秋口はお構いなしだ。どんどん佐山を引っ張って、廊下を奥の方へと進んでいる。
大股で歩く秋口の後を仕方なく小走りについていった佐山は、そのまま資材倉庫まで辿り着いた。資材倉庫とは名ばかりで、使い道はないが処分し辛い古びた備品や資料が押し込められた、狭いがらくた部屋だ。秋口はその部屋の中に佐山の手を引いて入ると、IDカードなんかなくても入れる壊れかけたドアを閉じた。
明かりはつけなかったが、ブラインドの掛かった窓から外の光が細く何条も漏れている。
佐山は何が起きたのかよくわからなくて、とにかく落ち着こうと、眼鏡に手を伸ばした。
それを、秋口のもう一本の手に止められた。両手を押さえるように掴まれ、佐山は顔が上げられなくなってしまった。自分の心音が奇妙に近い。まるで耳許に心臓があるみたいだ。
多分、きっと、期待してたと思う。
そして佐山の期待どおりに、秋口はそのまま身を屈め、そっと近づいてきた。佐山はやっぱり顔が上げられず、俯いたまま困り果てる。
どうして、と理由を問えば、秋口が逃げてしまう気がして何も言えなかった。秋口は俯いた佐山の顔を下から掬うように、ゆっくり唇を合わせてきた。佐山は少し迷ったあと目を閉じる。昨日みたいに、秋口に何度も接吻けられる間に少しずつ顎が上がった。気づいたら秋口にされっぱなしになっているわけではなく、自分からも唇を寄せて触れ合っているような格好になっていた。
(止まらない)
どこの世界に、好きな相手からキスされて、自分からその状況を手放せるような人間がいるのか。
佐山は面倒になって、もう理由なんて考えず秋口とキスを交わした。わけを聞くなら喋るために離れなくてはいけない。そんなの勿体ない。
秋口の舌が唇に触れると、佐山はほぼ無意識にそれを開いた。自分からも少し舌を差し出し、接吻けはすぐに深くなった。両手を戒めるように掴まれているのがわずかにもどかしい。でもどうせ両手が自由だって、自分から秋口の背を抱いたりすることはできなかっただろう。
秋口はどうしてか、佐山が逃げ出すことでも警戒するように、きつく手首を握っている。ちょっと痛かったが、佐山はそれに文句を言う気も起きなかった。
「……ん……」
息苦しいのと、気持ちいいので、微かに吐息に似た声を洩らしてしまう。その自分の声が部屋の中に響いたから、佐山は変に緊張した。つい夢中で舌を絡め合ったりしてしまったが、そういえばここは会社なのだと、いまさら思い出した。
それで無意識に佐山が少し身を引くと、濡れた音を立てて互いの舌と唇が離れた。その音がやたら淫らっぽくて佐山は頭がくらくらする。場所とか、相手のこととか、考えるだけで貧血でも起こしそうな気分になった。
血が下がっているのではなく、頭に昇っている方の眩暈なのかもしれない。
佐山は息が乱れているのを悟られたくなくて、ゆっくり深呼吸した。まだ間近にいる秋口からも吐息が漏れ、体が震えそうになるのをようやく堪える。
秋口はやっぱり何も言わなかった。佐山は声を出せばそれが上擦っていそうなのが怖くて、口が開けなかった。
黙ったままお互いそのまま向かい合い、しばらくの時が過ぎる。佐山は視線を落とし、薄暗がりの中で秋口の靴ばかりを見ていた。茶色い革靴。輪郭なんてぼやけてよくわからない。本当にそれが茶色いのかも。
「佐山さん、今日も夜」
不意に秋口の方から口を開き、佐山は小さく肩を揺らした。馬鹿みたいに驚いてしまって、それに秋口が気づかなければいいと必死に願った。
「空いてますか? また、飯でも」
佐山は少しの間を置いてから頷き、それではわからないかと、「うん」と小さな声で答えた。
「じゃ、終わったらメールか電話」
「わかった」
そう返事をしたのに、秋口はまだ佐山の手を離さなかった。
「……秋口、先出てくれ」
このまま秋口と一緒にこの部屋を出て、どういう顔をして自分のデスクに戻ればいいのか、佐山には見当もつかなかった。
秋口は頷くとやっと手を離し、あとは何も言わずにすぐ部屋を出て行った。
ドアが閉まる音をたしかめてから、佐山はその場にしゃがみ込み、項垂れて大きく溜息をついた。
◇◇◇
その日の夜は、たまには場所を変えるかと佐山の方から言って、いつもとは違う店に秋口と一緒に向かった。昨日の晩のことを思い出して平静ではいられない気がしたからだが、もちろんそんな理由は言わずにおいた。
いつもの店ほどではないが、そこそこ美味い料理をふたりで食べ、そのまま互いの家に帰った。テーブルを挟んでふたりともまったくいつもどおり、仕事の話とか、他愛ない世間話だけして別れた。
佐山は肩透かしを喰らったような、安堵したような、複雑な気分になって、この日もまたよく眠れなかった。
次の日の午後、佐山は外回りから帰ってきた秋口と休憩所で顔を合わせ、どちらからともなく人目を盗むようにまた倉庫に向かって、またキスを交わした。
本当はどうするべきなのかわからなかったが、わからないまま曖昧な気分で触れ合っているのも無駄なことだと思ったので、秋口とキスする間、佐山はその気持ちよさと嬉しさだけをひっそり味わった。それを表に出さないよう充分注意しながら、好きな相手と触れ合える幸福を受け取った。
ただし秋口と離れてしまえば、なるたけそんな気持ちも、秋口とそうしたこと自体も忘れるよう努めた。どうせ考えていたら仕事にならない。
その後は週末まで佐山も秋口も仕事が立て込んでいて、会社で言葉を交わすことも、一緒に食事に行くこともなかった。
一度そうなってしまえば貪欲なもので、秋口に会えない時間が辛くなる。それを忘れるために仕事に打ち込んでいたら上司に褒められたので、怪我の功名だと思っておいた。
「何か佐山、やつれてないか」
週明け、昼休みに食堂で御幸と行き会い、向かい合ってランチを取る最中、佐山は相手に顔を顰められてしまった。
「また面倒臭くて家で飯喰ってないんだろ。自炊しろなんて無駄なこと言わないから、せめてできあいの弁当でいいんだ、ちゃんと喰えよ。サプリだけじゃ栄養が足りるってことはないんだからな、カロリー取れカロリー」
佐山が食にあまり興味を持たないことを、つき合いの長い御幸はよく承知していた。まるで家族のような口調でそう言う。
「ここんとこ色艶よかったのに。秋口と飯、行ってたんだろ」
「まあ、たまに……」
佐山は曖昧に言葉を濁した。秋口の名前を聞いただけで、つい狼狽してしまいそうになる。食事に行っているのだろうと言われているだけで、それ以上の何をしていると問われたわけでもないのに。
動揺を誤魔化そうとした友人の態度に、目聡い御幸はすぐに気づいたようだった。
「何だ、おまえ。また秋口と何かあったのか」
「ないない」
佐山は御幸に片手を振って見せて、無理矢理料理を口に詰め込んだ。
「ん、噂をすれば」
疑わしそうに佐山を見ていた御幸が、その後ろの方に視線を向けて呟いた。佐山もさり気ないふうを装ってこっそり振り返ってみる。
食券売り場からチケットを取り出した秋口が、カウンタに向けて歩き出すところだった。相変わらず周りに数人女子社員を侍らせている。その様子を見るのがいまいち心臓によくない気がして、佐山はすぐに前を向こうと思ったが、その瞬間急に秋口と目が合った。佐山たちの座っている席からカウンタの辺りは大分距離があるのに、視線がかち合ってしまった。
佐山は慌てて顔を元に戻し、箸を持ち直す。一連の佐山の様子を見ていただろう御幸は、特に何を言うこともなく食事を終えた。
そのまま御幸と非常用の外階段に移動して煙草を吸った。食堂は八月から禁煙になってしまったし、休憩所はどこも混んでいる。今日は佐山も御幸も仕事はのんびりペースでよかったから、ついそのまま話し込んでしまった。
「佐山は夏休み、九月入ってからって言ってたよな」
「そう、有給も使って、結構たっぷり」
「埼玉戻るのか?」
「そうだな、そろそろ顔出さないと、心配させてるみたいだし」
「まあ心配するだろうな、おまえがゴミに埋もれて死んでやしないかと……」
御幸の言葉に佐山は苦笑した。もっともな言い分だ。
「俺もその辺りに休みだからさ」
御幸は吸い殻を一度踊り場に捨ててから、靴底で踏んで火を消し、それを屈んで拾い上げた。立ち上がってから佐山をまた見遣る。
「もし車いるような用事あったら、遠慮しないで声掛けろよ」
「……そうだな、ありがとう」
御幸の気遣った言い回しに感謝しつつ、佐山は頷いた。
「ついでにドライブでもしようぜ、最近全然走りに行ってないからストレス溜まる」
御幸は車道楽のきらいがあって、暇があれば愛車で遠出するのが趣味だ。運転は安全だったから、車に酔いやすい佐山も御幸となら一緒に出かけるのが苦痛ではない。
「いいな、じゃあ休みになったら」
「バケットのサンドイッチと鶏からもバスケットに詰めて」
料理も御幸の趣味のひとつだった。御幸が佐山の家を掃除しに来る時、手作りの夕食もついてくるのだからまったくありがたい。
「マメだなあ。楽しみにしてるよ」
「じゃ、俺先戻るわ」
御幸が非常口から建物の中に戻っていった。佐山も吸いかけの煙草を吸いきると、生温い風の吹く外から空調の効いたビルに入った。
涼しさに安堵の吐息を洩らしながら腕時計を見ると、昼休みの時間がもう終わっている。少しゆっくりしすぎてしまったことを反省しつつ、開発課に向かって廊下を進みかけた佐山は、その先にまだ御幸の姿があることに気づいた。あまり時間の差がなかったから追いついたようだ。
御幸は廊下の曲がり角で誰かと話している。相手は廊下の角の影になって見えなかったが、何の気なくそちらへ向かって歩いていた佐山は、御幸と入れ違いのようにこちらへやってくるのが秋口だと気づいて、急激な嬉しさが湧き上がってくるのを堪えなくてはならなかった。
(笑うなよ、顔)
感情を剥き出しにすることを、佐山はここのところ意識して我慢している。
佐山の方を見て、秋口が軽く頷くように挨拶する。佐山も少しだけ微笑んでそれに応えた。秋口は今週も忙しいらしいから、このまま通り過ぎてしまおうと思った佐山は、秋口が自分の前に立ちはだかったので自然と足を留めた。
「御幸さんと、煙草?」
訊ねられて、頷く。
「そう、ちょっと長居しすぎた。そっちの外にいたんだけど、暑くて――」
「汗かいてる」
額にうっすら浮かぶ汗を秋口に見られ、佐山は何となく恥じ入って手の甲でその辺りを押さえた。
「食堂が駄目になったからな。日増しに喫煙者の肩身が狭くなってくるよ」
「こっちでも、吸えますよ」
秋口が視線で自分の後ろを指し、つられてそちらを見遣った佐山は、すぐに相手の言わんとすることを察した。秋口の視線の向こうにあるのは、いつもの資材倉庫。踵を返して歩き出した秋口は、佐山がついてこないなんて思ってもいないような足取りだった。佐山は秋口の踵を見ながら歩き出す。なぜか餌をちらつかされて言うことを聞く、躾のいい犬に自分がなった気がした。
(俺と、秋口が、どういう関係なんだろうな……とか)
期待と、逆のベクトルの感情が、同じくらい大きく膨らんでいる。
(訊かない方がいいんだろうなあ)
その辺りをはっきりさせる気なら、秋口はとっくにそれについて言葉にしているだろう。
多分もう嫌われてはいないはずだ。以前みたいなとげとげしさは、もう秋口には塵ほども見あたらない。その代わり愛想は減った。嫌味を言ったり厳しく当たることはない代わりに、言葉数が少なくなって、笑うこともあまりなくなった気がする。自分も一緒だ。嬉しい気分と緊張と疑問が渦になって、時々自分勝手に疲れる。
だからこうして誘われる方が楽だった。触れてる間はそれだけに気持ちを傾けていいと自分で決めたから。
さり気なく周囲に人目のないことを確認してから、佐山は秋口に続いて資材倉庫の中に身を滑らせた。秋口が中からドアを閉め、続いて鍵の閉まる音が聞こえて佐山は少し驚いた。いつもはドアを閉めるだけで、佐山がそれに寄り掛かり、外から開かないよう一応警戒はしていたのだが。
驚いた顔の佐山と視線が合って、秋口が小さく首を傾げた。
「ドア、壊れてるんだよな」
聞こうと思ったことと、微妙にずれたことを佐山は口にした。
「細かいところでけちってますよね、この会社」
そうだな、と受け合いながら、佐山はポケットから煙草を取り出した。
「本当に吸うんだ」
一本口に咥えようとした動きを、少しおかしそうな秋口の声で佐山は止める。
「いや、こっちでも吸える、って……」
言い訳がましく佐山がもそもそと答えるうち、秋口の指先がそのこめかみ辺りに伸びた。佐山は咄嗟に身を引いて、その指から逃げてしまった。
秋口が微かに眉根を寄せる。
「汗かいてるから」
佐山の台詞はまた言い訳じみた響きになった。
「前と同じくらいでしょ」
秋口はさらに腕を伸ばして、手の甲で佐山のこめかみに触れた。
「前、って?」
じりじり後退さったら、すぐ背中に何かが当たって揺れた。資料なのかゴミなのかわからない紙束が収められたスチール棚だ。
「俺が、佐山さんち行った時くらい」
答えながら、秋口が佐山の方へ身を寄せ、唇ではなく手で触れた方と逆のこめかみに唇で触れた。
「一緒に寝た時、結構汗ばんでた」
「……覚えてない」
「酔っ払いでしたから」
その時のことを秋口が蒸し返したのは、先週の月曜――初めてキスをされた時以来だ。
とりあえず秋口と距離を取りたくて、佐山は横に逃れようとしたが、棚についた秋口の片手ひとつでそれを阻まれてしまった。
「煙草臭い」
秋口は唇を佐山のこめかみから頬の方へ移動させつつ、呟いた。
「さっきまで吸ってたんだ」
佐山は手に取ったままの煙草を持て余している。右手で箱を、その指に一本だけ取り出した煙草が所在なげに引っかかっている。
いっそするならさっさとしてくれと、佐山は少しやけくそ気味に顔を傾けた。秋口の唇を捜しながら目を閉じる。その動きを読んでいたように、秋口からも唇を合わせて来た。
(単に、おもしろがられてるだけなのかも)
一番考えたくない理由が頭に浮かんでしまい、佐山はそれを追い出して、秋口とのキスに集中しようとした。好意、同情、成り行き、興味、揶揄、それ以外。どれにしろ、自分が邪推したって、たとえ秋口の口から聞いたって、真実なんかそうそう簡単にわかるもんでもないだろう、と佐山は全部頭から追い出した。
秋口はすぐに佐山の唇に舌を割り入れてきた。煙草臭くて申し訳ないと思いつつ、佐山は秋口の動きに応える。大学の頃つき合っていた女の子は、佐山が煙草を吸うのを嫌った。その一時期気を遣って禁煙していたが、別れた後反動のように煙草の量が増えてしまった。
『あたしのこと好きだったら、煙草くらいやめられるでしょ』
つきあい始めてすぐそう言った彼女の顔はもうあまり思い出せないのに、その声や言葉のトーンだけやけに覚えている。あの頃はまだそれほど禁煙禁煙と世間では騒がれていなかった。飛行機でも普通に煙草が吸えた。
(って、何でこんなこと考えてるんだ)
余計なことを考えないようにしたら、関係ない思い出が蘇ってしまった。
秋口も煙草を吸っているはずだが、佐山ほど量が多いわけじゃないようだった。一緒に食事をしていると、秋口は酒を飲み、その間の分佐山が煙草を吸っている。それでも秋口の体からも微かに煙草の匂いがした。
そういえば煙草を吸う相手とキスしたのは初めてなんだ。佐山は今さらそんなことに思い至った。それ以前に男とキスしたのも初めてだったから、気にしていなかった。
そんなことを考えつつも、佐山は熱心に秋口とのキスの感触を味わった。深く接吻けをする場合、今までは男の自分からリードすることがほとんどだったから、積極的に口中を犯される感じは新鮮で、刺激的だった。
(んっ)
声には出さず、佐山はただ眉を顰めた。秋口に深く口蓋を探られ背中が震える。今日はもうずいぶん長い時間触れ合っている。秋口の指は少し長い佐山の髪を掻き上げるように耳許で動いていて、それがくすぐったい。その指がそのまま耳の裏に流れ、首筋を撫で下ろした時、佐山は隠しようもないくらい大きく肩を揺らしてしまった。スチール棚が壁にぶつかる音が聞こえて、少し気まずくなった。
――感じたのが、ばれてしまう。
もうそろそろいいだろう、と佐山は煙草を持った手で秋口の胸を押し遣ろうとした。だが相手の体はびくともしない。
「……きぐち」
名前を呼んで、失敗した。すっかり息が上がってしまっていた。
「もう、戻らないと」
何とか抑揚を抑えて言った佐山の声は、終わりの方を秋口の唇に吸い取られた。先刻より強く舌を吸われ、唇を食まれて、佐山は段々怖くなってきた。
(これ以上は)
まずいんじゃないだろうか、と思う。秋口の片手は佐山の腰骨の上に置かれ、少しずつ掌が動き出している。佐山はそれにいちいち震えてしまうのだ。秋口は明らかに意図的に掌を動かしている。
だがやっぱり、止めるのは勿体ないんじゃないか、などとも佐山は考えてしまう。かといって自分から積極的に応えるのもどうなのかと迷っているうち、秋口の唇が離れ、次には首に濡れた感触が当たった。
「っ、……」
首筋に軽く歯を立てられ、同時に、腰の辺りをさまよっていた掌が前に回ってきた。佐山は咄嗟に両手でもう一度秋口の胸を押した。
「動かないで」
びくともしない秋口に、何か言わなくてはと口を開いた佐山は、一言先に言われただけで身動き取れなくなった。下肢の間、ズボンの布越しに秋口の掌が触れて、佐山はきつく目を閉じた。これで秋口にも、自分が完全に快楽を覚えていることがわかってしまっただろう。『もう戻らないと』なんて理性的な声で言おうとしながら、佐山の中心は熱を持って昂ぶりかけている。
秋口はその昂ぶりをたしかめるようにしばらく掌を動かすと、それをやんわり上から握った。佐山は咄嗟に歯を喰い縛って快楽に耐えた。声を洩らさないよう必死に唇を閉じる。しかし秋口が休まずその辺りを揉みしだくから、いつの間にか閉じていたつもりの唇が開き、浅い呼吸を繰り返していた。
「あ、秋口……ちょっと、これ以上は」
「シッ」
佐山の弱音を一言で押さえ込み、秋口は開いている手で佐山のベルトに触れた。
(本当に、まずい……)
秋口は何なく佐山のベルトを外し、ズボンのボタンも外し、ジッパーも下ろしてしまった。
「もう、いいって、秋口」
囁くような、半泣きのような佐山の声を、秋口は頭っから無視した。
勿体ぶったほどゆっくりとした動きで、秋口の手が下着の中に忍び込んでくる。すぐに佐山の熱の在処を探り当て、今度は直接掌で握り込んだ。
「……ッ……」
身を強張らせて、それでも佐山は言われたとおり動かずにいた。秋口の言葉は呪文のように佐山をその場に縫いつけた。
少しの間秋口の掌は佐山の中心を優しく揉んで、次第にそれが固くなって来た頃、弄ぶように上下に揺らし出した。息と声を殺して、佐山は煙草の箱を握り潰してしまった。
顕著すぎる自分の反応が情けない。秋口は特別技巧をこらしているわけでもなく、ただ佐山の性器を擦っているだけだ。ときおり指先で先端を押された。それで佐山はもう腰砕けになっている。
秋口に中心を握られ、必死に我慢しようとした努力も虚しく、佐山はその掌に精液を吐き出してしまった。
「……」
呆然と、佐山は目を閉じたままスチール棚に寄り掛かった。瞼を下ろしていたが、秋口が自分の顔を覗き込んでいるのがわかった。
顔を見られて、荒い呼吸を聞かれて、堪えきれずに秋口の手の中で射精した。
佐山は何だかその場にしゃがみ込みたいほど衝撃を受けていたが、秋口が体を支えていたのでそうもいかなかった。秋口はポケットから取り出したハンカチで自分の手を拭い、佐山の性器を拭い、服を整えてくれた。
「ちょっと……濡れたかな、すみません」
ベルトまで填めた後に聞こえた秋口の呟きに、佐山は暴れて喚いてこの場から逃げ出したい気分を全力で押し殺し、代わりに小さく溜息を吐いた。
「……仕事、戻れよ。先行ってくれ」
秋口の手でイカされてしまった、という事態に頭が追いつかず、とにかくひとりになりたくて、佐山はそう言った。
「……」
秋口は何も言わず、ただ佐山をじっと見ている気配だけがした。
佐山がしばらく動かずにいると、そのうち秋口の気配が前から消えて、鍵が開く音が聞こえた。何も言わずに秋口が倉庫を出て行く。
佐山はまたすっかり汗ばんでしまった額を手の甲で拭い、大きく息を吐き出した。
いつもの店ほどではないが、そこそこ美味い料理をふたりで食べ、そのまま互いの家に帰った。テーブルを挟んでふたりともまったくいつもどおり、仕事の話とか、他愛ない世間話だけして別れた。
佐山は肩透かしを喰らったような、安堵したような、複雑な気分になって、この日もまたよく眠れなかった。
次の日の午後、佐山は外回りから帰ってきた秋口と休憩所で顔を合わせ、どちらからともなく人目を盗むようにまた倉庫に向かって、またキスを交わした。
本当はどうするべきなのかわからなかったが、わからないまま曖昧な気分で触れ合っているのも無駄なことだと思ったので、秋口とキスする間、佐山はその気持ちよさと嬉しさだけをひっそり味わった。それを表に出さないよう充分注意しながら、好きな相手と触れ合える幸福を受け取った。
ただし秋口と離れてしまえば、なるたけそんな気持ちも、秋口とそうしたこと自体も忘れるよう努めた。どうせ考えていたら仕事にならない。
その後は週末まで佐山も秋口も仕事が立て込んでいて、会社で言葉を交わすことも、一緒に食事に行くこともなかった。
一度そうなってしまえば貪欲なもので、秋口に会えない時間が辛くなる。それを忘れるために仕事に打ち込んでいたら上司に褒められたので、怪我の功名だと思っておいた。
「何か佐山、やつれてないか」
週明け、昼休みに食堂で御幸と行き会い、向かい合ってランチを取る最中、佐山は相手に顔を顰められてしまった。
「また面倒臭くて家で飯喰ってないんだろ。自炊しろなんて無駄なこと言わないから、せめてできあいの弁当でいいんだ、ちゃんと喰えよ。サプリだけじゃ栄養が足りるってことはないんだからな、カロリー取れカロリー」
佐山が食にあまり興味を持たないことを、つき合いの長い御幸はよく承知していた。まるで家族のような口調でそう言う。
「ここんとこ色艶よかったのに。秋口と飯、行ってたんだろ」
「まあ、たまに……」
佐山は曖昧に言葉を濁した。秋口の名前を聞いただけで、つい狼狽してしまいそうになる。食事に行っているのだろうと言われているだけで、それ以上の何をしていると問われたわけでもないのに。
動揺を誤魔化そうとした友人の態度に、目聡い御幸はすぐに気づいたようだった。
「何だ、おまえ。また秋口と何かあったのか」
「ないない」
佐山は御幸に片手を振って見せて、無理矢理料理を口に詰め込んだ。
「ん、噂をすれば」
疑わしそうに佐山を見ていた御幸が、その後ろの方に視線を向けて呟いた。佐山もさり気ないふうを装ってこっそり振り返ってみる。
食券売り場からチケットを取り出した秋口が、カウンタに向けて歩き出すところだった。相変わらず周りに数人女子社員を侍らせている。その様子を見るのがいまいち心臓によくない気がして、佐山はすぐに前を向こうと思ったが、その瞬間急に秋口と目が合った。佐山たちの座っている席からカウンタの辺りは大分距離があるのに、視線がかち合ってしまった。
佐山は慌てて顔を元に戻し、箸を持ち直す。一連の佐山の様子を見ていただろう御幸は、特に何を言うこともなく食事を終えた。
そのまま御幸と非常用の外階段に移動して煙草を吸った。食堂は八月から禁煙になってしまったし、休憩所はどこも混んでいる。今日は佐山も御幸も仕事はのんびりペースでよかったから、ついそのまま話し込んでしまった。
「佐山は夏休み、九月入ってからって言ってたよな」
「そう、有給も使って、結構たっぷり」
「埼玉戻るのか?」
「そうだな、そろそろ顔出さないと、心配させてるみたいだし」
「まあ心配するだろうな、おまえがゴミに埋もれて死んでやしないかと……」
御幸の言葉に佐山は苦笑した。もっともな言い分だ。
「俺もその辺りに休みだからさ」
御幸は吸い殻を一度踊り場に捨ててから、靴底で踏んで火を消し、それを屈んで拾い上げた。立ち上がってから佐山をまた見遣る。
「もし車いるような用事あったら、遠慮しないで声掛けろよ」
「……そうだな、ありがとう」
御幸の気遣った言い回しに感謝しつつ、佐山は頷いた。
「ついでにドライブでもしようぜ、最近全然走りに行ってないからストレス溜まる」
御幸は車道楽のきらいがあって、暇があれば愛車で遠出するのが趣味だ。運転は安全だったから、車に酔いやすい佐山も御幸となら一緒に出かけるのが苦痛ではない。
「いいな、じゃあ休みになったら」
「バケットのサンドイッチと鶏からもバスケットに詰めて」
料理も御幸の趣味のひとつだった。御幸が佐山の家を掃除しに来る時、手作りの夕食もついてくるのだからまったくありがたい。
「マメだなあ。楽しみにしてるよ」
「じゃ、俺先戻るわ」
御幸が非常口から建物の中に戻っていった。佐山も吸いかけの煙草を吸いきると、生温い風の吹く外から空調の効いたビルに入った。
涼しさに安堵の吐息を洩らしながら腕時計を見ると、昼休みの時間がもう終わっている。少しゆっくりしすぎてしまったことを反省しつつ、開発課に向かって廊下を進みかけた佐山は、その先にまだ御幸の姿があることに気づいた。あまり時間の差がなかったから追いついたようだ。
御幸は廊下の曲がり角で誰かと話している。相手は廊下の角の影になって見えなかったが、何の気なくそちらへ向かって歩いていた佐山は、御幸と入れ違いのようにこちらへやってくるのが秋口だと気づいて、急激な嬉しさが湧き上がってくるのを堪えなくてはならなかった。
(笑うなよ、顔)
感情を剥き出しにすることを、佐山はここのところ意識して我慢している。
佐山の方を見て、秋口が軽く頷くように挨拶する。佐山も少しだけ微笑んでそれに応えた。秋口は今週も忙しいらしいから、このまま通り過ぎてしまおうと思った佐山は、秋口が自分の前に立ちはだかったので自然と足を留めた。
「御幸さんと、煙草?」
訊ねられて、頷く。
「そう、ちょっと長居しすぎた。そっちの外にいたんだけど、暑くて――」
「汗かいてる」
額にうっすら浮かぶ汗を秋口に見られ、佐山は何となく恥じ入って手の甲でその辺りを押さえた。
「食堂が駄目になったからな。日増しに喫煙者の肩身が狭くなってくるよ」
「こっちでも、吸えますよ」
秋口が視線で自分の後ろを指し、つられてそちらを見遣った佐山は、すぐに相手の言わんとすることを察した。秋口の視線の向こうにあるのは、いつもの資材倉庫。踵を返して歩き出した秋口は、佐山がついてこないなんて思ってもいないような足取りだった。佐山は秋口の踵を見ながら歩き出す。なぜか餌をちらつかされて言うことを聞く、躾のいい犬に自分がなった気がした。
(俺と、秋口が、どういう関係なんだろうな……とか)
期待と、逆のベクトルの感情が、同じくらい大きく膨らんでいる。
(訊かない方がいいんだろうなあ)
その辺りをはっきりさせる気なら、秋口はとっくにそれについて言葉にしているだろう。
多分もう嫌われてはいないはずだ。以前みたいなとげとげしさは、もう秋口には塵ほども見あたらない。その代わり愛想は減った。嫌味を言ったり厳しく当たることはない代わりに、言葉数が少なくなって、笑うこともあまりなくなった気がする。自分も一緒だ。嬉しい気分と緊張と疑問が渦になって、時々自分勝手に疲れる。
だからこうして誘われる方が楽だった。触れてる間はそれだけに気持ちを傾けていいと自分で決めたから。
さり気なく周囲に人目のないことを確認してから、佐山は秋口に続いて資材倉庫の中に身を滑らせた。秋口が中からドアを閉め、続いて鍵の閉まる音が聞こえて佐山は少し驚いた。いつもはドアを閉めるだけで、佐山がそれに寄り掛かり、外から開かないよう一応警戒はしていたのだが。
驚いた顔の佐山と視線が合って、秋口が小さく首を傾げた。
「ドア、壊れてるんだよな」
聞こうと思ったことと、微妙にずれたことを佐山は口にした。
「細かいところでけちってますよね、この会社」
そうだな、と受け合いながら、佐山はポケットから煙草を取り出した。
「本当に吸うんだ」
一本口に咥えようとした動きを、少しおかしそうな秋口の声で佐山は止める。
「いや、こっちでも吸える、って……」
言い訳がましく佐山がもそもそと答えるうち、秋口の指先がそのこめかみ辺りに伸びた。佐山は咄嗟に身を引いて、その指から逃げてしまった。
秋口が微かに眉根を寄せる。
「汗かいてるから」
佐山の台詞はまた言い訳じみた響きになった。
「前と同じくらいでしょ」
秋口はさらに腕を伸ばして、手の甲で佐山のこめかみに触れた。
「前、って?」
じりじり後退さったら、すぐ背中に何かが当たって揺れた。資料なのかゴミなのかわからない紙束が収められたスチール棚だ。
「俺が、佐山さんち行った時くらい」
答えながら、秋口が佐山の方へ身を寄せ、唇ではなく手で触れた方と逆のこめかみに唇で触れた。
「一緒に寝た時、結構汗ばんでた」
「……覚えてない」
「酔っ払いでしたから」
その時のことを秋口が蒸し返したのは、先週の月曜――初めてキスをされた時以来だ。
とりあえず秋口と距離を取りたくて、佐山は横に逃れようとしたが、棚についた秋口の片手ひとつでそれを阻まれてしまった。
「煙草臭い」
秋口は唇を佐山のこめかみから頬の方へ移動させつつ、呟いた。
「さっきまで吸ってたんだ」
佐山は手に取ったままの煙草を持て余している。右手で箱を、その指に一本だけ取り出した煙草が所在なげに引っかかっている。
いっそするならさっさとしてくれと、佐山は少しやけくそ気味に顔を傾けた。秋口の唇を捜しながら目を閉じる。その動きを読んでいたように、秋口からも唇を合わせて来た。
(単に、おもしろがられてるだけなのかも)
一番考えたくない理由が頭に浮かんでしまい、佐山はそれを追い出して、秋口とのキスに集中しようとした。好意、同情、成り行き、興味、揶揄、それ以外。どれにしろ、自分が邪推したって、たとえ秋口の口から聞いたって、真実なんかそうそう簡単にわかるもんでもないだろう、と佐山は全部頭から追い出した。
秋口はすぐに佐山の唇に舌を割り入れてきた。煙草臭くて申し訳ないと思いつつ、佐山は秋口の動きに応える。大学の頃つき合っていた女の子は、佐山が煙草を吸うのを嫌った。その一時期気を遣って禁煙していたが、別れた後反動のように煙草の量が増えてしまった。
『あたしのこと好きだったら、煙草くらいやめられるでしょ』
つきあい始めてすぐそう言った彼女の顔はもうあまり思い出せないのに、その声や言葉のトーンだけやけに覚えている。あの頃はまだそれほど禁煙禁煙と世間では騒がれていなかった。飛行機でも普通に煙草が吸えた。
(って、何でこんなこと考えてるんだ)
余計なことを考えないようにしたら、関係ない思い出が蘇ってしまった。
秋口も煙草を吸っているはずだが、佐山ほど量が多いわけじゃないようだった。一緒に食事をしていると、秋口は酒を飲み、その間の分佐山が煙草を吸っている。それでも秋口の体からも微かに煙草の匂いがした。
そういえば煙草を吸う相手とキスしたのは初めてなんだ。佐山は今さらそんなことに思い至った。それ以前に男とキスしたのも初めてだったから、気にしていなかった。
そんなことを考えつつも、佐山は熱心に秋口とのキスの感触を味わった。深く接吻けをする場合、今までは男の自分からリードすることがほとんどだったから、積極的に口中を犯される感じは新鮮で、刺激的だった。
(んっ)
声には出さず、佐山はただ眉を顰めた。秋口に深く口蓋を探られ背中が震える。今日はもうずいぶん長い時間触れ合っている。秋口の指は少し長い佐山の髪を掻き上げるように耳許で動いていて、それがくすぐったい。その指がそのまま耳の裏に流れ、首筋を撫で下ろした時、佐山は隠しようもないくらい大きく肩を揺らしてしまった。スチール棚が壁にぶつかる音が聞こえて、少し気まずくなった。
――感じたのが、ばれてしまう。
もうそろそろいいだろう、と佐山は煙草を持った手で秋口の胸を押し遣ろうとした。だが相手の体はびくともしない。
「……きぐち」
名前を呼んで、失敗した。すっかり息が上がってしまっていた。
「もう、戻らないと」
何とか抑揚を抑えて言った佐山の声は、終わりの方を秋口の唇に吸い取られた。先刻より強く舌を吸われ、唇を食まれて、佐山は段々怖くなってきた。
(これ以上は)
まずいんじゃないだろうか、と思う。秋口の片手は佐山の腰骨の上に置かれ、少しずつ掌が動き出している。佐山はそれにいちいち震えてしまうのだ。秋口は明らかに意図的に掌を動かしている。
だがやっぱり、止めるのは勿体ないんじゃないか、などとも佐山は考えてしまう。かといって自分から積極的に応えるのもどうなのかと迷っているうち、秋口の唇が離れ、次には首に濡れた感触が当たった。
「っ、……」
首筋に軽く歯を立てられ、同時に、腰の辺りをさまよっていた掌が前に回ってきた。佐山は咄嗟に両手でもう一度秋口の胸を押した。
「動かないで」
びくともしない秋口に、何か言わなくてはと口を開いた佐山は、一言先に言われただけで身動き取れなくなった。下肢の間、ズボンの布越しに秋口の掌が触れて、佐山はきつく目を閉じた。これで秋口にも、自分が完全に快楽を覚えていることがわかってしまっただろう。『もう戻らないと』なんて理性的な声で言おうとしながら、佐山の中心は熱を持って昂ぶりかけている。
秋口はその昂ぶりをたしかめるようにしばらく掌を動かすと、それをやんわり上から握った。佐山は咄嗟に歯を喰い縛って快楽に耐えた。声を洩らさないよう必死に唇を閉じる。しかし秋口が休まずその辺りを揉みしだくから、いつの間にか閉じていたつもりの唇が開き、浅い呼吸を繰り返していた。
「あ、秋口……ちょっと、これ以上は」
「シッ」
佐山の弱音を一言で押さえ込み、秋口は開いている手で佐山のベルトに触れた。
(本当に、まずい……)
秋口は何なく佐山のベルトを外し、ズボンのボタンも外し、ジッパーも下ろしてしまった。
「もう、いいって、秋口」
囁くような、半泣きのような佐山の声を、秋口は頭っから無視した。
勿体ぶったほどゆっくりとした動きで、秋口の手が下着の中に忍び込んでくる。すぐに佐山の熱の在処を探り当て、今度は直接掌で握り込んだ。
「……ッ……」
身を強張らせて、それでも佐山は言われたとおり動かずにいた。秋口の言葉は呪文のように佐山をその場に縫いつけた。
少しの間秋口の掌は佐山の中心を優しく揉んで、次第にそれが固くなって来た頃、弄ぶように上下に揺らし出した。息と声を殺して、佐山は煙草の箱を握り潰してしまった。
顕著すぎる自分の反応が情けない。秋口は特別技巧をこらしているわけでもなく、ただ佐山の性器を擦っているだけだ。ときおり指先で先端を押された。それで佐山はもう腰砕けになっている。
秋口に中心を握られ、必死に我慢しようとした努力も虚しく、佐山はその掌に精液を吐き出してしまった。
「……」
呆然と、佐山は目を閉じたままスチール棚に寄り掛かった。瞼を下ろしていたが、秋口が自分の顔を覗き込んでいるのがわかった。
顔を見られて、荒い呼吸を聞かれて、堪えきれずに秋口の手の中で射精した。
佐山は何だかその場にしゃがみ込みたいほど衝撃を受けていたが、秋口が体を支えていたのでそうもいかなかった。秋口はポケットから取り出したハンカチで自分の手を拭い、佐山の性器を拭い、服を整えてくれた。
「ちょっと……濡れたかな、すみません」
ベルトまで填めた後に聞こえた秋口の呟きに、佐山は暴れて喚いてこの場から逃げ出したい気分を全力で押し殺し、代わりに小さく溜息を吐いた。
「……仕事、戻れよ。先行ってくれ」
秋口の手でイカされてしまった、という事態に頭が追いつかず、とにかくひとりになりたくて、佐山はそう言った。
「……」
秋口は何も言わず、ただ佐山をじっと見ている気配だけがした。
佐山がしばらく動かずにいると、そのうち秋口の気配が前から消えて、鍵が開く音が聞こえた。何も言わずに秋口が倉庫を出て行く。
佐山はまたすっかり汗ばんでしまった額を手の甲で拭い、大きく息を吐き出した。
◇◇◇
秋口が自分の仕事が終わる時間だけを件名もなく携帯メールで送れば、佐山が「了解」とひとこと返して、それで夜の約束は決まる。仕事の予定で無理な時は「今日は残業」とかやっぱり件名もなく短い返事を送ったが、その返事が来たことはなくて、たかがそれだけのことに佐山は落ち込んだ。次はもう誘われないのではとか、そういう不安ばっかりがうっすらと胸を翳らせていて、そんな自分に気づいては余計に落ち込んでしまう。
(何とかなんないもんかな)
自分の気持ちにどうにか収拾がつけられれば、これほどいいことはないと思うのだ。あやふやな関係なんて本当は好きじゃない。恋愛の駆け引きをしたがる性格でもなかったし、好きな相手には優しくしたかったし、されたかった。
遊びで体の関係が持てるほど器用じゃないとわかっているから、こういうのはよくないと思いながらも、佐山は気づけばもう片手で足りないほど秋口とキスよりもっと深い行為に及んでいる。
会社で、というのがどうも後ろめたいし、仕事の時間が削られるのもいただけなかったので、佐山は秋口にそう言った。『部屋、掃除しとくから』と婉曲な言い回しだったが、秋口にはすぐに通じたようだった。
それからは夜待ち合わせても、ゆっくり気に入りの店で食事をすることはなく、できあいの総菜を買ってふたりで佐山の家に行って、最初に佐山がシャワーを浴びている間に秋口が食事をすませ、秋口がシャワーを浴びている間に佐山が食事をすませ、少し濡れた体にタオルを巻いて風呂から出てきた秋口が、まだ髪も乾いていない佐山をベッドに誘って――という、色気があるような、ないような、佐山を妙な気分にさせる手順がすぐにできあがった。
もう一方的に秋口が佐山に触れるだけではなく、佐山の方も秋口の体に触れるようになった。
秋口に触れられるたび、いつでもちょっとずつ罪悪感のようなものが胸を占めていて、『せめて秋口にも気持ちいい思いをして欲しい』という気持ちが佐山の愛撫を熱心にさせた。
罪悪感というより、引け目に近いだろうということは自分でもわかっていた。秋口は好んで自分みたいにガリガリに痩せた男を選ばなくても、気が向けば簡単に柔らかい女性の体を抱くことができるのだ。
だからといって自分から機会を手放してしまうほど無欲ではないから、佐山はせめて秋口に気持ちのいい思いをさせてやりたいと、それなりに積極的に秋口に触れる。
クーラーの風に裸を晒して、佐山はベッドに座る秋口の胸先へ舌を這わせた。秋口の呼吸が乱れるのを嬉しいと感じる。部屋の明かりはいつも佐山が消した。秋口の裸を正気で見られそうもないし、自分のことを見て欲しくもなかった。どうせ暗がりでよく見えないから眼鏡も外した。裸眼で暗闇に秋口の肌を捜してする行為は、いつも佐山を妙な気分にさせた。夢みたいな、やけに現実的な、そういう感覚が曖昧な境界線を気軽に踏み越えて交互にやってくる。
まさか自分が年下の男のペニスを進んで口に含む時がやってくるなんて、ちょっと前まで想像もできなかったのだ。
一番最初に佐山から秋口に触れた時、秋口は少し驚いたように動きを止めたが、すぐにそれを受け入れた。キスをしながら秋口の掌に性器を包まれ、自分だけそうされるのに耐えられない佐山はあまり迷うこともなく同じ動きを相手に返した。最初はお互い手で射精を導くだけだったのに、先に舌や口を使うようになったのは佐山の方だ。
「……ん……」
低く呻く秋口の声を聞きながら、佐山は両手で支えた秋口の中心を唇に含み、先端を舌で嬲った。自分はもう秋口にそうされて、絶頂を味わった後だ。気怠い体を持て余しながら、秋口がしたように、胸や首筋や脇腹を丹念に愛撫しながら片手を下肢の間に伸ばし、扱いて、口に含む。
自分の手の中で固くなり、口中で熱を増す秋口に、佐山は気持ちを昂揚させた。ただその熱のことだけを考えて、夢中で手や舌を動かした。
「……ッ、もう、出る」
吐息を乱しながら、切れ切れに秋口が言って、佐山の頭を自分から離させた。引き寄せておいたボックスティッシュを数枚抜いて、つい今まで佐山の口中に収められていた場所に当てている。小さく身震いしながら射精する秋口から、佐山は今日も何となく目を逸らした。見たくなかったわけじゃなくて、見たいことが相手にばれてしまうのが気まずかったのだ。
秋口はさらに数枚ティッシュを抜き出して、佐山の方に差し出した。視界を掠ったぼんやり白いものを佐山は受け取り、それで濡れた口許を拭う。
仕事が終わって一緒に会社を出て、家に入るまで、入ってからも、必要最低限の言葉しか交わさず、この状態だ。
最近はずっとこうだよな、と佐山は舌先に残る苦い味を指先で擦りながら考えた。
何でこんなことになったんだっけ、とも。
(何て言うんだっけ、こういうの――下世話な言い方で)
思い出そうと努力しながら、佐山はベッドのサイドテーブルの上に置かれた煙草を手に取った。ほぼ無意識の動きで、咥えた煙草に火をつける。ライターの火が一瞬、佐山の部屋の中を浮かび上がらせた。掃除をしておくから、と秋口に告げつつ、結局あちこち散らばった荷物をまとめて終わった。
どうせベッドしかまともに使わないんだからいいか、とぼんやり思いながら、佐山はさっき浮かべた疑問の答えを思い出した。
(『相互オナニー』だ)
まったく下世話な表現だが、言い得て妙だと納得する。どこでこんな言葉を覚えたんだっけ、とついでに考えたが、これはどうしても思い出せなかった。きっと学生時代に悪友が見せてくれた類の雑誌だろう。
前回ことが終わった後に思いついた言葉は『セフレ』だが、別にセックスしているわけでもない気がするので、しっくりこなかったのだ。これですっきりした、と煙草を吸いながら、それにしたって自分はどうしてこんなバカみたいな下らないことを真剣に考えているのかと、佐山はおかしくなった。
秋口は何も喋らないし、佐山も口を噤んでいるから、思考ばかりが進んで嫌になる。
「一本、もらえますか」
どうやらベッドの上にあぐらをかいているらしい秋口が、ふとそう声を出した。
「どうぞ」
ベッドとくっついた壁に寄り掛かりながら、佐山は煙草とライターを一緒にして秋口の方に投げ 、灰皿をサイドテーブルからベッドの上に移動させた。
煙草を吸っていた秋口がまた不意に小さくくしゃみを洩らして、その様子が妙に可愛らしかったので佐山はひっそりと笑いながら、床から拾い上げたリモコンで冷房を少し弱めた。
「毎日暑いな」
リモコンをベッドに投げ出してから壁に寄り掛かり直し、佐山はそう言った。
「雨も全然降りませんよね」
佐山のつまらない言葉に秋口がつまらない言葉を返して、会話はそこでもう途切れてしまった。
煙草を一本吸いきると、秋口はベッドから起き出して風呂場に向かった。秋口が身支度を調えている間に、佐山も洗いっぱなしで畳まれもせず積み重なった洗濯物から適当にシャツやパンツを取り出して身につけた。
部屋に戻ってきた秋口が、自分の鞄を拾う。そのまま玄関に進む秋口の後について、佐山もドアの方に向かった。
「じゃあ、おやすみなさい」
靴を履いた秋口が、佐山の方を振り返りもせず、でも冷たくもない口調でそう告げる。
「おやすみ、気をつけて」
振り返った秋口が、一瞬だけ佐山に視線を向けて、すぐに外に出て行った。閉じたドアの鍵を閉め、佐山はそのまま生温い鉄のドアに額を押しつけた。
(――で)
秋口が帰った後の虚しさを、必死にやり過ごそうとする。悲しくも辛くもないのに、秋口がいなくなった後は何だか急激に疲れた。
(何でこうなったんだっけ?)
別に望んだことなんてひとつもない。望まないようにしていた。声が聞きたいとか自分を見て欲しいとか、触れて欲しいなんて思ったこともなかった。
それでも他愛ない会話を交わしながら美味い食事をとって、笑って、それが嬉しかったから一緒にいられる時間を自分から手放す気なんて毛頭起きなかったけれど。
キスされて、触れられて、勘違いしないように自分を戒めていた頃だって、まだ倖せだったと思えるくらいだ。
秋口が部屋に訪れるようになってから、世間話すら数えるほどしかしていない。秋口は何も言わないし佐山は何も聞かない。なのにお互い相手に快楽を与えるために熱心になっていたりする。
自分で決めた約束どおり、秋口と触れ合っている間は、その感触だけ夢中になって佐山は追った。
どうせ今、それを自分から手放せる余裕も度胸もない。こんな状況が本当に虚しいと思いながらも。
(何考えてるのだけでもいいから、聞きたい)
でも聞けない。聞いたら全部終わるだろうという予感はずっと持ち続けている。
(こんな形でも一緒にいたいわけだ)
触れるごとに執着心が募る気がして、佐山には少し怖かった。
こんなことが長く続くはずがないと、どうせいつか終わりが来ることは覚悟しているのに、会う回数が増えるたびにその『いつか』が近づくことが怖くなった。
(何とかなんないもんかな)
自分の気持ちにどうにか収拾がつけられれば、これほどいいことはないと思うのだ。あやふやな関係なんて本当は好きじゃない。恋愛の駆け引きをしたがる性格でもなかったし、好きな相手には優しくしたかったし、されたかった。
遊びで体の関係が持てるほど器用じゃないとわかっているから、こういうのはよくないと思いながらも、佐山は気づけばもう片手で足りないほど秋口とキスよりもっと深い行為に及んでいる。
会社で、というのがどうも後ろめたいし、仕事の時間が削られるのもいただけなかったので、佐山は秋口にそう言った。『部屋、掃除しとくから』と婉曲な言い回しだったが、秋口にはすぐに通じたようだった。
それからは夜待ち合わせても、ゆっくり気に入りの店で食事をすることはなく、できあいの総菜を買ってふたりで佐山の家に行って、最初に佐山がシャワーを浴びている間に秋口が食事をすませ、秋口がシャワーを浴びている間に佐山が食事をすませ、少し濡れた体にタオルを巻いて風呂から出てきた秋口が、まだ髪も乾いていない佐山をベッドに誘って――という、色気があるような、ないような、佐山を妙な気分にさせる手順がすぐにできあがった。
もう一方的に秋口が佐山に触れるだけではなく、佐山の方も秋口の体に触れるようになった。
秋口に触れられるたび、いつでもちょっとずつ罪悪感のようなものが胸を占めていて、『せめて秋口にも気持ちいい思いをして欲しい』という気持ちが佐山の愛撫を熱心にさせた。
罪悪感というより、引け目に近いだろうということは自分でもわかっていた。秋口は好んで自分みたいにガリガリに痩せた男を選ばなくても、気が向けば簡単に柔らかい女性の体を抱くことができるのだ。
だからといって自分から機会を手放してしまうほど無欲ではないから、佐山はせめて秋口に気持ちのいい思いをさせてやりたいと、それなりに積極的に秋口に触れる。
クーラーの風に裸を晒して、佐山はベッドに座る秋口の胸先へ舌を這わせた。秋口の呼吸が乱れるのを嬉しいと感じる。部屋の明かりはいつも佐山が消した。秋口の裸を正気で見られそうもないし、自分のことを見て欲しくもなかった。どうせ暗がりでよく見えないから眼鏡も外した。裸眼で暗闇に秋口の肌を捜してする行為は、いつも佐山を妙な気分にさせた。夢みたいな、やけに現実的な、そういう感覚が曖昧な境界線を気軽に踏み越えて交互にやってくる。
まさか自分が年下の男のペニスを進んで口に含む時がやってくるなんて、ちょっと前まで想像もできなかったのだ。
一番最初に佐山から秋口に触れた時、秋口は少し驚いたように動きを止めたが、すぐにそれを受け入れた。キスをしながら秋口の掌に性器を包まれ、自分だけそうされるのに耐えられない佐山はあまり迷うこともなく同じ動きを相手に返した。最初はお互い手で射精を導くだけだったのに、先に舌や口を使うようになったのは佐山の方だ。
「……ん……」
低く呻く秋口の声を聞きながら、佐山は両手で支えた秋口の中心を唇に含み、先端を舌で嬲った。自分はもう秋口にそうされて、絶頂を味わった後だ。気怠い体を持て余しながら、秋口がしたように、胸や首筋や脇腹を丹念に愛撫しながら片手を下肢の間に伸ばし、扱いて、口に含む。
自分の手の中で固くなり、口中で熱を増す秋口に、佐山は気持ちを昂揚させた。ただその熱のことだけを考えて、夢中で手や舌を動かした。
「……ッ、もう、出る」
吐息を乱しながら、切れ切れに秋口が言って、佐山の頭を自分から離させた。引き寄せておいたボックスティッシュを数枚抜いて、つい今まで佐山の口中に収められていた場所に当てている。小さく身震いしながら射精する秋口から、佐山は今日も何となく目を逸らした。見たくなかったわけじゃなくて、見たいことが相手にばれてしまうのが気まずかったのだ。
秋口はさらに数枚ティッシュを抜き出して、佐山の方に差し出した。視界を掠ったぼんやり白いものを佐山は受け取り、それで濡れた口許を拭う。
仕事が終わって一緒に会社を出て、家に入るまで、入ってからも、必要最低限の言葉しか交わさず、この状態だ。
最近はずっとこうだよな、と佐山は舌先に残る苦い味を指先で擦りながら考えた。
何でこんなことになったんだっけ、とも。
(何て言うんだっけ、こういうの――下世話な言い方で)
思い出そうと努力しながら、佐山はベッドのサイドテーブルの上に置かれた煙草を手に取った。ほぼ無意識の動きで、咥えた煙草に火をつける。ライターの火が一瞬、佐山の部屋の中を浮かび上がらせた。掃除をしておくから、と秋口に告げつつ、結局あちこち散らばった荷物をまとめて終わった。
どうせベッドしかまともに使わないんだからいいか、とぼんやり思いながら、佐山はさっき浮かべた疑問の答えを思い出した。
(『相互オナニー』だ)
まったく下世話な表現だが、言い得て妙だと納得する。どこでこんな言葉を覚えたんだっけ、とついでに考えたが、これはどうしても思い出せなかった。きっと学生時代に悪友が見せてくれた類の雑誌だろう。
前回ことが終わった後に思いついた言葉は『セフレ』だが、別にセックスしているわけでもない気がするので、しっくりこなかったのだ。これですっきりした、と煙草を吸いながら、それにしたって自分はどうしてこんなバカみたいな下らないことを真剣に考えているのかと、佐山はおかしくなった。
秋口は何も喋らないし、佐山も口を噤んでいるから、思考ばかりが進んで嫌になる。
「一本、もらえますか」
どうやらベッドの上にあぐらをかいているらしい秋口が、ふとそう声を出した。
「どうぞ」
ベッドとくっついた壁に寄り掛かりながら、佐山は煙草とライターを一緒にして秋口の方に投げ 、灰皿をサイドテーブルからベッドの上に移動させた。
煙草を吸っていた秋口がまた不意に小さくくしゃみを洩らして、その様子が妙に可愛らしかったので佐山はひっそりと笑いながら、床から拾い上げたリモコンで冷房を少し弱めた。
「毎日暑いな」
リモコンをベッドに投げ出してから壁に寄り掛かり直し、佐山はそう言った。
「雨も全然降りませんよね」
佐山のつまらない言葉に秋口がつまらない言葉を返して、会話はそこでもう途切れてしまった。
煙草を一本吸いきると、秋口はベッドから起き出して風呂場に向かった。秋口が身支度を調えている間に、佐山も洗いっぱなしで畳まれもせず積み重なった洗濯物から適当にシャツやパンツを取り出して身につけた。
部屋に戻ってきた秋口が、自分の鞄を拾う。そのまま玄関に進む秋口の後について、佐山もドアの方に向かった。
「じゃあ、おやすみなさい」
靴を履いた秋口が、佐山の方を振り返りもせず、でも冷たくもない口調でそう告げる。
「おやすみ、気をつけて」
振り返った秋口が、一瞬だけ佐山に視線を向けて、すぐに外に出て行った。閉じたドアの鍵を閉め、佐山はそのまま生温い鉄のドアに額を押しつけた。
(――で)
秋口が帰った後の虚しさを、必死にやり過ごそうとする。悲しくも辛くもないのに、秋口がいなくなった後は何だか急激に疲れた。
(何でこうなったんだっけ?)
別に望んだことなんてひとつもない。望まないようにしていた。声が聞きたいとか自分を見て欲しいとか、触れて欲しいなんて思ったこともなかった。
それでも他愛ない会話を交わしながら美味い食事をとって、笑って、それが嬉しかったから一緒にいられる時間を自分から手放す気なんて毛頭起きなかったけれど。
キスされて、触れられて、勘違いしないように自分を戒めていた頃だって、まだ倖せだったと思えるくらいだ。
秋口が部屋に訪れるようになってから、世間話すら数えるほどしかしていない。秋口は何も言わないし佐山は何も聞かない。なのにお互い相手に快楽を与えるために熱心になっていたりする。
自分で決めた約束どおり、秋口と触れ合っている間は、その感触だけ夢中になって佐山は追った。
どうせ今、それを自分から手放せる余裕も度胸もない。こんな状況が本当に虚しいと思いながらも。
(何考えてるのだけでもいいから、聞きたい)
でも聞けない。聞いたら全部終わるだろうという予感はずっと持ち続けている。
(こんな形でも一緒にいたいわけだ)
触れるごとに執着心が募る気がして、佐山には少し怖かった。
こんなことが長く続くはずがないと、どうせいつか終わりが来ることは覚悟しているのに、会う回数が増えるたびにその『いつか』が近づくことが怖くなった。
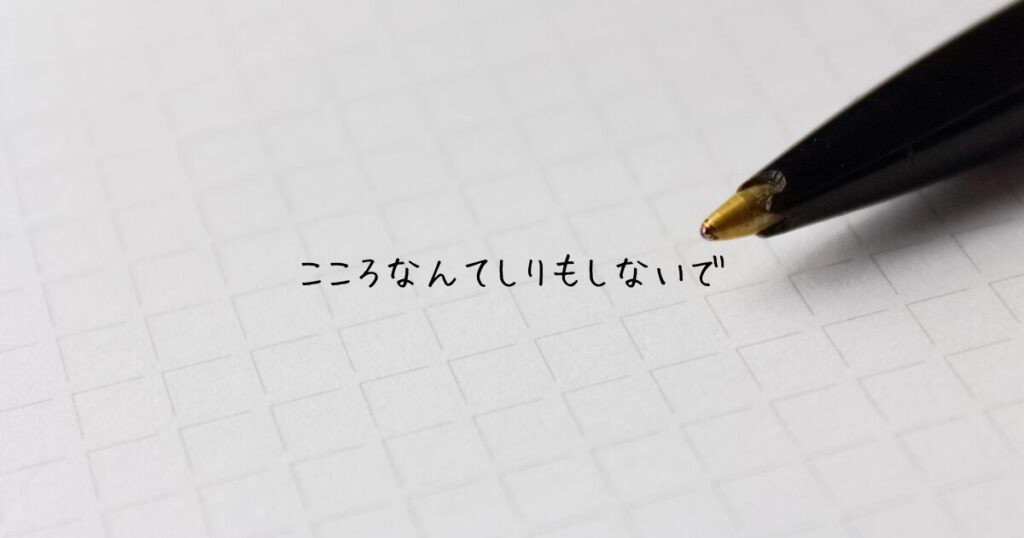
サラリーマン×サラリーマン

商業誌番外編

商業誌番外編

商業誌番外編
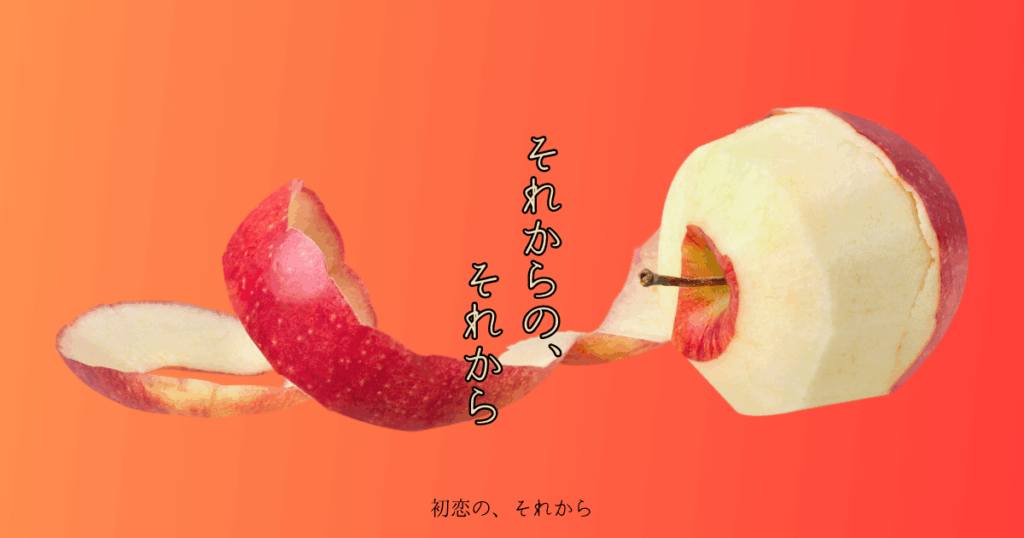
商業誌番外編
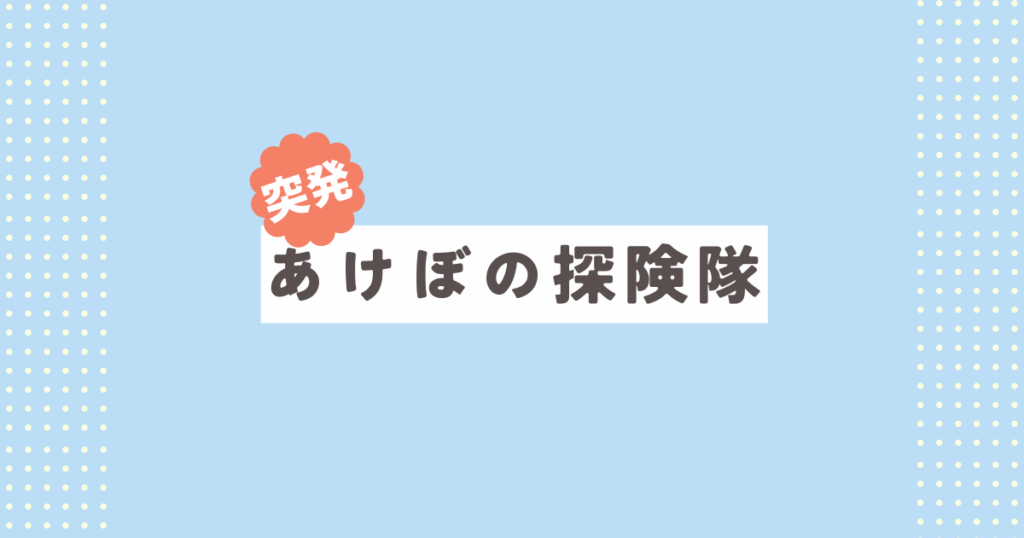
同人誌シリーズ番外編

高校生の恋未満読み切り