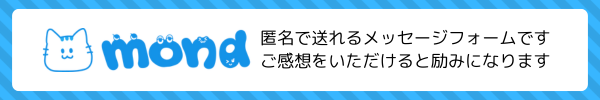「秋口、佐山との仕事、どうだ?」
自分の机で書類を書いていたら、青木がやってきてそう声を掛けてきた。
「どうって、まあ、特に滞りもなくって感じですかね」
手を止め、青木を見上げて秋口は答えた。
青木は佐山たちよりさらに年上のベテランで、今のところ営業一課で最も成績のいい社員だ。次の人事異動で間違いなく昇進するだろうと言われている。
入社以来仕事を教えてくれたのはこの青木で、秋口も彼に対しては一目置いていた。秋口の生意気な態度にも青木は懐が深く、たまに窘めつつも、仕事の飲み込みが早い後輩を可愛がっている。秋口が目に見えて孤立もせずに一課でやっていけるのは、青木の存在が大きかった。
秋口としては、足でも引っ張られない限り、たとえ男社員と一日口を聞かない状態だって、別に構わなかったのだが。
「T社の宮原課長、寸前になってあちこち注文変えるのが好きだから、間違いなく連絡できるように気をつけておけよ」
自分が前任していた仕事のせいだろう、青木は秋口にそう念を押した。引き継ぎの時も言われた台詞だ。
「今までの発注分も調べてあるし、やり方はわかります」
「そうか? ならいいんだけど。まあ、佐山がいるしな、何かあっても対処できるだろうし、大丈夫か」
青木の言葉に、秋口は少しムッとした。
「俺の仕事じゃ、信用できませんか?」
鼻っ柱の強い後輩の質問に、青木が鷹揚に笑った。
「そういうわけじゃないさ、ただ、佐山はT社との仕事に慣れてるし、営業の経験もあるしな。大抵の状況はフォローしてくれるから、秋口も安心して頼っていいってことだ」
青木はもともと佐山を信頼しているらしく、引き継ぎの時から何かあったら彼に頼るよう言ってきた。
沙和子といい、青木といい、それに御幸といい、どうしてあの貧相なメガネをそれほど評価するのか、秋口には不思議で仕方がない。
第一印象だけではわからないかもしれないと、秋口は理由をつけて佐山に話しかけてみたものの、やっぱり最初に下した評価と何ら変わるところはなかった。妙に及び腰だし、会話はつまらないし、怒らせたら人が変わるかと試してみれば、どうしたって愛想笑いを浮かべて反論もしない。
もし自分が後輩にあんな口を聞かれたら、嫌味の百や二百返して、再起不能にしてやるだろう。
「佐山さんって言えば」
苛立ちを抑えつつ、秋口は青木に問いかけた。
「総務の雛川さんとつき合ってたって、本当ですか」
総務部の他の女子社員にそれとなく訊ねてみたが、かなり前のことらしく、詳しくは知らないと言われてしまった。この会社が長い青木なら、少しは情報を持っているはずだ。
「ああ、だいぶ前にちらっとな。おまえが入社してくる前だよ」
案の定、青木がすぐに頷いた。
「雛川さんの方からコナかけたんだよ、たしか。あの子が入社して以来、男連中みんな躍起になって誘おうとしてたんだけど、ずっと綺麗に躱してたから、外に彼氏がいるんだろうって話になってたんだけど」
かく言う俺もフラレた口だ、と所帯持ちの青木がこっそり秋口に耳打ちする。
「二年くらい前かな、気づいたら雛川さんが佐山の周りによく顔見せるようになって、そのうちふたりで食堂行ったり、一緒に帰ったりするようになってたんだ。あん時は泣いた男が数知れずだよ」
「さぞかしみんな、口惜しがったでしょうね。佐山さんが相手じゃ」
「そりゃま、誰が相手でも、雛川さんを取られたら口惜しがるだろうけどな。俺は佐山だったら仕方がないって諦めたぜ、ひとりで我関せずの顔してたから、とんだ伏兵だとは思ったけど」
「雛川さんからコナかけたって……また、どうしてですかね」
「好みだったんじゃないか、単に。佐山は仕事できるしまじめだし、頼れるだろ。あと何だっけ、女の目からみたら、ああいうタイプは可愛いらしいぞ。俺はよくわからんけど」
可愛いねえ、と秋口は佐山の姿を思い出しながら首を捻った。
「俺もよくわかりませんね」
「恋愛沙汰なんて、当人じゃなきゃわからないってことだな。結局半年くらいで別れちまったみたいだし」
「どうして別れたのか、知ってますか?」
「さあ。噂じゃ雛川さんの浮気ってことらしいけど、特に人前で愁嘆場を演じたわけでなし、気づいたらつき合ってたってみたいに気づいたら別れてたんだ。今じゃ滅多に顔も合わせないようだし、ふたりがつき合ってたなんて話に昇ることもなくなってきてるな」
何しろ社員数の多い会社のこと、次から次へと噂話には尽きがない。
「それから佐山さんが他の恋人を作ったりとか、なかったんですか」
秋口が訊ねると、青木が首を捻った。
「さあな、もともと佐山、そういう話は全然しないから。雛川さんとつき合ってた時も、やっかんだ男連中とか噂好きの女の子たちにいろいろ聞かれてたのに、笑ってるだけで詳しいことは教えてくれなかったしな。万が一社外に女がいたとしたって、必要としなければ頑として口を割らないタイプだ」
「そうか……?」
今度は秋口が首を捻る番だった。あのいつもどこかしら落ち着かない様子の佐山だ、もしきつく問いつめたら、そのくらいのことへらへらしながら簡単に喋りそうだと思う。
「雛川さんの方は、総務部だか事業部だかの男とつき合ってるってちらっと噂流れたけどな。あんまり長く続かなかったみたいだ」
「それ以来フリー?」
「最近はちょっと相手の噂が出てる」
「へえ、誰です」
青木が、秋口に向かってにやにやとおかしそうな顔をした。
「おまえ」
秋口は軽く肩を竦めた。
「雛川さんの好みが佐山さんって言うんじゃ、俺はだいぶ外れてるんでしょうけど」
かといって自分が佐山に負けている気は毛頭ないが、秋口は一応、そう謙遜した。
青木が午後になって伸びてきた無精髭をてのひらで擦りながら、思案げに天井を見上げる。
「そうだなあ、佐山は芯がしっかりしてるし、苦労してきたっぽいから歳の割に落ち着いてるしな。雛川さんはあんまりキャピルンとしてるタイプじゃないから、そういう方がよかったのかも」
それではまるで自分の芯がしっかりしていなくて苦労知らずで落ち着きがないと言われているようだとか、キャピルンという表現はどうなのかとかいうことよりも、青木の語る佐山に関してが一番秋口の気になった。
どうも、自分の知っている佐山とは違う人間の話をされている気がする。
「あの、佐山って、開発課の佐山さんですよ?」
「ん? そうだよ」
「あの人が、しっかりしてる……?」
小銭をばらまいて慌てたり、ミルクを冷ましながら飲んでいる姿なら、秋口にも容易に思い出せるのだが。
「正直もうちょっとで終わるって仕事、他人に譲るのは迷ったんだけどな。でも秋口が佐山と仕事して何かしら勉強できるなら、おまえのためになるだろうから、引き継いだんだよ。しっかりやれよ」
疑問符ばかりを浮かべる秋口の内心に気づいたふうもなく、青木はその背中を叩くと、自分の席に戻っていってしまった。
(……なんっか、腹立つな)
青木の言いようでは、まるで自分の方が佐山よりも格下だと言っているようだ。
(俺のどこが、あのチビに劣るって言うんだ)
やっぱりすっきりしない。沙和子が佐山の名を出した時からずっと、秋口の中にはもやもやした苛立ちが宿って消えようとはしなかった。
(いっそ泣かせてやったら、雛川さんも青木さんもあいつがそういいもんじゃないって納得するのか?)
憮然とした手でペンを持ち直すと、秋口はいささか乱暴な調子で書類に文字を書きつけた。
自分の机で書類を書いていたら、青木がやってきてそう声を掛けてきた。
「どうって、まあ、特に滞りもなくって感じですかね」
手を止め、青木を見上げて秋口は答えた。
青木は佐山たちよりさらに年上のベテランで、今のところ営業一課で最も成績のいい社員だ。次の人事異動で間違いなく昇進するだろうと言われている。
入社以来仕事を教えてくれたのはこの青木で、秋口も彼に対しては一目置いていた。秋口の生意気な態度にも青木は懐が深く、たまに窘めつつも、仕事の飲み込みが早い後輩を可愛がっている。秋口が目に見えて孤立もせずに一課でやっていけるのは、青木の存在が大きかった。
秋口としては、足でも引っ張られない限り、たとえ男社員と一日口を聞かない状態だって、別に構わなかったのだが。
「T社の宮原課長、寸前になってあちこち注文変えるのが好きだから、間違いなく連絡できるように気をつけておけよ」
自分が前任していた仕事のせいだろう、青木は秋口にそう念を押した。引き継ぎの時も言われた台詞だ。
「今までの発注分も調べてあるし、やり方はわかります」
「そうか? ならいいんだけど。まあ、佐山がいるしな、何かあっても対処できるだろうし、大丈夫か」
青木の言葉に、秋口は少しムッとした。
「俺の仕事じゃ、信用できませんか?」
鼻っ柱の強い後輩の質問に、青木が鷹揚に笑った。
「そういうわけじゃないさ、ただ、佐山はT社との仕事に慣れてるし、営業の経験もあるしな。大抵の状況はフォローしてくれるから、秋口も安心して頼っていいってことだ」
青木はもともと佐山を信頼しているらしく、引き継ぎの時から何かあったら彼に頼るよう言ってきた。
沙和子といい、青木といい、それに御幸といい、どうしてあの貧相なメガネをそれほど評価するのか、秋口には不思議で仕方がない。
第一印象だけではわからないかもしれないと、秋口は理由をつけて佐山に話しかけてみたものの、やっぱり最初に下した評価と何ら変わるところはなかった。妙に及び腰だし、会話はつまらないし、怒らせたら人が変わるかと試してみれば、どうしたって愛想笑いを浮かべて反論もしない。
もし自分が後輩にあんな口を聞かれたら、嫌味の百や二百返して、再起不能にしてやるだろう。
「佐山さんって言えば」
苛立ちを抑えつつ、秋口は青木に問いかけた。
「総務の雛川さんとつき合ってたって、本当ですか」
総務部の他の女子社員にそれとなく訊ねてみたが、かなり前のことらしく、詳しくは知らないと言われてしまった。この会社が長い青木なら、少しは情報を持っているはずだ。
「ああ、だいぶ前にちらっとな。おまえが入社してくる前だよ」
案の定、青木がすぐに頷いた。
「雛川さんの方からコナかけたんだよ、たしか。あの子が入社して以来、男連中みんな躍起になって誘おうとしてたんだけど、ずっと綺麗に躱してたから、外に彼氏がいるんだろうって話になってたんだけど」
かく言う俺もフラレた口だ、と所帯持ちの青木がこっそり秋口に耳打ちする。
「二年くらい前かな、気づいたら雛川さんが佐山の周りによく顔見せるようになって、そのうちふたりで食堂行ったり、一緒に帰ったりするようになってたんだ。あん時は泣いた男が数知れずだよ」
「さぞかしみんな、口惜しがったでしょうね。佐山さんが相手じゃ」
「そりゃま、誰が相手でも、雛川さんを取られたら口惜しがるだろうけどな。俺は佐山だったら仕方がないって諦めたぜ、ひとりで我関せずの顔してたから、とんだ伏兵だとは思ったけど」
「雛川さんからコナかけたって……また、どうしてですかね」
「好みだったんじゃないか、単に。佐山は仕事できるしまじめだし、頼れるだろ。あと何だっけ、女の目からみたら、ああいうタイプは可愛いらしいぞ。俺はよくわからんけど」
可愛いねえ、と秋口は佐山の姿を思い出しながら首を捻った。
「俺もよくわかりませんね」
「恋愛沙汰なんて、当人じゃなきゃわからないってことだな。結局半年くらいで別れちまったみたいだし」
「どうして別れたのか、知ってますか?」
「さあ。噂じゃ雛川さんの浮気ってことらしいけど、特に人前で愁嘆場を演じたわけでなし、気づいたらつき合ってたってみたいに気づいたら別れてたんだ。今じゃ滅多に顔も合わせないようだし、ふたりがつき合ってたなんて話に昇ることもなくなってきてるな」
何しろ社員数の多い会社のこと、次から次へと噂話には尽きがない。
「それから佐山さんが他の恋人を作ったりとか、なかったんですか」
秋口が訊ねると、青木が首を捻った。
「さあな、もともと佐山、そういう話は全然しないから。雛川さんとつき合ってた時も、やっかんだ男連中とか噂好きの女の子たちにいろいろ聞かれてたのに、笑ってるだけで詳しいことは教えてくれなかったしな。万が一社外に女がいたとしたって、必要としなければ頑として口を割らないタイプだ」
「そうか……?」
今度は秋口が首を捻る番だった。あのいつもどこかしら落ち着かない様子の佐山だ、もしきつく問いつめたら、そのくらいのことへらへらしながら簡単に喋りそうだと思う。
「雛川さんの方は、総務部だか事業部だかの男とつき合ってるってちらっと噂流れたけどな。あんまり長く続かなかったみたいだ」
「それ以来フリー?」
「最近はちょっと相手の噂が出てる」
「へえ、誰です」
青木が、秋口に向かってにやにやとおかしそうな顔をした。
「おまえ」
秋口は軽く肩を竦めた。
「雛川さんの好みが佐山さんって言うんじゃ、俺はだいぶ外れてるんでしょうけど」
かといって自分が佐山に負けている気は毛頭ないが、秋口は一応、そう謙遜した。
青木が午後になって伸びてきた無精髭をてのひらで擦りながら、思案げに天井を見上げる。
「そうだなあ、佐山は芯がしっかりしてるし、苦労してきたっぽいから歳の割に落ち着いてるしな。雛川さんはあんまりキャピルンとしてるタイプじゃないから、そういう方がよかったのかも」
それではまるで自分の芯がしっかりしていなくて苦労知らずで落ち着きがないと言われているようだとか、キャピルンという表現はどうなのかとかいうことよりも、青木の語る佐山に関してが一番秋口の気になった。
どうも、自分の知っている佐山とは違う人間の話をされている気がする。
「あの、佐山って、開発課の佐山さんですよ?」
「ん? そうだよ」
「あの人が、しっかりしてる……?」
小銭をばらまいて慌てたり、ミルクを冷ましながら飲んでいる姿なら、秋口にも容易に思い出せるのだが。
「正直もうちょっとで終わるって仕事、他人に譲るのは迷ったんだけどな。でも秋口が佐山と仕事して何かしら勉強できるなら、おまえのためになるだろうから、引き継いだんだよ。しっかりやれよ」
疑問符ばかりを浮かべる秋口の内心に気づいたふうもなく、青木はその背中を叩くと、自分の席に戻っていってしまった。
(……なんっか、腹立つな)
青木の言いようでは、まるで自分の方が佐山よりも格下だと言っているようだ。
(俺のどこが、あのチビに劣るって言うんだ)
やっぱりすっきりしない。沙和子が佐山の名を出した時からずっと、秋口の中にはもやもやした苛立ちが宿って消えようとはしなかった。
(いっそ泣かせてやったら、雛川さんも青木さんもあいつがそういいもんじゃないって納得するのか?)
憮然とした手でペンを持ち直すと、秋口はいささか乱暴な調子で書類に文字を書きつけた。
◇◇◇
(あれ、あの人、まだ来てないのか?)
金曜日、仕事が終わった後に集まった営業一課と二課合同の飲み会。
馴染みの店に揃った顔ぶれの中に、今日なぜか混じるのだと告げられていた佐山の姿がみつからなくて、秋口は何となく辺りを見回した。
「秋口くん、どうしたの?」
テーブル席に座っているのは三十人近い人数。営業の全員が出席しているわけではないのに、他の部署の人間も紛れているから結局大勢になっている。先日声を掛けてきた巻野も、会社を出たところで白々しく偶然を装い、店では秋口の隣を確保して営業の女子社員から眉を顰められている。
その彼女に声をかけられ、秋口は「いや」と曖昧に首を横に振った。
佐山と仲のいい御幸の姿も店の中になかった。御幸はさほど熱心に飲み会に参加する方でもなかったので、珍しいことではないが。
(別に来たって来なくたって、どっちでもいいんだけど)
部外者、開発課である佐山が呼ばれたのが、営業の女子社員の希望だと聞いていたので、今回の飲み会がどうなるのか少し興味はあった。いつもは大体秋口の周りに女子社員の大半が集まり、その女子社員を狙った男性社員が間に割って入り、秋口に興味のない女子社員や輪に入って行けない女子社員が少し外れたところに固まり、秋口の「おこぼれ」に興味がない男性社員も男性同士で固まり、固まり同士がたまに接触する感じ。御幸が来た場合、彼は大抵男性社員の固まりの中に入って行くので、秋口狙いの女子社員はなかなか彼のそばに行き難い。御幸が派手で積極的な女を好まないのは皆何となく察している。
佐山が顔を出すのなら、まあ流れとして御幸と一緒に男性社員の固まりに収まるだろうが、彼を連れてこいと言った営業課の女子社員がどう出るのか見てみたい気分があった。佐山がどんなふうに女をあしらうかとか――あるいは、どんなふうにあしらわれるのかとか。
適当な人数が集まったところで誰かが勝手に乾杯の音頭を取って、なし崩し的に飲み会が始まった。特に誰かの歓迎会とか名目のある集まりではなかったから、みんながそれぞれ勝手に料理を頼み、酒を飲み、喋り、賑やかだ。
秋口の周りに群がる女の子たちは、皆競って秋口の皿に料理をよそったり、ビールを注いだり、話しかけたりと忙しい。秋口は適当に彼女たちに相槌を打って笑いかけながら、今日はどの子を持って帰ろうかなどと算段をまとめている。
途中で席を立ってトイレに向かったら、入口の方からやってくる御幸と鉢合わせた。
「あれ、お疲れ様です」
「よう」
秋口の姿をみとめ、御幸が軽く笑いかけてくる。相変わらず「王子様」みたいな様子で、秋口は彼にあまり浮いた噂がないのが不思議だった。恋人の話をまるで聞かない。もしかしたらこっそり社外の相手とつき合っているのかもしれないが。
「残業でした?」
「ちょっとな」
飲み会が始まって、一時間近く経っている。この時間になってから御幸がわざわざ店に足を運ぶことが意外だった。もしかしたら御幸の後ろから佐山が現れるのではと思って、秋口は彼の後ろの方に視線を向けたが、ただ店員が通り過ぎていくだけだ。
「佐山さん、来ないんですか?」
「ああ、あいつも残業。腹減ったっていうから、ちょっと食べ物持って行ってやろうと思ってさ。ここの料理美味いし、持ち帰りもできるだろ」
「そのためにわざわざ?」
秋口の驚きに、御幸は笑って頷いた。
「俺が来たの、皆には言わないでおいてくれ。今料理頼んでるところだけど、捕まったら戻れなくなりそうだし」
たしかに、御幸が来たことを女子社員たちが知ったら、きっと無理矢理テーブルに着かせて、時間一杯まで離さないことだろう。
「しっかし、いくら友達のためっていったって、よくそこまでしますねえ」
「あいつ、放っておくと飯抜くこと多いからな。心配なんだよ」
そういえば食が細そうだったっけ、と秋口は佐山と食堂で一緒になった時のことを思い出す。
「恋人かおふくろさんって風情ですね」
「こんなでかいおふくろじゃ、佐山も迷惑だろうけどな」
からかうつもりで秋口が言うと、御幸は気を悪くしたふうもなく、笑って流した。穏和な彼らしい反応だ。
「佐山さんは、他人から庇われて甘やかされるのに慣れてるって感じの人なのかな。正直なとこ、俺なんか反応見てたまに苛々しますけどね。何言ってもへらへら笑ってるし、プライドあるのかなって不思議だな」
「プライド、ね」
御幸が微笑んだまま、秋口を見返す。
「秋口はプライドっていうのが高そうだよな」
秋口も御幸に笑い返した。
「相応ですよ」
「俺はたとえば仕事に関してちゃんとした結果を出すために、真剣に取り組むことをプライドがあるって言うと思うけどな。人間として尊敬できる」
「それ、佐山さんのことですか?」
「そうだよ」
「営業についてけなくて、胃壊したってのに?」
「何も仕事が辛くて精神的に駄目になったとか、仕事を失敗したってわけじゃない。ただ、ひどい客に下戸なのをからかわれて無理に酒を飲まされて、入院しなくちゃならなかったんだ」
それだって男として情けないんじゃないか、とジョッキ三杯空けてもまだまだ素面に近い秋口は思った。
それを口に出さなかったのは、やんわり微笑んでいる御幸から、静かな怒りが伝わってきたからだ。
「秋口が何をたくらんでるのかは知らないけどな」
笑ったまま、とん、と軽く御幸が拳で秋口の胸を押す。秋口はお愛想笑いを返した。
「たくらんでるって、何ですか。おっかないな」
「T社の仕事。おまえが青木さんにねじ込んで、無理矢理引き継いだって聞いたぞ?」
「……」
「おまえだって複数口仕事持ってるだろうに、強引に変わってもらったって聞いて、不思議だったんだ。だから青木さんにたしかめたら、あの生意気な秋口が『青木さんはチーフになったんだし、新しい仕事に集中して下さい』とか殊勝なこと言ったって、感動してたぞ」
「本音言ったまでですよ、今度の仕事が成功したら、青木さん間違いなく昇進するだろうし、あの人にはお世話になってるから、恩返ししたいなって」
「そうだな、青木さんも、秋口は仕事できるからあいつになら任せられるって言ってたし。でかい仕事のチーフに任命されて緊張してたとこ、絆されたみたいな形で」
とんとんと、もう一度御幸が秋口の胸を叩いた。
「何をたくらんでわざわざ佐山と一緒の仕事を選んだのかは知らないけど、大概にしておけよ。つまらないことに横やり入れられて仕事が滞るようじゃ、佐山もいい迷惑だ」
「人聞き悪いな。俺が佐山さんに嫌がらせでもしてるような言い種じゃないですか」
秋口は不快になった。自分は佐山に対して思ったことを言っているだけだし、それを当人ではなくその友人からくさされるのでは、こちらこそいい迷惑だ。
「もしかして、佐山さんが御幸さんに泣きついたんですか。俺に何かされてるって」
「佐山がそんなこと言うかよ。あいつはたとえおまえにどれだけ悪口雑言吐かれたって、俺に泣きついたりしないさ」
「御幸さん、俺のこと目障りなんですか?」
自分と御幸は社内で同じくらい女子社員にもてるし、仕事の評価も高い。だからそういう自分に難癖つけているのだろうか――と疑う秋口に、御幸はこれまでとは少々質の違う笑顔を見せた。
哀れむような表情だと、秋口はそう気づいて瞬間的に背筋へ怒りを立ち昇らせた。
「ま……秋口が多少何か言ったところで、佐山の仕事に影響が出るほど大袈裟なことでもないかな。あいつの邪魔だけしてくれなければいいか」
「ご心配いただかなくても、青木さんと組んでた時以上に成果は出してみせますよ」
「そっか。頑張れ」
手を離した御幸に、もっと何か言い返してやりたかったが、そのタイミングで店員が御幸の頼んだ持ち帰り用の料理を運んで来たので、秋口は口を噤んだ。
「それじゃ、俺は戻るな」
料理を受け取った御幸が、穏やかな笑顔で秋口にそう告げた時、そのポケットの中で携帯電話の着信音が響いた。
「あれ、佐山だ」
電話の液晶画面を見た御幸が、そう言って通話ボタンを押す。他人の会話なんて聞いても仕方がないので、秋口はそもそもの目的であるトイレに向かいかけた。
「うん、今ちょうど店。おまえの好きなれんこんの揚げ物買ったぞ。――え? 秋口? ああ、今いるけど、ここに」
だが、自分の名を呼ばれて動きを止める。
「秋口、ちょっと、佐山から用があるって」
「俺に?」
仕事のことだろうかと、秋口は御幸の携帯電話を受け取った。自分の電話は、そういえば鞄と一緒に席に置いてきてしまった。御幸に会わなければ、用を足してすぐ戻るつもりだったのだ。
「もしもし? 秋口です」
『ああ、ごめん、佐山です。今ちょっといいか』
佐山の声音はいつになく真剣で、微かに重い。
秋口はすぐに、仕事上で何かトラブルがあったのだと察した。
『T社の発注書な、今確認したけど、もしかしたら俺が受け取ったのと仕様が変わってるかもしれない』
「え? まさか、そんなはずないですよ。向こうの担当に確認してもらって、サンプルでもオッケーもらったじゃないですか」
『うん、でも、昼間に送られてきたFAX、念のためってさっき確認してたら』
「FAX? 連絡は全部、メールか電話でしてるはずですよ」
『担当の宮原さん、急ぎの用だと、FAXで送ることがあるんだ。そっちの方が確実って思ってるみたいで』
「何だそれ、俺あれほど連絡は全部メールでって事前に」
『ともかく、まだ店にいるなら、悪いけど一旦戻ってきてくれないか。もう工場に発注しちゃってるから、変更するなら今のうちにしておかないと、月曜の朝イチにでも作り始めたらまずい』
「――わかりました、すぐ戻ります」
秋口は舌打ちしながら通話を切って、電話を御幸に返した。
「トラブルか?」
素直に頷く気にもなれず、秋口は御幸の問いを無視した。
「俺ちょっと、社に戻ります。ああ、料理届けるなら、俺やりますよ。御幸さんはついでに飲んでいったらどうです」
御幸と一緒に会社に戻るのは、秋口にとって避けたい事態だった。
「そうか? じゃあ、よろしく」
御幸はあっさり頷いて、秋口は助かったと思いつつ、彼に内心を見透かされた気がして、何だか不愉快な気分にもなった。
まるっきりの八つ当たりだと自覚していたので、辛うじて笑顔も作ったが。
「御幸さん来たら女の子たち喜びますよ、席、こっちです」
御幸を社員たちの集まる場所へ案内し、荷物を取ると、名残惜しむ女子社員たちを置いて、秋口は店を飛び出した。
店から会社まで小走りに進む。タクシーを使うほどの距離じゃない。秋口はすでにロックされている社員用の玄関をIDカードで通り抜け、まっさきに営業一課へと向かった。
業務用ファクシミリの受信済用紙を漁るが、それらしきものはない。営業時間中に受け取ったFAXは事務の社員が整理して担当の社員に渡すし、今日秋口がT社から連絡を受けた覚えはなかった。終業後に届いた通信の中にもT社からのものはない。
自分のデスクに駆け寄り、パソコンを立ち上げてメールチェックをするが、そこにも連絡は特になかった。
(ひょっとして)
思い当たり、秋口は青木のデスクに近づくと、悪いと思いながらも勝手にその上の書類を書き分けた。青木はあまり整理上手な方ではなく、必要なのかそうでないのかおそらく本人しかわからない書類が、適当に書類入れに突っ込まれていた。
「――あった」
商品と、ただ「ご担当者様」とだけ書かれたT社からのFAX。おそらく事務の社員が、青木の担当だと勘違いして振り分けてしまったのだろう。
焦燥する気分で確認すると、たしかに、殴り書きで仕様変更の指示が出ていた。
「普通口頭で確認するだろう」
ここにはいない担当者を罵り、そんな場合ではないと、秋口は急いで相手の会社に電話をかけた。しかし営業時間外のアナウンスが流れるだけで繋がらない。携帯電話も繋がらなかった。週末は金曜の夜から家族で旅行に出かけるとか話していたのに、愛想よく「羨ましいですね」なんて言った自分を秋口は思い出す。
「くそっ」
青木の椅子を蹴り上げ、FAX用紙を握り締めて秋口は営業一課を出た。
「佐山さん」
開発課の中に入り、ひとり残っている佐山に声を掛けると、佐山はちょうど電話中のようで、受話器を握ったまま秋口に片手を挙げて応えた。
「はい――はい、では、そのようにお願いいたします。遅くに申し訳ありません、失礼いたします」
電話を切った佐山の元に、秋口は苛立ちながら近づいた。
「FAX、ありましたよ。青木さんとこに」
「やっぱり。俺の方に流れてきたのに、秋口からは連絡ないから変だと思ってたんだ」
落ち着いた佐山の態度に、秋口はますます八つ当たり的に腹が立ってきた。
「担当者の名前くらい書けってんだ。大体、青木さんから引き継いだ時の挨拶で、連絡は全部メールでって念押ししておいたはずなのに」
「でもそれは、こっちの都合だろ。FAXが来たんなら、ちゃんと確認するべきだったんだ。ごめん、俺も昼間別の仕事にかかり切りだったから、こんな指示が出てると思わなくて」
申し訳なさそうな顔でそう言ってから、佐山はモニタの画面を指さした。
「部品のサイズを変えてもう一回図面引き直したから、秋口が確認してくれたらすぐ工場に再発注するよ」
「え、再発注って、でももう工場は終わって」
「さっき連絡したら、まだ担当の人が残ってて、仕事が詰まってるから明日機械回すつもりだったって。今日中にもう一回連絡する約束で待ってもらってるから、急ごう」
「……」
返事もなく黙り込んだ秋口に、佐山が少し首を傾げた。
「秋口?」
「それ、俺の仕事ですよね」
佐山から電話が来て、わずか二十分にも満たない。
自分があたふたと店から駆け戻ってきた間に、佐山が仕事相手にもう話をつけてきたことを、本当ならば感謝すべきなのはわかっていたが。
(俺だってそのくらい、できたのに)
よりによって『この』佐山にフォローされてしまったという事実が、いたく秋口の自尊心を傷つけた。
「あ――悪い、なるべく急いだ方がいいと思って、独断で連絡取ったんだ」
秋口の怒りを察して、咄嗟に申し訳なさそうな顔になる佐山の態度に、秋口はさらに苛立ってしまう。
明らかに自分のミスなのはわかっている。どんな手段であろうと取引相手からの連絡を見過ごしたことは、営業として致命的だろう。青木だって、T社の担当は寸前で仕様を変えるのが好きだから気をつけろと、わざわざ何度も念押ししていた。
わかっているのに、秋口はとても素直に礼を言う気分にはなれなかった。余計なことをしたと、庇わなくても自分がすぐにミスを取り返せたのにと、どうしても佐山を詰る方向に心が向いてしまう。
「ずいぶん手回しがいいんですね。もしかして、どうせ俺がミスするだろうって見越して待ち構えてました?」
「そんなわけないだろ。単に、俺の方が宮原さんとも工場ともつき合い長いし、やり方がわかってるだけだよ」
「俺はやり方がわかってなくてすみません。覚えておきますんで、これからは俺の許可なしに勝手なことしないで下さい。これじゃ急いで戻ってきた俺が馬鹿みたいじゃないか」
「……ごめん」
困り切った顔の佐山を見ていたら、もっとひどいことを言って泣き顔にでもさせてやりたいと、凶暴な衝動が秋口の中に湧き上がる。
(こんなこと言われて言い返しもしないなんて、俺のこと馬鹿にしてるに決まってる)
理不尽なことを言っているという罪悪感を隠すために、秋口はそれを佐山への苛立ちにすり替えた。
「……もう型は作ってあるらしいから、その損失分の計算も、できたら今日のうちに持って行きたいから」
俯き加減に佐山が言った。咄嗟にそのことに思い至らなかった自分を隠すため、応える秋口の言葉はひどく乱暴な調子になった。
「わかってますって。図面できたら、佐山さんもう帰っていいですよ。後は俺が全部やります」
「でもこれは、俺の仕事でもあるから」
「そんなに俺のこと信用できないんですか?」
「……」
「何なら全部佐山さんがやりますか? そうですよね、佐山さん俺より営業経験長いらしいし。自分でやる方が安心っていうのなら」
「わかった。じゃあ、先、帰るな」
耐えかねたように、佐山が秋口の言葉を遮って立ち上がった。秋口の方は見ず、プリンタを動かして図面を印刷している。
「何かあったら携帯、電話してくれ。何時でも待ってるから」
そう告げた佐山に応える気にならず、秋口はFAXを確認している素振りで無視した。
佐山が荷物をまとめ、自分の机から離れる。出口のところで気懸かりそうに振り返ったのが気配でわかったが、秋口はそれも無視した。
静かに足音が遠ざかっていく。秋口はひどく惨めな気分でそれを聞いていた。
金曜日、仕事が終わった後に集まった営業一課と二課合同の飲み会。
馴染みの店に揃った顔ぶれの中に、今日なぜか混じるのだと告げられていた佐山の姿がみつからなくて、秋口は何となく辺りを見回した。
「秋口くん、どうしたの?」
テーブル席に座っているのは三十人近い人数。営業の全員が出席しているわけではないのに、他の部署の人間も紛れているから結局大勢になっている。先日声を掛けてきた巻野も、会社を出たところで白々しく偶然を装い、店では秋口の隣を確保して営業の女子社員から眉を顰められている。
その彼女に声をかけられ、秋口は「いや」と曖昧に首を横に振った。
佐山と仲のいい御幸の姿も店の中になかった。御幸はさほど熱心に飲み会に参加する方でもなかったので、珍しいことではないが。
(別に来たって来なくたって、どっちでもいいんだけど)
部外者、開発課である佐山が呼ばれたのが、営業の女子社員の希望だと聞いていたので、今回の飲み会がどうなるのか少し興味はあった。いつもは大体秋口の周りに女子社員の大半が集まり、その女子社員を狙った男性社員が間に割って入り、秋口に興味のない女子社員や輪に入って行けない女子社員が少し外れたところに固まり、秋口の「おこぼれ」に興味がない男性社員も男性同士で固まり、固まり同士がたまに接触する感じ。御幸が来た場合、彼は大抵男性社員の固まりの中に入って行くので、秋口狙いの女子社員はなかなか彼のそばに行き難い。御幸が派手で積極的な女を好まないのは皆何となく察している。
佐山が顔を出すのなら、まあ流れとして御幸と一緒に男性社員の固まりに収まるだろうが、彼を連れてこいと言った営業課の女子社員がどう出るのか見てみたい気分があった。佐山がどんなふうに女をあしらうかとか――あるいは、どんなふうにあしらわれるのかとか。
適当な人数が集まったところで誰かが勝手に乾杯の音頭を取って、なし崩し的に飲み会が始まった。特に誰かの歓迎会とか名目のある集まりではなかったから、みんながそれぞれ勝手に料理を頼み、酒を飲み、喋り、賑やかだ。
秋口の周りに群がる女の子たちは、皆競って秋口の皿に料理をよそったり、ビールを注いだり、話しかけたりと忙しい。秋口は適当に彼女たちに相槌を打って笑いかけながら、今日はどの子を持って帰ろうかなどと算段をまとめている。
途中で席を立ってトイレに向かったら、入口の方からやってくる御幸と鉢合わせた。
「あれ、お疲れ様です」
「よう」
秋口の姿をみとめ、御幸が軽く笑いかけてくる。相変わらず「王子様」みたいな様子で、秋口は彼にあまり浮いた噂がないのが不思議だった。恋人の話をまるで聞かない。もしかしたらこっそり社外の相手とつき合っているのかもしれないが。
「残業でした?」
「ちょっとな」
飲み会が始まって、一時間近く経っている。この時間になってから御幸がわざわざ店に足を運ぶことが意外だった。もしかしたら御幸の後ろから佐山が現れるのではと思って、秋口は彼の後ろの方に視線を向けたが、ただ店員が通り過ぎていくだけだ。
「佐山さん、来ないんですか?」
「ああ、あいつも残業。腹減ったっていうから、ちょっと食べ物持って行ってやろうと思ってさ。ここの料理美味いし、持ち帰りもできるだろ」
「そのためにわざわざ?」
秋口の驚きに、御幸は笑って頷いた。
「俺が来たの、皆には言わないでおいてくれ。今料理頼んでるところだけど、捕まったら戻れなくなりそうだし」
たしかに、御幸が来たことを女子社員たちが知ったら、きっと無理矢理テーブルに着かせて、時間一杯まで離さないことだろう。
「しっかし、いくら友達のためっていったって、よくそこまでしますねえ」
「あいつ、放っておくと飯抜くこと多いからな。心配なんだよ」
そういえば食が細そうだったっけ、と秋口は佐山と食堂で一緒になった時のことを思い出す。
「恋人かおふくろさんって風情ですね」
「こんなでかいおふくろじゃ、佐山も迷惑だろうけどな」
からかうつもりで秋口が言うと、御幸は気を悪くしたふうもなく、笑って流した。穏和な彼らしい反応だ。
「佐山さんは、他人から庇われて甘やかされるのに慣れてるって感じの人なのかな。正直なとこ、俺なんか反応見てたまに苛々しますけどね。何言ってもへらへら笑ってるし、プライドあるのかなって不思議だな」
「プライド、ね」
御幸が微笑んだまま、秋口を見返す。
「秋口はプライドっていうのが高そうだよな」
秋口も御幸に笑い返した。
「相応ですよ」
「俺はたとえば仕事に関してちゃんとした結果を出すために、真剣に取り組むことをプライドがあるって言うと思うけどな。人間として尊敬できる」
「それ、佐山さんのことですか?」
「そうだよ」
「営業についてけなくて、胃壊したってのに?」
「何も仕事が辛くて精神的に駄目になったとか、仕事を失敗したってわけじゃない。ただ、ひどい客に下戸なのをからかわれて無理に酒を飲まされて、入院しなくちゃならなかったんだ」
それだって男として情けないんじゃないか、とジョッキ三杯空けてもまだまだ素面に近い秋口は思った。
それを口に出さなかったのは、やんわり微笑んでいる御幸から、静かな怒りが伝わってきたからだ。
「秋口が何をたくらんでるのかは知らないけどな」
笑ったまま、とん、と軽く御幸が拳で秋口の胸を押す。秋口はお愛想笑いを返した。
「たくらんでるって、何ですか。おっかないな」
「T社の仕事。おまえが青木さんにねじ込んで、無理矢理引き継いだって聞いたぞ?」
「……」
「おまえだって複数口仕事持ってるだろうに、強引に変わってもらったって聞いて、不思議だったんだ。だから青木さんにたしかめたら、あの生意気な秋口が『青木さんはチーフになったんだし、新しい仕事に集中して下さい』とか殊勝なこと言ったって、感動してたぞ」
「本音言ったまでですよ、今度の仕事が成功したら、青木さん間違いなく昇進するだろうし、あの人にはお世話になってるから、恩返ししたいなって」
「そうだな、青木さんも、秋口は仕事できるからあいつになら任せられるって言ってたし。でかい仕事のチーフに任命されて緊張してたとこ、絆されたみたいな形で」
とんとんと、もう一度御幸が秋口の胸を叩いた。
「何をたくらんでわざわざ佐山と一緒の仕事を選んだのかは知らないけど、大概にしておけよ。つまらないことに横やり入れられて仕事が滞るようじゃ、佐山もいい迷惑だ」
「人聞き悪いな。俺が佐山さんに嫌がらせでもしてるような言い種じゃないですか」
秋口は不快になった。自分は佐山に対して思ったことを言っているだけだし、それを当人ではなくその友人からくさされるのでは、こちらこそいい迷惑だ。
「もしかして、佐山さんが御幸さんに泣きついたんですか。俺に何かされてるって」
「佐山がそんなこと言うかよ。あいつはたとえおまえにどれだけ悪口雑言吐かれたって、俺に泣きついたりしないさ」
「御幸さん、俺のこと目障りなんですか?」
自分と御幸は社内で同じくらい女子社員にもてるし、仕事の評価も高い。だからそういう自分に難癖つけているのだろうか――と疑う秋口に、御幸はこれまでとは少々質の違う笑顔を見せた。
哀れむような表情だと、秋口はそう気づいて瞬間的に背筋へ怒りを立ち昇らせた。
「ま……秋口が多少何か言ったところで、佐山の仕事に影響が出るほど大袈裟なことでもないかな。あいつの邪魔だけしてくれなければいいか」
「ご心配いただかなくても、青木さんと組んでた時以上に成果は出してみせますよ」
「そっか。頑張れ」
手を離した御幸に、もっと何か言い返してやりたかったが、そのタイミングで店員が御幸の頼んだ持ち帰り用の料理を運んで来たので、秋口は口を噤んだ。
「それじゃ、俺は戻るな」
料理を受け取った御幸が、穏やかな笑顔で秋口にそう告げた時、そのポケットの中で携帯電話の着信音が響いた。
「あれ、佐山だ」
電話の液晶画面を見た御幸が、そう言って通話ボタンを押す。他人の会話なんて聞いても仕方がないので、秋口はそもそもの目的であるトイレに向かいかけた。
「うん、今ちょうど店。おまえの好きなれんこんの揚げ物買ったぞ。――え? 秋口? ああ、今いるけど、ここに」
だが、自分の名を呼ばれて動きを止める。
「秋口、ちょっと、佐山から用があるって」
「俺に?」
仕事のことだろうかと、秋口は御幸の携帯電話を受け取った。自分の電話は、そういえば鞄と一緒に席に置いてきてしまった。御幸に会わなければ、用を足してすぐ戻るつもりだったのだ。
「もしもし? 秋口です」
『ああ、ごめん、佐山です。今ちょっといいか』
佐山の声音はいつになく真剣で、微かに重い。
秋口はすぐに、仕事上で何かトラブルがあったのだと察した。
『T社の発注書な、今確認したけど、もしかしたら俺が受け取ったのと仕様が変わってるかもしれない』
「え? まさか、そんなはずないですよ。向こうの担当に確認してもらって、サンプルでもオッケーもらったじゃないですか」
『うん、でも、昼間に送られてきたFAX、念のためってさっき確認してたら』
「FAX? 連絡は全部、メールか電話でしてるはずですよ」
『担当の宮原さん、急ぎの用だと、FAXで送ることがあるんだ。そっちの方が確実って思ってるみたいで』
「何だそれ、俺あれほど連絡は全部メールでって事前に」
『ともかく、まだ店にいるなら、悪いけど一旦戻ってきてくれないか。もう工場に発注しちゃってるから、変更するなら今のうちにしておかないと、月曜の朝イチにでも作り始めたらまずい』
「――わかりました、すぐ戻ります」
秋口は舌打ちしながら通話を切って、電話を御幸に返した。
「トラブルか?」
素直に頷く気にもなれず、秋口は御幸の問いを無視した。
「俺ちょっと、社に戻ります。ああ、料理届けるなら、俺やりますよ。御幸さんはついでに飲んでいったらどうです」
御幸と一緒に会社に戻るのは、秋口にとって避けたい事態だった。
「そうか? じゃあ、よろしく」
御幸はあっさり頷いて、秋口は助かったと思いつつ、彼に内心を見透かされた気がして、何だか不愉快な気分にもなった。
まるっきりの八つ当たりだと自覚していたので、辛うじて笑顔も作ったが。
「御幸さん来たら女の子たち喜びますよ、席、こっちです」
御幸を社員たちの集まる場所へ案内し、荷物を取ると、名残惜しむ女子社員たちを置いて、秋口は店を飛び出した。
店から会社まで小走りに進む。タクシーを使うほどの距離じゃない。秋口はすでにロックされている社員用の玄関をIDカードで通り抜け、まっさきに営業一課へと向かった。
業務用ファクシミリの受信済用紙を漁るが、それらしきものはない。営業時間中に受け取ったFAXは事務の社員が整理して担当の社員に渡すし、今日秋口がT社から連絡を受けた覚えはなかった。終業後に届いた通信の中にもT社からのものはない。
自分のデスクに駆け寄り、パソコンを立ち上げてメールチェックをするが、そこにも連絡は特になかった。
(ひょっとして)
思い当たり、秋口は青木のデスクに近づくと、悪いと思いながらも勝手にその上の書類を書き分けた。青木はあまり整理上手な方ではなく、必要なのかそうでないのかおそらく本人しかわからない書類が、適当に書類入れに突っ込まれていた。
「――あった」
商品と、ただ「ご担当者様」とだけ書かれたT社からのFAX。おそらく事務の社員が、青木の担当だと勘違いして振り分けてしまったのだろう。
焦燥する気分で確認すると、たしかに、殴り書きで仕様変更の指示が出ていた。
「普通口頭で確認するだろう」
ここにはいない担当者を罵り、そんな場合ではないと、秋口は急いで相手の会社に電話をかけた。しかし営業時間外のアナウンスが流れるだけで繋がらない。携帯電話も繋がらなかった。週末は金曜の夜から家族で旅行に出かけるとか話していたのに、愛想よく「羨ましいですね」なんて言った自分を秋口は思い出す。
「くそっ」
青木の椅子を蹴り上げ、FAX用紙を握り締めて秋口は営業一課を出た。
「佐山さん」
開発課の中に入り、ひとり残っている佐山に声を掛けると、佐山はちょうど電話中のようで、受話器を握ったまま秋口に片手を挙げて応えた。
「はい――はい、では、そのようにお願いいたします。遅くに申し訳ありません、失礼いたします」
電話を切った佐山の元に、秋口は苛立ちながら近づいた。
「FAX、ありましたよ。青木さんとこに」
「やっぱり。俺の方に流れてきたのに、秋口からは連絡ないから変だと思ってたんだ」
落ち着いた佐山の態度に、秋口はますます八つ当たり的に腹が立ってきた。
「担当者の名前くらい書けってんだ。大体、青木さんから引き継いだ時の挨拶で、連絡は全部メールでって念押ししておいたはずなのに」
「でもそれは、こっちの都合だろ。FAXが来たんなら、ちゃんと確認するべきだったんだ。ごめん、俺も昼間別の仕事にかかり切りだったから、こんな指示が出てると思わなくて」
申し訳なさそうな顔でそう言ってから、佐山はモニタの画面を指さした。
「部品のサイズを変えてもう一回図面引き直したから、秋口が確認してくれたらすぐ工場に再発注するよ」
「え、再発注って、でももう工場は終わって」
「さっき連絡したら、まだ担当の人が残ってて、仕事が詰まってるから明日機械回すつもりだったって。今日中にもう一回連絡する約束で待ってもらってるから、急ごう」
「……」
返事もなく黙り込んだ秋口に、佐山が少し首を傾げた。
「秋口?」
「それ、俺の仕事ですよね」
佐山から電話が来て、わずか二十分にも満たない。
自分があたふたと店から駆け戻ってきた間に、佐山が仕事相手にもう話をつけてきたことを、本当ならば感謝すべきなのはわかっていたが。
(俺だってそのくらい、できたのに)
よりによって『この』佐山にフォローされてしまったという事実が、いたく秋口の自尊心を傷つけた。
「あ――悪い、なるべく急いだ方がいいと思って、独断で連絡取ったんだ」
秋口の怒りを察して、咄嗟に申し訳なさそうな顔になる佐山の態度に、秋口はさらに苛立ってしまう。
明らかに自分のミスなのはわかっている。どんな手段であろうと取引相手からの連絡を見過ごしたことは、営業として致命的だろう。青木だって、T社の担当は寸前で仕様を変えるのが好きだから気をつけろと、わざわざ何度も念押ししていた。
わかっているのに、秋口はとても素直に礼を言う気分にはなれなかった。余計なことをしたと、庇わなくても自分がすぐにミスを取り返せたのにと、どうしても佐山を詰る方向に心が向いてしまう。
「ずいぶん手回しがいいんですね。もしかして、どうせ俺がミスするだろうって見越して待ち構えてました?」
「そんなわけないだろ。単に、俺の方が宮原さんとも工場ともつき合い長いし、やり方がわかってるだけだよ」
「俺はやり方がわかってなくてすみません。覚えておきますんで、これからは俺の許可なしに勝手なことしないで下さい。これじゃ急いで戻ってきた俺が馬鹿みたいじゃないか」
「……ごめん」
困り切った顔の佐山を見ていたら、もっとひどいことを言って泣き顔にでもさせてやりたいと、凶暴な衝動が秋口の中に湧き上がる。
(こんなこと言われて言い返しもしないなんて、俺のこと馬鹿にしてるに決まってる)
理不尽なことを言っているという罪悪感を隠すために、秋口はそれを佐山への苛立ちにすり替えた。
「……もう型は作ってあるらしいから、その損失分の計算も、できたら今日のうちに持って行きたいから」
俯き加減に佐山が言った。咄嗟にそのことに思い至らなかった自分を隠すため、応える秋口の言葉はひどく乱暴な調子になった。
「わかってますって。図面できたら、佐山さんもう帰っていいですよ。後は俺が全部やります」
「でもこれは、俺の仕事でもあるから」
「そんなに俺のこと信用できないんですか?」
「……」
「何なら全部佐山さんがやりますか? そうですよね、佐山さん俺より営業経験長いらしいし。自分でやる方が安心っていうのなら」
「わかった。じゃあ、先、帰るな」
耐えかねたように、佐山が秋口の言葉を遮って立ち上がった。秋口の方は見ず、プリンタを動かして図面を印刷している。
「何かあったら携帯、電話してくれ。何時でも待ってるから」
そう告げた佐山に応える気にならず、秋口はFAXを確認している素振りで無視した。
佐山が荷物をまとめ、自分の机から離れる。出口のところで気懸かりそうに振り返ったのが気配でわかったが、秋口はそれも無視した。
静かに足音が遠ざかっていく。秋口はひどく惨めな気分でそれを聞いていた。
◇◇◇
やり残したことがあるような気分で会社を出ると、まっすぐ自宅へ戻る気にもならず、佐山は何となく行き着けの料理屋へ足を向けた。
あまり広くも綺麗でもない、だが料理は絶品の定食屋。混み合っているのでカウンタ席へ回され、食欲はないけれど水だけというわけにもいかないので、味噌汁だけ頼んで店に妙な顔をされた。
(――さすがに)
カウンタに突っ伏し、細く息を吐き出す。
(応えたなあ……)
味噌汁がやってきても、手を着ける気にならず佐山はひたすらカウンタに額を押しつけた。後ろでは賑やかに笑いさざめく声が響いている。誰もいない部屋で夜を過ごす気にはなれず店に赴いたものの、周りの楽しげな話し声が聞こえてしまえば、自分だけ疎外されているようで無性に寂しい。
(無理矢理でも、秋口のところに居座ってやればよかったか)
取り返しがつかないくらい疎まれてしまえば、いっそもうその姿を見ようなんて気にもならないかもしれない。そんなことを思って、自分の後ろ向きさ加減を佐山はひとり嗤った。
誰かが隣に座る気配がして、こんなふうにカウンタに突っ伏していては他の客の邪魔になると、そう思ったのに佐山は億劫で起き上がる気力も湧いてこない。
「すみません、鮭定食と生」
「はーい」
聞こえた声に驚いて、佐山はやっと顔を上げた。隣には御幸がすました顔で座っていた。
「よ。味噌汁、冷めるぞ」
「御幸……何で」
御幸はおしぼりで手を拭きながら、佐山の顔を見て軽く肩を竦めた。
「飲み会、途中から顔出したんだけどさ。秋口がいなくなった後釜みたいな扱いってのも居心地悪くて、逃げてきたんだ。ろくにメシ喰えなかったからここに来てみたら、佐山がいたんだよ」
「そうだ、御幸、俺の夕飯買いに行ってくれてたんだよな。俺、おまえが帰ってくる前に出てきちゃって」
「食事は秋口に預けたぞ、会社戻るって言うから。折詰めもらわなかったか?」
「いや」
秋口がそんな荷物を持っていたかも、佐山には思い出せない。佐山が首を振ると、御幸が大仰に眉を顰めた。
「あいつ、俺の差し入れ横領しやがったな」
「ごめん、後で金」
「いいよ、もともと陣中見舞いで奢るつもりだったんだから」
御幸がポケットから煙草を取り出して咥え、佐山にも勧めてくれた。佐山はそれを受け取って一本唇に挟む。御幸がライターで火もつけてくれた。
煙草を吸って、親友の顔を見て、人心地つく。佐山はこのタイミングで御幸がやってきてくれた偶然に、心から感謝した。
「はい、生です」
店の女の子が生ビールを運んできて、それを受け取りながら、御幸が佐山の手許を見下ろす。
「おまえ、味噌汁と水だけ?」
「あんまり腹減ってなくて」
「せめて飲み物頼めよ、すみません、グレープフルーツジュースひとつ!」
御幸が勝手に佐山の分の飲み物を頼んで、すぐにやってきたそのグラスを佐山に勧めた。
「何かトラブルあったんだろ。秋口との仕事で」
秋口の携帯電話が繋がらなかったので、彼がいる店に向かった御幸と連絡を取った。秋口と話していた時、御幸もその場にいただろうから、うすうす事情は察しているのだろう。
「うん、ちょっとな、連絡ミスっていうか」
「秋口のミス?」
「っていうのか、どうなのか……」
佐山はかいつまんで御幸に状況を話した。
「だから、メールでって言ったのを無視してFAX一枚入れて、向こうが確認も取らなかったってことなんだけど」
「結局秋口の落ち度ってことだよな。連絡来たのを見過ごしたんだから」
「でも、俺の方にもFAXは来てたんだから、俺のミスでもあるだろ。そう思って、連絡取れるところには秋口に断らずに取っておいたんだけど」
「逆ギレされたか?」
「……」
黙り込んだ佐山に、御幸はそれを肯定と受け取って、軽く溜息をついた。
「タイミングもあったかなあ」
「タイミング?」
「いや、佐山から電話来る前、ちょっと秋口に釘刺しておいたんだよ、俺。あんまり佐山をいじめるなってさ」
驚いて顔を上げた佐山に、御幸が軽く苦笑する。
「いろいろキツイこと言われてただろ。俺の前でだっておまえへの当て擦り言ってるのに、あいつの性格からして、おまえの前では口噤むなんてことないだろうし」
「……根本的に、合わないみたいなんだよなあ」
ジュースのグラスを手に、佐山は深々と溜息をついた。
「俺は別に、秋口に何かした覚えもないんだけど。それであの態度なら、虫が好かないっていうか、そりが合わないっていうか、そういうことなんだろうな」
御幸は「秋口は男相手なら誰にでもそういう態度だから」と言っていたが、それにしたって自分への風当たりがきつすぎるように佐山は思う。
「話してると、秋口が苛々してくるのが空気でわかるんだよ。そうすると焦って、何とか場を和ませようとするんだけど空振って、泥沼っていうか」
「俺は雛川さんか秋口かっていうなら、雛川さんを推すな」
溜息混じりに話していた佐山は、さらりと友人の言った言葉の意味がよくわからず、彼のことをじっと見返してしまった。
御幸も頬杖をついて、佐山のことを眺めている。
「何でここで、そういう選択肢なんだ?」
「雛川さんも、佐山のよさをちゃんと理解しないで、他の男に走ったような人だけどさ。それでも秋口が相手っていうよりは、まだしも友人として応援できる」
「……御幸?」
妙な風に、心臓が跳ね上がる。自分の気持ちを見透かしたような御幸の言葉に、佐山は緊張して、顔を強張らせた。
「佐山はもう雛川さんに未練がないみたいだから、あんまり意味のない人選かもしれないけど」
「御幸、おまえ」
「気づいちゃうんだよなあ、これが」
ひとりごとのように御幸が言った時、店の女の子が鮭定食を運んできて、御幸の前に置いた。割り箸を割って、「いただきます」と御幸が丁寧に両手を合わせる。
「当たってるだろ?」
「……何でわかったんだ」
御幸に自分の気持ちを話した覚えも、言い当てられるほど露骨な行動をした覚えもない。秋口と言葉を交わすようになったのだってここ最近のことだし、あんまり驚いてしまって、佐山は誤魔化そうという気分もなくなってしまった。
「何年友達やってると思ってんだよ。ずっと様子おかしかっただろ、急に考え込んだり、溜息ついたり、物憂げな感じだったり。だからきっとこれは恋煩いに違いないと思って、こっそり見守ってたんだよ」
「俺、そんなにわかりやすかったか?」
だとしたら恥ずかしい。佐山は何だか消え入りたい気持ちになった。万が一秋口自身や周囲の人間にまで自分の気持ちが伝わってしまっているのなら、どんな顔をして会社に行けばいいのか、もうわからない。
「いや。多分他の奴は気づきもしないだろ、俺だからわかったんだよ」
「……どういうところで?」
「視線、かな。廊下や休憩所でおまえの姿みかけた時、食堂でとか、ずっと動かないでどこかを見てるとしたら、かならずおまえの視線の先に秋口がいるんだよ。だから、ピンと来た」
「でもそんな、たまたま目に止まっただけかもしれないじゃないか。秋口は目立つし」
「誰が相手でも、佐山があんなふうに誰かをみつめることなんてこれまでなかったよ。あんなに美人の雛川さんと恋人同士になった時だってさ」
「……」
沙和子との時は、彼女の方から佐山に近づいて、それでつき合うようになった。たとえ彼女を社内でみかけたとしても、仕事中だからと、簡単に意識の外へ遣ることができた。
なのに秋口だけは駄目だった。声が聞こえると、姿が視界に引っかかると、どうしても視線で追ってしまう。あまり見ていては変に思われると、必死に目を逸らしている間も、意識しすぎて不自然な態度になりやしないかと不安だった。
「それにそもそも、顔がさ。何ていうか、恋してるんだよな」
「は……恥ずかしいな」
恋してる、なんて表現をされるなんて思ってもみなかった。佐山は何となく顔を赤らめ、グレープフルーツジュースを呷った。
「よりによって何で秋口かって、思わずにいられないわけだけど。親友としては」
「……俺もそう思うよ」
御幸が呆れる気持ちはわかる。男の目から見て、秋口の態度は最悪だ。生意気で女たらし、容姿がいいのを鼻にかけて、目上を相手に嫌味を言って平然としている。
よりによってどうして自分が秋口を好きなのかなんて、やっぱり未だに佐山自身にもわからないのだ。
「今日、トラブっただろ。それで俺はフォローしたつもりなんだけど、秋口は怒ってさ。ああ、こいつはまだまだ子供なんだなあと思ったし、責められたことは理不尽だと思ったのに――そういう相手にがっかりするとか、怒ったりするっていうより、嫌われて悲しいとか、そういう気持ちばっかり先に立つんだよな……」
グラスを額に押しつけ、冷たさを味わいながら佐山は目を閉じた。
今日が出会って一番ひどいことを言われた気がする。トロいだの貧相だの声に出したり態度で言われた時も、まだ溜息をつく程度ですんだのに、今は何だか泣けてきそうだ。
「佐山は、どうしたいんだ?」
御幸に訊ねられ、佐山は目を閉じたまま応えた。
「どうって?」
「だから、秋口とさ。好きになったのなら、気持ちを伝えるとか、それともあいつの性格に呆れて見放して嫌いになるとか」
「……どっちも、ピンと来ないなあ」
告白なんてしたところで、一笑に付されるか、気味が悪いと露骨に嫌悪を示されるか。想像するだに気が遠くなる。
いっそ嫌いになれれば楽だと思うのに、それもやっぱり不可能な気が、佐山にはするのだ。
「本当にどうして、秋口なんだろう。別に今まで男に興味持ったことなんて一度もないんだ。可愛くて気の利く優しい女の子なら会社の中だってたくさんいるだろうし、そういう子と家庭築くのが夢なのに、秋口が相手なんて不毛すぎる。どうやったら秋口のこと考えずにすむのか、誰かに教えてほしいよ」
「ま――どうやったら嫌いになれるかとか、考えちゃう時点でもう無理なんだろうけどな」
「……本当にひどいこと言われるんだ。大したことじゃないって自分に言い聞かせてたけど、やっぱりひどいこと言われてるんだよ。侮られてるのが嫌ってほどわかる。普通なら殴ったって、みんな俺の味方するだろうなってわかるくらいだ。なのに俺は、殴ろうなんて気も起こさずに、ただしょんぼりしてるんだよ。馬鹿げてる」
「理屈で計れるなら、面倒なんてひとつもないよ、佐山。美人で優しくてついでに仕事もできて、って相手をみんなが好きになるなら、それこそ世の中の男全員が雛川さんに結婚申し込むだろうし」
そう、沙和子は誰が見てもいい女だ。
(でも……沙和子の時は、こんなふうにならなかった)
相手を思って眠れない夜があるとか、何をしていても気を抜けばその人のことを考えてしまうとか、学生でもないのにそんな事態が訪れるなんて、佐山は知らなかった。
「秋口に、気持ちに応えて欲しいなんて思ってないんだ。そんなところ想像もつかないし」
「本当に?」
「え?」
佐山は瞑っていた瞼を開き、傍らの御幸を見遣った。御幸がじっと佐山のことをみていた。
「本当に、考えたことないのか? 好きになったんだから相手に想い返して欲しいとか、自分のこと考えて欲しいとか、無理だって思ってても、どこかで想像したことないのか? 一度も?」
「……」
それは佐山が必死になって蓋をしてきた『欲』だ。
気づけば辛い思いをするから、何も望んでいないし、何も求めていないと自分に言い聞かせていた願いだ。
「やめてくれよ、そんなこと、考えるようになったらますます目の前真っ暗だ」
「一生に一度くらいなら、そういう体験したっていいと思うぜ、俺は」
佐山は困って黙り込んだ。御幸が焚きつけるでもない、穏やかな口調で続ける。
「佐山がそういうの避けて、平凡で穏やかな家庭作りたいって思ってるのは、知ってるけどさ」
「……御幸」
「せっかく好きになったのに、自分からなかったことにする必要はないと思うんだよ。何ていうか……雛川さんとつき合ってた時、おまえ、必死だっただろ。ちゃんと結婚して、ちゃんと家庭作って、倖せにならなきゃって、それは普通に、誰でも自然と望むことなはずなのに、使命感っていうか、仕事みたいな感じでさ。あんな美人とつき合ってるのに、倖せな感じが全然しなかった。一生懸命倖せになろうとしてるのが、見てて俺の方も辛かったんだよ」
「……」
「今のおまえも充分辛そうだけど、でも悪くはないぜ。義務感で幸福掴もうとして不幸になるより、不幸のために不幸になる方が、よっぽどちゃんと生きてるって感じがする」
「どっちにしろ不幸になるのかよ」
御幸の言い種に、佐山はちょっと笑ってしまった。御幸も笑っていた。
「だって相手、秋口だぜ」
「だよなあ……」
考えると、途方もない気分になる。秋口に自分の気持ちが通じて、想い返してもらうことを、本当は気持ちの奥底で望まないわけではないのに想像がつかない。そういう自分たちの姿に。
「諦めきれるんなら、いいんだ。俺もあいつはお勧めしない。でも、さ。万が一、どうしても、忘れることができないっていうなら」
笑いながら、でもまじめな声で、友人が優しく佐山を唆す。
「人生一回きりって覚悟で、言い寄ったっていいと思うんだ。好きになって簡単に『やっぱり嫌い』ってなれるくらいなら、そもそもあんな面倒なの好きにはならなかっただろ」
「でも、もし気持ち伝えたとしたって、大笑いして終わりだと思うぞ」
「『今は』だろ。秋口は絶対佐山のこと誤解してるから、単純に、それで終わるのも俺は口惜しいし。せいぜい、おまえの男ぶりをあいつに見せつけてやれよ、それだけで少しは状況が変わってくると思うし」
「そうかな……」
「そうさ」
「優しいな、御幸は」
「逆だろ、優しかったら、みすみす茨の道を親友に踏ませないって」
「茨か……」
呟いた佐山に、御幸が少し慌てたようにつけ足した。
「あ、言っておくけど、相手が秋口ってことだけだからな」
「わかってるよ」
苦笑して、佐山は頷く。御幸が、たとえ自分が同性を好きな人間であったとしても、それを嘲笑うような男ではないことは佐山もよく知っている。
「変に未練が残ってずっと辛い思いするより、ズバッと突き進んでズバッと振られて来い」
「やっぱり振られるんじゃないか」
冗談めかした御幸の言葉に笑って、佐山はずいぶんと自分の心が軽くなっていることに気づいた。黙ってひとりで思い悩んでいた時よりも、御幸に笑ってもらえてすっきりする。
(そうだよな、悶々と『嫌いになれたら』なんて思うより)
好きなんだから仕方ないと、諦めてしまう方が前向きだ。
「ありがとうな、御幸」
心から感謝して佐山がそう言うと、御幸はちょっと気障っぽく肩を竦めただけで、何も応えず定食の続きを食べ始めた。
あまり広くも綺麗でもない、だが料理は絶品の定食屋。混み合っているのでカウンタ席へ回され、食欲はないけれど水だけというわけにもいかないので、味噌汁だけ頼んで店に妙な顔をされた。
(――さすがに)
カウンタに突っ伏し、細く息を吐き出す。
(応えたなあ……)
味噌汁がやってきても、手を着ける気にならず佐山はひたすらカウンタに額を押しつけた。後ろでは賑やかに笑いさざめく声が響いている。誰もいない部屋で夜を過ごす気にはなれず店に赴いたものの、周りの楽しげな話し声が聞こえてしまえば、自分だけ疎外されているようで無性に寂しい。
(無理矢理でも、秋口のところに居座ってやればよかったか)
取り返しがつかないくらい疎まれてしまえば、いっそもうその姿を見ようなんて気にもならないかもしれない。そんなことを思って、自分の後ろ向きさ加減を佐山はひとり嗤った。
誰かが隣に座る気配がして、こんなふうにカウンタに突っ伏していては他の客の邪魔になると、そう思ったのに佐山は億劫で起き上がる気力も湧いてこない。
「すみません、鮭定食と生」
「はーい」
聞こえた声に驚いて、佐山はやっと顔を上げた。隣には御幸がすました顔で座っていた。
「よ。味噌汁、冷めるぞ」
「御幸……何で」
御幸はおしぼりで手を拭きながら、佐山の顔を見て軽く肩を竦めた。
「飲み会、途中から顔出したんだけどさ。秋口がいなくなった後釜みたいな扱いってのも居心地悪くて、逃げてきたんだ。ろくにメシ喰えなかったからここに来てみたら、佐山がいたんだよ」
「そうだ、御幸、俺の夕飯買いに行ってくれてたんだよな。俺、おまえが帰ってくる前に出てきちゃって」
「食事は秋口に預けたぞ、会社戻るって言うから。折詰めもらわなかったか?」
「いや」
秋口がそんな荷物を持っていたかも、佐山には思い出せない。佐山が首を振ると、御幸が大仰に眉を顰めた。
「あいつ、俺の差し入れ横領しやがったな」
「ごめん、後で金」
「いいよ、もともと陣中見舞いで奢るつもりだったんだから」
御幸がポケットから煙草を取り出して咥え、佐山にも勧めてくれた。佐山はそれを受け取って一本唇に挟む。御幸がライターで火もつけてくれた。
煙草を吸って、親友の顔を見て、人心地つく。佐山はこのタイミングで御幸がやってきてくれた偶然に、心から感謝した。
「はい、生です」
店の女の子が生ビールを運んできて、それを受け取りながら、御幸が佐山の手許を見下ろす。
「おまえ、味噌汁と水だけ?」
「あんまり腹減ってなくて」
「せめて飲み物頼めよ、すみません、グレープフルーツジュースひとつ!」
御幸が勝手に佐山の分の飲み物を頼んで、すぐにやってきたそのグラスを佐山に勧めた。
「何かトラブルあったんだろ。秋口との仕事で」
秋口の携帯電話が繋がらなかったので、彼がいる店に向かった御幸と連絡を取った。秋口と話していた時、御幸もその場にいただろうから、うすうす事情は察しているのだろう。
「うん、ちょっとな、連絡ミスっていうか」
「秋口のミス?」
「っていうのか、どうなのか……」
佐山はかいつまんで御幸に状況を話した。
「だから、メールでって言ったのを無視してFAX一枚入れて、向こうが確認も取らなかったってことなんだけど」
「結局秋口の落ち度ってことだよな。連絡来たのを見過ごしたんだから」
「でも、俺の方にもFAXは来てたんだから、俺のミスでもあるだろ。そう思って、連絡取れるところには秋口に断らずに取っておいたんだけど」
「逆ギレされたか?」
「……」
黙り込んだ佐山に、御幸はそれを肯定と受け取って、軽く溜息をついた。
「タイミングもあったかなあ」
「タイミング?」
「いや、佐山から電話来る前、ちょっと秋口に釘刺しておいたんだよ、俺。あんまり佐山をいじめるなってさ」
驚いて顔を上げた佐山に、御幸が軽く苦笑する。
「いろいろキツイこと言われてただろ。俺の前でだっておまえへの当て擦り言ってるのに、あいつの性格からして、おまえの前では口噤むなんてことないだろうし」
「……根本的に、合わないみたいなんだよなあ」
ジュースのグラスを手に、佐山は深々と溜息をついた。
「俺は別に、秋口に何かした覚えもないんだけど。それであの態度なら、虫が好かないっていうか、そりが合わないっていうか、そういうことなんだろうな」
御幸は「秋口は男相手なら誰にでもそういう態度だから」と言っていたが、それにしたって自分への風当たりがきつすぎるように佐山は思う。
「話してると、秋口が苛々してくるのが空気でわかるんだよ。そうすると焦って、何とか場を和ませようとするんだけど空振って、泥沼っていうか」
「俺は雛川さんか秋口かっていうなら、雛川さんを推すな」
溜息混じりに話していた佐山は、さらりと友人の言った言葉の意味がよくわからず、彼のことをじっと見返してしまった。
御幸も頬杖をついて、佐山のことを眺めている。
「何でここで、そういう選択肢なんだ?」
「雛川さんも、佐山のよさをちゃんと理解しないで、他の男に走ったような人だけどさ。それでも秋口が相手っていうよりは、まだしも友人として応援できる」
「……御幸?」
妙な風に、心臓が跳ね上がる。自分の気持ちを見透かしたような御幸の言葉に、佐山は緊張して、顔を強張らせた。
「佐山はもう雛川さんに未練がないみたいだから、あんまり意味のない人選かもしれないけど」
「御幸、おまえ」
「気づいちゃうんだよなあ、これが」
ひとりごとのように御幸が言った時、店の女の子が鮭定食を運んできて、御幸の前に置いた。割り箸を割って、「いただきます」と御幸が丁寧に両手を合わせる。
「当たってるだろ?」
「……何でわかったんだ」
御幸に自分の気持ちを話した覚えも、言い当てられるほど露骨な行動をした覚えもない。秋口と言葉を交わすようになったのだってここ最近のことだし、あんまり驚いてしまって、佐山は誤魔化そうという気分もなくなってしまった。
「何年友達やってると思ってんだよ。ずっと様子おかしかっただろ、急に考え込んだり、溜息ついたり、物憂げな感じだったり。だからきっとこれは恋煩いに違いないと思って、こっそり見守ってたんだよ」
「俺、そんなにわかりやすかったか?」
だとしたら恥ずかしい。佐山は何だか消え入りたい気持ちになった。万が一秋口自身や周囲の人間にまで自分の気持ちが伝わってしまっているのなら、どんな顔をして会社に行けばいいのか、もうわからない。
「いや。多分他の奴は気づきもしないだろ、俺だからわかったんだよ」
「……どういうところで?」
「視線、かな。廊下や休憩所でおまえの姿みかけた時、食堂でとか、ずっと動かないでどこかを見てるとしたら、かならずおまえの視線の先に秋口がいるんだよ。だから、ピンと来た」
「でもそんな、たまたま目に止まっただけかもしれないじゃないか。秋口は目立つし」
「誰が相手でも、佐山があんなふうに誰かをみつめることなんてこれまでなかったよ。あんなに美人の雛川さんと恋人同士になった時だってさ」
「……」
沙和子との時は、彼女の方から佐山に近づいて、それでつき合うようになった。たとえ彼女を社内でみかけたとしても、仕事中だからと、簡単に意識の外へ遣ることができた。
なのに秋口だけは駄目だった。声が聞こえると、姿が視界に引っかかると、どうしても視線で追ってしまう。あまり見ていては変に思われると、必死に目を逸らしている間も、意識しすぎて不自然な態度になりやしないかと不安だった。
「それにそもそも、顔がさ。何ていうか、恋してるんだよな」
「は……恥ずかしいな」
恋してる、なんて表現をされるなんて思ってもみなかった。佐山は何となく顔を赤らめ、グレープフルーツジュースを呷った。
「よりによって何で秋口かって、思わずにいられないわけだけど。親友としては」
「……俺もそう思うよ」
御幸が呆れる気持ちはわかる。男の目から見て、秋口の態度は最悪だ。生意気で女たらし、容姿がいいのを鼻にかけて、目上を相手に嫌味を言って平然としている。
よりによってどうして自分が秋口を好きなのかなんて、やっぱり未だに佐山自身にもわからないのだ。
「今日、トラブっただろ。それで俺はフォローしたつもりなんだけど、秋口は怒ってさ。ああ、こいつはまだまだ子供なんだなあと思ったし、責められたことは理不尽だと思ったのに――そういう相手にがっかりするとか、怒ったりするっていうより、嫌われて悲しいとか、そういう気持ちばっかり先に立つんだよな……」
グラスを額に押しつけ、冷たさを味わいながら佐山は目を閉じた。
今日が出会って一番ひどいことを言われた気がする。トロいだの貧相だの声に出したり態度で言われた時も、まだ溜息をつく程度ですんだのに、今は何だか泣けてきそうだ。
「佐山は、どうしたいんだ?」
御幸に訊ねられ、佐山は目を閉じたまま応えた。
「どうって?」
「だから、秋口とさ。好きになったのなら、気持ちを伝えるとか、それともあいつの性格に呆れて見放して嫌いになるとか」
「……どっちも、ピンと来ないなあ」
告白なんてしたところで、一笑に付されるか、気味が悪いと露骨に嫌悪を示されるか。想像するだに気が遠くなる。
いっそ嫌いになれれば楽だと思うのに、それもやっぱり不可能な気が、佐山にはするのだ。
「本当にどうして、秋口なんだろう。別に今まで男に興味持ったことなんて一度もないんだ。可愛くて気の利く優しい女の子なら会社の中だってたくさんいるだろうし、そういう子と家庭築くのが夢なのに、秋口が相手なんて不毛すぎる。どうやったら秋口のこと考えずにすむのか、誰かに教えてほしいよ」
「ま――どうやったら嫌いになれるかとか、考えちゃう時点でもう無理なんだろうけどな」
「……本当にひどいこと言われるんだ。大したことじゃないって自分に言い聞かせてたけど、やっぱりひどいこと言われてるんだよ。侮られてるのが嫌ってほどわかる。普通なら殴ったって、みんな俺の味方するだろうなってわかるくらいだ。なのに俺は、殴ろうなんて気も起こさずに、ただしょんぼりしてるんだよ。馬鹿げてる」
「理屈で計れるなら、面倒なんてひとつもないよ、佐山。美人で優しくてついでに仕事もできて、って相手をみんなが好きになるなら、それこそ世の中の男全員が雛川さんに結婚申し込むだろうし」
そう、沙和子は誰が見てもいい女だ。
(でも……沙和子の時は、こんなふうにならなかった)
相手を思って眠れない夜があるとか、何をしていても気を抜けばその人のことを考えてしまうとか、学生でもないのにそんな事態が訪れるなんて、佐山は知らなかった。
「秋口に、気持ちに応えて欲しいなんて思ってないんだ。そんなところ想像もつかないし」
「本当に?」
「え?」
佐山は瞑っていた瞼を開き、傍らの御幸を見遣った。御幸がじっと佐山のことをみていた。
「本当に、考えたことないのか? 好きになったんだから相手に想い返して欲しいとか、自分のこと考えて欲しいとか、無理だって思ってても、どこかで想像したことないのか? 一度も?」
「……」
それは佐山が必死になって蓋をしてきた『欲』だ。
気づけば辛い思いをするから、何も望んでいないし、何も求めていないと自分に言い聞かせていた願いだ。
「やめてくれよ、そんなこと、考えるようになったらますます目の前真っ暗だ」
「一生に一度くらいなら、そういう体験したっていいと思うぜ、俺は」
佐山は困って黙り込んだ。御幸が焚きつけるでもない、穏やかな口調で続ける。
「佐山がそういうの避けて、平凡で穏やかな家庭作りたいって思ってるのは、知ってるけどさ」
「……御幸」
「せっかく好きになったのに、自分からなかったことにする必要はないと思うんだよ。何ていうか……雛川さんとつき合ってた時、おまえ、必死だっただろ。ちゃんと結婚して、ちゃんと家庭作って、倖せにならなきゃって、それは普通に、誰でも自然と望むことなはずなのに、使命感っていうか、仕事みたいな感じでさ。あんな美人とつき合ってるのに、倖せな感じが全然しなかった。一生懸命倖せになろうとしてるのが、見てて俺の方も辛かったんだよ」
「……」
「今のおまえも充分辛そうだけど、でも悪くはないぜ。義務感で幸福掴もうとして不幸になるより、不幸のために不幸になる方が、よっぽどちゃんと生きてるって感じがする」
「どっちにしろ不幸になるのかよ」
御幸の言い種に、佐山はちょっと笑ってしまった。御幸も笑っていた。
「だって相手、秋口だぜ」
「だよなあ……」
考えると、途方もない気分になる。秋口に自分の気持ちが通じて、想い返してもらうことを、本当は気持ちの奥底で望まないわけではないのに想像がつかない。そういう自分たちの姿に。
「諦めきれるんなら、いいんだ。俺もあいつはお勧めしない。でも、さ。万が一、どうしても、忘れることができないっていうなら」
笑いながら、でもまじめな声で、友人が優しく佐山を唆す。
「人生一回きりって覚悟で、言い寄ったっていいと思うんだ。好きになって簡単に『やっぱり嫌い』ってなれるくらいなら、そもそもあんな面倒なの好きにはならなかっただろ」
「でも、もし気持ち伝えたとしたって、大笑いして終わりだと思うぞ」
「『今は』だろ。秋口は絶対佐山のこと誤解してるから、単純に、それで終わるのも俺は口惜しいし。せいぜい、おまえの男ぶりをあいつに見せつけてやれよ、それだけで少しは状況が変わってくると思うし」
「そうかな……」
「そうさ」
「優しいな、御幸は」
「逆だろ、優しかったら、みすみす茨の道を親友に踏ませないって」
「茨か……」
呟いた佐山に、御幸が少し慌てたようにつけ足した。
「あ、言っておくけど、相手が秋口ってことだけだからな」
「わかってるよ」
苦笑して、佐山は頷く。御幸が、たとえ自分が同性を好きな人間であったとしても、それを嘲笑うような男ではないことは佐山もよく知っている。
「変に未練が残ってずっと辛い思いするより、ズバッと突き進んでズバッと振られて来い」
「やっぱり振られるんじゃないか」
冗談めかした御幸の言葉に笑って、佐山はずいぶんと自分の心が軽くなっていることに気づいた。黙ってひとりで思い悩んでいた時よりも、御幸に笑ってもらえてすっきりする。
(そうだよな、悶々と『嫌いになれたら』なんて思うより)
好きなんだから仕方ないと、諦めてしまう方が前向きだ。
「ありがとうな、御幸」
心から感謝して佐山がそう言うと、御幸はちょっと気障っぽく肩を竦めただけで、何も応えず定食の続きを食べ始めた。
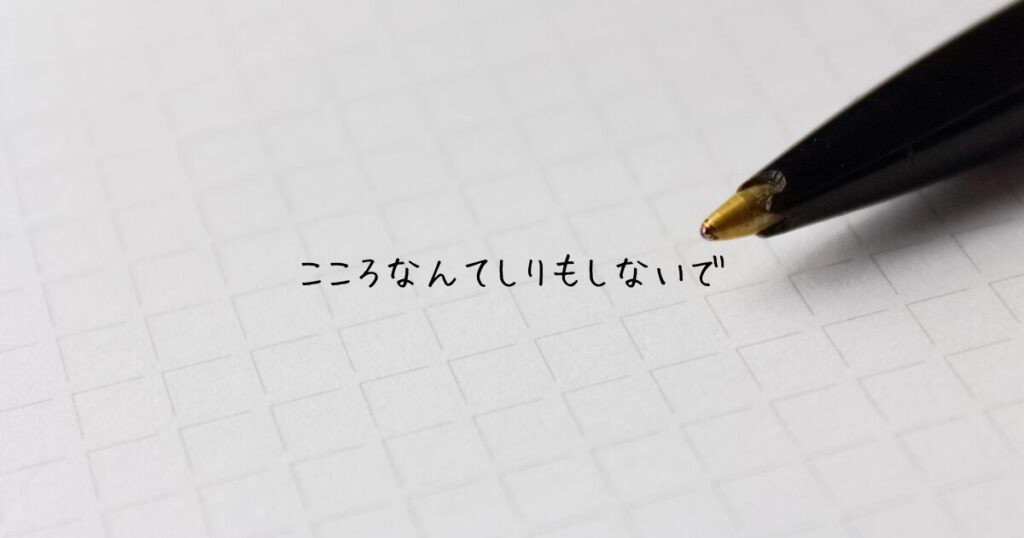
サラリーマン×サラリーマン

商業誌番外編

商業誌番外編

商業誌番外編
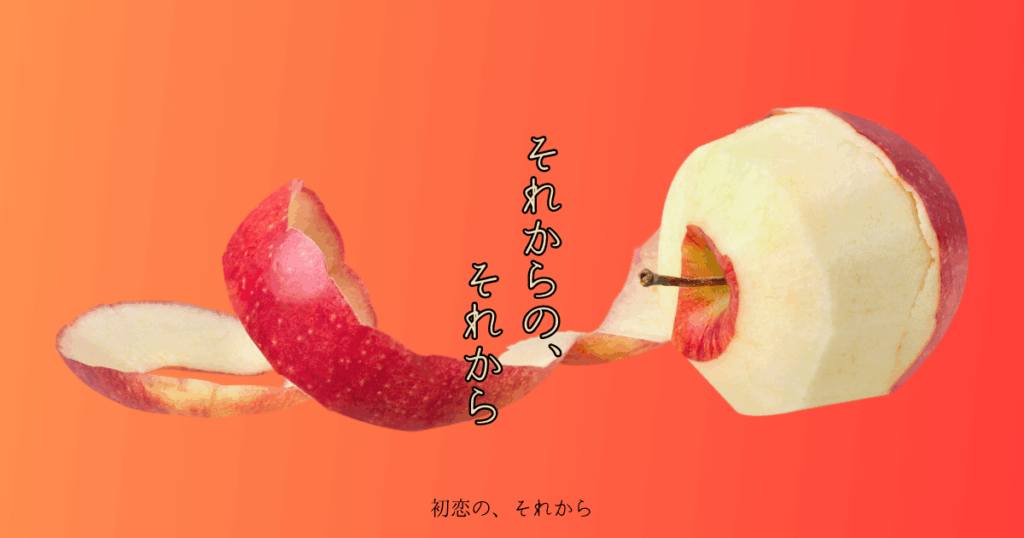
商業誌番外編
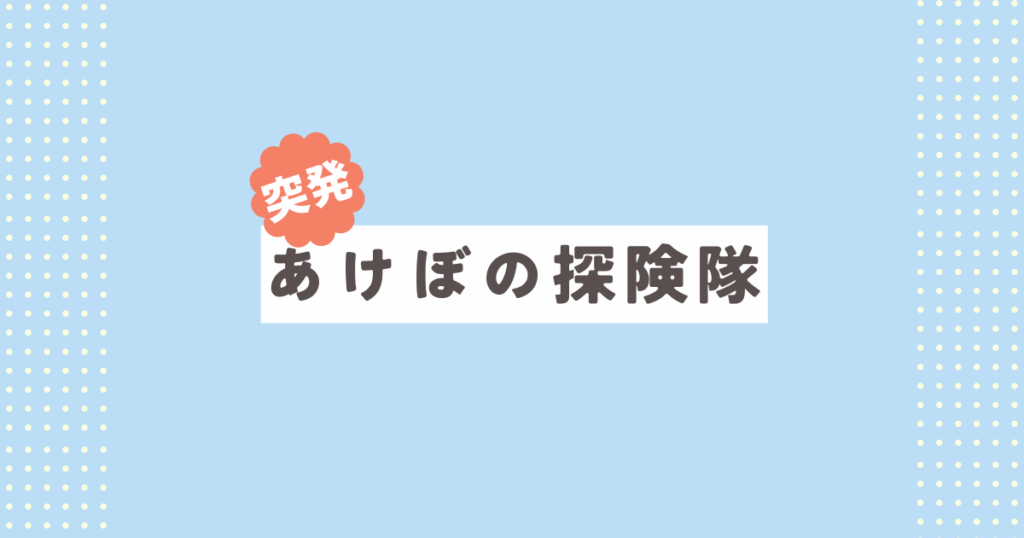
同人誌シリーズ番外編

高校生の恋未満読み切り