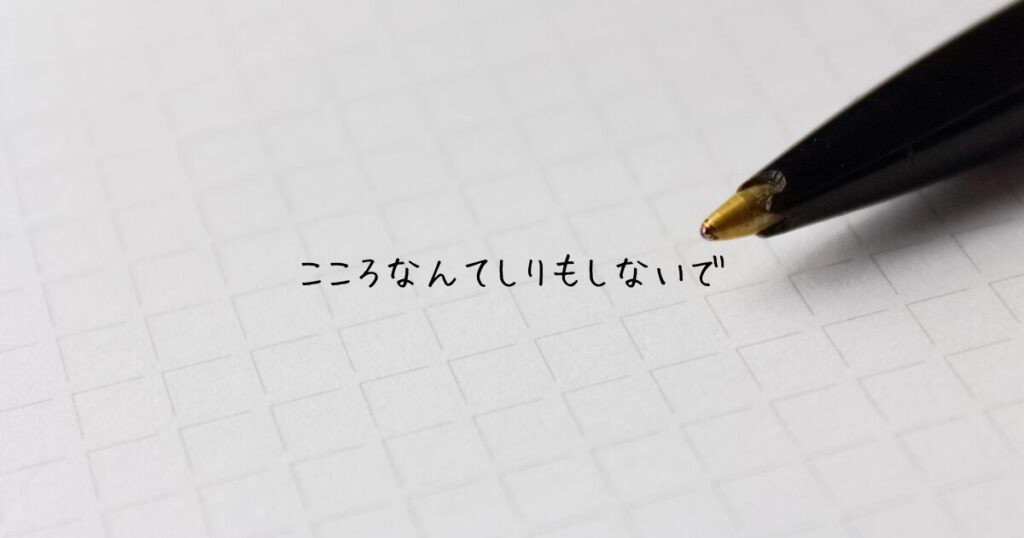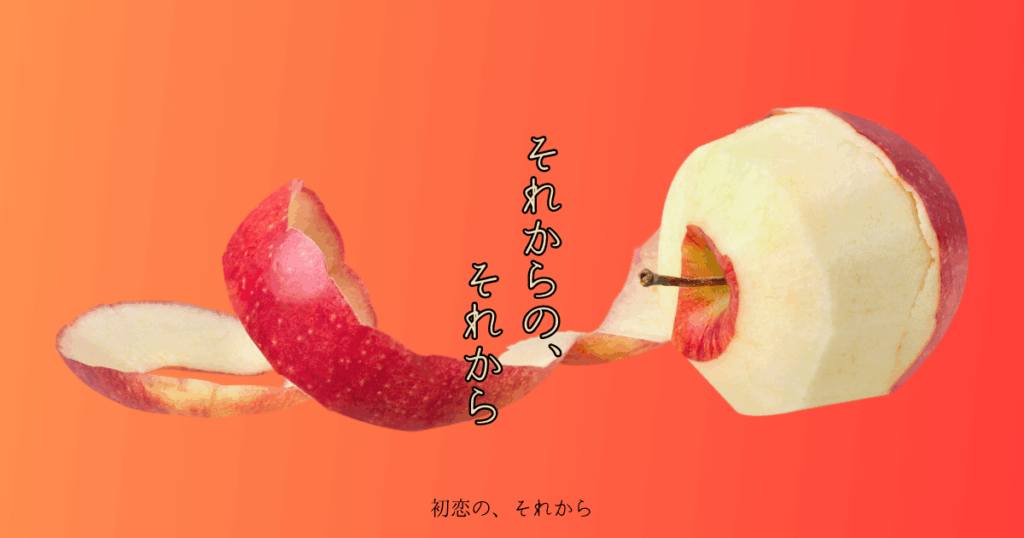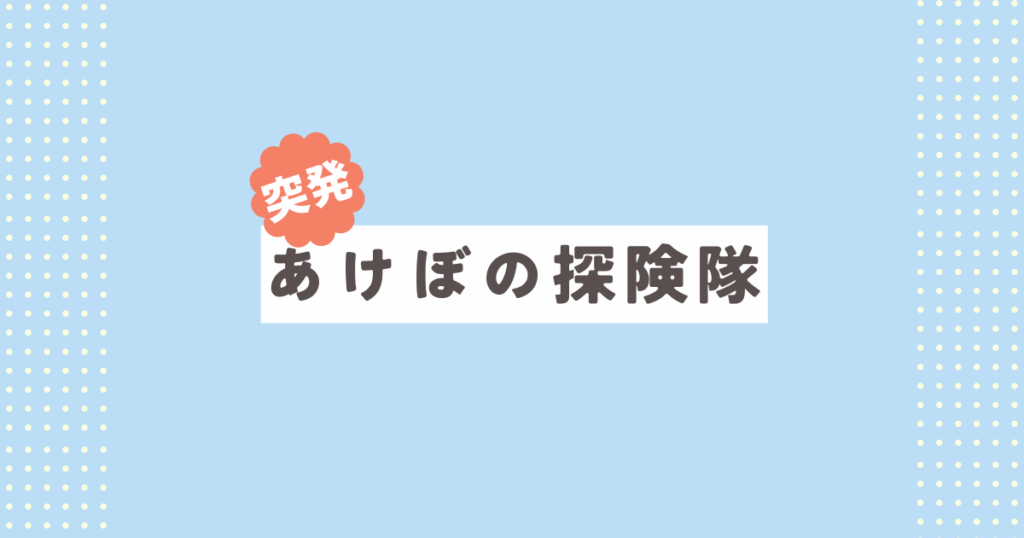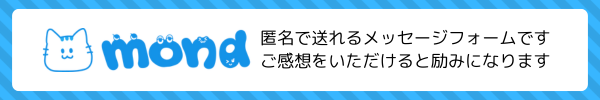しかし、佐山のところには、何かというと秋口が姿を見せていた。
「じゃ、この分向こうさんに見せますから、いいですね」
秋口に見せられた書類を一瞥だけして、佐山は頷く。
「それくらいなら、秋口の独断で構わないから」
電話やメールでも構わないような用件なのに、秋口はいちいち開発課を訪れては佐山に目視で確認を取った。
秋口と仕事をすることになってから三日、日に二度は秋口が佐山の元を訪れる。
正直佐山は困惑していた。好きな男にしょっちゅう会えるのが嬉しいなどという単純なものではない。秋口が来れば緊張するし、緊張していることに気づかれでもしたら情けないので、できれば会いたくはないのだ。
遠くから眺めているくらいがちょうどよかった。何というか、面倒なのだ。相手の一挙手一投足で一喜一憂するなんて、学生時代でもあるまいし。
「引き継ぎはちゃんと終わったんだろ。やり方は青木さんに合わせてくれればいいし」
「センパイから引き継いだ仕事、失敗したら申し訳が立ちませんので」
あくまできちんと書類を確認させようとする秋口に、佐山は少し意外な気分になった。
(結構、まじめなんだな)
秋口の仕事ぶりを目の当たりにしたことはないので、イメージの問題だが、佐山はもう少し彼が軽く、簡単に仕事をしていると思っていた。いい加減という意味ではなく、さらっとこなしている印象があったのだ。
「秋口ももう二年目だし、いつも営業を信用して任せることにしてるから」
あまり細かくやっていたら身が保たないだろうと、相手のまじめさを心配してそう言った佐山を見下ろし、秋口は物分かりの悪い子供をあやすような笑顔で別の書類を差し出した。
「俺の仕事はもちろん俺が責任持ちますけど、佐山さんと仕事するのは初めてですから、細かいところまで確認しておかないと不安なんですよ」
「……あ、そう……」
つまり、こっちの仕事が信用できないと、そういうことらしい。
佐山はかすかに鼻白みつつ、書類を受け取った。途中で加わった変更点のみならず、納期やら、商品に対する先方の指定やら、今さら確認するまでもない基本的なことばかりが書かれている。
(まあ、最初だし)
秋口がそういうやり方をするタイプなら、仕方ない。佐山は開発課で四年働いているが、その仕事が信用できないと言われるのなら信用してもらえるまで相手に従うだけだ。
しかし自分が相手ならともかく、他の、たとえばもっとキャリアのある社員を相手にこれをやったら馬鹿にされたと激怒を買うだけではないだろうか。特にここの開発課は、職人気質のスタッフが揃っていて、その分プライドの高い人間も多い。心配になって、佐山は秋口を見上げた。
「秋口、いつもこういう細かいところまで、最初ならともかく途中でも確認取ってるのか?」
「いえ?」
あっさり否定され、佐山は少々肩透かしを喰った。
「佐山さん、ちょっとトロそう、いや鈍そう、いや、マイペースそうなんで。他人に足を引っ張られて仕事失敗したりするの、嫌なんですよね、俺」
笑顔でそんなことを言う。
佐山は秋口につられて笑った。ひどい言い種に、冗談なのかと思ったが、特にオチも入らない。
トロそう、などと面と向かって他人に言われたのは、生まれて初めての経験だった。
「営業ってね、大変なんですよ、他人の失敗も自分の失敗として謝らなきゃいけないでしょ」
そう言ってから、秋口は今さら気づいたように「あ」と眉を上げた。
「なんて、営業やったことある佐山さんがわからないはずないですよね、すみません」
「いやー……」
何と答えたものか。
ひたすら愛想笑いを浮かべる自分を見下ろす秋口の目が、次第に軽蔑の色を帯びたものになるのが、佐山にもわかった。
でもどうしようもない。
「それとも、わかんないから営業クビになったのかな」
(……ひょっとしなくても)
佐山は喉が渇いて仕方がなくて、デスクの上に置いたミネラルウォーターを口に運んだ。
(俺は、秋口に嫌われてないか?)
初対面の時から、テンポの遅さに苛立たれているのはわかった。きっと秋口は何をするにも回転の速いタイプなのだろう。佐山は自分が特別テンポの遅い方だとは思わないが、秋口が早いのだから、彼の基準で見れば遅いということになるのか。
「まあ……秋口が納得できるようにやりたいなら、合わせるけど」
受け取った書類に目を通し、それを返しながら佐山が秋口を見上げると、何だか呆れたような眼差しを向けられてしまった。
「どうかしたか?」
「いや。合わせていただけるなら、ありがたいですよ」
多分何か、反駁した方がいい。
そうは思ったが、じゃあ何をどう言えばいいのか佐山が迷っているうち、秋口は書類を手にさっさと開発課から出て行ってしまった。
「……」
かすかに、佐山は溜息をつく。
(担当、青木さんに戻らないかな)
どうも秋口とは噛み合わない自分がもどかしいし、情けない。
(遠くにありて思うもの――っていうのは)
無意味に、目の前のパソコンの画面上、マウスのポインタを動かしてそれを眺めてみたりする。
(秋口のことだよなあ)
離れたところで眺めていたり、ふとした時に「秋口はどうしているかな」などと考えたりする分には、それなりにしあわせなのだが。
近くで会って仕事の話をすれば、さっきの調子だ。笑顔で侮られている。そういう印象。
けれども、なるべく遠くにあって欲しいと思いつつ、会えて嬉しいと思う自分の気持ちも否定できず、佐山には複雑だ。
「めんどくさいなあ」
ぼやき、佐山はもう一度溜息をついた。
昼休み、大抵佐山は社員食堂を使った。安くてメニューも豊富だし、割合美味い。コンビニ弁当よりは体にもよさそうだ。
それで佐山が日替わり定食を手に空いた席を捜していると、先に座っていた秋口に声を掛けられた。
「あれ、佐山さんも今飯ですか。よかったらこっち、来ません?」
まるで昔からの知人のように親しげに話しかけてくる秋口の周りは、おそらく営業部だけではない、あちこちの部署の女子社員が取り囲んでいる。まるで餌に群がる蟻のようだとぼんやり感想を浮かべつつ、佐山は苦笑して首を横に振った。
「いや、向こう、空いてるから」
佐山は窓際の方の席を指さした。秋口たちは食堂の真ん中辺りを占拠していて、実に目立つ。この中に入っていく度胸は佐山にはなかった。
逃げるように秋口のそばから離れ、隅っこの席に落ち着くと、佐山はほっと息を吐いた。どんな顔をして、秋口のそばを取り囲む女子社員と一緒に、秋口の近くで食事などすればいいのか。
ややもすれば、競って楽しげな女子社員の笑い声が、佐山のいる席まで届く。
秋口には入社以来、決まった恋人はいないようだった。誰それと最近親しいと噂が流れ、それが噂に疎い佐山の元にも届く頃には、別の相手と懇ろになっているという塩梅だ。それで親しくなった相手と疎遠になることはないから、秋口の周りをうろうろする女性は増える一方だった。秋口航という男に目を掛けられることが、女子社員内で一種勲章のようなものになっているらしいと、佐山も気づいている。
(俺が女だったら)
割り箸を割りつつ、佐山は眉根を寄せた。
(やっぱり、秋口の周りでうろうろするうちのひとりになるのか?)
そんなことを考えてしまい、佐山は一気に食欲の失くなる思いだった。くだらない想像。自分が女だったら、などと考えること自体が正気の沙汰じゃない。
「気持ち悪ィ……」
「佐山さん、具合悪いんですか?」
唸るように呟いた時、真横から声をかけられた。その声にぎょっとして見上げれば、定食の載ったトレイを手にした秋口がそこに立っていて、佐山はさらに驚く。
「あれ……どうかしたのか? 向こうにいたのに」
みっともなく仰天している様子を表に出すまいと、佐山はつとめて平静な口調で秋口に問いかけた。
秋口は佐山の了承も取らず、佐山の向かいの席へ回り込むと、その椅子に座ってしまった。
「人が増えちゃって収拾つかないんで、置いてきました」
佐山が振り返ると、女子社員たちが数人、不満げに秋口の方を見ている。
「でも、向こうと約束とかしてたんだろ」
「してませんよ、約束なんて。食堂に来る間に勝手についてきたのと、食堂で俺の姿見て勝手に集まってきたのと」
秋口の口調は自慢げでも、面倒げでもなく、まるで『蛇口を捻ったから水が出た』というようなあたりまえのことを語る感じだった。
「面倒だから、プライベートで約束はしないんです。タイミングですからね、顔を合わせて時間があれば一緒に飯なり飲みに行くなり、その後なり。タイミングとかフィーリングって大事だと思うんです」
「はあ」
秋口は佐山の向かいで食事を始めた。佐山はどうして秋口が自分の前に来るのかわからないまま、しかし追い出す理由もないので、仕方なく自分も定食をつつき始める。
「向こうに営業の人いるけど、あっちには行かないのか?」
秋口と向かい合わせで食事を摂るというのが、どうしても居心地悪く、佐山は食堂を見回してそう言った。佐山や秋口たちから少し離れたところで、秋口と同じ部署の社員が数人固まって食事を摂っている。
「メシの時まで、上司でもない年上の同僚と一緒にいたくありませんから。入社の早い遅いだけで、やれ茶を取ってこいだの醤油を渡せだの言われんの、面倒なんですよね」
課が違うとはいえ、自分だって同じような立場なのに……と佐山が疑問に思いつつ向かいを見遣り、目が合った秋口がにっこり笑う。
「その点、佐山さんなら気ィ遣わなくてすみそうだし」
どういう意味だ、とさらに疑問に思ったが、佐山はあえて聞かずにおいた。あまり嬉しい返事が来そうにもない雰囲気だ。
「それに一課のセンパイたちも割と顔広いから、ほら、結構いろんな人が寄って来るでしょ」
秋口に釣られて佐山が一課の面々を見遣ると、たしかに男女問わず、彼らに次々声を掛けたり、その近くで食事を始めたりしている。
「それもまた面倒。佐山さんの近くなら、別に人が集まって来るわけじゃないだろうし、楽かなーって」
どう相槌を打ったものか、佐山は曖昧に頷きながら定食に視線を落とした。
「あんまり群れられるの、そろそろ鬱陶しくなってきたんですよね。仕事でもないのにその場にいる全員に気遣えるタイプじゃないし、全員が物分かりがよければ楽なのに、自分が一番じゃないと嫌だって相手同士が揉めると、こっちにアタリがきつくなるし。――あ、すみません、こんなこと佐山さんに言っても、わからないですよね」
明るく笑い声を立てる秋口の前で、ますます佐山の食欲は減退していく。
「そうだな、もうちょっと、わかりそうな相手に話した方がいいんじゃないか?」
辛うじてそれだけ佐山が返すと、秋口が「わかってないなあ」と大きく頭を振る。
「恋愛に多少通じてそうな相手に言ったら、やっかまれるだけですよ。佐山さんならほら、サッパリわからなくて適当に流すしかないでしょ?」
いよいよ食欲が失くなって、佐山は半分も食べていない定食の盆の上に箸を置いた。
「あれ、佐山さん、もう食べないんですか」
「あー……もう、腹一杯」
「全然減ってないじゃないですか。そんなんで保つんですか、午後」
「もともとそんなに食べる方じゃないから」
「だからそんな、チ……細身なんじゃないですか? ダイエット中の女の子みたいだ」
佐山は口に入れた白飯が飲み込みきれないような、息苦しい感じになりながら笑った。テーブルの上のポットからお茶を注ぎ、冷まし冷まし湯呑みを手に取る。
「体質なんだよ、そういう」
秋口は佐山の様子に気づいたふうもない。
「じゃ、この唐揚げとサラダもらっていいですか」
「どうぞ」
「あ、俺にもお茶下さい」
「……」
佐山は無言で、秋口のためにもお茶を注いでやった。湯呑みを秋口の前に押し遣ると、「どうも」と簡単なお礼が返ってくる。
佐山は秋口が食べ尽くした自分の分のトレイを持って、立ち上がった。
「じゃあ、俺は戻るな」
「俺も行きます」
お茶を飲み干し、秋口も一緒になって立ち上がった。別に自分につき合ったわけではなく、ひとりで食堂に残れば他の人に話しかけられて『面倒』なのだろうと、佐山は察しをつけた。
トレイをカウンタへ返し、秋口と並んで食堂から出た時、ちょうど廊下を御幸が歩いてきた。
「よう、もうメシ終わったのか?」
御幸の顔を見て、佐山は思わず大きく安堵の息を吐き出してしまう。
秋口がそんな佐山の様子をちらりと一瞥してから、御幸に軽く頭を下げた。
「今な。御幸は、これからか」
「外回りだったから、ついでに外で食べてこようと思ったんだけど、店が混んでてさ。腹減った」
笑いながら、御幸が腹を押さえている。
「あ、そうだ佐山、これやるよ。N工業行ったらくれたんだけど」
ポケットから取り出した小さなチョコレートの包みを、御幸が佐山に手渡した。受け取りながら、佐山はちょっと笑う。
「またもらったのか、あそこの事務の子から」
「最初に受け取ったのが不味かったよな、今さら甘いもの苦手なんて言い出せないし」
困ったふうに笑い返しながら、御幸が秋口に目を移す。
「秋口も、食べるか?」
「いえ、俺も甘いもの嫌いなんで」
そう言って秋口が首を振った。
(そうか、秋口も、甘いもの嫌いなのか)
秋口の答えを、佐山は無意識に頭の中で反芻してから、少し恥じ入る。相手の些細な趣味嗜好を知って嬉しいなんて、まるで高校生の女の子みたいだと思った。
「それじゃ、俺はこれで」
恥じ入りつつ、佐山が御幸にもらったチョコレートをポケットに突っ込んでいると、秋口がそう言ってふたりのそばから離れていった。
あっさりした退場に、佐山は何となく、秋口は御幸のことも好きではないのだろうかと感じた。
ただそれは、自分に向ける感情とかなり違う方向性だと思える。どっちにしろ秋口は『男が嫌い』らしいが、少なくとも御幸に対しては、自分に向けるような軽口を叩いたりしないだろう。そんな気がする。
「佐山? どうした、しかめっ面して」
秋口の後ろ姿を見送りながら考え込んでしまった佐山の顔を、御幸が横から覗き込む。
佐山は慌てて首を横に振った。
「いや、別に」
「秋口にまた苛められたか?」
勘のいい御幸に、佐山はちょっとぎくりとした。
「苛められたって、そんな、学生でもあるまいし」
「ならいいけどさ」
それじゃ俺も食堂行くからと行って、御幸も佐山のそばから去っていく。
ともかく佐山は、秋口との仕事が終わって、また安心して遠くからその姿が見られるよう何かに向けて祈った。
そう、小馬鹿にされていても、構われているのが嬉しいなんて気持ちが、これ以上膨らんでいかないうちに――。