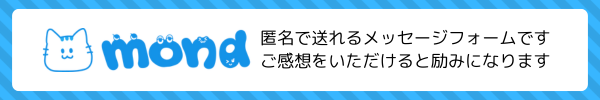唖然、という表現がもっともぴったりだっただろう。
佐山も、御幸も、そして秋口も、目と、すぐには言葉の出ない口を開いている。
「あれ、どうかしました?」
唯一、縞の声だけが脳天気に響いていた。
「あの……縞さんのご親戚っていうのは……」
一目瞭然のことを佐山が問わずにいられなかったのは、目の前の事実がやっぱりすぐには信じられなかったからだ。
縞が、佐山を見て、秋口を見て、もう一度佐山を見直してから頷く。
「これです。あれ、もしかしてみなさんお知り合いですか?」
自分の隣に立つ秋口を指さし、三人の反応で、縞もその偶然をすぐに察したらしい。佐山はどうにも気まずい気分で頷きながら、秋口の顔が見る見る憮然とした表情に変わっていくのを眺めていた。
また縞から連絡があったのは、前回御幸と三人で食事をしてから二日後だった。縞は御幸も是非一緒にと誘ってきて、仕事が詰まっていると言っていたはずの御幸は、その仕事を無理矢理終わらせてついてきた。
御幸も来られそうだという佐山のメールに、縞からは近くに住む歳の近い親戚がいるからついでに誘うがいいか、とさらに返信が来た。佐山も御幸も特別異存はなかったので、じゃあこの間と同じ店で待ち合わせ、ということになったのだが。
佐山と御幸が先に店に着き、適当に飲み食いを始めて間もない頃、縞の明るい声がした。
それで佐山と御幸は一緒に振り返り、縞の隣によく見知った顔をみつけ、呆然とするに至ったわけだった。
「すごい偶然だなあ。これ、従弟なんですけどね、母親同士が姉妹。もう知り合いなら、じゃあ、自己紹介いらないか」
今日は四人がけのボックス席に案内されて、御幸と向かい合って座っていた佐山の隣に、縞がさっさと腰を下ろす。仏頂面の従弟の顔を見て、首を捻った。
「何ボケーッと突っ立ってんだよ、航。さっさと座れ」
縞に促され、秋口はいかにも不承不承といった態で御幸の隣に腰を下ろした。
「あれ、でも、どういう知り合いです?」
店員の運んできたおしぼりで手を拭きながら、縞がまた首を傾げる。
「同じ会社の先輩」
不機嫌な声で答えたのは、秋口だった。
佐山はひたすら驚いたまま、その秋口のことを見遣る。
(ああ……そりゃ、似てるよな)
血縁関係があるというのなら、縞が秋口に似ていたって不思議はないのだ。
この顔合わせになったのが、ただ偶然すぎたと言うだけで。
秋口の答えを聞いて、縞も得心がいったように何度も頷いている。
「あー、どうりでおふたりからもらった名刺、社名に見覚えがある気がしたんだ」
「……おまえ、本当に俺に興味がないよな」
秋口が小声でぼそりと吐き捨てる。縞と秋口はあまり仲睦まじい雰囲気ではなかったが、こんな場に呼ぶくらいだし、遠慮がない関係ってやつだろうと佐山は察する。
「まあまあ、あ、すみませんお姉さん、生ふたつ。あ、おまえ生でいいよな」
「どうとでも」
「佐山さんは、まだお代わりいいですか?」
ひょい、と御幸が佐山の手許のグラスを覗き込む。すでに佐山は烏龍茶を、御幸はビールを頼んでいる。
「あ、俺たちもさっき来たばっかりですから。すみません、先に始めちゃってて」
「いえいえ、こっちが約束の時間より遅れちゃったんですから」
秋口は無言で煙草を取り出して咥えている。御幸が灰皿を秋口の方へ押し遣ってやり、秋口が小さく頭を下げる。
――という様子を眺めながら、佐山も煙草の箱を取り出した。
「あ、灰皿もうひとつ」
生ビールふたつを運んできた店員に、縞がすかさず声をかける。佐山は恐縮して頭を下げた。
「すみません」
「俺も吸いますから」
にっこり笑って縞がポケットから煙草を取り出してみせる。本当に縞はこういうところにそつがない、と佐山は感心する。
「じゃあまあ、とりあえず乾杯しますか。奇縁にってことで」
縞がそう言いながらビールのジョッキを掲げ、佐山は苦笑してそれに倣った。御幸も苦笑い気味に、半分に減ったジョッキを手にする。
「ほら航、おまえも」
縞に促され、ひとり我関せずの顔で煙草をふかしていた秋口も、また不承不承にビールを持ち上げた。
「はい、かんぱーい」
縞の音頭に続いて、バラバラに乾杯の声が続く。
佐山は何だか尻の据わりが悪くて仕方がなかった。
「食べ物もじゃんじゃん頼んじゃいましょう、俺、腹減ってて」
縞がメニュー表を手に取り、ひとつを御幸と秋口の方へ渡し、もうひとつを広げて佐山の前に押し遣って、自分は佐山に身を寄せてそれを覗き込んだ。
「もう何か、頼みました?」
「いや、縞さん……たちが、来てからと思って」
「すみません、じゃ、佐山さんも腹減ったでしょ」
「そんなでもないですよ、昼飯遅かったし」
「あ、お仕事お疲れ様です」
「縞さんこそ。今日もこっちで仕事の用があったんですか?」
「いえいえ、今日は佐山さんの顔が見たくて予定を空けたんですよ」
「佐山、そっち、何頼む?」
冗談めかした縞の言葉に佐山が笑い返していると、御幸が声をかけてきた。
「こっちは鶏唐となすの揚げ浸しとチーズ上げと山菜サラダってあたりなんだけど」
こっち、と言いつつ、決めたのは御幸ひとりのようだった。秋口は「どうでもいい」という顔で明後日の方を見ながら煙草を吸い続けている。
「そうだなあ、佐山さん今日は何食べますか?」
「ええと、なるべくさっぱりしたもの系が……」
訊ねてきた縞に佐山は答えたが、秋口の姿を見た瞬間に食欲なんて半減していた。できればこのまま帰って寝てしまいたかったが、それもまた気まずい結果になってしまう気がする。
縞があれこれ佐山に話しかけながらメニューを決めていき、適当に注文をすませた。
「佐山さん何か、今日は疲れてます?」
小さく溜息をついた佐山に目敏く気づいて、縞が顔を覗き込んでくる。
「いえ、そんなことありませんよ」
慌てて首を振る佐山に、縞が相好を崩した。
「佐山さん、今日もかぁわいいなあ。疲れてても全然気にしないでください、俺の前で無理しなくていいんですよ」
「ははは……」
「万が一酔い潰れたら、俺が責任持って佐山さんのお宅まで送り届けますから」
相変わらず臆面なく、笑顔のままそんなことを言う縞に、佐山はつい本気で笑ってしまった。
「酒は飲みませんから、潰れたりしませんよ」
「たまに、一口くらいは飲まないんですか?」
あー、と佐山は低く呻き声を上げてから、縞の方へ耳を寄せた。小声で囁く。
「……その、酒で失敗したことがあるので、戒めのためにもう飲まないようにと」
目の前に、その『失敗した』相手がいるのでは、そんなことも告白しづらい。
「……女性関係?」
縞も同じく声をひそめ、佐山に耳打ちする。
佐山はついつい赤くなった。やっぱり、本人を前にしての話題じゃない。適当に誤魔化せばよかったのに、つい馬鹿正直に答えてしまった。
「いや、その、そういうわけでも、ないんですが」
「うーん、そうか、佐山さんは何とかして酒で潰したら何とかなると」
「何とかって、何ですか」
佐山は笑って言い返してから、何となく盛り上がっているこちら側とは対照的に、御幸と秋口側の席が会話もなく白けた空気が流れているのに気づいた。
「あ、御幸、秋口も、飲み物大丈夫か?」
訊ねながら、佐山は秋口の名前を呼んで、秋口を見て、秋口に直接声をかけるなんて、ずいぶん久しぶりだなと思った。
「いえ、俺はまだ」
「俺も大丈夫」
「何だ航ちゃん、進んでないな。綺麗どころに囲まれて緊張してるのか?」
(航ちゃん……)
佐山はまじまじと縞を見てしまう。そうか、この人は秋口の親戚なんだよなと改めて確認した。ずいぶん可愛らしい呼び名に、つい小さく笑いがこぼれた。
「男で綺麗どころもあるかよ」
血縁関係の遠慮のなさだろうか、秋口が他人に対して嫌みで応酬するでなく、こんなふうにぞんざいな口調になるのを佐山が見るのは、初めてだった。
「おまえね、先輩に対してそういう言い種はないでしょ」
「おまえに言ってるんだよ」
仏頂面で言った秋口に、佐山はまたこらえきれず笑い声をたててしまった。
「ん? 何かおかしかったですか?」
そう訊ねたのは、縞。
「いや……すみません、仲いいんだなって思って」
「可愛い子分ですよ」
笑って頷いた縞に、「誰が子分だ」とまた秋口が憮然と呟いたが、縞に反論するというよりも独り言のような呟きだった。
「兄弟みたいにして育ったとか?」
「会うのはたまにですけどね。佐山さんはご兄弟は?」
「俺は、ひとりっ子で」
「へえ、じゃあ俺とお揃いですね」
縞は今日もよく喋り、つられて佐山も饒舌になった。向かい側の沈黙が気にはなったが、縞がそのふたりに話を振っても、御幸は普通に応えるものの、秋口が木で鼻を括るような返事をするものだから後が続かない。
そのたび縞がまた絶妙なタイミングで佐山に話を戻して、決定的に白々しい雰囲気になることだけは避けられたが、秋口だけではなく御幸もそこはかとなく機嫌が悪いようで、佐山はどうもやっぱり落ち着かない。
こうなると、明るく話しかけてくれる縞だけが救いな気がした。
「ちょっと、失礼」
そしてそんな状態がしばらく続いた後、縞がふと席を立った。電話か手洗いだろう、と察しつつ、縞の不在が心許なくなって佐山は立ち上がったその顔を見上げた。
そんな佐山の内心に気づいたように、縞が佐山を見返して優しく笑う。
「すぐ戻りますね」
言い置いて縞がいなくなり、さてこの気まずい沈黙をどうしようか……と佐山が重い気持ちになった時、御幸も椅子から立ち上がった。
「――俺も、ちょっと」
そう言って、御幸も縞の向かった手洗い方面へ去っていってしまう。
(……ええと)
そうして、後に残されたのは、佐山と、よりによって秋口ひとり。
気まずいことこの上なかった。
佐山も、御幸も、そして秋口も、目と、すぐには言葉の出ない口を開いている。
「あれ、どうかしました?」
唯一、縞の声だけが脳天気に響いていた。
「あの……縞さんのご親戚っていうのは……」
一目瞭然のことを佐山が問わずにいられなかったのは、目の前の事実がやっぱりすぐには信じられなかったからだ。
縞が、佐山を見て、秋口を見て、もう一度佐山を見直してから頷く。
「これです。あれ、もしかしてみなさんお知り合いですか?」
自分の隣に立つ秋口を指さし、三人の反応で、縞もその偶然をすぐに察したらしい。佐山はどうにも気まずい気分で頷きながら、秋口の顔が見る見る憮然とした表情に変わっていくのを眺めていた。
また縞から連絡があったのは、前回御幸と三人で食事をしてから二日後だった。縞は御幸も是非一緒にと誘ってきて、仕事が詰まっていると言っていたはずの御幸は、その仕事を無理矢理終わらせてついてきた。
御幸も来られそうだという佐山のメールに、縞からは近くに住む歳の近い親戚がいるからついでに誘うがいいか、とさらに返信が来た。佐山も御幸も特別異存はなかったので、じゃあこの間と同じ店で待ち合わせ、ということになったのだが。
佐山と御幸が先に店に着き、適当に飲み食いを始めて間もない頃、縞の明るい声がした。
それで佐山と御幸は一緒に振り返り、縞の隣によく見知った顔をみつけ、呆然とするに至ったわけだった。
「すごい偶然だなあ。これ、従弟なんですけどね、母親同士が姉妹。もう知り合いなら、じゃあ、自己紹介いらないか」
今日は四人がけのボックス席に案内されて、御幸と向かい合って座っていた佐山の隣に、縞がさっさと腰を下ろす。仏頂面の従弟の顔を見て、首を捻った。
「何ボケーッと突っ立ってんだよ、航。さっさと座れ」
縞に促され、秋口はいかにも不承不承といった態で御幸の隣に腰を下ろした。
「あれ、でも、どういう知り合いです?」
店員の運んできたおしぼりで手を拭きながら、縞がまた首を傾げる。
「同じ会社の先輩」
不機嫌な声で答えたのは、秋口だった。
佐山はひたすら驚いたまま、その秋口のことを見遣る。
(ああ……そりゃ、似てるよな)
血縁関係があるというのなら、縞が秋口に似ていたって不思議はないのだ。
この顔合わせになったのが、ただ偶然すぎたと言うだけで。
秋口の答えを聞いて、縞も得心がいったように何度も頷いている。
「あー、どうりでおふたりからもらった名刺、社名に見覚えがある気がしたんだ」
「……おまえ、本当に俺に興味がないよな」
秋口が小声でぼそりと吐き捨てる。縞と秋口はあまり仲睦まじい雰囲気ではなかったが、こんな場に呼ぶくらいだし、遠慮がない関係ってやつだろうと佐山は察する。
「まあまあ、あ、すみませんお姉さん、生ふたつ。あ、おまえ生でいいよな」
「どうとでも」
「佐山さんは、まだお代わりいいですか?」
ひょい、と御幸が佐山の手許のグラスを覗き込む。すでに佐山は烏龍茶を、御幸はビールを頼んでいる。
「あ、俺たちもさっき来たばっかりですから。すみません、先に始めちゃってて」
「いえいえ、こっちが約束の時間より遅れちゃったんですから」
秋口は無言で煙草を取り出して咥えている。御幸が灰皿を秋口の方へ押し遣ってやり、秋口が小さく頭を下げる。
――という様子を眺めながら、佐山も煙草の箱を取り出した。
「あ、灰皿もうひとつ」
生ビールふたつを運んできた店員に、縞がすかさず声をかける。佐山は恐縮して頭を下げた。
「すみません」
「俺も吸いますから」
にっこり笑って縞がポケットから煙草を取り出してみせる。本当に縞はこういうところにそつがない、と佐山は感心する。
「じゃあまあ、とりあえず乾杯しますか。奇縁にってことで」
縞がそう言いながらビールのジョッキを掲げ、佐山は苦笑してそれに倣った。御幸も苦笑い気味に、半分に減ったジョッキを手にする。
「ほら航、おまえも」
縞に促され、ひとり我関せずの顔で煙草をふかしていた秋口も、また不承不承にビールを持ち上げた。
「はい、かんぱーい」
縞の音頭に続いて、バラバラに乾杯の声が続く。
佐山は何だか尻の据わりが悪くて仕方がなかった。
「食べ物もじゃんじゃん頼んじゃいましょう、俺、腹減ってて」
縞がメニュー表を手に取り、ひとつを御幸と秋口の方へ渡し、もうひとつを広げて佐山の前に押し遣って、自分は佐山に身を寄せてそれを覗き込んだ。
「もう何か、頼みました?」
「いや、縞さん……たちが、来てからと思って」
「すみません、じゃ、佐山さんも腹減ったでしょ」
「そんなでもないですよ、昼飯遅かったし」
「あ、お仕事お疲れ様です」
「縞さんこそ。今日もこっちで仕事の用があったんですか?」
「いえいえ、今日は佐山さんの顔が見たくて予定を空けたんですよ」
「佐山、そっち、何頼む?」
冗談めかした縞の言葉に佐山が笑い返していると、御幸が声をかけてきた。
「こっちは鶏唐となすの揚げ浸しとチーズ上げと山菜サラダってあたりなんだけど」
こっち、と言いつつ、決めたのは御幸ひとりのようだった。秋口は「どうでもいい」という顔で明後日の方を見ながら煙草を吸い続けている。
「そうだなあ、佐山さん今日は何食べますか?」
「ええと、なるべくさっぱりしたもの系が……」
訊ねてきた縞に佐山は答えたが、秋口の姿を見た瞬間に食欲なんて半減していた。できればこのまま帰って寝てしまいたかったが、それもまた気まずい結果になってしまう気がする。
縞があれこれ佐山に話しかけながらメニューを決めていき、適当に注文をすませた。
「佐山さん何か、今日は疲れてます?」
小さく溜息をついた佐山に目敏く気づいて、縞が顔を覗き込んでくる。
「いえ、そんなことありませんよ」
慌てて首を振る佐山に、縞が相好を崩した。
「佐山さん、今日もかぁわいいなあ。疲れてても全然気にしないでください、俺の前で無理しなくていいんですよ」
「ははは……」
「万が一酔い潰れたら、俺が責任持って佐山さんのお宅まで送り届けますから」
相変わらず臆面なく、笑顔のままそんなことを言う縞に、佐山はつい本気で笑ってしまった。
「酒は飲みませんから、潰れたりしませんよ」
「たまに、一口くらいは飲まないんですか?」
あー、と佐山は低く呻き声を上げてから、縞の方へ耳を寄せた。小声で囁く。
「……その、酒で失敗したことがあるので、戒めのためにもう飲まないようにと」
目の前に、その『失敗した』相手がいるのでは、そんなことも告白しづらい。
「……女性関係?」
縞も同じく声をひそめ、佐山に耳打ちする。
佐山はついつい赤くなった。やっぱり、本人を前にしての話題じゃない。適当に誤魔化せばよかったのに、つい馬鹿正直に答えてしまった。
「いや、その、そういうわけでも、ないんですが」
「うーん、そうか、佐山さんは何とかして酒で潰したら何とかなると」
「何とかって、何ですか」
佐山は笑って言い返してから、何となく盛り上がっているこちら側とは対照的に、御幸と秋口側の席が会話もなく白けた空気が流れているのに気づいた。
「あ、御幸、秋口も、飲み物大丈夫か?」
訊ねながら、佐山は秋口の名前を呼んで、秋口を見て、秋口に直接声をかけるなんて、ずいぶん久しぶりだなと思った。
「いえ、俺はまだ」
「俺も大丈夫」
「何だ航ちゃん、進んでないな。綺麗どころに囲まれて緊張してるのか?」
(航ちゃん……)
佐山はまじまじと縞を見てしまう。そうか、この人は秋口の親戚なんだよなと改めて確認した。ずいぶん可愛らしい呼び名に、つい小さく笑いがこぼれた。
「男で綺麗どころもあるかよ」
血縁関係の遠慮のなさだろうか、秋口が他人に対して嫌みで応酬するでなく、こんなふうにぞんざいな口調になるのを佐山が見るのは、初めてだった。
「おまえね、先輩に対してそういう言い種はないでしょ」
「おまえに言ってるんだよ」
仏頂面で言った秋口に、佐山はまたこらえきれず笑い声をたててしまった。
「ん? 何かおかしかったですか?」
そう訊ねたのは、縞。
「いや……すみません、仲いいんだなって思って」
「可愛い子分ですよ」
笑って頷いた縞に、「誰が子分だ」とまた秋口が憮然と呟いたが、縞に反論するというよりも独り言のような呟きだった。
「兄弟みたいにして育ったとか?」
「会うのはたまにですけどね。佐山さんはご兄弟は?」
「俺は、ひとりっ子で」
「へえ、じゃあ俺とお揃いですね」
縞は今日もよく喋り、つられて佐山も饒舌になった。向かい側の沈黙が気にはなったが、縞がそのふたりに話を振っても、御幸は普通に応えるものの、秋口が木で鼻を括るような返事をするものだから後が続かない。
そのたび縞がまた絶妙なタイミングで佐山に話を戻して、決定的に白々しい雰囲気になることだけは避けられたが、秋口だけではなく御幸もそこはかとなく機嫌が悪いようで、佐山はどうもやっぱり落ち着かない。
こうなると、明るく話しかけてくれる縞だけが救いな気がした。
「ちょっと、失礼」
そしてそんな状態がしばらく続いた後、縞がふと席を立った。電話か手洗いだろう、と察しつつ、縞の不在が心許なくなって佐山は立ち上がったその顔を見上げた。
そんな佐山の内心に気づいたように、縞が佐山を見返して優しく笑う。
「すぐ戻りますね」
言い置いて縞がいなくなり、さてこの気まずい沈黙をどうしようか……と佐山が重い気持ちになった時、御幸も椅子から立ち上がった。
「――俺も、ちょっと」
そう言って、御幸も縞の向かった手洗い方面へ去っていってしまう。
(……ええと)
そうして、後に残されたのは、佐山と、よりによって秋口ひとり。
気まずいことこの上なかった。
◇◇◇
「縞さん」
呼び止めると、縞はすぐ後ろに御幸がいることなんてお見通しだったかのように、あたりまえの顔で振り返った。
「はい、何でしょう」
そして、胡散臭いほどの笑顔。
御幸はどうやってもこの男のことは信用ならないと、一目相手を見た時から抱いていた警戒心をさらに強くした。
愛想のいい笑顔、過剰なリップサービスの連続、まるで詐欺師だ。どうして佐山が縞に懐いているのか理解に苦しむ。
いや――
(あたりまえって言ったら、あたりまえか)
初対面で驚いたのは、まずその胡散臭い愛想のよさと、それ以上に、秋口とあまりに似ていることだった。佐山が秋口以外に男性を恋愛対象に見る性癖ではないと理解している御幸だって、一瞬、『佐山はこういうタイプの好きな面喰いなんだな』と納得しそうになるくらい。
「呼び止めておいて黙り込むとは、どういう手管かな」
手洗いへ続くひとけのない廊下で、咄嗟に後を追ってきたはいいが、何をどう言うべきか考えあぐねてしまった御幸のそばに、気づくと縞が歩み寄っていた。
(近い)
まったくこの縞という男の他人に対する距離感は、近すぎる。物理的に。
佐山にもやたら顔を近づけたり手を触れたり、アピールはあからさまで、御幸が「もし勘違いだったら失礼だ」などと不安すら抱けないほどだった。
「縞さんは、どういうつもりで佐山に近づいてるんですか」
この男相手に遠回しに切り出してものらくらと躱されるだけで話にならないだろうと判断して、御幸はやんわりした笑みをたたえながら、そう訊ねた。
縞は、おもしろそうな顔で目を見開き、御幸を見遣る。
「どうもこうも、気に入ったから仲よくしたいという、純粋で素直な気持ちですよ」
「秋口が同じ会社って、本当に知らなかったんですか」
「はい?」
縞が小首を傾げる。御幸は愛想笑いのひとつも出す気がもう起きず、それを見返した。
「自分の従弟をネタにしてまで佐山と『仲よく』なろうっていうのなら、ずいぶん手が込んでますよね」
「知らなかったのは本当ですよ、まあ、好都合だと思ってるのも本当ですけど」
答えてから、縞はますます興味深そうな顔になって、御幸を見遣った。
「それで、御幸さんは、大事な佐山さんが俺なんかにちょっかいかけられないように、わざわざ牽制に来たってわけですか」
「個人的に、そうだったらやり方に品がないと思って聞いただけですよ」
さりげなく、御幸は半歩後ろに下がった。縞はそばの壁に片腕で寄りかかって、何となく、御幸の方へさらに身を寄せるような格好になっている。
「恋愛の駆け引きなんて、どうやってもお上品になるもんじゃないでしょう?」
恋愛、と臆面もなく言った縞に、やっぱりこいつは始末に負えないタイプの人間だと、確信を深めて御幸は溜息を押し殺す。
「まあ、お好きに。縞さんは他人が何を言っても往く我が道を変えないタイプでしょうから、俺からあなたに言うことはもうありませんよ」
身を避け、御幸は縞を追い越すと手洗いの方へ向かった。
「御幸さんて、佐山さんのお母さんみたいですね」
背中から聞こえた笑いを含んだ言葉に、御幸は腹を立てるでもなく、小さく肩を竦めた。
「そうだったらいっそ、頭ごなしにできて楽ですよ」
縞の笑い声が、すぐ後ろから聞こえた。
「御幸さんて、俺のこと嫌いですか」
「好きか嫌いか判断できるほど親しいわけじゃないでしょう」
御幸が手洗いのドアを押し開けると、すぐにそのドアを縞が引き継いだ。割合広い手洗いの中に、他の客の姿は見あたらない。
「大事な大事な佐山さんに手を出す相手は、誰も彼も悪者だとか――」
この男といい、従弟といい、発想が同じだ。御幸はゆるく首を振って鏡の前の水道で手を洗った。一応用足しするつもりでここへ来たのだが、何となく、縞と並んで――という状況に気が進まない。
縞の方は、さっさと朝顔の前で用を足している。
「ってわけでも、ないのか」
縞がそう続けたので、御幸はつい彼の方を見遣ってしまった。
縞はちょうど衣服を直していることろだった。
目が合って、にやっと、縞が口許で笑う。
そこで御幸は、相手が思っていた以上にタチのよくない人間なのではということに気づいた。佐山に向けていた屈託のない笑顔とは、まったく質の違う表情だった。
「ええ。俺は親友にその気になれるほど、幅の広い人生を送ってませんから」
「でも口出しはするわけだ」
「佐山が傷つけるような真似をして欲しくないだけです。本気なら止めないって言ったでしょう」
普段だったら、佐山に害のありそうな人間を牽制するなんてことを、決して御幸がするはずがないのだ。秋口の時だって黙って成り行きを見守っていた。どんなに歯がゆい思いをしていたとしても、佐山なら自分の力で解決するだろうし、もし助けを求められればすぐにでも手を貸すつもりで、それまでは静観するのが自分の役割だとわきまえていた。
ただ、今は、時期が悪すぎる。
佐山本人は気づいているのかいないのか、すっかりと草臥れ果て、消耗しきっている。
佐山が弱い人間ではないと信じていても、縞がよりによって秋口の血縁関係者だとわかってしまっては、御幸には黙っていることができなくなってしまったのだ。
(単に秋口に似てるだけっていうのなら、まあいいさ)
秋口に似た、秋口よりはいくらか性格がましな相手に佐山がよろめくのであれば、それはそれで構わないと思う。一時的にでも佐山の気が休まるのならそれでいい。
だが、縞と秋口の間に繋がりがあるのなら、佐山はきっとそのうち辛くなるばかりだ。
今以上に。
(まあ……多分、どうあったって、言って聞くってタイプじゃないだろうけど)
自分の隣に来て手を洗う縞を鏡越し横目で見つつ、御幸は思った。いくら自分が気をもんで佐山にちょっかいかけるなと脅したところで、縞はどこ吹く風だろうし、むしろ、障害があるほど燃えるなどと言い出しかねない気がする。
今日この場に秋口まで現れた都合のよさに、黙っていられずつい縞を追いかけてきてしまったが、もしかしたら早まったかもしれないと御幸は後悔した。
「せっかくひさびさにみつけた上玉なのに、不戦敗なんて俺の男がすたるなあ」
案の定、縞は薄笑いのとぼけた口調でそんなことを言っている。
上玉、と佐山を評したところだけは褒めてやっていいと思ったが、やはりさんざんしていたアプローチは遊びでしかなかったのだと確認して、御幸は気持ちが冷えた。鏡の縞から目を逸らす。
「佐山はあなたの暇つぶしのおもちゃじゃありませんよ」
「じゃ、あんたが相手してくれんの、御幸ちゃん?」
「え?」
驚いて再び顔を上げた時、ごくごく間近に相手の顔があることに気づいて御幸はぎょっとする。気配を感じなかった。
咄嗟に横へ逃げようとした御幸の腕を、縞が素早く掴んだ。
笑ったまま、さらに御幸へ顔を寄せる。
「離してくれませんか」
怯んだら負ける気がして、もう逃げようとはせず、御幸は冷淡な目で相手を見返した。
蔑むような御幸の表情を見て、縞は愉快そうに肩を揺らしている。
(本当に、タチが悪い――)
さすが秋口の血縁だ、と御幸は腹が立った。
「佐山さんも可愛いけどおたくも相当ですよ、ふたり並んでるのは奇蹟だと思ったね……っていうか」
にこっと、今度は邪気のない笑顔で縞が笑う。もちろんそれで御幸が安心できるはずもなかった。
笑いながら、縞が御幸の鼻先へ人差し指を向ける。何となくこのまま走って手洗いから逃げ出したい気がしてきた御幸の、しかしその腕は縞が相変わらず強い力で掴んでいる。
「本命、こっち」
「はあ?」
紛れもなく縞の指は御幸を指さしていた。
「だから御幸ちゃん、飛んで火に入る夏の虫」
じわっと、背中を嫌な汗が伝うのを、御幸は感じた。
縞はただただ、楽しそうだった。
呼び止めると、縞はすぐ後ろに御幸がいることなんてお見通しだったかのように、あたりまえの顔で振り返った。
「はい、何でしょう」
そして、胡散臭いほどの笑顔。
御幸はどうやってもこの男のことは信用ならないと、一目相手を見た時から抱いていた警戒心をさらに強くした。
愛想のいい笑顔、過剰なリップサービスの連続、まるで詐欺師だ。どうして佐山が縞に懐いているのか理解に苦しむ。
いや――
(あたりまえって言ったら、あたりまえか)
初対面で驚いたのは、まずその胡散臭い愛想のよさと、それ以上に、秋口とあまりに似ていることだった。佐山が秋口以外に男性を恋愛対象に見る性癖ではないと理解している御幸だって、一瞬、『佐山はこういうタイプの好きな面喰いなんだな』と納得しそうになるくらい。
「呼び止めておいて黙り込むとは、どういう手管かな」
手洗いへ続くひとけのない廊下で、咄嗟に後を追ってきたはいいが、何をどう言うべきか考えあぐねてしまった御幸のそばに、気づくと縞が歩み寄っていた。
(近い)
まったくこの縞という男の他人に対する距離感は、近すぎる。物理的に。
佐山にもやたら顔を近づけたり手を触れたり、アピールはあからさまで、御幸が「もし勘違いだったら失礼だ」などと不安すら抱けないほどだった。
「縞さんは、どういうつもりで佐山に近づいてるんですか」
この男相手に遠回しに切り出してものらくらと躱されるだけで話にならないだろうと判断して、御幸はやんわりした笑みをたたえながら、そう訊ねた。
縞は、おもしろそうな顔で目を見開き、御幸を見遣る。
「どうもこうも、気に入ったから仲よくしたいという、純粋で素直な気持ちですよ」
「秋口が同じ会社って、本当に知らなかったんですか」
「はい?」
縞が小首を傾げる。御幸は愛想笑いのひとつも出す気がもう起きず、それを見返した。
「自分の従弟をネタにしてまで佐山と『仲よく』なろうっていうのなら、ずいぶん手が込んでますよね」
「知らなかったのは本当ですよ、まあ、好都合だと思ってるのも本当ですけど」
答えてから、縞はますます興味深そうな顔になって、御幸を見遣った。
「それで、御幸さんは、大事な佐山さんが俺なんかにちょっかいかけられないように、わざわざ牽制に来たってわけですか」
「個人的に、そうだったらやり方に品がないと思って聞いただけですよ」
さりげなく、御幸は半歩後ろに下がった。縞はそばの壁に片腕で寄りかかって、何となく、御幸の方へさらに身を寄せるような格好になっている。
「恋愛の駆け引きなんて、どうやってもお上品になるもんじゃないでしょう?」
恋愛、と臆面もなく言った縞に、やっぱりこいつは始末に負えないタイプの人間だと、確信を深めて御幸は溜息を押し殺す。
「まあ、お好きに。縞さんは他人が何を言っても往く我が道を変えないタイプでしょうから、俺からあなたに言うことはもうありませんよ」
身を避け、御幸は縞を追い越すと手洗いの方へ向かった。
「御幸さんて、佐山さんのお母さんみたいですね」
背中から聞こえた笑いを含んだ言葉に、御幸は腹を立てるでもなく、小さく肩を竦めた。
「そうだったらいっそ、頭ごなしにできて楽ですよ」
縞の笑い声が、すぐ後ろから聞こえた。
「御幸さんて、俺のこと嫌いですか」
「好きか嫌いか判断できるほど親しいわけじゃないでしょう」
御幸が手洗いのドアを押し開けると、すぐにそのドアを縞が引き継いだ。割合広い手洗いの中に、他の客の姿は見あたらない。
「大事な大事な佐山さんに手を出す相手は、誰も彼も悪者だとか――」
この男といい、従弟といい、発想が同じだ。御幸はゆるく首を振って鏡の前の水道で手を洗った。一応用足しするつもりでここへ来たのだが、何となく、縞と並んで――という状況に気が進まない。
縞の方は、さっさと朝顔の前で用を足している。
「ってわけでも、ないのか」
縞がそう続けたので、御幸はつい彼の方を見遣ってしまった。
縞はちょうど衣服を直していることろだった。
目が合って、にやっと、縞が口許で笑う。
そこで御幸は、相手が思っていた以上にタチのよくない人間なのではということに気づいた。佐山に向けていた屈託のない笑顔とは、まったく質の違う表情だった。
「ええ。俺は親友にその気になれるほど、幅の広い人生を送ってませんから」
「でも口出しはするわけだ」
「佐山が傷つけるような真似をして欲しくないだけです。本気なら止めないって言ったでしょう」
普段だったら、佐山に害のありそうな人間を牽制するなんてことを、決して御幸がするはずがないのだ。秋口の時だって黙って成り行きを見守っていた。どんなに歯がゆい思いをしていたとしても、佐山なら自分の力で解決するだろうし、もし助けを求められればすぐにでも手を貸すつもりで、それまでは静観するのが自分の役割だとわきまえていた。
ただ、今は、時期が悪すぎる。
佐山本人は気づいているのかいないのか、すっかりと草臥れ果て、消耗しきっている。
佐山が弱い人間ではないと信じていても、縞がよりによって秋口の血縁関係者だとわかってしまっては、御幸には黙っていることができなくなってしまったのだ。
(単に秋口に似てるだけっていうのなら、まあいいさ)
秋口に似た、秋口よりはいくらか性格がましな相手に佐山がよろめくのであれば、それはそれで構わないと思う。一時的にでも佐山の気が休まるのならそれでいい。
だが、縞と秋口の間に繋がりがあるのなら、佐山はきっとそのうち辛くなるばかりだ。
今以上に。
(まあ……多分、どうあったって、言って聞くってタイプじゃないだろうけど)
自分の隣に来て手を洗う縞を鏡越し横目で見つつ、御幸は思った。いくら自分が気をもんで佐山にちょっかいかけるなと脅したところで、縞はどこ吹く風だろうし、むしろ、障害があるほど燃えるなどと言い出しかねない気がする。
今日この場に秋口まで現れた都合のよさに、黙っていられずつい縞を追いかけてきてしまったが、もしかしたら早まったかもしれないと御幸は後悔した。
「せっかくひさびさにみつけた上玉なのに、不戦敗なんて俺の男がすたるなあ」
案の定、縞は薄笑いのとぼけた口調でそんなことを言っている。
上玉、と佐山を評したところだけは褒めてやっていいと思ったが、やはりさんざんしていたアプローチは遊びでしかなかったのだと確認して、御幸は気持ちが冷えた。鏡の縞から目を逸らす。
「佐山はあなたの暇つぶしのおもちゃじゃありませんよ」
「じゃ、あんたが相手してくれんの、御幸ちゃん?」
「え?」
驚いて再び顔を上げた時、ごくごく間近に相手の顔があることに気づいて御幸はぎょっとする。気配を感じなかった。
咄嗟に横へ逃げようとした御幸の腕を、縞が素早く掴んだ。
笑ったまま、さらに御幸へ顔を寄せる。
「離してくれませんか」
怯んだら負ける気がして、もう逃げようとはせず、御幸は冷淡な目で相手を見返した。
蔑むような御幸の表情を見て、縞は愉快そうに肩を揺らしている。
(本当に、タチが悪い――)
さすが秋口の血縁だ、と御幸は腹が立った。
「佐山さんも可愛いけどおたくも相当ですよ、ふたり並んでるのは奇蹟だと思ったね……っていうか」
にこっと、今度は邪気のない笑顔で縞が笑う。もちろんそれで御幸が安心できるはずもなかった。
笑いながら、縞が御幸の鼻先へ人差し指を向ける。何となくこのまま走って手洗いから逃げ出したい気がしてきた御幸の、しかしその腕は縞が相変わらず強い力で掴んでいる。
「本命、こっち」
「はあ?」
紛れもなく縞の指は御幸を指さしていた。
「だから御幸ちゃん、飛んで火に入る夏の虫」
じわっと、背中を嫌な汗が伝うのを、御幸は感じた。
縞はただただ、楽しそうだった。
◇◇◇
「……あの、今さら何だけど、お疲れさん」
黙っているのも耐え難く、佐山は努めていつもどおりに――と思いながら秋口に声をかけた。
本当に久しぶりで、どういう態度が『いつもどおり』なのか、あやふやになってしまったが。
「……どうも」
秋口は、相変わらず不機嫌さを隠そうともせず、頷くように頭を下げた。
「本当に、すごい偶然だよな。まさか縞さんの従弟っていうのが秋口だなんて、想像もしなかった」
秋口は黙って煙草をふかしている。
間が保たなくて、佐山も煙草に火をつけた。
しばらく重たい沈黙が続いた。ふたりでいて気まずいなんて一度や二度のことじゃないが、今日はまた格別だ。佐山は自分からもう話題を振る気も起きなくて、意味もなくメニュー表を眺めながらひたすら煙を吐き出した。
それがまるで溜息のようだと自分で思った時、今度は秋口の方から口を開いた。
「亮人といる時の方が楽しそうですね」
ぼそりと、低く吐き出された呟きが、佐山には一瞬うまく聞き取れなかった。
「アキト? ……ああ、縞さん?」
下の名前で言われたので、よけいに何のことか、咄嗟にはわからなかったのだ。
「ずいぶん話が弾んでたみたいだし」
明らかに、秋口は拗ねている。佐山は今度こそ本当の溜息をついてしまわないために、多大な努力を要求された。
「そりゃあ、まあ」
溜息をつかないようにすることへ気を取られて、つい本音を漏らしてしまった。
しまった、と思った時にはもう遅い。秋口を取り巻く空気がさっと強張り、その顔からは表情が消えた。
「俺、他に用事があるのを亮人に無理矢理つれてこられただけなんで」
秋口は財布から紙幣を何枚か取り出し、テーブルの上に置いた。
「料理、まだ全部来てないぞ」
立ち上がろうとする秋口の動きを留めるように、佐山はその紙幣を相手の方へ押し遣る。
そんな佐山を見遣って、秋口は笑っていた。
「どうぞみなさんで、ごゆっくり」
久しぶりに見た秋口の笑顔に、そういえばこういう奴だったんだよなと、いまさら佐山は思い出した。自尊心が高くて、嫌みで、子供っぽい。
本当に何だって、自分はまだこんな相手が好きなんだろうかと思いながら、佐山は秋口を見遣った。
「秋口、俺と会えて嬉しくないか」
「こんな場所で?」
訊ねた佐山の質問に、秋口がすぐに反問する。
「佐山さんは嬉しいっていうんですか。気詰まりな、会いたくもない俺が、せっかく楽しく亮人と会ってるところに馬鹿面下げてのこのこ会いに来たのを見て、楽しいって?」
「……そうだな」
笑ったままの秋口に、佐山は自分も力なく笑い返し、首を振った。
「これで、楽しいはずがない」
「ならそんなこと聞くなよ」
秋口の語調は吐き捨てるようだった。
「友達と食事するくらい、俺はいつだってやるよ。秋口だって――」
言ってからまたしまったと思ったが、もう取り返しはつかない。佐山が言葉を飲み込むより早く、秋口がまた皮肉っぽい笑みをその表情に浮かべた。
「俺が、何です」
「……秋口だって、気詰まりな相手といるよりも、楽しくいられる相手と一緒に過ごした方がいいだろ」
他のどんな言い方をしたって、当て擦りになりそうで佐山は怖かった。以前にも同じことを口にしてしまった。秋口だって他の女の子と会っているだろうと。
あの時秋口から返ってきたのは嘲笑だった。思い出せば、佐山はやりきれない気分になる。
あれから秋口が、自分たちの間が、どれほど変わったと言うのか。
そして今も秋口は冷めたような笑い顔を作って、佐山を見下ろしている。その口から出る言葉を聞きたくなくて、佐山は俯いて言を継いだ。
「それに関して俺は何も言わないよ。言う立場じゃない。秋口は秋口が楽しいと思う人と一緒にいればいいと思うし、俺もそうする。でも俺は、できるなら――」
「あんた一体、何なんだ?」
もう苛立ちを隠そうとせず、秋口が佐山の言葉を遮るように言う。
「何……って」
「もう会わないって言ったり、会えて嬉しくないのかって言ったり、そんなに人のこと振り回して楽しいんですか」
振り回す、などという言葉があまりに思いがけず、佐山は何だかぎょっとした。
「振り回すって、俺は、そんなつもり全然」
「俺には佐山さんの考えてることがさっぱりわかりませんよ。こんな場で他の奴と楽しそうに、俺といる時よりもよっぽど笑ってるあんた見て、俺にどうしろって言うんですか。どうすれば満足なんですか、わけわかんねぇよ」
吐き捨てるように言って、秋口が苛々と髪を掻き上げる。
佐山はさっきからやたら鳴っている心臓を持て余した。怖いのか、辛いのか、それとももっと別の感情が沸き上がっているのか、自分でも判別つかずに戸惑いながら、一度大きく息を吸い込んだ。
秋口はそんな佐山の様子に気づいたふうもなく、うんざりした顔で横を向いてしまっている。
「俺は……ただ、秋口にそうやって俺が誰かと会うたびに機嫌を悪くするのを、やめて欲しい」
「……」
秋口は相槌も打たずに同じ格好でいる。
「そんなんじゃ、秋口以外の誰とも話せなくなる。そういうのは嫌だ」
「あんたは俺のこと好きなんだから、俺とだけ話してればいい」
ぶっきらぼうに秋口が呟いた。まただ、と佐山は思った。秋口はまたこうやって自分のことを、感情で押さえ込もうとする。
それにどうしようもない嫌悪感と不安を覚えずにはいられないことを、どうやったら秋口に伝えられるのか。
「冗談じゃない」
気づくと、佐山は撥ねつけるようにそう言っていた。その強い語調に驚いたように、秋口が佐山を見る。
「そりゃ、俺は秋口のことが好きだよ。気持ちは変わらない」
「だったらどうして」
「だからってそんなふうに拘束される謂われはないよ。そんなこと言われるくらいなら、俺は秋口とは一緒にいられない。いたくない」
きっぱりと断言した佐山に、秋口が一瞬言葉を失くした。
だが、その次の瞬間には、まるで売り言葉に買い言葉のように口を開く。
「俺なしでいられるのかよ」
子供じみたそんな言葉に、佐山は小さく息を吐いた。
結局どう言っても、自分の気持ちなんてきっと秋口には伝わらない気がする。
「秋口が他の誰と何しようと、俺は何も言わないって言っただろ」
「……」
「だから秋口も、俺が誰と会っても、何をしても、口出ししないでくれ」
「……何だよそれ」
短く、秋口が息を吐くように嗤った。
「じゃあ結局、佐山さんが俺を好きだなんて言ったのは嘘じゃないか」
「嘘じゃない。俺は、秋口のことが好きだよ」
幸い周りはできあがった酔客が大きな声で騒いでいたが、佐山は小さな呟きで、もう一度秋口に気持ちを告げた。
秋口はしばらく黙ったまま、佐山のことを見返した。
短い沈黙の後、先に目を逸らしたのは秋口だった。
「……信じられるわけないだろ、そんなこと」
小さな声でそう言うと、秋口は椅子から立ち上がった。
止める言葉ももう思いつかず、佐山は黙って秋口の後ろ姿を見送った。
(ああ……結局、言いはぐった)
先刻、言いかけて、秋口に遮られた言葉。
――でも俺は、できるなら、他の誰とでもない、おまえと楽しく一緒にいられるようにしたいんだ。何か言えばすぐ崩れそうになるような関係のまま、びくびくしておまえの隣にいるのが辛いから、どうしたらそうじゃなくいられるのか、考えたくて――でも俺だって、どうしたらいいのかわからないんだよ。
続けるつもりだった言葉を頭の中で捏ねかけてから、それはもう無意味な作業だと諦める。秋口はもう店を出て行ってしまった。
追い縋ってでもその台詞を言うことができないのは、怖いからだ。
拒絶されるのがではなく、そんなやり方を秋口が受け入れてしまうことが。
(俺も意固地になってる)
あの時、もう一ヵ月以上も前、どうしたら佐山が傷つかずにすむのかと秋口が必死に訊ねた時は、これから少しずつでも何かが変わっていくと信じることができたのだ。だからそれまで言われた言葉もされた仕打ちも全部許そうと思った。
なのに秋口はまだ他の女と会い続けているし、そのくせ佐山には友人とすら会うことを許さない。それがどんなに自分勝手で卑怯なことなのか、本当に秋口は気づいていないのか。佐山は途方に暮れる思いだった。
自分も秋口以外の誰とも会わないから、秋口も自分だけ見ていて欲しいとか――もし秋口が望んでいるのがそんな言葉だとしたら、もしそれで永遠にふたりでいられる保証が手に入るとしても、佐山は口が裂けたってそんなことは言えない。
(たとえ本当は、心のどこかでそれを望んでるとしても)
考えかけ、佐山はそんな自分に気づいて全身が総毛立つ思いになった。
(それじゃ駄目なんだ)
きつく、テーブルの上で両手を握り締める。
(頼むから……気づいてくれよ、秋口)
もう一歩、あと一歩でいいから秋口が近づいてくれるのなら、そうしたら、秋口のことも、自分のことも、佐山は信じることができるのだ。
食欲も湧かずに、佐山が煙草ばかりふかしていると、縞が戻ってきた。後ろに御幸もいる。
「あれ、航は?」
佐山しかしないテーブルを見て、縞が首を傾げた。佐山は苦笑するしかなかった。
「用事思い出したとかで、先に帰りました」
「何だあいつ、挨拶もなしで躾のなってない……」
「御幸? どうした、具合が悪いのか」
縞について席まで歩いてきた御幸の顔色が、ずいぶん悪いことに気づいて、佐山は眉を顰めた。御幸は蒼白な顔で、心なしか足許もふらついているように見える。
「……悪酔いしたみたいだ」
口許を抑えながら、呻くように御幸が言った。自分の上着と荷物に手を伸ばしている。
「御幸が? 珍しいな、これくらいの酒で。大丈夫か? もう帰った方がいいよな?」
御幸が頷いたのを見て、佐山も自分の荷物を取った。
「送るよ。縞さん、すみませんけど今日はこれでお開きに」
「うーん、残念。もうちょっと飲みたい気分だったんですけど」
縞は心から残念そうな顔をしている。全員帰ってしまっては縞に申し訳ないとは思ったが、佐山ものんびり飲み食いする気分ではなくなってしまった。
「じゃ、御幸さんお大事に。佐山さんも気をつけて」
いつもどおり愛想よく言う縞に見送られながら、佐山は御幸と共に、重たい足を引きずりながら店を後にした。
黙っているのも耐え難く、佐山は努めていつもどおりに――と思いながら秋口に声をかけた。
本当に久しぶりで、どういう態度が『いつもどおり』なのか、あやふやになってしまったが。
「……どうも」
秋口は、相変わらず不機嫌さを隠そうともせず、頷くように頭を下げた。
「本当に、すごい偶然だよな。まさか縞さんの従弟っていうのが秋口だなんて、想像もしなかった」
秋口は黙って煙草をふかしている。
間が保たなくて、佐山も煙草に火をつけた。
しばらく重たい沈黙が続いた。ふたりでいて気まずいなんて一度や二度のことじゃないが、今日はまた格別だ。佐山は自分からもう話題を振る気も起きなくて、意味もなくメニュー表を眺めながらひたすら煙を吐き出した。
それがまるで溜息のようだと自分で思った時、今度は秋口の方から口を開いた。
「亮人といる時の方が楽しそうですね」
ぼそりと、低く吐き出された呟きが、佐山には一瞬うまく聞き取れなかった。
「アキト? ……ああ、縞さん?」
下の名前で言われたので、よけいに何のことか、咄嗟にはわからなかったのだ。
「ずいぶん話が弾んでたみたいだし」
明らかに、秋口は拗ねている。佐山は今度こそ本当の溜息をついてしまわないために、多大な努力を要求された。
「そりゃあ、まあ」
溜息をつかないようにすることへ気を取られて、つい本音を漏らしてしまった。
しまった、と思った時にはもう遅い。秋口を取り巻く空気がさっと強張り、その顔からは表情が消えた。
「俺、他に用事があるのを亮人に無理矢理つれてこられただけなんで」
秋口は財布から紙幣を何枚か取り出し、テーブルの上に置いた。
「料理、まだ全部来てないぞ」
立ち上がろうとする秋口の動きを留めるように、佐山はその紙幣を相手の方へ押し遣る。
そんな佐山を見遣って、秋口は笑っていた。
「どうぞみなさんで、ごゆっくり」
久しぶりに見た秋口の笑顔に、そういえばこういう奴だったんだよなと、いまさら佐山は思い出した。自尊心が高くて、嫌みで、子供っぽい。
本当に何だって、自分はまだこんな相手が好きなんだろうかと思いながら、佐山は秋口を見遣った。
「秋口、俺と会えて嬉しくないか」
「こんな場所で?」
訊ねた佐山の質問に、秋口がすぐに反問する。
「佐山さんは嬉しいっていうんですか。気詰まりな、会いたくもない俺が、せっかく楽しく亮人と会ってるところに馬鹿面下げてのこのこ会いに来たのを見て、楽しいって?」
「……そうだな」
笑ったままの秋口に、佐山は自分も力なく笑い返し、首を振った。
「これで、楽しいはずがない」
「ならそんなこと聞くなよ」
秋口の語調は吐き捨てるようだった。
「友達と食事するくらい、俺はいつだってやるよ。秋口だって――」
言ってからまたしまったと思ったが、もう取り返しはつかない。佐山が言葉を飲み込むより早く、秋口がまた皮肉っぽい笑みをその表情に浮かべた。
「俺が、何です」
「……秋口だって、気詰まりな相手といるよりも、楽しくいられる相手と一緒に過ごした方がいいだろ」
他のどんな言い方をしたって、当て擦りになりそうで佐山は怖かった。以前にも同じことを口にしてしまった。秋口だって他の女の子と会っているだろうと。
あの時秋口から返ってきたのは嘲笑だった。思い出せば、佐山はやりきれない気分になる。
あれから秋口が、自分たちの間が、どれほど変わったと言うのか。
そして今も秋口は冷めたような笑い顔を作って、佐山を見下ろしている。その口から出る言葉を聞きたくなくて、佐山は俯いて言を継いだ。
「それに関して俺は何も言わないよ。言う立場じゃない。秋口は秋口が楽しいと思う人と一緒にいればいいと思うし、俺もそうする。でも俺は、できるなら――」
「あんた一体、何なんだ?」
もう苛立ちを隠そうとせず、秋口が佐山の言葉を遮るように言う。
「何……って」
「もう会わないって言ったり、会えて嬉しくないのかって言ったり、そんなに人のこと振り回して楽しいんですか」
振り回す、などという言葉があまりに思いがけず、佐山は何だかぎょっとした。
「振り回すって、俺は、そんなつもり全然」
「俺には佐山さんの考えてることがさっぱりわかりませんよ。こんな場で他の奴と楽しそうに、俺といる時よりもよっぽど笑ってるあんた見て、俺にどうしろって言うんですか。どうすれば満足なんですか、わけわかんねぇよ」
吐き捨てるように言って、秋口が苛々と髪を掻き上げる。
佐山はさっきからやたら鳴っている心臓を持て余した。怖いのか、辛いのか、それとももっと別の感情が沸き上がっているのか、自分でも判別つかずに戸惑いながら、一度大きく息を吸い込んだ。
秋口はそんな佐山の様子に気づいたふうもなく、うんざりした顔で横を向いてしまっている。
「俺は……ただ、秋口にそうやって俺が誰かと会うたびに機嫌を悪くするのを、やめて欲しい」
「……」
秋口は相槌も打たずに同じ格好でいる。
「そんなんじゃ、秋口以外の誰とも話せなくなる。そういうのは嫌だ」
「あんたは俺のこと好きなんだから、俺とだけ話してればいい」
ぶっきらぼうに秋口が呟いた。まただ、と佐山は思った。秋口はまたこうやって自分のことを、感情で押さえ込もうとする。
それにどうしようもない嫌悪感と不安を覚えずにはいられないことを、どうやったら秋口に伝えられるのか。
「冗談じゃない」
気づくと、佐山は撥ねつけるようにそう言っていた。その強い語調に驚いたように、秋口が佐山を見る。
「そりゃ、俺は秋口のことが好きだよ。気持ちは変わらない」
「だったらどうして」
「だからってそんなふうに拘束される謂われはないよ。そんなこと言われるくらいなら、俺は秋口とは一緒にいられない。いたくない」
きっぱりと断言した佐山に、秋口が一瞬言葉を失くした。
だが、その次の瞬間には、まるで売り言葉に買い言葉のように口を開く。
「俺なしでいられるのかよ」
子供じみたそんな言葉に、佐山は小さく息を吐いた。
結局どう言っても、自分の気持ちなんてきっと秋口には伝わらない気がする。
「秋口が他の誰と何しようと、俺は何も言わないって言っただろ」
「……」
「だから秋口も、俺が誰と会っても、何をしても、口出ししないでくれ」
「……何だよそれ」
短く、秋口が息を吐くように嗤った。
「じゃあ結局、佐山さんが俺を好きだなんて言ったのは嘘じゃないか」
「嘘じゃない。俺は、秋口のことが好きだよ」
幸い周りはできあがった酔客が大きな声で騒いでいたが、佐山は小さな呟きで、もう一度秋口に気持ちを告げた。
秋口はしばらく黙ったまま、佐山のことを見返した。
短い沈黙の後、先に目を逸らしたのは秋口だった。
「……信じられるわけないだろ、そんなこと」
小さな声でそう言うと、秋口は椅子から立ち上がった。
止める言葉ももう思いつかず、佐山は黙って秋口の後ろ姿を見送った。
(ああ……結局、言いはぐった)
先刻、言いかけて、秋口に遮られた言葉。
――でも俺は、できるなら、他の誰とでもない、おまえと楽しく一緒にいられるようにしたいんだ。何か言えばすぐ崩れそうになるような関係のまま、びくびくしておまえの隣にいるのが辛いから、どうしたらそうじゃなくいられるのか、考えたくて――でも俺だって、どうしたらいいのかわからないんだよ。
続けるつもりだった言葉を頭の中で捏ねかけてから、それはもう無意味な作業だと諦める。秋口はもう店を出て行ってしまった。
追い縋ってでもその台詞を言うことができないのは、怖いからだ。
拒絶されるのがではなく、そんなやり方を秋口が受け入れてしまうことが。
(俺も意固地になってる)
あの時、もう一ヵ月以上も前、どうしたら佐山が傷つかずにすむのかと秋口が必死に訊ねた時は、これから少しずつでも何かが変わっていくと信じることができたのだ。だからそれまで言われた言葉もされた仕打ちも全部許そうと思った。
なのに秋口はまだ他の女と会い続けているし、そのくせ佐山には友人とすら会うことを許さない。それがどんなに自分勝手で卑怯なことなのか、本当に秋口は気づいていないのか。佐山は途方に暮れる思いだった。
自分も秋口以外の誰とも会わないから、秋口も自分だけ見ていて欲しいとか――もし秋口が望んでいるのがそんな言葉だとしたら、もしそれで永遠にふたりでいられる保証が手に入るとしても、佐山は口が裂けたってそんなことは言えない。
(たとえ本当は、心のどこかでそれを望んでるとしても)
考えかけ、佐山はそんな自分に気づいて全身が総毛立つ思いになった。
(それじゃ駄目なんだ)
きつく、テーブルの上で両手を握り締める。
(頼むから……気づいてくれよ、秋口)
もう一歩、あと一歩でいいから秋口が近づいてくれるのなら、そうしたら、秋口のことも、自分のことも、佐山は信じることができるのだ。
食欲も湧かずに、佐山が煙草ばかりふかしていると、縞が戻ってきた。後ろに御幸もいる。
「あれ、航は?」
佐山しかしないテーブルを見て、縞が首を傾げた。佐山は苦笑するしかなかった。
「用事思い出したとかで、先に帰りました」
「何だあいつ、挨拶もなしで躾のなってない……」
「御幸? どうした、具合が悪いのか」
縞について席まで歩いてきた御幸の顔色が、ずいぶん悪いことに気づいて、佐山は眉を顰めた。御幸は蒼白な顔で、心なしか足許もふらついているように見える。
「……悪酔いしたみたいだ」
口許を抑えながら、呻くように御幸が言った。自分の上着と荷物に手を伸ばしている。
「御幸が? 珍しいな、これくらいの酒で。大丈夫か? もう帰った方がいいよな?」
御幸が頷いたのを見て、佐山も自分の荷物を取った。
「送るよ。縞さん、すみませんけど今日はこれでお開きに」
「うーん、残念。もうちょっと飲みたい気分だったんですけど」
縞は心から残念そうな顔をしている。全員帰ってしまっては縞に申し訳ないとは思ったが、佐山ものんびり飲み食いする気分ではなくなってしまった。
「じゃ、御幸さんお大事に。佐山さんも気をつけて」
いつもどおり愛想よく言う縞に見送られながら、佐山は御幸と共に、重たい足を引きずりながら店を後にした。
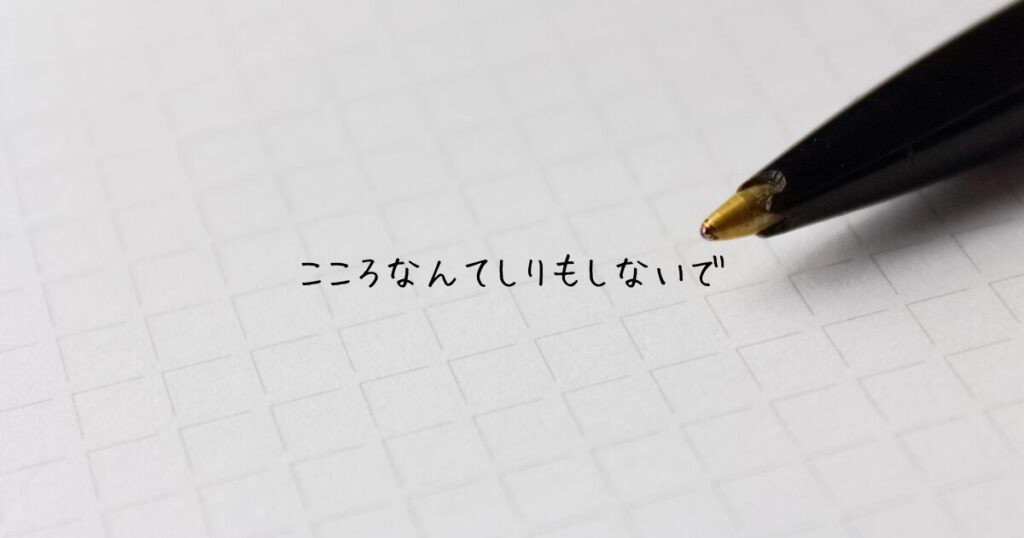
サラリーマン×サラリーマン

商業誌番外編

商業誌番外編

商業誌番外編
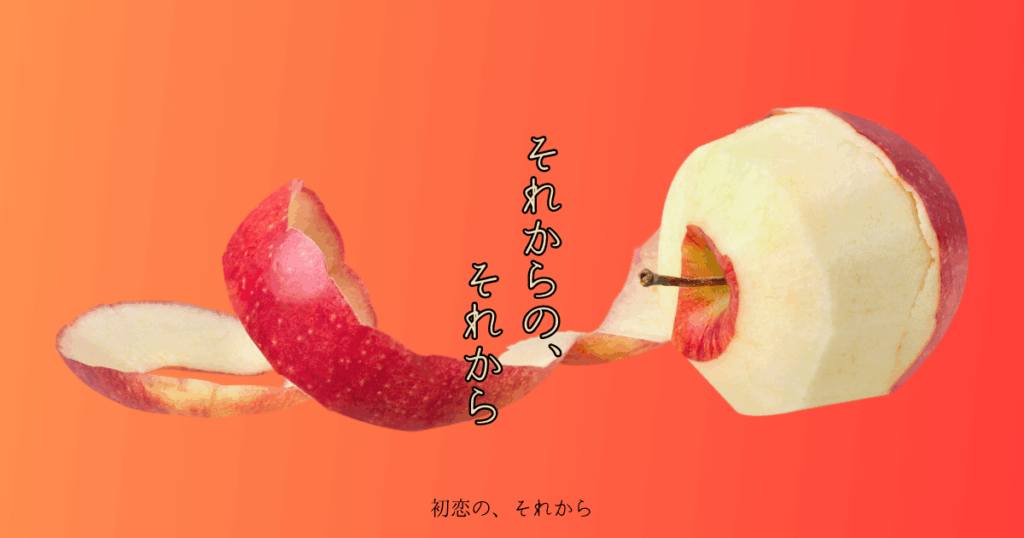
商業誌番外編
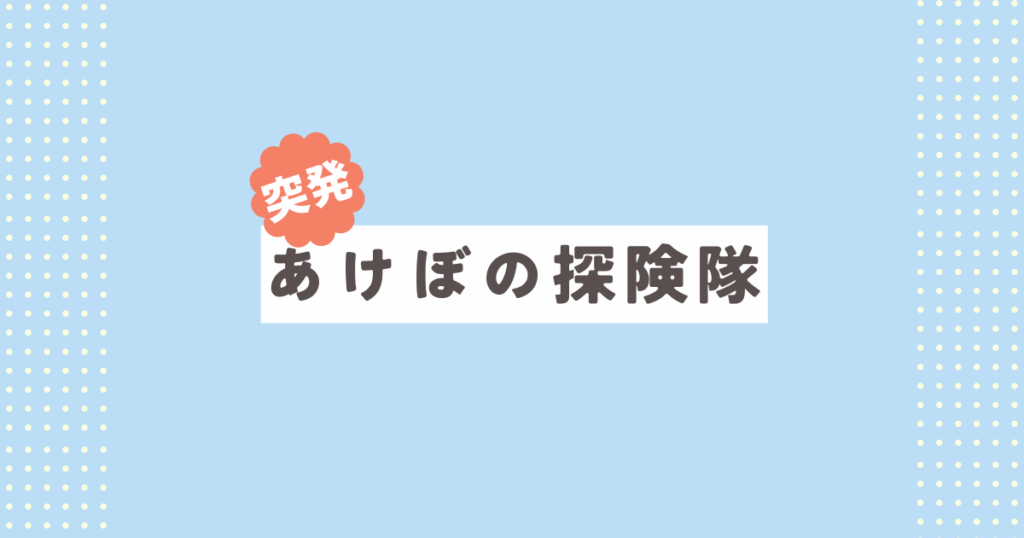
同人誌シリーズ番外編

高校生の恋未満読み切り