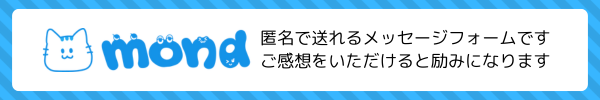エレベーターでばったり秋口と乗り合わせた。
「あ」
先に秋口が乗っていたところに、佐山が後から乗り込む形だ。タイミングがいいのか悪いのか、他に乗客はいない。多分悪い方だ、と思いながら佐山はエレベータに乗り込む。苦笑気味に佐山が秋口を見ると、突慳貪な、顎で頷くような仕種が返ってきた。
「九階ですか」
「あ、うん」
秋口と佐山の仕事場は同じフロアにある。先にその階のボタンが押されていたのでそのままエレベータの奥に収まったら、秋口が声をかけてきて、佐山は少し驚く。
「秋口は外回りか?」
「はあ、まあ」
自分から声をかけてきた割に、秋口の語調は無愛想だ。
「……佐山さんは?」
「ああ、俺は沙和――総務に用事。出さなきゃいけない書類があって」
それでも言葉が交わせたことが嬉しくて答えた佐山に、秋口は返事をしなかった。エレベータはあっという間に九階についてしまい、秋口はやっぱり振り返ることもなく、足早に廊下を去っていってしまった。
取り残され、佐山はぼんやりとその後ろ姿を見送る。
背が高くて、モデルみたいな体型で、脚が長くて、歩き方まで見事なもんだと、佐山は感心してしまう。
(……怒るところだったのか、今のは)
元恋人のことをつい名前で呼んでしまった瞬間、しまったと思って言い直したのだから、それが地雷らしいというのは佐山も承知の上だったのだ。
以前秋口は、彼女、雛川沙和子と佐山がいるところを見て不機嫌になった。
(何もしない割に、俺が『秋口にとって』他人のものだと思えることには腹を立てるんだよな)
そういうふうに、今あの背中を追いかけていって言ってみたら、秋口はどういう反応を示すだろうか。
想像して、佐山は溜息をついた。
だったら何だよと、余計に不機嫌になって終わりだろうと、簡単に想像がつく。
そしてそう言われてしまえば、自分には答えようなく、黙り込んでしまうしか道はないということも。
「煮え切らないなあ……」
自分も、秋口も。
佐山が大きく溜息をついた時、ポケットの中で携帯電話の着信メロディが鳴った。アドレス帳に登録していない番号用の音楽だ。取引先の誰かだろうか、と思いながら通話ボタンを押し、電話を耳につけた。
「はい、佐山」
『あ、突然すみません、先日お会いした縞です』
(シマ――?)
耳慣れない名前の響きを聞きながら、佐山は背筋が震える感覚を味わった。
低くて、よく響く、そして柔らかい感触の声だった。
『ほら、先週の水曜日に一緒に警察にご厄介になった』
「ああ、あの時の」
言われて思い出した。先週、買い物の途中で引ったくりに遭遇した時、一緒にその犯人を捕まえた若い男だ。そう言えば名刺を交換した。あの日は慌ただしかったので(結局佐山は背広を買えずに帰る羽目になった)、改めて礼をしたいと言われ、大したことじゃないからと遠慮したのだが、先に名刺を出されてつい自分のものも渡してしまった。営業担当時代に染みついた悲しい癖だ。
「お怪我はもう大丈夫ですか?」
犯人と格闘して、痛々しい傷が顔にできていたのを佐山は思い出す。電話の向こうで照れ臭そうに笑う気配がした。
(うわ……)
佐山は再び心臓を鳴らす。
『おかげさまで。やっと痕が消えてきたので、お約束どおり誘いの電話です。今晩辺りお時間いただけないかと思いまして』
「や――あの、でも、本当にこっちが何したってわけじゃありませんから」
戸惑いつつ、佐山は狼狽した様子が相手に伝わらないよう気をつけて答えた。
『ご迷惑ですか?』
「いえ、そういうわけじゃ」
『仕事で、今晩またこの間の駅の方まで寄るんですよ。佐山さんの会社からも近いみたいだから。駄目ですか?』
――この声で、そんなふうに問われて、無下にできるほど今の佐山は元気じゃない。
「……俺、酒が一切駄目なんです。それでも大丈夫なら」
『料理のおいしい店、夜までに捜しておきますよ』
嬉しそうに、笑った調子で答える声。佐山もつい、つられて微笑んでしまった。
「じゃあ、楽しみにさせていただきます」
待ち合わせの場所と時間を決めて、佐山は縞との電話を切った。
ポケットに電話をしまう途中、思い出して今度は手帳を取り出す。カバーの見返しに挟んでおいた名刺を確認した。
『縞亮人』という名前には肩書きがなく、ただ『Akito Shima』とローマ字で読み仮名が振ってある。あとは個人の自宅らしいマンションの住所と、ファックスと共用の電話番号、メールアドレス、携帯電話の番号。事務的な名刺よりもデザイン的で紙の色も質も凝っている。
(何やってる人なんだろう)
出会った日に着ていたのはたしかそれほどかっちりしていないジャケットにシャツ、服装では自分と同じような会社員には見えなかった。その雰囲気も。
「よう、どうした佐山。こんなところに突っ立って」
名刺に見入っていると、後ろから肩を叩かれた。振り返ると、御幸の姿がある。エレベータから降りたところで佐山の姿をみつけたらしい。
「ん? 新しい仕事の相手か? ずいぶん個性的な名刺だな」
佐山の手にした事務的とは言えない珍しい名刺に目を止め、御幸が首を傾げる。
「仕事の相手じゃなくて――」
佐山は縞と出会った状況や、たった今食事に誘われたことを御幸にかいつまんで説明した。
御幸は佐山の話を聞きながら、そこはかとなく表情を曇らせている。
「何だそれ、大丈夫か? 変なやつじゃないだろうな」
「変って、宗教とか?」
御幸の心配も、佐山には理解できる。連絡するとは言われていたが、社交辞令のようなものだと理解していたし、一週間も経った今になって、本当に誘われるとは佐山も思っていなかった。
「そう、マルチとか。その名刺、肩書きがなくておかしいぞ」
「怪しい人には見えなかったけどな、すごく人当たりがよくて、事件に遭っておろおろしてる被害者のおばあさんを励ましてあげてたし、いい人みたいだった」
「見るからにいい人なんてむしろ怪しいだろ、このご時世」
「そんなこと言ったら、御幸も充分怪しい範疇だぞ」
御幸も、きっと初対面の、ましてや見るからに動揺している女性がいたら、間違いなく優しくするだろう。
そう佐山に言われて、御幸は複雑そうな顔で息を吐いた。
「俺がついていければいいんだけど、今日残業なんだよな」
「大丈夫だって、本当におかしな人には見えなかったし、それにいざ何かあったら、殴り飛ばして逃げるよ」
「まあ……滅多なことは考えないか、相手も。佐山が引ったくり犯のしたところを目の当たりにしたんだもんな」
御幸はそう言って自分を納得させ、それでも「何かあったらすぐ俺に連絡しろよ」と佐山に言い含めてから去っていった。
佐山はもう一度名刺に視線を落としてから、それを再び手帳に挟み込んで丁寧にしまう。
どことなく、自分の心が夜の再開を楽しみにして浮き上がっているのを感じた。
「あ」
先に秋口が乗っていたところに、佐山が後から乗り込む形だ。タイミングがいいのか悪いのか、他に乗客はいない。多分悪い方だ、と思いながら佐山はエレベータに乗り込む。苦笑気味に佐山が秋口を見ると、突慳貪な、顎で頷くような仕種が返ってきた。
「九階ですか」
「あ、うん」
秋口と佐山の仕事場は同じフロアにある。先にその階のボタンが押されていたのでそのままエレベータの奥に収まったら、秋口が声をかけてきて、佐山は少し驚く。
「秋口は外回りか?」
「はあ、まあ」
自分から声をかけてきた割に、秋口の語調は無愛想だ。
「……佐山さんは?」
「ああ、俺は沙和――総務に用事。出さなきゃいけない書類があって」
それでも言葉が交わせたことが嬉しくて答えた佐山に、秋口は返事をしなかった。エレベータはあっという間に九階についてしまい、秋口はやっぱり振り返ることもなく、足早に廊下を去っていってしまった。
取り残され、佐山はぼんやりとその後ろ姿を見送る。
背が高くて、モデルみたいな体型で、脚が長くて、歩き方まで見事なもんだと、佐山は感心してしまう。
(……怒るところだったのか、今のは)
元恋人のことをつい名前で呼んでしまった瞬間、しまったと思って言い直したのだから、それが地雷らしいというのは佐山も承知の上だったのだ。
以前秋口は、彼女、雛川沙和子と佐山がいるところを見て不機嫌になった。
(何もしない割に、俺が『秋口にとって』他人のものだと思えることには腹を立てるんだよな)
そういうふうに、今あの背中を追いかけていって言ってみたら、秋口はどういう反応を示すだろうか。
想像して、佐山は溜息をついた。
だったら何だよと、余計に不機嫌になって終わりだろうと、簡単に想像がつく。
そしてそう言われてしまえば、自分には答えようなく、黙り込んでしまうしか道はないということも。
「煮え切らないなあ……」
自分も、秋口も。
佐山が大きく溜息をついた時、ポケットの中で携帯電話の着信メロディが鳴った。アドレス帳に登録していない番号用の音楽だ。取引先の誰かだろうか、と思いながら通話ボタンを押し、電話を耳につけた。
「はい、佐山」
『あ、突然すみません、先日お会いした縞です』
(シマ――?)
耳慣れない名前の響きを聞きながら、佐山は背筋が震える感覚を味わった。
低くて、よく響く、そして柔らかい感触の声だった。
『ほら、先週の水曜日に一緒に警察にご厄介になった』
「ああ、あの時の」
言われて思い出した。先週、買い物の途中で引ったくりに遭遇した時、一緒にその犯人を捕まえた若い男だ。そう言えば名刺を交換した。あの日は慌ただしかったので(結局佐山は背広を買えずに帰る羽目になった)、改めて礼をしたいと言われ、大したことじゃないからと遠慮したのだが、先に名刺を出されてつい自分のものも渡してしまった。営業担当時代に染みついた悲しい癖だ。
「お怪我はもう大丈夫ですか?」
犯人と格闘して、痛々しい傷が顔にできていたのを佐山は思い出す。電話の向こうで照れ臭そうに笑う気配がした。
(うわ……)
佐山は再び心臓を鳴らす。
『おかげさまで。やっと痕が消えてきたので、お約束どおり誘いの電話です。今晩辺りお時間いただけないかと思いまして』
「や――あの、でも、本当にこっちが何したってわけじゃありませんから」
戸惑いつつ、佐山は狼狽した様子が相手に伝わらないよう気をつけて答えた。
『ご迷惑ですか?』
「いえ、そういうわけじゃ」
『仕事で、今晩またこの間の駅の方まで寄るんですよ。佐山さんの会社からも近いみたいだから。駄目ですか?』
――この声で、そんなふうに問われて、無下にできるほど今の佐山は元気じゃない。
「……俺、酒が一切駄目なんです。それでも大丈夫なら」
『料理のおいしい店、夜までに捜しておきますよ』
嬉しそうに、笑った調子で答える声。佐山もつい、つられて微笑んでしまった。
「じゃあ、楽しみにさせていただきます」
待ち合わせの場所と時間を決めて、佐山は縞との電話を切った。
ポケットに電話をしまう途中、思い出して今度は手帳を取り出す。カバーの見返しに挟んでおいた名刺を確認した。
『縞亮人』という名前には肩書きがなく、ただ『Akito Shima』とローマ字で読み仮名が振ってある。あとは個人の自宅らしいマンションの住所と、ファックスと共用の電話番号、メールアドレス、携帯電話の番号。事務的な名刺よりもデザイン的で紙の色も質も凝っている。
(何やってる人なんだろう)
出会った日に着ていたのはたしかそれほどかっちりしていないジャケットにシャツ、服装では自分と同じような会社員には見えなかった。その雰囲気も。
「よう、どうした佐山。こんなところに突っ立って」
名刺に見入っていると、後ろから肩を叩かれた。振り返ると、御幸の姿がある。エレベータから降りたところで佐山の姿をみつけたらしい。
「ん? 新しい仕事の相手か? ずいぶん個性的な名刺だな」
佐山の手にした事務的とは言えない珍しい名刺に目を止め、御幸が首を傾げる。
「仕事の相手じゃなくて――」
佐山は縞と出会った状況や、たった今食事に誘われたことを御幸にかいつまんで説明した。
御幸は佐山の話を聞きながら、そこはかとなく表情を曇らせている。
「何だそれ、大丈夫か? 変なやつじゃないだろうな」
「変って、宗教とか?」
御幸の心配も、佐山には理解できる。連絡するとは言われていたが、社交辞令のようなものだと理解していたし、一週間も経った今になって、本当に誘われるとは佐山も思っていなかった。
「そう、マルチとか。その名刺、肩書きがなくておかしいぞ」
「怪しい人には見えなかったけどな、すごく人当たりがよくて、事件に遭っておろおろしてる被害者のおばあさんを励ましてあげてたし、いい人みたいだった」
「見るからにいい人なんてむしろ怪しいだろ、このご時世」
「そんなこと言ったら、御幸も充分怪しい範疇だぞ」
御幸も、きっと初対面の、ましてや見るからに動揺している女性がいたら、間違いなく優しくするだろう。
そう佐山に言われて、御幸は複雑そうな顔で息を吐いた。
「俺がついていければいいんだけど、今日残業なんだよな」
「大丈夫だって、本当におかしな人には見えなかったし、それにいざ何かあったら、殴り飛ばして逃げるよ」
「まあ……滅多なことは考えないか、相手も。佐山が引ったくり犯のしたところを目の当たりにしたんだもんな」
御幸はそう言って自分を納得させ、それでも「何かあったらすぐ俺に連絡しろよ」と佐山に言い含めてから去っていった。
佐山はもう一度名刺に視線を落としてから、それを再び手帳に挟み込んで丁寧にしまう。
どことなく、自分の心が夜の再開を楽しみにして浮き上がっているのを感じた。
◇◇◇
縞が指定したのは、駅から歩いて少しの蕎麦屋だった。駅で待ち合わせをして店まで歩き、向かい合って座る。そう広くはない店内はほぼ満席だったが、ひとつひとつの席がついたてで仕切られているし、落ち着いた上品そうな雰囲気の店だから騒がしくもない。
「静かで、いいお店ですね」
鴨南蛮を注文し、お手拭を使いながら、佐山は心から言った。
「でしょう、俺は昼しか来たことがなかったんですけど、夜も酔っぱらいとか学生のたまり場なんかにはならないから、ゆっくり食事するにはいいって聞いて」
縞はヘンリーネックのカットソーにデニムパンツと、よく似合っているが、やはり堅気の会社員には見えない格好をしていた。細見でとてもセンスがいい。見た目も結構な男前だったが、それよりも彼の持つ明るく人好きのする雰囲気に、佐山は好感を持った。
「ご自宅は神奈川の方みたいですけど、この辺はお仕事で?」
もらった名刺のことを思い出しながら、佐山は訊ねてみた。煙草が吸いたかったが、生憎この店は終日禁煙だ。
「ええ、納品先がここら辺で。作業自体は自宅でやってるんですけどね」
「じゃあ、自営業の方ですか。アパレル関係とか……」
彼の服や持っているもののセンスのよさから、佐山がそう訊ねてみると、笑って否定された。
「そう見えてるんだったら嬉しいなあ、実はオタクなんです。フリーのライター兼グラフィックデザイナーみたいなことやってて」
「じゃあ、近いのは出版社」
「そうです。この間はやっと仕上げた雑誌の企画ページを持って届けにいくところで」
「徹夜明けっておっしゃってましたよね、そういえば」
佐山は心底から縞に同情した。警察から事情を聞かれる間はともかく、被害者のおばあさんが何しろけたたましく、涙混じりのお礼から始まって、最近の若者には珍しく勇敢だ、うちの子供や孫なんて……と身の上話が続き、その間縞はたまに眠たそうに目を擦りながらも、根気よく彼女の相手をしていた。
佐山も同じだけつき合わされたのだが。
「でも何でも経験すれはメシの種ですからね。何にでもなるべく首突っ込もうってやっかいな癖があるんです」
「すごいなあ、プロ根性ってやつですね」
「いやそんな大袈裟なもんじゃ全然ないですよ」
照れたように笑った縞の表情が好ましくて、佐山はつられてにっこりした。
そんな佐山を、縞がしげしげと眺める。表情に気づいて、佐山は少し首を傾げた。
「何か?」
「いやね。この間、あの引ったくり犯を捕まえたのがここにいる人だって言うのが、いまいち信じられないんですよ。あの時、咄嗟に俺も手を出しちゃったけど、完全に力負けしてみっともなく転がされるし。でも佐山さん、結構あっさり相手のこと、やっつけてたでしょう」
佐山は自分が決して立派な体格とは言えないことを承知している。縞の驚きはもっともだと思った。
「たまたま、運がよかったんですよ」
ほぼ初対面の人の前で、実はよく通りすがりに因縁をつけられますとか、昔いじめっ子と戦っていたら喧嘩のコツを覚えましたなどと説明するわけにもいかず、佐山はそう言い訳した。
「格好よかったなあ、あの時の佐山さん。暴漢をよろめかして、顔面に一発! 自分がやられて地面に倒れてるってのに、つい見とれてしまいました」
「野蛮で……お恥ずかしい」
「勇猛果敢と言っておきましょうよ。だからね、あんなに大立ち回りをした勇敢な人が、こんなに可憐だなんて、そのギャップがおもしろい」
佐山は飲みかけのお茶を吹きそうになった。
「可憐……って、あんまりいい年の男に使う言葉じゃありませんよね」
「性別にはこだわらないタチなんです」
「はあ」
物書きをしているというから、言語センスが常人と違うのだろう、と佐山が自分を納得させた時、お互い注文した蕎麦がテーブルにやってきた。縞が頼んだのはあなごの天ぷら蕎麦だ。
「おもしろそうな人だなと思って、声かけたんですよ。穏やかそうな優しい笑顔の下に、どんな心が隠れてるのかなって」
割り箸を割りながら、縞が言う。佐山もそれに倣いながら、苦笑した。
「ごく平凡なサラリーマンですよ。とりたてて人に誇るような部分もないし」
「俺の知り合いには、暴漢をふたりのしちゃえるような平凡なサラリーマンはいませんから。いろんな人つき合って見識を広めるのも、俺の仕事と趣味なんです」
サンプル扱いされているようなものだったが、人なつこい縞の態度のおかげか不快感はまるでない。佐山も一緒に笑った。
「俺も男に可憐っていう言葉を使うライターさんの知り合いは初めてです」
「仲よくしてやってください」
言われるまでもなく、佐山はこの会って二回目の男に、好感を抱いていた。
(何だろう、やっぱり、縞さんといるのは楽しいな)
アルコールはもちろん入っていないのに、佐山の心臓が少し早い。慣れない相手に緊張している感じとも違った。
蕎麦は美味く、食事も会話も進む。縞はあちこち出かけたり人と会ったりを生業にしているようなものだと本人が言うだけあって、話題は多彩だし、何より話し上手で、佐山はとても楽しい時間を過ごすことができた。
待ち合わせたのが佐山の都合で八時頃、のんびり食事をして、お茶を飲みながら気づけば二時間近く、お互いの仕事の都合で、河岸を変えることもなく十時過ぎに店を出て、佐山は縞と並んで駅に向かった。
会計の時、縞は助けてもらったお礼に奢ると申し出たのだが、佐山が遠慮して、結局折半になった。
「その代わり、また食事つき合ってもらえますか?」
縞の言葉に、佐山は笑って頷いた。週に一度は都内に出るが、仕事相手とのつきあいでの飲み食いは煩わしい、断る口実がほしいのだと説明されて、断る理由もない。奇妙な出会いではあったが、食事を終える頃には、佐山は最初の印象よりもっと縞に好感を持った。
ここのところ、仕事絡み以外で知り合いができることなんて滅多になかったから、こういうのも悪くないよなと思った。
「そういえば今日電話した時、もしかしなくてもお仕事中でしたよね。すみません、お邪魔してしまって」
並んで歩道を歩く縞が、思い出したように佐山に言った。
「ちょうど手の空いた時だったから、大丈夫でしたよ」
「自分が不規則な仕事してるもんだから、時間の感覚がおかしくなってるんです。次連絡するなら、メールの方がいいかな。佐山さん携帯同じ会社ですよね、直通メール入れてもいいですか?」
どうやら社交辞令ではなく誘ってくれているらしい。
「構いませんよ、すぐには返事できない時もあるかもしれないけど」
「都合あった時で全然。割と思いつきで動くタチなんで、急に連絡することも多いだろうから、気にせず返事下さい」
「わかりました」
駅の近くまで来た時、それまで車通りは多いが混み合うわけでもなく、クラクションで煽る者もいなかったから静かだった隣の車道が、不意に騒がしくなった。事故でもあったのか、病院の救急車輌がサイレンを鳴らしながら信号を渡ろうとしている。道を開けるよう救急隊員が放送する声に、しかしいくつかの乗用車は従わず、青信号を平然と渡っていった。
「マナー悪いなあ」
様子を見ていた縞が、憤った声を上げる。
「本当に。救急なんだから、少しくらい待てばいいのに――」
頷きながら縞の方を何気なく見上げた佐山は、瞬間、小さく目を瞠った。
今日会った時から終始明るい笑みを浮かべていた縞の、初めて見る曇った表情。
その顔に、佐山はぎくりとしてしまった。
(秋口に、似てる……)
声が似ているとも思っていた。だが、顔立ちまで似ているとは気づかなかった。顔の造りのどこが似ているというわけでもない。秋口は涼しげな切れ長の目をしていたが、縞は目尻に笑いじわの寄る優しい顔立ちだったし、秋口の唇は少し薄情そうに薄いけれど、縞は妙に色気のある、厚みを持った尻上がりの唇だ。
タイプはまったく違うのに、ふとした表情と角度で、驚くほどふたりが似ていて、佐山は思わず絶句した。
「ん?」
目を瞠って自分を見ている佐山の視線に気づき、縞が不思議そうに首を傾げた。
明るい笑い声もあまり似ていない。少しひそめて低くなった時や、冗談めかしてまじめな声音になった時は、心臓が止まりそうなくらいそっくりだった。
「佐山さん? どうかしましたか?」
間近で顔を覗き込まれ、佐山はぎょっとして軽く身を引いた。縞がますます怪訝そうな顔になる。さすがに失礼な反応だと、佐山は慌てた。
「す、すみません……あんまりいい男だから、見とれちゃって」
冗談で誤魔化そうと、佐山は初対面の時と同じ言い訳をして、しかしその言葉の気恥ずかしさにひとり赤くなった。
縞はそんな佐山の反応を興味深そうに眺めて、変に思われたに違いないと佐山がいたたまれない気分になる半歩手前のタイミングでにっこり笑うと、
「よく言われます」
とてらいもなく答えた。
「静かで、いいお店ですね」
鴨南蛮を注文し、お手拭を使いながら、佐山は心から言った。
「でしょう、俺は昼しか来たことがなかったんですけど、夜も酔っぱらいとか学生のたまり場なんかにはならないから、ゆっくり食事するにはいいって聞いて」
縞はヘンリーネックのカットソーにデニムパンツと、よく似合っているが、やはり堅気の会社員には見えない格好をしていた。細見でとてもセンスがいい。見た目も結構な男前だったが、それよりも彼の持つ明るく人好きのする雰囲気に、佐山は好感を持った。
「ご自宅は神奈川の方みたいですけど、この辺はお仕事で?」
もらった名刺のことを思い出しながら、佐山は訊ねてみた。煙草が吸いたかったが、生憎この店は終日禁煙だ。
「ええ、納品先がここら辺で。作業自体は自宅でやってるんですけどね」
「じゃあ、自営業の方ですか。アパレル関係とか……」
彼の服や持っているもののセンスのよさから、佐山がそう訊ねてみると、笑って否定された。
「そう見えてるんだったら嬉しいなあ、実はオタクなんです。フリーのライター兼グラフィックデザイナーみたいなことやってて」
「じゃあ、近いのは出版社」
「そうです。この間はやっと仕上げた雑誌の企画ページを持って届けにいくところで」
「徹夜明けっておっしゃってましたよね、そういえば」
佐山は心底から縞に同情した。警察から事情を聞かれる間はともかく、被害者のおばあさんが何しろけたたましく、涙混じりのお礼から始まって、最近の若者には珍しく勇敢だ、うちの子供や孫なんて……と身の上話が続き、その間縞はたまに眠たそうに目を擦りながらも、根気よく彼女の相手をしていた。
佐山も同じだけつき合わされたのだが。
「でも何でも経験すれはメシの種ですからね。何にでもなるべく首突っ込もうってやっかいな癖があるんです」
「すごいなあ、プロ根性ってやつですね」
「いやそんな大袈裟なもんじゃ全然ないですよ」
照れたように笑った縞の表情が好ましくて、佐山はつられてにっこりした。
そんな佐山を、縞がしげしげと眺める。表情に気づいて、佐山は少し首を傾げた。
「何か?」
「いやね。この間、あの引ったくり犯を捕まえたのがここにいる人だって言うのが、いまいち信じられないんですよ。あの時、咄嗟に俺も手を出しちゃったけど、完全に力負けしてみっともなく転がされるし。でも佐山さん、結構あっさり相手のこと、やっつけてたでしょう」
佐山は自分が決して立派な体格とは言えないことを承知している。縞の驚きはもっともだと思った。
「たまたま、運がよかったんですよ」
ほぼ初対面の人の前で、実はよく通りすがりに因縁をつけられますとか、昔いじめっ子と戦っていたら喧嘩のコツを覚えましたなどと説明するわけにもいかず、佐山はそう言い訳した。
「格好よかったなあ、あの時の佐山さん。暴漢をよろめかして、顔面に一発! 自分がやられて地面に倒れてるってのに、つい見とれてしまいました」
「野蛮で……お恥ずかしい」
「勇猛果敢と言っておきましょうよ。だからね、あんなに大立ち回りをした勇敢な人が、こんなに可憐だなんて、そのギャップがおもしろい」
佐山は飲みかけのお茶を吹きそうになった。
「可憐……って、あんまりいい年の男に使う言葉じゃありませんよね」
「性別にはこだわらないタチなんです」
「はあ」
物書きをしているというから、言語センスが常人と違うのだろう、と佐山が自分を納得させた時、お互い注文した蕎麦がテーブルにやってきた。縞が頼んだのはあなごの天ぷら蕎麦だ。
「おもしろそうな人だなと思って、声かけたんですよ。穏やかそうな優しい笑顔の下に、どんな心が隠れてるのかなって」
割り箸を割りながら、縞が言う。佐山もそれに倣いながら、苦笑した。
「ごく平凡なサラリーマンですよ。とりたてて人に誇るような部分もないし」
「俺の知り合いには、暴漢をふたりのしちゃえるような平凡なサラリーマンはいませんから。いろんな人つき合って見識を広めるのも、俺の仕事と趣味なんです」
サンプル扱いされているようなものだったが、人なつこい縞の態度のおかげか不快感はまるでない。佐山も一緒に笑った。
「俺も男に可憐っていう言葉を使うライターさんの知り合いは初めてです」
「仲よくしてやってください」
言われるまでもなく、佐山はこの会って二回目の男に、好感を抱いていた。
(何だろう、やっぱり、縞さんといるのは楽しいな)
アルコールはもちろん入っていないのに、佐山の心臓が少し早い。慣れない相手に緊張している感じとも違った。
蕎麦は美味く、食事も会話も進む。縞はあちこち出かけたり人と会ったりを生業にしているようなものだと本人が言うだけあって、話題は多彩だし、何より話し上手で、佐山はとても楽しい時間を過ごすことができた。
待ち合わせたのが佐山の都合で八時頃、のんびり食事をして、お茶を飲みながら気づけば二時間近く、お互いの仕事の都合で、河岸を変えることもなく十時過ぎに店を出て、佐山は縞と並んで駅に向かった。
会計の時、縞は助けてもらったお礼に奢ると申し出たのだが、佐山が遠慮して、結局折半になった。
「その代わり、また食事つき合ってもらえますか?」
縞の言葉に、佐山は笑って頷いた。週に一度は都内に出るが、仕事相手とのつきあいでの飲み食いは煩わしい、断る口実がほしいのだと説明されて、断る理由もない。奇妙な出会いではあったが、食事を終える頃には、佐山は最初の印象よりもっと縞に好感を持った。
ここのところ、仕事絡み以外で知り合いができることなんて滅多になかったから、こういうのも悪くないよなと思った。
「そういえば今日電話した時、もしかしなくてもお仕事中でしたよね。すみません、お邪魔してしまって」
並んで歩道を歩く縞が、思い出したように佐山に言った。
「ちょうど手の空いた時だったから、大丈夫でしたよ」
「自分が不規則な仕事してるもんだから、時間の感覚がおかしくなってるんです。次連絡するなら、メールの方がいいかな。佐山さん携帯同じ会社ですよね、直通メール入れてもいいですか?」
どうやら社交辞令ではなく誘ってくれているらしい。
「構いませんよ、すぐには返事できない時もあるかもしれないけど」
「都合あった時で全然。割と思いつきで動くタチなんで、急に連絡することも多いだろうから、気にせず返事下さい」
「わかりました」
駅の近くまで来た時、それまで車通りは多いが混み合うわけでもなく、クラクションで煽る者もいなかったから静かだった隣の車道が、不意に騒がしくなった。事故でもあったのか、病院の救急車輌がサイレンを鳴らしながら信号を渡ろうとしている。道を開けるよう救急隊員が放送する声に、しかしいくつかの乗用車は従わず、青信号を平然と渡っていった。
「マナー悪いなあ」
様子を見ていた縞が、憤った声を上げる。
「本当に。救急なんだから、少しくらい待てばいいのに――」
頷きながら縞の方を何気なく見上げた佐山は、瞬間、小さく目を瞠った。
今日会った時から終始明るい笑みを浮かべていた縞の、初めて見る曇った表情。
その顔に、佐山はぎくりとしてしまった。
(秋口に、似てる……)
声が似ているとも思っていた。だが、顔立ちまで似ているとは気づかなかった。顔の造りのどこが似ているというわけでもない。秋口は涼しげな切れ長の目をしていたが、縞は目尻に笑いじわの寄る優しい顔立ちだったし、秋口の唇は少し薄情そうに薄いけれど、縞は妙に色気のある、厚みを持った尻上がりの唇だ。
タイプはまったく違うのに、ふとした表情と角度で、驚くほどふたりが似ていて、佐山は思わず絶句した。
「ん?」
目を瞠って自分を見ている佐山の視線に気づき、縞が不思議そうに首を傾げた。
明るい笑い声もあまり似ていない。少しひそめて低くなった時や、冗談めかしてまじめな声音になった時は、心臓が止まりそうなくらいそっくりだった。
「佐山さん? どうかしましたか?」
間近で顔を覗き込まれ、佐山はぎょっとして軽く身を引いた。縞がますます怪訝そうな顔になる。さすがに失礼な反応だと、佐山は慌てた。
「す、すみません……あんまりいい男だから、見とれちゃって」
冗談で誤魔化そうと、佐山は初対面の時と同じ言い訳をして、しかしその言葉の気恥ずかしさにひとり赤くなった。
縞はそんな佐山の反応を興味深そうに眺めて、変に思われたに違いないと佐山がいたたまれない気分になる半歩手前のタイミングでにっこり笑うと、
「よく言われます」
とてらいもなく答えた。
◇◇◇
「それで、ライターさんってだけあっていろんなことを知ってるし、本人は『広く浅くですよ』なんて言ってるけど話し出したら詳しいんだ。きっと努力家なんだろうな。そこを鼻にかけるようなところはないから、嫌みじゃない」
「ふーん」
「記事の載ってる雑誌のタイトル教えてもらったから、今日の朝買ってみたんだ。後で読んでみよう」
「佐山、おまえさ」
縞と再会した夜から数日後の昼休み、たまたま社食で顔を合わせた御幸の向かいでランチを食べていた佐山は、怪訝そうな友人の表情に首を傾げた。
「何?」
「ずいぶん機嫌がいいんだな」
指摘されて、なぜか佐山は少し後ろめたい気分になった。そんな気分になる『筋合い』は、自分にはないと思うのに。
「そうかな、別にずいぶんってことはないだろ」
「ここ最近で、眉間に皺寄ってない顔と一回も溜息ついてない佐山の姿なんて、かなり珍しいぞ」
「大袈裟だなあ。まあ開発だって、営業ほどじゃないけど忙しかったし、疲れてたのかもな」
「その疲れが、その何とかいうライターとの食事で癒されたってわけか」
「うーん、まあ……本当に、楽しくはあったよ。あんなに笑ったのは久しぶりってくらい、縞さんの話してくれることがいちいちおかしくて」
「まあ、いかにも悩んでます、気が重いですって顔でしかめっ面してる佐山を見てるより、よっぽど気が楽だけどさ、俺は」
焼き魚定食を箸で突きつつ、御幸が少し小声になった。
「で、あっちの方はどうなったんだよ」
訊ねつつ、御幸は視線だけ、自分たちの右側にある席の方を見遣った。佐山が先刻からなるべく目に入れないようにしている方向だ。営業事務の女の子と向かい合って食事をしている秋口の姿なんて、いつものこととはいえ目の当たりにしたくない。
「あいつあそこまで切羽詰まった様子さらしておいて、何でまだ他の女とああなんだ」
「知らないよ、俺は」
こっちが聞きたいし、なのに聞けないことなのだ。
「おまえらのことだし、ああまでなったら後は何言っても馬に蹴られるだけだと思って、聞かずにいたけどさ。いい加減口挟みたくもなる、どうなってんだおまえら」
佐山はもう一度深々と溜息をつくと、ちょうどお互い食事が終わったところだったので、御幸を誘って非常ドアの外に出た。すっかり禁煙化が進んで居づらくなった社屋の、唯一人目を気にせず喫煙しながらゆっくり話ができるところだ。
御幸と並んで煙草をふかしながら、佐山は例の一件、御幸の目の前で自分が秋口を殴ったその後の話をそのまま話した。
「つまり――なんにもなってない、と?」
信じがたい、という顔で、御幸が佐山の説明をまとめた。
「どうもこうも進展してないし、会社帰りに飯喰う以外にデートのひとつもしてないってわけか」
佐山は歯で煙草のフィルターを噛みつつ、頷いた。
「もしかしたら、秋口が女とまだいちゃついてるのはカモフラージュかと思ってたんだぞ、俺は。佐山恋しさが表沙汰になったら問題だからって」
「だから、喧嘩もできない程度だって言ったろ。恋とか愛とか好きとか嫌いとか、そういうのを云々するってレベルでもないんだよ」
呆れ顔で御幸が顎を落とし、ついでに煙草も落としそうになって、慌てて指で押さえている。
「待て、待て待て待て。まさかとは思うけど、おまえら、告白もまだなのか!? いや、告白っていうか、ともかく、お互いの気持ちを相手に伝えるような言葉なり行動なり」
「俺はとっくに本人に言ってる」
溜息混じりに佐山は応えた。
ただし、言った記憶は佐山本人にもなかったし、何だかもうずいぶん昔のことにも思えてしまうのだが。
「……秋口は?」
なぜかおそるおそる訊ねてくる御幸に、佐山は緩く首を横に振って見せた。
「一度も。まあなんだか俺のこと独り占めしたい、って意味のようなことは言われたけど。おまえや、沙和子と一緒に俺がいるのが気に喰わないみたいな。あとは、俺に離れないで欲しいとか」
「それって、充分愛の告白ってやつなんじゃないか」
「向こうは他の誰とでも一緒にいるのに?」
「――ああ……」
先刻他の女と仲よくランチを取っていた姿を見てしまっては、御幸にもフォローの余地がない。
「何度も思うよ。これだったらひとりで勝手に好きだった頃の方がまだしもだって」
眉間に皺を寄せてしまう佐山の肩を、御幸がちょっと乱暴に揺する。
「あんまり考えすぎておまえばっかり疲れることもないだろ。奢るし、今日は俺とうまいもんでも喰いに行こうぜ。ちょうどヤマひとつ超えたんだ、大口契約取れた祝い」
ああ、でも――と御幸が言を継ぎ、
「俺と出かけるの、秋口は嫌がるんだっけ?」
「知るもんか、行こう」
少し自棄気味に答えた友人に、御幸は軽く肩を竦めただけだった。
「ふーん」
「記事の載ってる雑誌のタイトル教えてもらったから、今日の朝買ってみたんだ。後で読んでみよう」
「佐山、おまえさ」
縞と再会した夜から数日後の昼休み、たまたま社食で顔を合わせた御幸の向かいでランチを食べていた佐山は、怪訝そうな友人の表情に首を傾げた。
「何?」
「ずいぶん機嫌がいいんだな」
指摘されて、なぜか佐山は少し後ろめたい気分になった。そんな気分になる『筋合い』は、自分にはないと思うのに。
「そうかな、別にずいぶんってことはないだろ」
「ここ最近で、眉間に皺寄ってない顔と一回も溜息ついてない佐山の姿なんて、かなり珍しいぞ」
「大袈裟だなあ。まあ開発だって、営業ほどじゃないけど忙しかったし、疲れてたのかもな」
「その疲れが、その何とかいうライターとの食事で癒されたってわけか」
「うーん、まあ……本当に、楽しくはあったよ。あんなに笑ったのは久しぶりってくらい、縞さんの話してくれることがいちいちおかしくて」
「まあ、いかにも悩んでます、気が重いですって顔でしかめっ面してる佐山を見てるより、よっぽど気が楽だけどさ、俺は」
焼き魚定食を箸で突きつつ、御幸が少し小声になった。
「で、あっちの方はどうなったんだよ」
訊ねつつ、御幸は視線だけ、自分たちの右側にある席の方を見遣った。佐山が先刻からなるべく目に入れないようにしている方向だ。営業事務の女の子と向かい合って食事をしている秋口の姿なんて、いつものこととはいえ目の当たりにしたくない。
「あいつあそこまで切羽詰まった様子さらしておいて、何でまだ他の女とああなんだ」
「知らないよ、俺は」
こっちが聞きたいし、なのに聞けないことなのだ。
「おまえらのことだし、ああまでなったら後は何言っても馬に蹴られるだけだと思って、聞かずにいたけどさ。いい加減口挟みたくもなる、どうなってんだおまえら」
佐山はもう一度深々と溜息をつくと、ちょうどお互い食事が終わったところだったので、御幸を誘って非常ドアの外に出た。すっかり禁煙化が進んで居づらくなった社屋の、唯一人目を気にせず喫煙しながらゆっくり話ができるところだ。
御幸と並んで煙草をふかしながら、佐山は例の一件、御幸の目の前で自分が秋口を殴ったその後の話をそのまま話した。
「つまり――なんにもなってない、と?」
信じがたい、という顔で、御幸が佐山の説明をまとめた。
「どうもこうも進展してないし、会社帰りに飯喰う以外にデートのひとつもしてないってわけか」
佐山は歯で煙草のフィルターを噛みつつ、頷いた。
「もしかしたら、秋口が女とまだいちゃついてるのはカモフラージュかと思ってたんだぞ、俺は。佐山恋しさが表沙汰になったら問題だからって」
「だから、喧嘩もできない程度だって言ったろ。恋とか愛とか好きとか嫌いとか、そういうのを云々するってレベルでもないんだよ」
呆れ顔で御幸が顎を落とし、ついでに煙草も落としそうになって、慌てて指で押さえている。
「待て、待て待て待て。まさかとは思うけど、おまえら、告白もまだなのか!? いや、告白っていうか、ともかく、お互いの気持ちを相手に伝えるような言葉なり行動なり」
「俺はとっくに本人に言ってる」
溜息混じりに佐山は応えた。
ただし、言った記憶は佐山本人にもなかったし、何だかもうずいぶん昔のことにも思えてしまうのだが。
「……秋口は?」
なぜかおそるおそる訊ねてくる御幸に、佐山は緩く首を横に振って見せた。
「一度も。まあなんだか俺のこと独り占めしたい、って意味のようなことは言われたけど。おまえや、沙和子と一緒に俺がいるのが気に喰わないみたいな。あとは、俺に離れないで欲しいとか」
「それって、充分愛の告白ってやつなんじゃないか」
「向こうは他の誰とでも一緒にいるのに?」
「――ああ……」
先刻他の女と仲よくランチを取っていた姿を見てしまっては、御幸にもフォローの余地がない。
「何度も思うよ。これだったらひとりで勝手に好きだった頃の方がまだしもだって」
眉間に皺を寄せてしまう佐山の肩を、御幸がちょっと乱暴に揺する。
「あんまり考えすぎておまえばっかり疲れることもないだろ。奢るし、今日は俺とうまいもんでも喰いに行こうぜ。ちょうどヤマひとつ超えたんだ、大口契約取れた祝い」
ああ、でも――と御幸が言を継ぎ、
「俺と出かけるの、秋口は嫌がるんだっけ?」
「知るもんか、行こう」
少し自棄気味に答えた友人に、御幸は軽く肩を竦めただけだった。
◇◇◇
ふたり行きつけの定食屋、カウンタ席で並んで夕食をとった。珍しく佐山も御幸も定時から大した時間が経たずに会社を出ることができた。
契約がうまくいった、という御幸を、ビールと、佐山はウーロン茶で乾杯して労う。頼んだ料理が来るまで、来て箸をつけてからも、お互いの仕事の話や近況をとりとめもなく話した。佐山が御幸とこの店に来て、ゆっくり話をするのも、ひさびさのことだった。
「沙和子とも、食事くらいまたって約束してるんだけど。なかなかタイミングが……って言うか、その気にならなくて、何となくもやもやするんだよな」
そして話は結局、昼休みの続きに向かってしまう。この一ヵ月ほど、ひとり悶々と考え続けていたことが、思いのほか佐山のストレスになっていたらしい。こんな話を御幸に聞かせるのは申し訳ない気がしたが、御幸は嫌な顔ひとつせず佐山の話に耳を傾けてくれた。
「沙和子と俺が一緒にいるのを秋口が気に喰わないからって、つきあいを絶つ必要はないと思うんだ。もちろん御幸とも。沙和子とは、昔特別なつきあいだったけど、今は俺にそういう気はないわけだし……俺が好きなのは、別の人だし」
考え続けていたことを実際口にする佐山の言葉は、溜息混じりのものになった。
「だからここって俺の方から気を遣うとこでもないんじゃないかと思いつつ、でも秋口が気にしてるのはわかるしって堂々巡りで、それにしたって秋口の方が俺をどう思ってるかをちゃんと俺言わない限りは、俺が考えるだけ無駄なのかもしれないってことも考えるし」
「秋口的には、ま、自分が優位に立ちたいってことなのかもしれないな。あいつのプライドが高いのは誰が見ても明らかだろ。自分からお願いするのは自尊心が許せない、佐山の方が自分のことを好きなんだから、佐山が気を遣うのが当然だってさ」
実際、そのようなことを秋口に言われた覚えがあるので、佐山は御幸の推論に頷くしかない。
「足許見られてるのかもな、っていうのは何となく……で、秋口にとって自分がどういう形にしろ、特別なんだろうなっていうのも何となくわかるんだ。でも……っていうかだからこそ、なんにも言わないし、自分が嫌だからって俺にやめさせようとすることを、自分はしてる向こうに、失望する」
最後の方は、御幸に聞かせるというより、独り言に近くなった。
「自分の全部投げ打って、相手の他は何もいらないって縋れば秋口は満足するんだろうと思う。でもそういうのは好きじゃない、好きじゃないって言うか……」
言い淀んだ佐山の言葉を引き継ぐように、御幸が訊ねる。
「怖い?」
佐山は頷いた。
「暴力みたいなもんだと思うんだ、まあ実際殴ったのは俺だけど」
その時のことを思い出したのか、御幸が吹き出した。
「感情にものを言わせて相手を縛りつけるようなやり方、覚えちゃいけないんだよ。それがどんどんエスカレートしていくのを、俺はずっと見てきたし」
「……」
「そういう恋愛もあるのかもしれないけど、いい大人がやることじゃない。人間、ふたりだけで生きてきけるわけは絶対にないんだから」
佐山は大きく息を吐き出した。
「秋口には、俺が自分のそばにいることじゃなくて、自分が俺のそばにいることを選んで欲しいと思ってるんだ。そうしたら、俺も同じこと素直に望めるし……って思うのは、贅沢だろうし、ただ意地張ってるだけなのかもしれないけど」
「いいや、ごく当然の望みだね」
御幸が即座に断言したので、佐山は少し笑ってしまった。
「好きな人間のために自分を変えるなんて、馬鹿げてると俺は思う。ちょっとの生活習慣とか、考え方とか、影響されて自然と変わっていったり、我慢のできる範囲で相手に合わせることは必要だとしてもさ」
「……うん」
「俺は佐山贔屓だから見方はおまえに偏るけどさ。嫌なこととか、怖くて辛いことは、無理してやることも――思い出すこともないだろ」
ビールの入ったグラスを片手に、御幸は頬杖をついて隣の佐山を見遣った。
「まあ、話し合いの余地がありそうなら、その辺のことあいつにも話してみたらどうだ? たぶんおまえ、まだそういう話、してないだろ」
「必要あるかなあ」
つられて頬杖をつきつつ、佐山は店の天井を見上げた。
「聞いて楽しいことじゃないだろ。重いし、滅入らせるだけな気がする」
「……うーん……」
考え込むように、目を閉じた御幸がきつく眉間に皺を寄せた。
「御幸に話すのも、沙和子に話すのも勇気がいったよ。おまえの時はなりゆきみたいなところがあったし、沙和子の時は俺は結婚のこと考えてたから、そうすると沙和子にも関わってくるし、隠す方がフェアじゃないって思ったから話したけど」
「ああ……要するに、秋口のことを信頼できる状態じゃ、まだ全然ないってわけだな。当然か」
「信頼かあ、信頼……」
その言葉は、佐山にとって何だか途方もないもののように思えた。
「……信用がないのは、お互い様ってことか……」
うんざりする気分で佐山が呟いた時、そのポケットで携帯電話のベルが鳴った。直通メールが届いた報せだ。
「あ、縞さんだ」
携帯電話の液晶画面には、先日登録したばかりの『縞亮人』の名前。
「縞って、例のライター?」
「そう、今都内に出てるから、よかったらまた食事でもって。今隣の駅みたいだ」
画面から、佐山は御幸の方へ視線を移した。
「混じっても平気か?」
「俺は別に構わないけど……」
「聞いてみる」
佐山が連れが一緒だが構わないかと返信すると、すぐに佐山とその連れの人さえよければ、とまた返信が来る。佐山がさらに店の場所をメールしてからそう時間が経たず、縞が店内に姿を見せた。
「縞さん、こっち」
入口から中を見渡す縞に、佐山は手を挙げて合図を送った。縞がすぐそれに気づき、人なつっこい笑顔になって近づいてくる。
「こんばんは佐山さん、この間ぶり。――すみません、図々しくお邪魔しちゃって」
前半は佐山に向けて、後半は御幸に向けて、縞が挨拶する。
「はじめまして、縞って言います。佐山さんとはたまたま奇縁っていうか、ひょんなことから知り合って」
「あ、その辺は説明しました、な、御幸」
縞から友人に視線を移した佐山は、相手が軽く目を瞠っていることに気づいて首を傾げた。
「御幸?」
「あ……ああ、はじめまして、佐山と同じ会社の、御幸と言います」
「ミユキさん? かわいい名前ですね」
ちょうど空いていた佐山の隣のカウンタ席に腰を下ろしながら、縞が笑って言う。
御幸も、佐山を挟んで縞を見返しながら、にっこりといつもながら貴公子然とした笑みを浮かべた。
「御幸が苗字で、名前は暢彦というんですよ」
「いい名前ですね」
「ありがとうございます」
カウンタ越しに、店員が縞の分の水とつきだしを差し出した。
「俺はこういう名前です」
縞が、名刺を取り出して御幸に手渡す。どうも、と頷いて、御幸も半ば習慣のような仕種で自分の名刺を縞に渡した。
「ああなるほど、こういう字ね。で、佐山さんとは部署が違うんだ」
呟きながら、縞が何か首を傾げている。
「うーん、やっぱり、この社名に覚えがあるような……」
「縞さん、もう食事すまされましたか? まだだったら、ここの料理も結構いけますよ」
言いながら佐山が品書きを差し出すと、縞がにこにこしながらそれを受け取った。
「あ、ちょうど腹減ってたんですよね。どこか適当に店入ろうと思ったんだけど、ひとりじゃ味気ないしと思ったら佐山さんのこと思い出して、急に会いたくなって」
縞の台詞に、佐山は笑い声をたてる。
「それは、光栄だなあ。ああこの煮物とか、おすすめです」
「じゃそれと、じゃこ飯でもいこうかな。ええと、あとはどれがおすすめ?」
佐山の方へメニューと一緒に身を寄せて、縞が訊ねてくる。佐山もメニューを覗き込みながら、鶏の唐揚げや、笊豆腐などを指さしていった。
「この辺かな」
「ふんふん」
「――近い」
小さく低い呟きが聞こえて、佐山は怪訝に顔を上げた。声は御幸の方から聞こえた。
「御幸、何か言ったか?」
佐山に、御幸はいつもの穏やかな笑顔で首を振って見せた。
「いや、別に。ああ、縞さん、飲まれるんでしたらここの生搾りのサワーがおすすめですよ」
「そしたらその辺頼んでみよう、すみません!」
近くを通りがかった店員を捉まえ、縞がてきぱきと注文をすませている。
次々飲み物と食事がやってきて、三人でそれぞれ自分の皿をつまみながら、当たり障りなくお互いの話をした。
「へえ、じゃあ、佐山さんと御幸さんは入社以来の親友ってことか」
「いろいろ世話かけてます、俺は全然営業向きじゃなかったから、かなり御幸に助けてもらって」
料理は美味いし、縞との会話は楽しいしで、佐山は普段よりも饒舌になる。それよりさらに縞がよくしゃべったが。
「俺なんて、会社自体向いてないから、そもそも就職したことすらありませんよ。朝起きて電車に乗るってのがまず不可能です、陽に当たりすぎると溶けちゃいますから」
「まるで吸血鬼ですね」
「あ、いいな吸血鬼。美女の生き血を啜りながら永遠の命を生きるなんて、ロマンだなあ」
笑いながら、縞がさりげない仕種で佐山の片手を取る。
「佐山さんも、どうですか、一緒に永久の命と快楽を」
「あ、すみませんお茶いただけますか? 佐山、おまえも飲むだろ、それとももう少し冷たいもの飲むか」
縞の反対隣から御幸が無造作に品書きを放ってきて、佐山は慌てて両手でそれを受け取った。
「俺もお茶でいいや。縞さんはどうしますか?」
「俺も同じで」
「すみません、お茶あともうふたつ」
店員に頼んでから、御幸がカウンタに両手で頬杖をつきつつ、愛想よく縞の方を見遣った。
「お噂どおり、縞さんは本当にお話上手ですね」
「口から先に生まれたと言われています」
「違いない。さすが、ライターなんてご職業に就かれるだけあるってことですか」
「天職だといいんですけどね」
和やかに話すふたりを眺めつつ、佐山はカウンタに置かれたそば茶を啜った。ふたりとも優しいいい声をしていて、淀みなく話す言葉を聞いているのは気持ちがよかった。
「いつからそういうお仕事をなさってるんですか」
「大学生の頃からだから、もう七、八年かな。――あ、佐山さん、唐揚げ食べません? 冷めてきたけどまだ美味しいですよ」
御幸に答えつつ箸で唐揚げを摘んだ縞が、それを佐山の方に向ける。急に自分の方に言葉を向けられて、佐山は反射的に促されるまま口を開けてしまった。
「はい、あーん」
「んん?」
「美味しいですか?」
もともと佐山のおすすめだ。唐揚げを咀嚼しながら頷くと、縞はずいぶん嬉しそうな笑顔になって佐山の顔をみつめた。
「かぁわいいなあ、佐山さん」
照れも恥じらいもなく言う縞に、佐山は思わず吹き出した。
「また、そういうことを言う」
「今、ひな鳥みたいですごく可愛かったですよ。ねえ、御幸さん」
皿を全部空にして、煙草を吸い始めていた御幸が、煙を吐き出してから苦笑した。
「いい大人の男に向かって、可愛いもないでしょうけど」
「年は関係ないですよ、いくつになっても可愛いものは可愛い」
笑ったまま、縞が御幸を見返す。
「御幸さんはどっちかっていうと、美人さんってタイプだけど」
「それはどうも」
御幸は適当に肩を竦めて、まだ長い煙草を灰皿で揉み消した。
「それじゃあ、食事も終わったし、俺たちはそろそろ失礼しようか、佐山」
「え、もう?」
縞が少し不満そうに唇を尖らせる。佐山が腕時計で時間を確認すると、もう十時近くになっていた。
「まだ全然宵の口じゃないですか」
「俺たちは、明日も会社ですから」
「でもどうせ、フレックスだし」
せっかく楽しい時間だし、もう少し縞と話していたい気がしてそう言いかけた佐山の腕を、立ち上がりながら御幸が素早く引いて、耳許に唇を寄せた。
「おまえ、帰って鏡見てみろ。すっかり疲れた顔してるぞ」
「え……そうかな」
佐山も椅子から立ち上がりつつ、片手で自分の頬に触れた。あまり肉のついていないやつれた顔は、今に始まったことじゃない。特にこの数ヵ月というもの。
「帰って風呂でも入ってさっさと寝ろよ、まだ今週終わったわけじゃないんだぞ」
「――わかった」
あまり御幸に心配ばかりかけるのも申し訳ない。ふたりと話したことでだいぶ気持ちも明るくなったし、たしかにはしゃいでダウンしては週末まで辛くなるばかりだ。
「すみません、縞さん。また次の機会に」
縞は隠さずがっかりした表情になって、彼こそが大人の男なのに『可愛い』んじゃないかと佐山はこっそり笑った。
「じゃあ今度は休みの前にゆっくり会いましょう、絶対ですよ」
「はい、ぜひ」
「また連絡します、あ、佐山さんの方からもメールでも電話でもくださいね。用事なんかなくてもいいから、ひとりが寂しい夜なんて特に」
自分の携帯電話を掲げて見せた縞に、佐山も同じ仕種を笑って返した。
「それじゃ失礼します、佐山、行くぞ」
御幸も縞に微笑んで挨拶して見せてからレジに向かい、佐山もその後についてから、名残惜しくて何となく後ろを振り返った。
縞も佐山の方を見ていて、軽く手を挙げている。佐山もまた同じ仕種を返してから、レジで会計をすませる御幸の隣に歩んだ。
「本当に奢りでいいのか、ここ」
「そうするって言っただろ。今度何かあったら佐山が奢れよ」
「サンキュ、ごちそうさま」
会計を終えて店を出ながら、佐山の隣で御幸がひとり小さく首を横に振っていた。
「まったく口から先にってのが言い得て妙な……」
「ああ、縞さん、楽しい人だろ」
その呟きを聞き止めて佐山が言うと、駅に向かう道の半ばで御幸が急に足を止めた。つられて立ち止まる佐山を見下ろしてから口を開き、だが何も言わずにそのままの格好で動きを止めた後、溜息をつく。
「――やめた。まあ、いいや」
ひとりで呟いてひとりで納得し、御幸が再び歩き出す。佐山もまたその隣を進み出した。
「佐山も別に、道理のわからない子供ってわけでもないんだしな」
聞こえた御幸の呟きはまたひとりごとのように聞こえたので、佐山は特にその意味は問い返さずにおいた。
契約がうまくいった、という御幸を、ビールと、佐山はウーロン茶で乾杯して労う。頼んだ料理が来るまで、来て箸をつけてからも、お互いの仕事の話や近況をとりとめもなく話した。佐山が御幸とこの店に来て、ゆっくり話をするのも、ひさびさのことだった。
「沙和子とも、食事くらいまたって約束してるんだけど。なかなかタイミングが……って言うか、その気にならなくて、何となくもやもやするんだよな」
そして話は結局、昼休みの続きに向かってしまう。この一ヵ月ほど、ひとり悶々と考え続けていたことが、思いのほか佐山のストレスになっていたらしい。こんな話を御幸に聞かせるのは申し訳ない気がしたが、御幸は嫌な顔ひとつせず佐山の話に耳を傾けてくれた。
「沙和子と俺が一緒にいるのを秋口が気に喰わないからって、つきあいを絶つ必要はないと思うんだ。もちろん御幸とも。沙和子とは、昔特別なつきあいだったけど、今は俺にそういう気はないわけだし……俺が好きなのは、別の人だし」
考え続けていたことを実際口にする佐山の言葉は、溜息混じりのものになった。
「だからここって俺の方から気を遣うとこでもないんじゃないかと思いつつ、でも秋口が気にしてるのはわかるしって堂々巡りで、それにしたって秋口の方が俺をどう思ってるかをちゃんと俺言わない限りは、俺が考えるだけ無駄なのかもしれないってことも考えるし」
「秋口的には、ま、自分が優位に立ちたいってことなのかもしれないな。あいつのプライドが高いのは誰が見ても明らかだろ。自分からお願いするのは自尊心が許せない、佐山の方が自分のことを好きなんだから、佐山が気を遣うのが当然だってさ」
実際、そのようなことを秋口に言われた覚えがあるので、佐山は御幸の推論に頷くしかない。
「足許見られてるのかもな、っていうのは何となく……で、秋口にとって自分がどういう形にしろ、特別なんだろうなっていうのも何となくわかるんだ。でも……っていうかだからこそ、なんにも言わないし、自分が嫌だからって俺にやめさせようとすることを、自分はしてる向こうに、失望する」
最後の方は、御幸に聞かせるというより、独り言に近くなった。
「自分の全部投げ打って、相手の他は何もいらないって縋れば秋口は満足するんだろうと思う。でもそういうのは好きじゃない、好きじゃないって言うか……」
言い淀んだ佐山の言葉を引き継ぐように、御幸が訊ねる。
「怖い?」
佐山は頷いた。
「暴力みたいなもんだと思うんだ、まあ実際殴ったのは俺だけど」
その時のことを思い出したのか、御幸が吹き出した。
「感情にものを言わせて相手を縛りつけるようなやり方、覚えちゃいけないんだよ。それがどんどんエスカレートしていくのを、俺はずっと見てきたし」
「……」
「そういう恋愛もあるのかもしれないけど、いい大人がやることじゃない。人間、ふたりだけで生きてきけるわけは絶対にないんだから」
佐山は大きく息を吐き出した。
「秋口には、俺が自分のそばにいることじゃなくて、自分が俺のそばにいることを選んで欲しいと思ってるんだ。そうしたら、俺も同じこと素直に望めるし……って思うのは、贅沢だろうし、ただ意地張ってるだけなのかもしれないけど」
「いいや、ごく当然の望みだね」
御幸が即座に断言したので、佐山は少し笑ってしまった。
「好きな人間のために自分を変えるなんて、馬鹿げてると俺は思う。ちょっとの生活習慣とか、考え方とか、影響されて自然と変わっていったり、我慢のできる範囲で相手に合わせることは必要だとしてもさ」
「……うん」
「俺は佐山贔屓だから見方はおまえに偏るけどさ。嫌なこととか、怖くて辛いことは、無理してやることも――思い出すこともないだろ」
ビールの入ったグラスを片手に、御幸は頬杖をついて隣の佐山を見遣った。
「まあ、話し合いの余地がありそうなら、その辺のことあいつにも話してみたらどうだ? たぶんおまえ、まだそういう話、してないだろ」
「必要あるかなあ」
つられて頬杖をつきつつ、佐山は店の天井を見上げた。
「聞いて楽しいことじゃないだろ。重いし、滅入らせるだけな気がする」
「……うーん……」
考え込むように、目を閉じた御幸がきつく眉間に皺を寄せた。
「御幸に話すのも、沙和子に話すのも勇気がいったよ。おまえの時はなりゆきみたいなところがあったし、沙和子の時は俺は結婚のこと考えてたから、そうすると沙和子にも関わってくるし、隠す方がフェアじゃないって思ったから話したけど」
「ああ……要するに、秋口のことを信頼できる状態じゃ、まだ全然ないってわけだな。当然か」
「信頼かあ、信頼……」
その言葉は、佐山にとって何だか途方もないもののように思えた。
「……信用がないのは、お互い様ってことか……」
うんざりする気分で佐山が呟いた時、そのポケットで携帯電話のベルが鳴った。直通メールが届いた報せだ。
「あ、縞さんだ」
携帯電話の液晶画面には、先日登録したばかりの『縞亮人』の名前。
「縞って、例のライター?」
「そう、今都内に出てるから、よかったらまた食事でもって。今隣の駅みたいだ」
画面から、佐山は御幸の方へ視線を移した。
「混じっても平気か?」
「俺は別に構わないけど……」
「聞いてみる」
佐山が連れが一緒だが構わないかと返信すると、すぐに佐山とその連れの人さえよければ、とまた返信が来る。佐山がさらに店の場所をメールしてからそう時間が経たず、縞が店内に姿を見せた。
「縞さん、こっち」
入口から中を見渡す縞に、佐山は手を挙げて合図を送った。縞がすぐそれに気づき、人なつっこい笑顔になって近づいてくる。
「こんばんは佐山さん、この間ぶり。――すみません、図々しくお邪魔しちゃって」
前半は佐山に向けて、後半は御幸に向けて、縞が挨拶する。
「はじめまして、縞って言います。佐山さんとはたまたま奇縁っていうか、ひょんなことから知り合って」
「あ、その辺は説明しました、な、御幸」
縞から友人に視線を移した佐山は、相手が軽く目を瞠っていることに気づいて首を傾げた。
「御幸?」
「あ……ああ、はじめまして、佐山と同じ会社の、御幸と言います」
「ミユキさん? かわいい名前ですね」
ちょうど空いていた佐山の隣のカウンタ席に腰を下ろしながら、縞が笑って言う。
御幸も、佐山を挟んで縞を見返しながら、にっこりといつもながら貴公子然とした笑みを浮かべた。
「御幸が苗字で、名前は暢彦というんですよ」
「いい名前ですね」
「ありがとうございます」
カウンタ越しに、店員が縞の分の水とつきだしを差し出した。
「俺はこういう名前です」
縞が、名刺を取り出して御幸に手渡す。どうも、と頷いて、御幸も半ば習慣のような仕種で自分の名刺を縞に渡した。
「ああなるほど、こういう字ね。で、佐山さんとは部署が違うんだ」
呟きながら、縞が何か首を傾げている。
「うーん、やっぱり、この社名に覚えがあるような……」
「縞さん、もう食事すまされましたか? まだだったら、ここの料理も結構いけますよ」
言いながら佐山が品書きを差し出すと、縞がにこにこしながらそれを受け取った。
「あ、ちょうど腹減ってたんですよね。どこか適当に店入ろうと思ったんだけど、ひとりじゃ味気ないしと思ったら佐山さんのこと思い出して、急に会いたくなって」
縞の台詞に、佐山は笑い声をたてる。
「それは、光栄だなあ。ああこの煮物とか、おすすめです」
「じゃそれと、じゃこ飯でもいこうかな。ええと、あとはどれがおすすめ?」
佐山の方へメニューと一緒に身を寄せて、縞が訊ねてくる。佐山もメニューを覗き込みながら、鶏の唐揚げや、笊豆腐などを指さしていった。
「この辺かな」
「ふんふん」
「――近い」
小さく低い呟きが聞こえて、佐山は怪訝に顔を上げた。声は御幸の方から聞こえた。
「御幸、何か言ったか?」
佐山に、御幸はいつもの穏やかな笑顔で首を振って見せた。
「いや、別に。ああ、縞さん、飲まれるんでしたらここの生搾りのサワーがおすすめですよ」
「そしたらその辺頼んでみよう、すみません!」
近くを通りがかった店員を捉まえ、縞がてきぱきと注文をすませている。
次々飲み物と食事がやってきて、三人でそれぞれ自分の皿をつまみながら、当たり障りなくお互いの話をした。
「へえ、じゃあ、佐山さんと御幸さんは入社以来の親友ってことか」
「いろいろ世話かけてます、俺は全然営業向きじゃなかったから、かなり御幸に助けてもらって」
料理は美味いし、縞との会話は楽しいしで、佐山は普段よりも饒舌になる。それよりさらに縞がよくしゃべったが。
「俺なんて、会社自体向いてないから、そもそも就職したことすらありませんよ。朝起きて電車に乗るってのがまず不可能です、陽に当たりすぎると溶けちゃいますから」
「まるで吸血鬼ですね」
「あ、いいな吸血鬼。美女の生き血を啜りながら永遠の命を生きるなんて、ロマンだなあ」
笑いながら、縞がさりげない仕種で佐山の片手を取る。
「佐山さんも、どうですか、一緒に永久の命と快楽を」
「あ、すみませんお茶いただけますか? 佐山、おまえも飲むだろ、それとももう少し冷たいもの飲むか」
縞の反対隣から御幸が無造作に品書きを放ってきて、佐山は慌てて両手でそれを受け取った。
「俺もお茶でいいや。縞さんはどうしますか?」
「俺も同じで」
「すみません、お茶あともうふたつ」
店員に頼んでから、御幸がカウンタに両手で頬杖をつきつつ、愛想よく縞の方を見遣った。
「お噂どおり、縞さんは本当にお話上手ですね」
「口から先に生まれたと言われています」
「違いない。さすが、ライターなんてご職業に就かれるだけあるってことですか」
「天職だといいんですけどね」
和やかに話すふたりを眺めつつ、佐山はカウンタに置かれたそば茶を啜った。ふたりとも優しいいい声をしていて、淀みなく話す言葉を聞いているのは気持ちがよかった。
「いつからそういうお仕事をなさってるんですか」
「大学生の頃からだから、もう七、八年かな。――あ、佐山さん、唐揚げ食べません? 冷めてきたけどまだ美味しいですよ」
御幸に答えつつ箸で唐揚げを摘んだ縞が、それを佐山の方に向ける。急に自分の方に言葉を向けられて、佐山は反射的に促されるまま口を開けてしまった。
「はい、あーん」
「んん?」
「美味しいですか?」
もともと佐山のおすすめだ。唐揚げを咀嚼しながら頷くと、縞はずいぶん嬉しそうな笑顔になって佐山の顔をみつめた。
「かぁわいいなあ、佐山さん」
照れも恥じらいもなく言う縞に、佐山は思わず吹き出した。
「また、そういうことを言う」
「今、ひな鳥みたいですごく可愛かったですよ。ねえ、御幸さん」
皿を全部空にして、煙草を吸い始めていた御幸が、煙を吐き出してから苦笑した。
「いい大人の男に向かって、可愛いもないでしょうけど」
「年は関係ないですよ、いくつになっても可愛いものは可愛い」
笑ったまま、縞が御幸を見返す。
「御幸さんはどっちかっていうと、美人さんってタイプだけど」
「それはどうも」
御幸は適当に肩を竦めて、まだ長い煙草を灰皿で揉み消した。
「それじゃあ、食事も終わったし、俺たちはそろそろ失礼しようか、佐山」
「え、もう?」
縞が少し不満そうに唇を尖らせる。佐山が腕時計で時間を確認すると、もう十時近くになっていた。
「まだ全然宵の口じゃないですか」
「俺たちは、明日も会社ですから」
「でもどうせ、フレックスだし」
せっかく楽しい時間だし、もう少し縞と話していたい気がしてそう言いかけた佐山の腕を、立ち上がりながら御幸が素早く引いて、耳許に唇を寄せた。
「おまえ、帰って鏡見てみろ。すっかり疲れた顔してるぞ」
「え……そうかな」
佐山も椅子から立ち上がりつつ、片手で自分の頬に触れた。あまり肉のついていないやつれた顔は、今に始まったことじゃない。特にこの数ヵ月というもの。
「帰って風呂でも入ってさっさと寝ろよ、まだ今週終わったわけじゃないんだぞ」
「――わかった」
あまり御幸に心配ばかりかけるのも申し訳ない。ふたりと話したことでだいぶ気持ちも明るくなったし、たしかにはしゃいでダウンしては週末まで辛くなるばかりだ。
「すみません、縞さん。また次の機会に」
縞は隠さずがっかりした表情になって、彼こそが大人の男なのに『可愛い』んじゃないかと佐山はこっそり笑った。
「じゃあ今度は休みの前にゆっくり会いましょう、絶対ですよ」
「はい、ぜひ」
「また連絡します、あ、佐山さんの方からもメールでも電話でもくださいね。用事なんかなくてもいいから、ひとりが寂しい夜なんて特に」
自分の携帯電話を掲げて見せた縞に、佐山も同じ仕種を笑って返した。
「それじゃ失礼します、佐山、行くぞ」
御幸も縞に微笑んで挨拶して見せてからレジに向かい、佐山もその後についてから、名残惜しくて何となく後ろを振り返った。
縞も佐山の方を見ていて、軽く手を挙げている。佐山もまた同じ仕種を返してから、レジで会計をすませる御幸の隣に歩んだ。
「本当に奢りでいいのか、ここ」
「そうするって言っただろ。今度何かあったら佐山が奢れよ」
「サンキュ、ごちそうさま」
会計を終えて店を出ながら、佐山の隣で御幸がひとり小さく首を横に振っていた。
「まったく口から先にってのが言い得て妙な……」
「ああ、縞さん、楽しい人だろ」
その呟きを聞き止めて佐山が言うと、駅に向かう道の半ばで御幸が急に足を止めた。つられて立ち止まる佐山を見下ろしてから口を開き、だが何も言わずにそのままの格好で動きを止めた後、溜息をつく。
「――やめた。まあ、いいや」
ひとりで呟いてひとりで納得し、御幸が再び歩き出す。佐山もまたその隣を進み出した。
「佐山も別に、道理のわからない子供ってわけでもないんだしな」
聞こえた御幸の呟きはまたひとりごとのように聞こえたので、佐山は特にその意味は問い返さずにおいた。
◇◇◇
ひとりになりたくて、なるべく早く総務部の女子社員との食事を切り上げてきたというのに、玄関のドアを開けた秋口は沓脱にまた自分のものではない靴を見つけて溜息をついた。
「何だおまえ、また来てたのか」
部屋に入ると案の定、従兄の姿がソファにある。だらしなく足を投げ出して、家主の姿に気づくと、手にした缶ビールを振って見せている。テレビで放映しているのか、借りてきたのか、ブラウン管から古い映画のシーンが流れていた。
「よー、お帰り航ちゃん」
「ちゃんとか言うな、気色悪い」
秋口は不機嫌さを隠そうともせず言いながら、上着を脱いで頭から縞にかぶせた。
縞はげらげら笑いながら、上着をソファの背もたれに掛ける。秋口は従兄の手からビールを取り上げてそれを呷った。
「なーんだよ、また、仏頂面しちゃってさあ」
質問なのか感想なのかわからない酔っぱらいの言葉を、秋口は無視した。
「何でまた勝手に入ってるんだよ、人の部屋」
「近くまで来たから遊びに寄ってやったんだよ」
「頼んでない」
「思ったより便利いいんだよな、この部屋。いい別宅を見つけた……」
「鍵返せよ、おまえがどうしても仕事明けに一眠りしたいって言ったから、あの時だけ預けたんだぞ」
「合い鍵もう作っちゃった」
縞がにやにやしながら手に取った鍵を、秋口はひったくった。
「それがおまえに借りたやつ。こっち合い鍵」
もうひとつポケットから取り出された鍵を奪おうと秋口は手を伸ばしたが、縞はさっとそれを自分の背中に隠してしまった。
「返せ」
「イ、ヤ」
秋口が腹を立てて縞の背中に手を突っ込むと、縞が黄色い奇声を発した。
「いやあー! 航ちゃんに犯されるぅ!」
「……」
秋口は深々と溜息をついて、縞から離れた。あとで鍵ごと変えてしまおう、と決意する。
まったくこの従兄には昔から敵わない。正直言って苦手な相手なのに、どうして家に居座られなくてはいけないのか、秋口は腑に落ちなかった。
「航ちゃんさあ」
合い鍵をポケットにしまい直し、縞はテーブルに置いてあった新しいビール缶に手を伸ばした。プルタブを開けながら秋口を見遣る。秋口はネクタイを緩め、床に並んだ空き缶数個をキッチンに運んだ。中をゆすいで、収集日にゴミ捨て場に持って行かなければならない。
「だからちゃんって呼ぶな。いい年して、気持ち悪い」
「おまえ、欲求不満なんじゃない?」
「……」
乱暴に、秋口はシンクに空き缶を投げ出した。怒って叩きつけたわけではない。動揺して取り落としたのだ。
「やーっぱりなあ、何だよ、女と会ってたんじゃないの? 逃げられたのか? 例の彼女に」
答えず、秋口は空き缶を水で洗った。
縞は従弟の『本命』が彼女ではなく彼だということを知らない。秋口には言うつもりもなかった。何しろ物心ついた時から筋金入りの両刀遣いである縞と違って、秋口は完全なるヘテロ、男に欲情する従兄の気が知れない鉄壁の女好きだったのだ。今さら男に恋をしましたなんてどの面下げて言えばいいのか、わからなかった。
「可哀想になあ、貧しい恋をしてるんだな」
「よけいなお世話だ」
秋口は缶を洗い終え、乱暴に蛇口を閉めた。振り返って、何か言い返してやろうと口を開きかけた秋口は、縞がやたら楽しそうな顔で鼻歌まで歌っていることに気づき、毒気を抜かれてしまう。こんな相手に、文句や嫌みを言うだけ無駄だ。どうせ小さい頃から、この従兄に秋口が言葉で勝った試しがない。
「……おまえはずいぶん楽しそうだな、亮人」
代わりに、呆れるような、もしかすると羨ましげな呟きが秋口の口から洩れる。
「楽しいよー、って言うか最高。今日、この間の人にまた会ったんだ」
「この間って、ひったくりだかを一緒に捕まえたとかいう?」
秋口は縞の隣に腰を下ろし、もう一本ビールに手を伸ばした。明日も出社だから、そろそろ風呂に入って寝た方がいいとは思うが、ちっとも眠たくないし、飲まずにはいられない気分でもあった。
「そっ、何となく、暇だから連絡するってタイプじゃないみたいだから、こっちから押しとこうと思って」
上機嫌に、縞はまたビールに口をつけた。
「ちょうどいいタイミングで、向こうも店にいるって言うから、友達といるとこに合流してさ。メシはうまいし、相手美人だし、最高」
気楽なもんだよ、と秋口もまたビールを呷った。
「いやほんと、いい夜だった。向こう会社勤めだからって先に帰られたけど……あれはやっぱり、警戒されてんのか?」
縞は秋口へ質問というより、自問の調子で言って首を傾げている。
「何だ、おまえも逃げられてるんじゃないか」
「最初から簡単に股開くような尻軽は好みじゃないからいいんだよ。多少お堅い方が、楽しみも増えるし」
縞の言葉が負け惜しみでないことは、今までの経験上秋口にもわかっている。縞は遊んでいるふうであって、本気なら割合まじめな恋をする。身持ちの堅いタイプが好きで、自分も恋人がいる間は決して他の相手に目をくれることがなく、一途に相手のことを大事にし続ける。
それまで色恋沙汰なんてくだらないと言わんばかりに四角四面な心持ちと見てくれだった人間が、縞に大事に甘やかされて、信じられないくらい色気のある様子になっていく奇跡を秋口も見たことがあった。
ただし、フリーの時はちょっと気に入った相手でも口癖みたいに熱心に口説くから、やっぱり遊んでいると言わざるを得ない辺り、自分と同類だと秋口は思う。
「何つーか、容姿も表情も言動も、いちいちこっちのツボ突いてくるんだよな。どうにかしてやりたいの抑えるのに必死だったよ、本気で。最初は当たり柔らかそうな印象だったのに、実は気が強そうな感じがするとこなんてもう」
縞はアルコールで上気した頬、軽く潤んだ瞳で、うっとりと溜息をついた。
「ああいう相手を泣かせたら、気持ちいいだろうなあ……」
「その相手と会うところが、俺の家に近いってことか」
酔っぱらいの戯言を本気で聞くまでもなく、秋口は相手の言葉を遮るようにそう訊ねた。
秋口が就職してからここ数年、法事以外でまともに顔を合わせたこともなかった縞が今ここに居座っているのは、今後もここを拠点に置いて、意中の相手を口説こうとしているからだ。秋口はそう理解した。縞が『便利がいい』と言ったのはそういう意味だ。
「そう。この辺から家に帰るの面倒だし、タクシー代も馬鹿にならない」
「間違ってもホテル代わりに使ったりするなよ、相手連れ込んだらすぐおばさんに電話して、実家に連れ帰らせるぞ」
「やなこと言うねえ、おまえ」
縞は大袈裟に鼻の頭へ皺を寄せた。定職にも就かずに物書き仕事で生計を立てている縞が、未だに親からその仕事に反対されていることはもちろん秋口も承知の上だ。縞の両親は実直で厳しい人たちだったから、とっくに成人した息子を本気で家に連れ戻そうとするだろう。実際そうはならなくても、間違いなく何時間も説教を喰らう。縞がそのお説教を大の苦手としていることも、秋口は熟知していた。
「あれか、彼女に冷たくされて、意地悪になってるのか」
そして縞の逆襲だ。今度は秋口が眉間に皺を寄せる羽目になった。
「おまえも、そんな暴力的で冷たい恋人のことなんて忘れて、そうだ、今度一緒にメシでも行こうぜ。向こう、仲のいい友達同士なんだ。一対一で会ったらよけい警戒されそうだし、おまえ、来いよ」
「何で俺が。相手って男だろ」
たしかに今秋口の心を惑わせている相手はれっきとした男性だが、何も他の男まで恋愛の範囲内に入ったわけではないのだ。秋口は今も男のことがちゃんと嫌いだった。そういう対象になるという意味では。
「だからだよ、バーカ。惚れた女ができて、これからゆっくり愛をはぐくんで行きましょうって段階だったとしたら、おまえなんかと死んでも会わせるもんか。五秒でホテルに連れ込まれる。男ならおまえの食指も動かないだろ」
縞も、たまにしか会わない割に、従弟の恋愛観はよく理解している。
「頭数合わせだ、今度連絡してやるから、呼ばれたら絶対来いよ。もし来なかったら……」
言いながら、縞がソファの隙間に手を突っ込んだ。そこから、女物のストッキングをずるりと引っ張り出す。ガーターベルト用の黒い網模様だ。
「秋口さんちの可愛い航ちゃんが、こーんなエッチなものつける女を部屋に連れ込みまくりですって、聖絵と美里に電話してやる」
「……」
聖絵と美里は、昔から何かと弟の世話を焼きたがる秋口の姉だ。そんなことが知れたが最後、彼女がいるなら家につれてこいだの、掃除しに行ってやるから鍵を寄越せだの、うるさく言われることだろう。
黙り込んだ秋口を見て、縞がにっこりと笑顔になる。
「決まりな。ま、残業なさそうな日教えてくれたら少しは考慮してやるから。逃げんなよ」
駄目押しのように縞が言って、秋口は反論することもできなかった。本当に、昔からこの従兄のことは苦手だった。
「何だおまえ、また来てたのか」
部屋に入ると案の定、従兄の姿がソファにある。だらしなく足を投げ出して、家主の姿に気づくと、手にした缶ビールを振って見せている。テレビで放映しているのか、借りてきたのか、ブラウン管から古い映画のシーンが流れていた。
「よー、お帰り航ちゃん」
「ちゃんとか言うな、気色悪い」
秋口は不機嫌さを隠そうともせず言いながら、上着を脱いで頭から縞にかぶせた。
縞はげらげら笑いながら、上着をソファの背もたれに掛ける。秋口は従兄の手からビールを取り上げてそれを呷った。
「なーんだよ、また、仏頂面しちゃってさあ」
質問なのか感想なのかわからない酔っぱらいの言葉を、秋口は無視した。
「何でまた勝手に入ってるんだよ、人の部屋」
「近くまで来たから遊びに寄ってやったんだよ」
「頼んでない」
「思ったより便利いいんだよな、この部屋。いい別宅を見つけた……」
「鍵返せよ、おまえがどうしても仕事明けに一眠りしたいって言ったから、あの時だけ預けたんだぞ」
「合い鍵もう作っちゃった」
縞がにやにやしながら手に取った鍵を、秋口はひったくった。
「それがおまえに借りたやつ。こっち合い鍵」
もうひとつポケットから取り出された鍵を奪おうと秋口は手を伸ばしたが、縞はさっとそれを自分の背中に隠してしまった。
「返せ」
「イ、ヤ」
秋口が腹を立てて縞の背中に手を突っ込むと、縞が黄色い奇声を発した。
「いやあー! 航ちゃんに犯されるぅ!」
「……」
秋口は深々と溜息をついて、縞から離れた。あとで鍵ごと変えてしまおう、と決意する。
まったくこの従兄には昔から敵わない。正直言って苦手な相手なのに、どうして家に居座られなくてはいけないのか、秋口は腑に落ちなかった。
「航ちゃんさあ」
合い鍵をポケットにしまい直し、縞はテーブルに置いてあった新しいビール缶に手を伸ばした。プルタブを開けながら秋口を見遣る。秋口はネクタイを緩め、床に並んだ空き缶数個をキッチンに運んだ。中をゆすいで、収集日にゴミ捨て場に持って行かなければならない。
「だからちゃんって呼ぶな。いい年して、気持ち悪い」
「おまえ、欲求不満なんじゃない?」
「……」
乱暴に、秋口はシンクに空き缶を投げ出した。怒って叩きつけたわけではない。動揺して取り落としたのだ。
「やーっぱりなあ、何だよ、女と会ってたんじゃないの? 逃げられたのか? 例の彼女に」
答えず、秋口は空き缶を水で洗った。
縞は従弟の『本命』が彼女ではなく彼だということを知らない。秋口には言うつもりもなかった。何しろ物心ついた時から筋金入りの両刀遣いである縞と違って、秋口は完全なるヘテロ、男に欲情する従兄の気が知れない鉄壁の女好きだったのだ。今さら男に恋をしましたなんてどの面下げて言えばいいのか、わからなかった。
「可哀想になあ、貧しい恋をしてるんだな」
「よけいなお世話だ」
秋口は缶を洗い終え、乱暴に蛇口を閉めた。振り返って、何か言い返してやろうと口を開きかけた秋口は、縞がやたら楽しそうな顔で鼻歌まで歌っていることに気づき、毒気を抜かれてしまう。こんな相手に、文句や嫌みを言うだけ無駄だ。どうせ小さい頃から、この従兄に秋口が言葉で勝った試しがない。
「……おまえはずいぶん楽しそうだな、亮人」
代わりに、呆れるような、もしかすると羨ましげな呟きが秋口の口から洩れる。
「楽しいよー、って言うか最高。今日、この間の人にまた会ったんだ」
「この間って、ひったくりだかを一緒に捕まえたとかいう?」
秋口は縞の隣に腰を下ろし、もう一本ビールに手を伸ばした。明日も出社だから、そろそろ風呂に入って寝た方がいいとは思うが、ちっとも眠たくないし、飲まずにはいられない気分でもあった。
「そっ、何となく、暇だから連絡するってタイプじゃないみたいだから、こっちから押しとこうと思って」
上機嫌に、縞はまたビールに口をつけた。
「ちょうどいいタイミングで、向こうも店にいるって言うから、友達といるとこに合流してさ。メシはうまいし、相手美人だし、最高」
気楽なもんだよ、と秋口もまたビールを呷った。
「いやほんと、いい夜だった。向こう会社勤めだからって先に帰られたけど……あれはやっぱり、警戒されてんのか?」
縞は秋口へ質問というより、自問の調子で言って首を傾げている。
「何だ、おまえも逃げられてるんじゃないか」
「最初から簡単に股開くような尻軽は好みじゃないからいいんだよ。多少お堅い方が、楽しみも増えるし」
縞の言葉が負け惜しみでないことは、今までの経験上秋口にもわかっている。縞は遊んでいるふうであって、本気なら割合まじめな恋をする。身持ちの堅いタイプが好きで、自分も恋人がいる間は決して他の相手に目をくれることがなく、一途に相手のことを大事にし続ける。
それまで色恋沙汰なんてくだらないと言わんばかりに四角四面な心持ちと見てくれだった人間が、縞に大事に甘やかされて、信じられないくらい色気のある様子になっていく奇跡を秋口も見たことがあった。
ただし、フリーの時はちょっと気に入った相手でも口癖みたいに熱心に口説くから、やっぱり遊んでいると言わざるを得ない辺り、自分と同類だと秋口は思う。
「何つーか、容姿も表情も言動も、いちいちこっちのツボ突いてくるんだよな。どうにかしてやりたいの抑えるのに必死だったよ、本気で。最初は当たり柔らかそうな印象だったのに、実は気が強そうな感じがするとこなんてもう」
縞はアルコールで上気した頬、軽く潤んだ瞳で、うっとりと溜息をついた。
「ああいう相手を泣かせたら、気持ちいいだろうなあ……」
「その相手と会うところが、俺の家に近いってことか」
酔っぱらいの戯言を本気で聞くまでもなく、秋口は相手の言葉を遮るようにそう訊ねた。
秋口が就職してからここ数年、法事以外でまともに顔を合わせたこともなかった縞が今ここに居座っているのは、今後もここを拠点に置いて、意中の相手を口説こうとしているからだ。秋口はそう理解した。縞が『便利がいい』と言ったのはそういう意味だ。
「そう。この辺から家に帰るの面倒だし、タクシー代も馬鹿にならない」
「間違ってもホテル代わりに使ったりするなよ、相手連れ込んだらすぐおばさんに電話して、実家に連れ帰らせるぞ」
「やなこと言うねえ、おまえ」
縞は大袈裟に鼻の頭へ皺を寄せた。定職にも就かずに物書き仕事で生計を立てている縞が、未だに親からその仕事に反対されていることはもちろん秋口も承知の上だ。縞の両親は実直で厳しい人たちだったから、とっくに成人した息子を本気で家に連れ戻そうとするだろう。実際そうはならなくても、間違いなく何時間も説教を喰らう。縞がそのお説教を大の苦手としていることも、秋口は熟知していた。
「あれか、彼女に冷たくされて、意地悪になってるのか」
そして縞の逆襲だ。今度は秋口が眉間に皺を寄せる羽目になった。
「おまえも、そんな暴力的で冷たい恋人のことなんて忘れて、そうだ、今度一緒にメシでも行こうぜ。向こう、仲のいい友達同士なんだ。一対一で会ったらよけい警戒されそうだし、おまえ、来いよ」
「何で俺が。相手って男だろ」
たしかに今秋口の心を惑わせている相手はれっきとした男性だが、何も他の男まで恋愛の範囲内に入ったわけではないのだ。秋口は今も男のことがちゃんと嫌いだった。そういう対象になるという意味では。
「だからだよ、バーカ。惚れた女ができて、これからゆっくり愛をはぐくんで行きましょうって段階だったとしたら、おまえなんかと死んでも会わせるもんか。五秒でホテルに連れ込まれる。男ならおまえの食指も動かないだろ」
縞も、たまにしか会わない割に、従弟の恋愛観はよく理解している。
「頭数合わせだ、今度連絡してやるから、呼ばれたら絶対来いよ。もし来なかったら……」
言いながら、縞がソファの隙間に手を突っ込んだ。そこから、女物のストッキングをずるりと引っ張り出す。ガーターベルト用の黒い網模様だ。
「秋口さんちの可愛い航ちゃんが、こーんなエッチなものつける女を部屋に連れ込みまくりですって、聖絵と美里に電話してやる」
「……」
聖絵と美里は、昔から何かと弟の世話を焼きたがる秋口の姉だ。そんなことが知れたが最後、彼女がいるなら家につれてこいだの、掃除しに行ってやるから鍵を寄越せだの、うるさく言われることだろう。
黙り込んだ秋口を見て、縞がにっこりと笑顔になる。
「決まりな。ま、残業なさそうな日教えてくれたら少しは考慮してやるから。逃げんなよ」
駄目押しのように縞が言って、秋口は反論することもできなかった。本当に、昔からこの従兄のことは苦手だった。
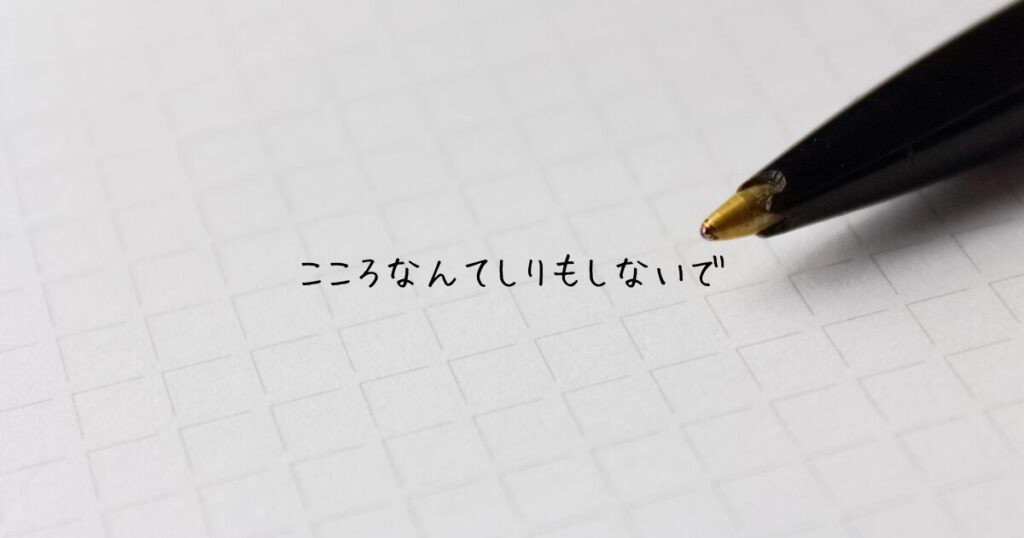
サラリーマン×サラリーマン

商業誌番外編

商業誌番外編

商業誌番外編
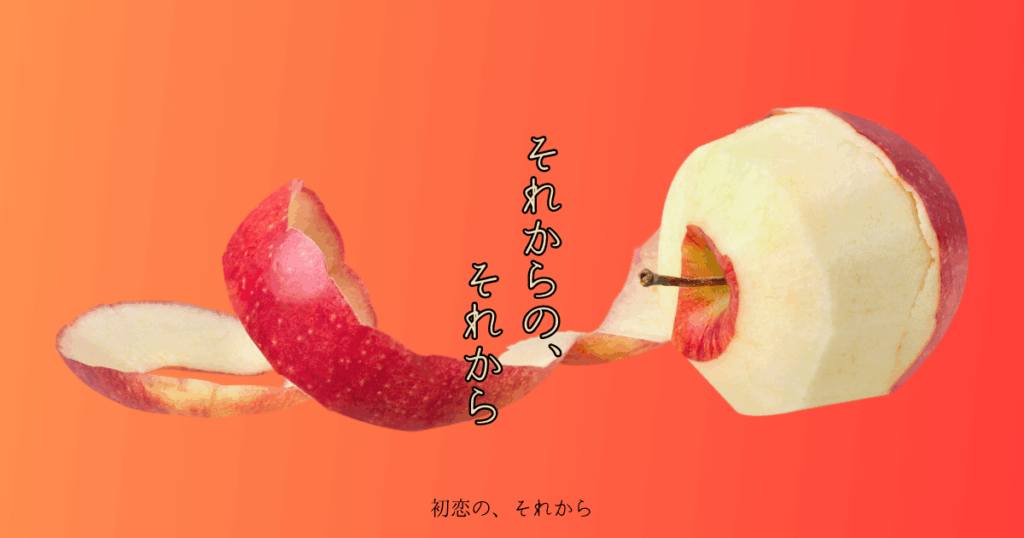
商業誌番外編
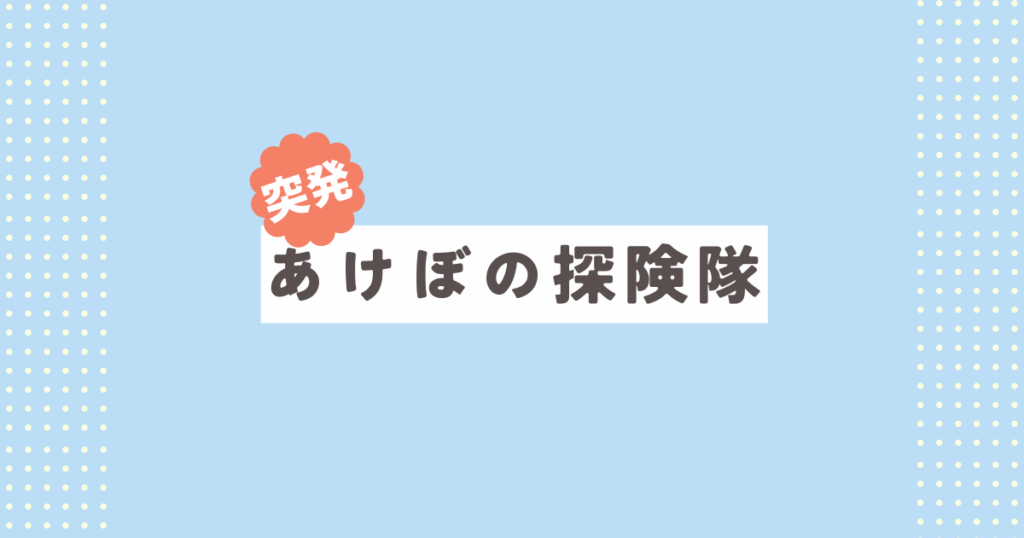
同人誌シリーズ番外編

高校生の恋未満読み切り