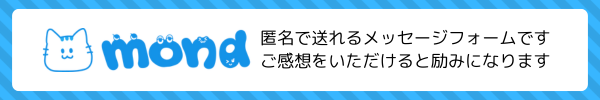(そうだ、金下ろさないと)
忙しさにかまけていたら、財布の中身がすっかり寂しくなっていた。
珍しく、奇蹟的に定時に仕事を終えて会社を出た平日の夕方、佐山は自宅に戻る前に途中の駅で電車を降り、銀行に向かった。そろそろ同じスーツやシャツばかり着続けているのはどうかと、昼間顔を合わせた御幸に言われ、そういえば最近服なんて買ったことがなかったと思い出したのだ。
土日に混み合う店をうろうろするのに気が進まず、延ばし延ばしにしていたが、時間ができたので、金を下ろして気晴らしにぶらぶらすることにした。
秋口と、当分会わずにすむよう仕向けてから、今日で五日。
これで少しは気分が落ち着くかと思ったのに、どうしたって秋口のことを考えては憂鬱な気分になってしまうのだから救いようがない。
(遠くから見るってのも、やりづらいしなあ)
会社でお互いの姿をみつければ、無視するわけにも行かずにこっちからちょっと笑いかけたり、向こうが小さく会釈を返したり、ぎこちないことこの上ない空気だ。喧嘩をしたわけじゃない。気軽に声を掛け合うこともできない。この中途半端さが佐山の気をいよいよ重くさせる。
(……俺は、どうしたいんだ? 結局)
ぼんやりと、答えを本気で出すわけでもなく考えつつ、佐山はATMで金を下ろした。もう窓口は閉まっているが、数人の客がATMを利用するため店の中にいる。下ろした金とカードをを財布にしまい、服屋のあるビルへ歩き出した佐山は、背後で女性の悲鳴を聞き、驚いて振り返った。
「だ、誰かぁ、ひったくり――」
駅前だが、コンコースから外れた人通りのまばらな道だ。佐山から少し離れた場所で初老の女性が歩道に倒れ込み、彼女の手を伸ばす先――佐山の方へ、若い男ふたりが慌ただしく走ってくるのが見えた。通りすがりのOLふたりが彼らに突き飛ばされかけ、慌てて道を避けていた。他にサラリーマンふうの男が佐山と逃げてくる男たちの間にいたが、迷惑そうな顔で立ち止まるだけだった。
「捕まえて、誰かぁ」
甲高い女性の悲鳴を聞きながら、佐山は考えるより先に、走ってくる男たちの進路を阻む位置に移動していた。
「どけ!」
怒声を聞いてももちろん道は譲らず、先を走る男の足先に自分の足を差し出す。
佐山の足に引っかかって、男が派手に地面へ転がった。だが、後から来た男が相棒の醜態には目もくれず、地面に落ちたバッグを素早く拾い上げる。
佐山も手を伸ばしたが、間に合わず、男は道の先を行ってしまった。追いかけようとした佐山の足を、地面に転がったままの男が掴み、佐山も転びかけたが、すぐそばのガードレールに捕まってこらえた。
「てめぇ」
転ばされた怒りにまかせ、男が佐山の肩を掴み、自分の方へ体を向けさせる。振り上げられた拳が降りてくる前に、佐山は手にしていた鞄でそれを払い、体勢が崩れたところで渾身拳を相手の土手っ腹へ叩き込んだ。佐山のひょろりと頼りない体に油断していた男は、思い切りのいい攻撃を予測できず、もろに喰らった。
呻き声を洩らしてうずくまる男を地面へ俯せに押さえつけながら、片手を背中の方へねじ上げる。相手の動きを封じ込めてしまってから、もうひとりはどうしたかと、佐山は辺りを見回した。
すぐに、少し離れた場所で他の通行人と揉み合っているのをみつけた。
「すみません、これ、押さえてて。あと、一一○番お願いします」
「えっ、あ、はい!」
近くの野次馬たちへ強引に男を預け、佐山は揉み合うふたりのそばに駆け寄った。
簡単にのせてしまった先刻の相手よりも、鞄を手にした男の方が体格がよく、暴力に慣れている感じがした。その男と取っ組み合っている方も背が高く大柄だったが、必死な相手の勢いに押されている。
佐山が駆け寄り辿り着く直前、ひったくりの男の蹴りが、止めようとする男の脇腹に当たった。地面に倒れ込む相手を踏みつけて再び走り出そうとする引ったくり犯の背中に、佐山はそばにあった消費者金融の小さな立て看板を両手で掴んで叩きつけた。
「うぐぉッ」
背後からの打撃に体勢を崩しかけた男は、それでも何とか踏みとどまった。痛みと驚きで逆上して、低い叫び声を上げながら振り返り、佐山の方へ突進してくる。佐山は看板を、今度は相手の足許目掛けて投げつけ足止めすると、怯んだ相手の鼻面に鞄を叩きつけた。
周りの野次馬たちが、男がよろめいたのを見ると一斉に飛びかかり、数人で押さえつけにかかった。
振り返ると、先に捕まえた男も、騒ぎを聞きつけて集まった人たちがしっかり動きを封じている。
それを確認すると、佐山は引ったくり犯に蹴られた脇腹を押さえながら立ち上がろうとしている男の方へ近づき、手を貸した。
「大丈夫ですか?」
「いてて……いや、すみません、平気です。ありがとう」
佐山と同年代に見える若い男は、腹を押さえながら反対の手で佐山の手に掴まり、立ち上がった。声が少し嗄れている。しばらく呻いていたのかもしれない。相当強く蹴りつけられたのが佐山の位置からでも見えた。
痛みに顰められた男の顔がどことなく青白く見えて、佐山は顔を曇らせる。
「顔色、悪いですよ。骨はやられてませんか、ひどく傷むようなら病院に」
「実は徹夜明けなんです。せっかくカッコつけて飛び出したのはいいけど、思うように体が動かなくて。年かなぁ」
「――……」
心配させまいとしてか、おどけて言った男の声は掠れが治り、おそらく彼本来の響きになった。
そしてその声を耳にして、佐山は思わず体の動きを止めた。
「ん? どうかしました?」
様子に気づいて、男が不思議そうに首を傾げる。
ハッと我に返った佐山は、つい顔を赤らめる。
「す、すみません――あんまり言い声なんで、聞き惚れちゃって」
「ああ。よく言われます」
男は照れもせず、笑顔でしれっとそう答えた。佐山は思わず吹き出し、相手も、軽く笑い声を立てた。
「は、は、いてて……とにかく、ありがとう。助かりました」
体を支える佐山の腕に掴まったまま、男が頭を下げる。佐山は恐縮した。
「いや、こちらこそ、ひとりじゃ捕まえられませんでしたから」
佐山と男は、同時に後ろを振り返った。パトカーがやってきて、警官が野次馬たちから引ったくり犯ふたりを引き取る様子が見える。
バッグを盗られて助けを求めていた老女が、佐山たちの方を指さしていた。
「あっ、あの人たちですよ、あのお兄さんたちが捕まえてくれたの」
彼女に言われて近づいてくる警官を見て、男が「しまった」と小さく声を上げた。
「さっさと退散するんだった、安眠が遠くなる……」
「すみません、調書を取りたいので、少しお時間いただけますか?」
男のぼやき声と重なるように、警官が佐山たちに声をかけてくる。
佐山と男は顔を見合わせ、苦笑気味に笑い合う。
「はい」
「いいですよ」
同時に答えながら、佐山は男と自分が奇妙な連帯感を味わっているのがわかって、おかしくなった。
男が佐山に耳打ちしてくる。
「仕方ない、お役所仕事だから時間はかかるだろうけど、これも正義の味方の試練だと思って共に堪え忍びましょう」
男の茶化した囁き声に笑いを返しながら、佐山は何だかどぎまぎして止まらなかった。
(何だ、この動悸は――)
理由なんて、本当はもうわかっている。
男の声が、あまりに秋口に似すぎていたからだ。
忙しさにかまけていたら、財布の中身がすっかり寂しくなっていた。
珍しく、奇蹟的に定時に仕事を終えて会社を出た平日の夕方、佐山は自宅に戻る前に途中の駅で電車を降り、銀行に向かった。そろそろ同じスーツやシャツばかり着続けているのはどうかと、昼間顔を合わせた御幸に言われ、そういえば最近服なんて買ったことがなかったと思い出したのだ。
土日に混み合う店をうろうろするのに気が進まず、延ばし延ばしにしていたが、時間ができたので、金を下ろして気晴らしにぶらぶらすることにした。
秋口と、当分会わずにすむよう仕向けてから、今日で五日。
これで少しは気分が落ち着くかと思ったのに、どうしたって秋口のことを考えては憂鬱な気分になってしまうのだから救いようがない。
(遠くから見るってのも、やりづらいしなあ)
会社でお互いの姿をみつければ、無視するわけにも行かずにこっちからちょっと笑いかけたり、向こうが小さく会釈を返したり、ぎこちないことこの上ない空気だ。喧嘩をしたわけじゃない。気軽に声を掛け合うこともできない。この中途半端さが佐山の気をいよいよ重くさせる。
(……俺は、どうしたいんだ? 結局)
ぼんやりと、答えを本気で出すわけでもなく考えつつ、佐山はATMで金を下ろした。もう窓口は閉まっているが、数人の客がATMを利用するため店の中にいる。下ろした金とカードをを財布にしまい、服屋のあるビルへ歩き出した佐山は、背後で女性の悲鳴を聞き、驚いて振り返った。
「だ、誰かぁ、ひったくり――」
駅前だが、コンコースから外れた人通りのまばらな道だ。佐山から少し離れた場所で初老の女性が歩道に倒れ込み、彼女の手を伸ばす先――佐山の方へ、若い男ふたりが慌ただしく走ってくるのが見えた。通りすがりのOLふたりが彼らに突き飛ばされかけ、慌てて道を避けていた。他にサラリーマンふうの男が佐山と逃げてくる男たちの間にいたが、迷惑そうな顔で立ち止まるだけだった。
「捕まえて、誰かぁ」
甲高い女性の悲鳴を聞きながら、佐山は考えるより先に、走ってくる男たちの進路を阻む位置に移動していた。
「どけ!」
怒声を聞いてももちろん道は譲らず、先を走る男の足先に自分の足を差し出す。
佐山の足に引っかかって、男が派手に地面へ転がった。だが、後から来た男が相棒の醜態には目もくれず、地面に落ちたバッグを素早く拾い上げる。
佐山も手を伸ばしたが、間に合わず、男は道の先を行ってしまった。追いかけようとした佐山の足を、地面に転がったままの男が掴み、佐山も転びかけたが、すぐそばのガードレールに捕まってこらえた。
「てめぇ」
転ばされた怒りにまかせ、男が佐山の肩を掴み、自分の方へ体を向けさせる。振り上げられた拳が降りてくる前に、佐山は手にしていた鞄でそれを払い、体勢が崩れたところで渾身拳を相手の土手っ腹へ叩き込んだ。佐山のひょろりと頼りない体に油断していた男は、思い切りのいい攻撃を予測できず、もろに喰らった。
呻き声を洩らしてうずくまる男を地面へ俯せに押さえつけながら、片手を背中の方へねじ上げる。相手の動きを封じ込めてしまってから、もうひとりはどうしたかと、佐山は辺りを見回した。
すぐに、少し離れた場所で他の通行人と揉み合っているのをみつけた。
「すみません、これ、押さえてて。あと、一一○番お願いします」
「えっ、あ、はい!」
近くの野次馬たちへ強引に男を預け、佐山は揉み合うふたりのそばに駆け寄った。
簡単にのせてしまった先刻の相手よりも、鞄を手にした男の方が体格がよく、暴力に慣れている感じがした。その男と取っ組み合っている方も背が高く大柄だったが、必死な相手の勢いに押されている。
佐山が駆け寄り辿り着く直前、ひったくりの男の蹴りが、止めようとする男の脇腹に当たった。地面に倒れ込む相手を踏みつけて再び走り出そうとする引ったくり犯の背中に、佐山はそばにあった消費者金融の小さな立て看板を両手で掴んで叩きつけた。
「うぐぉッ」
背後からの打撃に体勢を崩しかけた男は、それでも何とか踏みとどまった。痛みと驚きで逆上して、低い叫び声を上げながら振り返り、佐山の方へ突進してくる。佐山は看板を、今度は相手の足許目掛けて投げつけ足止めすると、怯んだ相手の鼻面に鞄を叩きつけた。
周りの野次馬たちが、男がよろめいたのを見ると一斉に飛びかかり、数人で押さえつけにかかった。
振り返ると、先に捕まえた男も、騒ぎを聞きつけて集まった人たちがしっかり動きを封じている。
それを確認すると、佐山は引ったくり犯に蹴られた脇腹を押さえながら立ち上がろうとしている男の方へ近づき、手を貸した。
「大丈夫ですか?」
「いてて……いや、すみません、平気です。ありがとう」
佐山と同年代に見える若い男は、腹を押さえながら反対の手で佐山の手に掴まり、立ち上がった。声が少し嗄れている。しばらく呻いていたのかもしれない。相当強く蹴りつけられたのが佐山の位置からでも見えた。
痛みに顰められた男の顔がどことなく青白く見えて、佐山は顔を曇らせる。
「顔色、悪いですよ。骨はやられてませんか、ひどく傷むようなら病院に」
「実は徹夜明けなんです。せっかくカッコつけて飛び出したのはいいけど、思うように体が動かなくて。年かなぁ」
「――……」
心配させまいとしてか、おどけて言った男の声は掠れが治り、おそらく彼本来の響きになった。
そしてその声を耳にして、佐山は思わず体の動きを止めた。
「ん? どうかしました?」
様子に気づいて、男が不思議そうに首を傾げる。
ハッと我に返った佐山は、つい顔を赤らめる。
「す、すみません――あんまり言い声なんで、聞き惚れちゃって」
「ああ。よく言われます」
男は照れもせず、笑顔でしれっとそう答えた。佐山は思わず吹き出し、相手も、軽く笑い声を立てた。
「は、は、いてて……とにかく、ありがとう。助かりました」
体を支える佐山の腕に掴まったまま、男が頭を下げる。佐山は恐縮した。
「いや、こちらこそ、ひとりじゃ捕まえられませんでしたから」
佐山と男は、同時に後ろを振り返った。パトカーがやってきて、警官が野次馬たちから引ったくり犯ふたりを引き取る様子が見える。
バッグを盗られて助けを求めていた老女が、佐山たちの方を指さしていた。
「あっ、あの人たちですよ、あのお兄さんたちが捕まえてくれたの」
彼女に言われて近づいてくる警官を見て、男が「しまった」と小さく声を上げた。
「さっさと退散するんだった、安眠が遠くなる……」
「すみません、調書を取りたいので、少しお時間いただけますか?」
男のぼやき声と重なるように、警官が佐山たちに声をかけてくる。
佐山と男は顔を見合わせ、苦笑気味に笑い合う。
「はい」
「いいですよ」
同時に答えながら、佐山は男と自分が奇妙な連帯感を味わっているのがわかって、おかしくなった。
男が佐山に耳打ちしてくる。
「仕方ない、お役所仕事だから時間はかかるだろうけど、これも正義の味方の試練だと思って共に堪え忍びましょう」
男の茶化した囁き声に笑いを返しながら、佐山は何だかどぎまぎして止まらなかった。
(何だ、この動悸は――)
理由なんて、本当はもうわかっている。
男の声が、あまりに秋口に似すぎていたからだ。
◇◇◇
玄関に自分のものではない男物の靴をみつけ、秋口は軽く眉をしかめた。
短い廊下を進んですぐのダイニングキッチンのドアを開けると、ソファに座って新聞を広げる男の姿がある。秋口に気づいて顔を上げ、気安い調子でひらひら手を振っていた。
「よっ、おかえり」
「まだいたのか」
秋口は素っ気なく言って、上着を脱ぐと鞄と一緒にソファへ放り投げ、自分も男の隣へ腰を下ろした。
「何て言い種だ。優しいお兄ちゃんは、こんな夜中まで帰ってこない悪い子を待っててやったんだぞ」
「頼んだ覚えもないしおまえみたいな兄を持った覚えもないし」
相手の軽口に億劫げに応酬してソファに凭れると、近づいてきた顔に首筋の匂いを嗅がれた。
「うん。まごうかたなく女の匂い」
秋口は自分にくっつく頭を邪険に押し戻した。相手は気を悪くしたふうもなく、笑いながら立ち上がって秋口を見下ろす。
「コーヒー淹れてやるよ、結構飲んだみたいだな」
指摘されたとおり、秋口は少し酒を過ごして、頭も体もすっきりしない。しかも決して楽しい酒ではなかった。
「一杯飲んで帰ろうとしたのに、他の女と鉢合わせして……」
重たい頭を押さえつつ秋口が呻くように言うと、キッチンの方から笑い声が返ってきた。
「どっちかと泊まってくりゃよかったのに。もう終電もなかっただろ」
他人の部屋なのに、文字どおり勝手知ったる様子でコーヒーを淹れる背中を、秋口は溜息をつきながら見遣った。
「自由業のおまえと同じ尺度で測らないでくれ、明日も会社なんだ」
「ああ、そういや平日だっけ」
これだよ、と秋口は軽く首を横に振った。
「そうか、おまえももう社会人なんだよなあ。あんなに小さくて可愛かった航ちゃんが」
「何を今さら。大学卒業してもう二年だぞ」
「そんなに経つのか、俺も年取るわけだなあ」
しみじみ言いつつソファに戻ってきた相手から、秋口はコーヒーカップを受け取る。
「じじくさい……」
「いやもう徹夜が辛いしさ、三十路を間近に控えて。部屋貸してくれて助かったよ、家に帰るまでに行き倒れるところだった」
コーヒーを啜りつつ、秋口はふと、コーヒーカップを手に隣に腰を下ろした相手の顔に、大きなすり傷があるのに気づいた。
「おまえ、どうした、ここ」
傷の辺りを突いてやると、痛そうに少しその顔が顰められる。
「いて、触るなよ。暴漢に襲われたんだ、名誉の負傷」
相手の説明を、秋口ははなから本気にしなかった。
「捨てた女にでもやられたんじゃないのか」
「そんなポカしません、航とは違います」
すました顔で言われた言葉に、秋口は憮然となった。
「すごいよな、おまえの本命ってのも。顔と腹に一発ずつだっけ、まあそのうちそういう目に遭うかもとは思ってたけど」
「俺の話はいいだろ、別に」
秋口はますます不機嫌な顔で、おもしろがっている相手の言葉を遮った。
ゆうべ遅くに仕事の都合があるから秋口の部屋に泊まらせてほしいと連絡があって以来、相手の顔を見て話したのは今で初めてだが、『別に構わないけど』と答えた声音で簡単に不機嫌を見破られ、おもしろ半分に追求されてつい話してしまった。
色恋沙汰がこじれて、自分のひどい仕打ちへの仕返しに殴られたと正直に話したら、電話の向こうで大喜びされて、秋口はよりいっそう不機嫌になったわけであるが。
さすがに、鉄槌を下したのが同じ男だと言うことまでは秋口も話していない。さらに喜ばれそうな予感がしたからだ。
「おまえの怪我はどこの誰にやられたのかって訊いてるんだよ」
「誰だったかな、名前は忘れちゃったけど。通りすがりの引ったくり犯だよ。銀行出たところで、下ろしたばっかりのおばあさんの金を狙ってきた」
「わざわざ助けたのか」
「そりゃ放っておけないだろ、かよわきお年寄りを狙った許し難き犯罪」
もっともらしく力説するまじめぶった顔を、秋口は胡散臭いものを見る目で見遣った。
「本当に被害者、老人だったのか。亮人好みのフェロモン系歳上女か、美形の男だったなら信じるけど」
「吉森益江さん六十五歳、十年前に夫に先立たれて、嫁いだ娘は連絡を滅多に寄越さない寂しいご老人だ。まあ、若い時はきっと美人だっであろう顔立ちだったけど」
「……詳しく聞いたもんだな」
「不安がってたから、警察までついて行ってやったんだよ。そしたらまあ喋ること喋ること。俺ももうひとりも、立ち回りよりおばあさんの相手に苦労した」
「もうひとり?」
「ああ、一緒に引ったくり犯捕まえた――っていうか、そっちの活躍で無事掴まったって言うか。すごかったぜぇ、結構大柄な男相手で、俺なんかあっという間に吹っ飛ばされたのに、あっという間にふたりのしちゃって。痛快っていうか、何て言うか」
その時のことを思い出してか楽しげに話す言葉を、疲れていた秋口は話半分に聞き流した。
「ふうん。世の中には物好きな正義の味方が多いんだな」
コーヒーを飲み干し、カップをテーブルに置いて立ち上がる。
「まあコロスキンでも塗っておけよ。俺は風呂入って寝る」
「はいはい、お湯沸いてるよ」
どうやら家主より先に客が風呂を浴びたらしい。掃除して湯を張って、と時間を取るのが秋口には面倒だったので、ありがたくはあったが。
「俺はソファ借りるな、航が明日会社行ってる間に出てくから」
「どうぞ」
適当に応え、秋口は風呂場に向かった。服を脱ぎ、すぐに湯に漬かる。
とにかく疲れていた。
「くそ……」
顔にぬるくなった湯を浴びせ、誰にともなく悪態をつく。
それでも自分と鉄拳制裁を与えた相手について、根掘り葉掘り聞かれなかったことが多少救いになった。今そんな話を聞かれたら、きっとみっともなく泣き言をぶちまけてしまうに違いない。今この家にいる歳上の従兄は、秋口がもっとも自分を飾り立てせず話せてしまう相手だ。もっとも根が自尊心の高い性格なので、『他人に較べれば』と注釈は入るが。
(……これ以上他人に無様なところを見せるなんて)
それでなくてもここ最近、何かとそんな姿を晒し続けてしまっているというのに。
今日だって、連れがいるのに他の女とバッティングするなんて、しかも両方から人前で不実を責められるなんて、みっともないことこの上ない。
今まで後腐れない相手を選んできたつもりだったのに、誤算の連続だ。
自分の思いどおりに行かないことばかりで、いい加減うんざりも限界を超えてきた。
(……今日も結局、メールのひとつもないし)
そもそも向こうから自主的にメールが来たことなど一度もないが。
その事実に思い当たって、秋口は湯につけた唇をむっと曲げた。
(向こうから距離置きたいって言ってきたんだ。向こうが連絡くれないと、声かけていいのかわからないじゃないか)
――もちろんそれが自分に対する言い訳で、こちらから声をかけた時に袖にされたり、無視でもされたら耐えられないからだとわかっている。だから自分から連絡を取ることに二の足を踏んでいるのだと。
「……」
何もかもうまくいかない。
自業自得だとわかっていても、苛立ちは止められない。
(あと、もう少し)
風呂釜にでも八つ当たりをしたい気分をどうにか抑えて、秋口は自分にそう言い聞かせた。
(もう少しだけ――当分、佐山さんに会うのは我慢しよう)
それから秋口は、明日はどの課のどの女の子と会うか算段しながら、しばらく風呂に浸かり続けた。
短い廊下を進んですぐのダイニングキッチンのドアを開けると、ソファに座って新聞を広げる男の姿がある。秋口に気づいて顔を上げ、気安い調子でひらひら手を振っていた。
「よっ、おかえり」
「まだいたのか」
秋口は素っ気なく言って、上着を脱ぐと鞄と一緒にソファへ放り投げ、自分も男の隣へ腰を下ろした。
「何て言い種だ。優しいお兄ちゃんは、こんな夜中まで帰ってこない悪い子を待っててやったんだぞ」
「頼んだ覚えもないしおまえみたいな兄を持った覚えもないし」
相手の軽口に億劫げに応酬してソファに凭れると、近づいてきた顔に首筋の匂いを嗅がれた。
「うん。まごうかたなく女の匂い」
秋口は自分にくっつく頭を邪険に押し戻した。相手は気を悪くしたふうもなく、笑いながら立ち上がって秋口を見下ろす。
「コーヒー淹れてやるよ、結構飲んだみたいだな」
指摘されたとおり、秋口は少し酒を過ごして、頭も体もすっきりしない。しかも決して楽しい酒ではなかった。
「一杯飲んで帰ろうとしたのに、他の女と鉢合わせして……」
重たい頭を押さえつつ秋口が呻くように言うと、キッチンの方から笑い声が返ってきた。
「どっちかと泊まってくりゃよかったのに。もう終電もなかっただろ」
他人の部屋なのに、文字どおり勝手知ったる様子でコーヒーを淹れる背中を、秋口は溜息をつきながら見遣った。
「自由業のおまえと同じ尺度で測らないでくれ、明日も会社なんだ」
「ああ、そういや平日だっけ」
これだよ、と秋口は軽く首を横に振った。
「そうか、おまえももう社会人なんだよなあ。あんなに小さくて可愛かった航ちゃんが」
「何を今さら。大学卒業してもう二年だぞ」
「そんなに経つのか、俺も年取るわけだなあ」
しみじみ言いつつソファに戻ってきた相手から、秋口はコーヒーカップを受け取る。
「じじくさい……」
「いやもう徹夜が辛いしさ、三十路を間近に控えて。部屋貸してくれて助かったよ、家に帰るまでに行き倒れるところだった」
コーヒーを啜りつつ、秋口はふと、コーヒーカップを手に隣に腰を下ろした相手の顔に、大きなすり傷があるのに気づいた。
「おまえ、どうした、ここ」
傷の辺りを突いてやると、痛そうに少しその顔が顰められる。
「いて、触るなよ。暴漢に襲われたんだ、名誉の負傷」
相手の説明を、秋口ははなから本気にしなかった。
「捨てた女にでもやられたんじゃないのか」
「そんなポカしません、航とは違います」
すました顔で言われた言葉に、秋口は憮然となった。
「すごいよな、おまえの本命ってのも。顔と腹に一発ずつだっけ、まあそのうちそういう目に遭うかもとは思ってたけど」
「俺の話はいいだろ、別に」
秋口はますます不機嫌な顔で、おもしろがっている相手の言葉を遮った。
ゆうべ遅くに仕事の都合があるから秋口の部屋に泊まらせてほしいと連絡があって以来、相手の顔を見て話したのは今で初めてだが、『別に構わないけど』と答えた声音で簡単に不機嫌を見破られ、おもしろ半分に追求されてつい話してしまった。
色恋沙汰がこじれて、自分のひどい仕打ちへの仕返しに殴られたと正直に話したら、電話の向こうで大喜びされて、秋口はよりいっそう不機嫌になったわけであるが。
さすがに、鉄槌を下したのが同じ男だと言うことまでは秋口も話していない。さらに喜ばれそうな予感がしたからだ。
「おまえの怪我はどこの誰にやられたのかって訊いてるんだよ」
「誰だったかな、名前は忘れちゃったけど。通りすがりの引ったくり犯だよ。銀行出たところで、下ろしたばっかりのおばあさんの金を狙ってきた」
「わざわざ助けたのか」
「そりゃ放っておけないだろ、かよわきお年寄りを狙った許し難き犯罪」
もっともらしく力説するまじめぶった顔を、秋口は胡散臭いものを見る目で見遣った。
「本当に被害者、老人だったのか。亮人好みのフェロモン系歳上女か、美形の男だったなら信じるけど」
「吉森益江さん六十五歳、十年前に夫に先立たれて、嫁いだ娘は連絡を滅多に寄越さない寂しいご老人だ。まあ、若い時はきっと美人だっであろう顔立ちだったけど」
「……詳しく聞いたもんだな」
「不安がってたから、警察までついて行ってやったんだよ。そしたらまあ喋ること喋ること。俺ももうひとりも、立ち回りよりおばあさんの相手に苦労した」
「もうひとり?」
「ああ、一緒に引ったくり犯捕まえた――っていうか、そっちの活躍で無事掴まったって言うか。すごかったぜぇ、結構大柄な男相手で、俺なんかあっという間に吹っ飛ばされたのに、あっという間にふたりのしちゃって。痛快っていうか、何て言うか」
その時のことを思い出してか楽しげに話す言葉を、疲れていた秋口は話半分に聞き流した。
「ふうん。世の中には物好きな正義の味方が多いんだな」
コーヒーを飲み干し、カップをテーブルに置いて立ち上がる。
「まあコロスキンでも塗っておけよ。俺は風呂入って寝る」
「はいはい、お湯沸いてるよ」
どうやら家主より先に客が風呂を浴びたらしい。掃除して湯を張って、と時間を取るのが秋口には面倒だったので、ありがたくはあったが。
「俺はソファ借りるな、航が明日会社行ってる間に出てくから」
「どうぞ」
適当に応え、秋口は風呂場に向かった。服を脱ぎ、すぐに湯に漬かる。
とにかく疲れていた。
「くそ……」
顔にぬるくなった湯を浴びせ、誰にともなく悪態をつく。
それでも自分と鉄拳制裁を与えた相手について、根掘り葉掘り聞かれなかったことが多少救いになった。今そんな話を聞かれたら、きっとみっともなく泣き言をぶちまけてしまうに違いない。今この家にいる歳上の従兄は、秋口がもっとも自分を飾り立てせず話せてしまう相手だ。もっとも根が自尊心の高い性格なので、『他人に較べれば』と注釈は入るが。
(……これ以上他人に無様なところを見せるなんて)
それでなくてもここ最近、何かとそんな姿を晒し続けてしまっているというのに。
今日だって、連れがいるのに他の女とバッティングするなんて、しかも両方から人前で不実を責められるなんて、みっともないことこの上ない。
今まで後腐れない相手を選んできたつもりだったのに、誤算の連続だ。
自分の思いどおりに行かないことばかりで、いい加減うんざりも限界を超えてきた。
(……今日も結局、メールのひとつもないし)
そもそも向こうから自主的にメールが来たことなど一度もないが。
その事実に思い当たって、秋口は湯につけた唇をむっと曲げた。
(向こうから距離置きたいって言ってきたんだ。向こうが連絡くれないと、声かけていいのかわからないじゃないか)
――もちろんそれが自分に対する言い訳で、こちらから声をかけた時に袖にされたり、無視でもされたら耐えられないからだとわかっている。だから自分から連絡を取ることに二の足を踏んでいるのだと。
「……」
何もかもうまくいかない。
自業自得だとわかっていても、苛立ちは止められない。
(あと、もう少し)
風呂釜にでも八つ当たりをしたい気分をどうにか抑えて、秋口は自分にそう言い聞かせた。
(もう少しだけ――当分、佐山さんに会うのは我慢しよう)
それから秋口は、明日はどの課のどの女の子と会うか算段しながら、しばらく風呂に浸かり続けた。
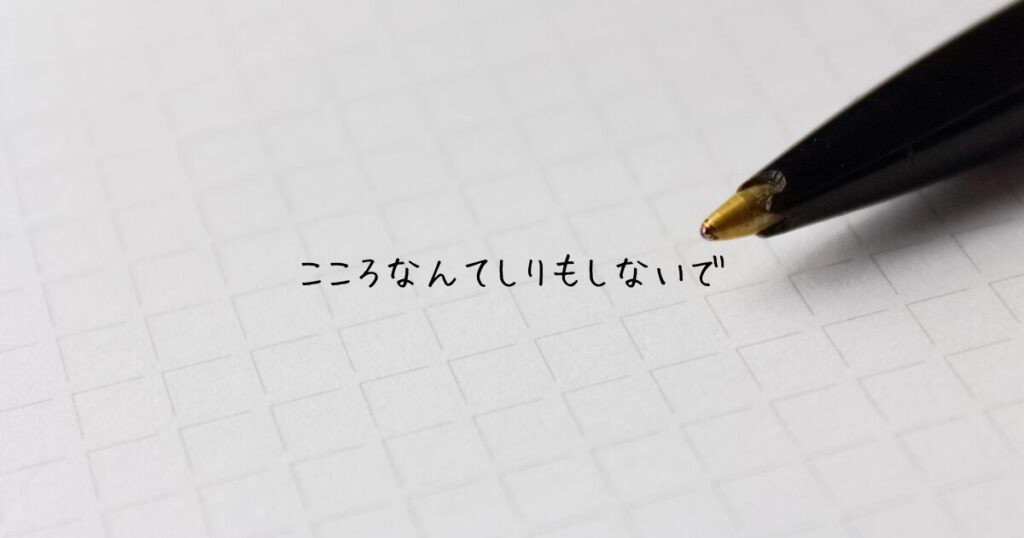
サラリーマン×サラリーマン

商業誌番外編

商業誌番外編

商業誌番外編
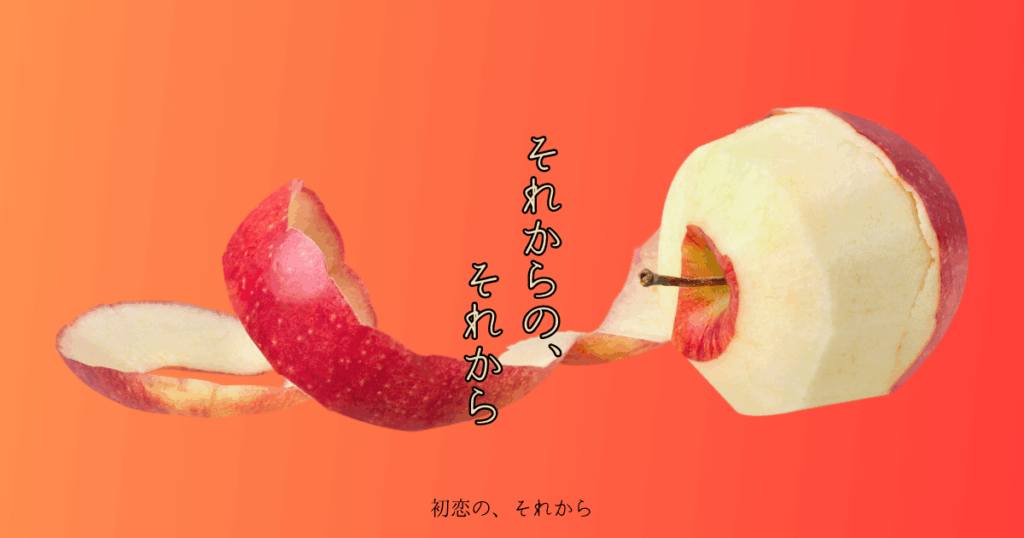
商業誌番外編
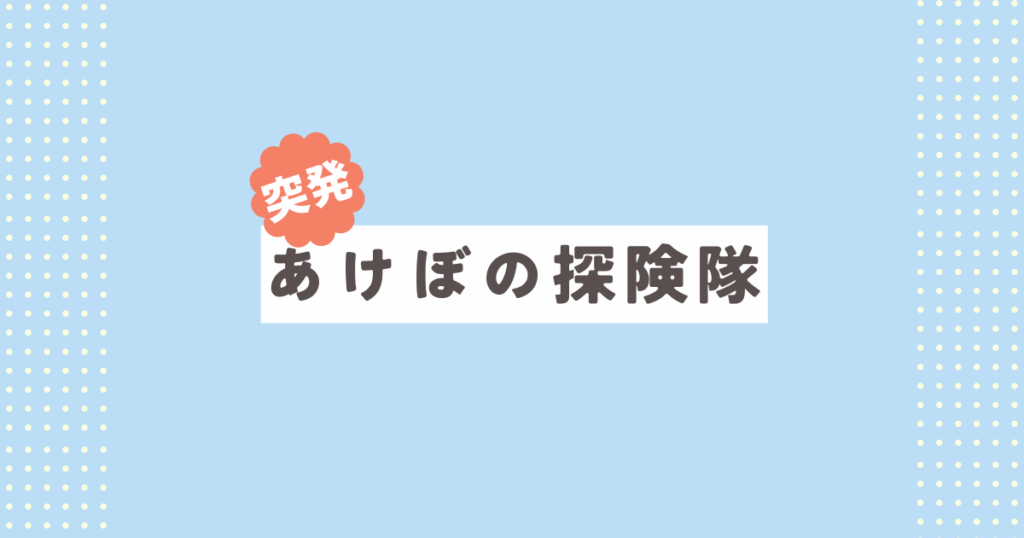
同人誌シリーズ番外編

高校生の恋未満読み切り